
Old Money & New Money;ジグザグに発展してきた貨幣の歴史

Photos by H.Okada in Shanghai
ビットコインが登場して以来、貨幣とは何かを問う論稿が数多く世に出された。その中でも、多くの人々の目に触れたのが、イングランド銀行で開催された勉強会の資料である。
英国の中央銀行であるイングランド銀行は、2015年5月に開催された「イングランド銀行/中央銀行研究センター・チーフエコノミスト・ワークショップ」(BoE / CCBS Chief Economists’ Workshop)と題する勉強会において Old Money, New Money というタイトルの資料を公表した。それは、貨幣の発生にまで遡って、信頼の源泉とは何かを問い、仮想通貨の貨幣としての意義を問う意欲的な報告であった。
Old Money, New Money と題して発表したのは、イングランド銀行のチーフエコノミストであるマイケル・カムホフ(Michael Kumhof)氏である。
カムホフ氏は、貨幣というものが成立する根拠を、大きく「クレジット型」と「トークン型」の二つに分類して説明する。ここでクレジット型とは、人々の信頼の対象となる主体が貸し借りの記録を帳簿上に記載し、その記録の正確性を担保として貨幣としての機能を提供するものをいう。これに対してトークン型とは、貴金属片や硬貨などの物理的存在に価値があるという社会的約束を成立させて、この物理的存在を移転させることによって貨幣としての機能を果たすものをいう。
カムホフ氏の考察によれば、貨幣はクレジット型とトークン型の二つの方式の間をジグザグに進みながら発展してきた。図の左にクレジット型、右にトークン型が位置取られている。ジグザグの線は図の左下からスタートする。
初期農業帝国における楔形文字で刻まれた台帳は、貸し借りの記録を国家の権威を背景として書き込んだクレジット型であった。ウル第三王朝のジッグラドには、粘土板に刻まれた楔形文字のレリーフに貸借の記録が残されていた。これがクレジット型による貨幣の源流である。
次にジグザグの線は右上方へと向かう。初期にトークン型の貨幣が登場したのは、小アジアのリディアにおいて稀少金属の合金に刻印を押したエレクトロン貨であった。これがギリシャ・ローマ時代におけるトークン型の貨幣、すなわちコインの原型となった。同じように、インド文明・中華文明においても、トークン型の貨幣として、稀少金属に刻印し、もしくは鋳造したコインが流通した。これら四つの文明において、トークン型の貨幣に存在根拠を与えたのは、国家ないしは皇帝の権威であった。
ジグザグの線は、左端の上方へと戻っていく。中世のヨーロッパにおいては、トークン型の貨幣が日常生活において流通することはなかったからである。
中世の終焉すなわち大航海時代の幕開けとともに、トークン型の貨幣は復活を遂げる。だがジグザグの線は右端までは伸びず、真ん中あたりで止まる。この時代は、クレジット型とトークン型が併存したからである。
大航海時代には、欧州域内においては銀行制度の発達によって紙と万年筆によってつくり出されるクレジット型の貨幣が信頼を得たのとは対照的に、植民地諸国に対しては、金貨や銀貨によってあらゆるものを購入することができるという、新しい価値観の輸出が推進された。こうした二面性ゆえ、ジグザグの線は中央で止まるのであった。
ジグザグの線は再び折り返し、今度は左端に限りなく近づく。これが現代である。トークン型の貨幣も発行されているが、流通量の大半を占めるのはクレジット型の貨幣である。通貨の総量において見た時、銀行の預金通貨のようなクレジット型の貨幣が占める割合が圧倒的に高く、トークン型の貨幣は相対的にみて僅かな量である。
さて、ここからが発表の本題である。ビットコインのような仮想通貨というのは、チーフエコノミストの眼にはどう映っているのだろうか。ジグザグの線は、右上方へと伸びる。仮想通貨はトークン型の貨幣として位置づけられるらしい。これは納得がいく。信頼の源泉を求めるクレジット型とは対照的に、分散型仮想通貨には発行主体がないからである。
図をよく見ると、もう一本の線が引かれていて、右下方へ向かっている。実は、この図では、国家の権威による貨幣を下に、民間の創意による貨幣を上に書くことになっている。右下方へ伸びる線が意味するもの、それは中央銀行が発行するブロックチェーン通貨である。それはトークン型の貨幣の一種であって、金属の代わりにブロックチェーン技術を使って「鋳造」したものを指す。
右上方へ伸びるのは、国家の権威からもっとも距離を置いた分散型仮想通貨であり、右下方へ向かうのは、同じような技術を使いながらも国家の権威に裏打ちされた法定通貨である。どちらか一方が残るのか、あるいは大航海時代のように二つの異なる貨幣が目的を異にしながら共存するのか。
歴史のジグザグの続きが楽しみである。
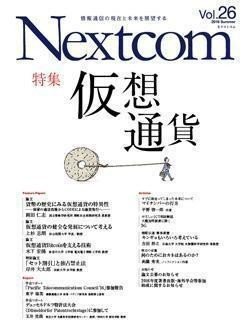
季刊 Nextcom 特集「仮想通貨」vol.26 (2016 Summer)『貨幣の歴史にみる仮想通貨の特異性-国家の通貨高権からCODEによる通貨発行へ-』KDDI Research(要読者登録)。
同じ内容をやや別の視点から再掲したものとして、下記がある。
DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー 2017年8月号 特集「ブロックチェーンの衝撃」『歴史から考察する「貨幣らしさ」の正体-仮想通貨に「信頼」は成立するのか-』

