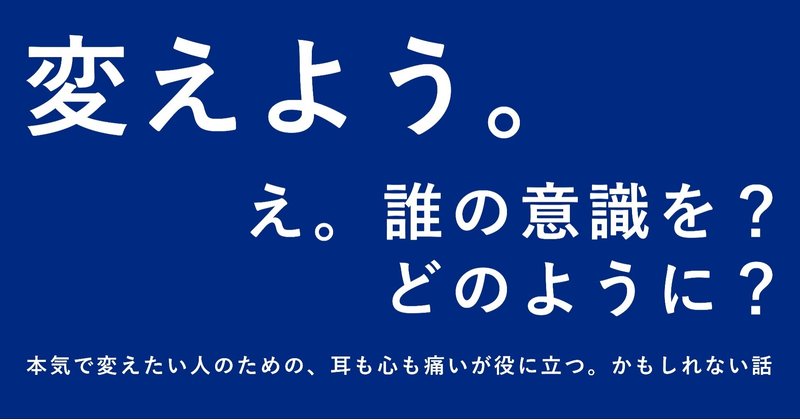
変えよう。え。誰の意識を?どのように?本気で変えたい人のための、耳も心も痛いが役に立つ。かもしれない話(衆院選ワタシ的総括)
個人的にサプライズだったこと
衆院選お疲れさまでした。
はじめて選挙そのものを拒否しました。
つまり投票に行きませんでした。
いろんなスタンスの方がいらっしゃると思います。
「投票行かなかった奴の投稿なんか読みたくない。」
お気持ちよくわかります。そう思われた方はお手数ですがそっ閉じしてください。あなたに必要のない情報を押し売りするつもりはありません。
でも、もしも何かしらこの選挙結果に思うところがあり、「なんとかしたい。」と考える忍耐強い方がいらっしゃれば、ワタシはその方のためだけにこの記事を書きたいと思います。
実を言うと、どうなっちゃうのか自分でも想像がつかなかったのですが、まぁでもなんの感慨も湧かないです。
驚くほど怒りも悲しみもザマァというような歓喜?すら湧かない。
はじめての選挙拒否で何を感じたかって、
途方もない感情的なラクさ。
親きょうだいと絶縁したとき同様の解放感です。
意外でした。
でもこれはすごく納得できるものでした。
なぜこんなにも投票に行くことへのハードルが高いのか
単に投票に行くというだけの行為。これは通常なら自宅のドアから10分もあれば終了するプロセスなんです。誰に入れようか悩むことはあっても動作性の点ではさほど難しいことではないはずです。少なくとも海外在住だとか障がいがあるとかじゃない限り。
となると難しいのは感情面なんですよね。
政治にコミットするということは、その経過や結果に関心を持つことを意味します。応援した候補が当選すれば嬉しいし、落選すれば残念な気持ちになるでしょう。
投票に行かないということは良くも悪くも感情が引っ張られないことなんだなと実感します。
これはとてもストレスの少ない状態です。
期待し、行動をし、裏切られ、落胆や怒りを感じる。
というプロセスを一個取り除くだけで、ほんのすこししかQOLを短期的に下げないことは、特により日々の生活にしんどさを抱えている人にとっては束の間の休息になるのでしょう。
まさに、この層こそを取りに行かねばなりませんでした。
実は皆さんが開票速報に沸き立っている間、ワタシは仕事でMTGに参加していました。そのあと軽く雑談する機会があったのですが、誰一人選挙の話はしませんでした。
それなりの人数がいたのに。さすがに自分の人生で今までそんなことなかったんで面食らいました。
でも彼らに政治観が全くないわけではないんですよ。我々の業界ではよく知られた「業種にも政治にもバリバリ発言している有名人」がいます。それに自民党総裁選に対して「なんも変わらず、うちら置き去りで相変わらず政争やってる」なんてことも口にもしていたのですから。
ですが、そもそも普段の発言から考えて、もう彼らは政治に何も期待していないのです。
一般的には、無党派層は自民に入れたくない層が多い。だって入れたかったら行きますから。政権を維持するために。
つまり基本的には、無党派層は潜在的には野党寄りのはずなんですよね。それを取りに行けてない。
安定の自民党政権に対して積極的になれないのに、かといって、入れたいと思うほどの野党もない。
これが「入れるところがない」の理由だと思います。
その時その時の選挙によって無党派層が動いた場合の投票先は変わりますが、今回は与野党どちらにもいれたくないからユ党の方がいいと判断した。と、仮説を立てるなら、
維新が票を伸ばすのは、今回の場合、必然ではないでしょうか。
依存してるのはどっちだ?
自助、共助などと取り立てて言われずとも、肌身で政治側の無責任さを感じている人たちは、もはや政治を頼りにせず、自分達でコミュニティを作って、その中で支えあってしまっているのが現状です。それらはビジネスだったり宗教だったり、或いは趣味のコミュニティの場面で見かけます。
これをワタシは「政治からの自立」とは呼びませんが、彼らの感覚としてはそうなのです。
むしろ彼らからすると、「政治の側が自分達に依存している」という感覚です。
既に政治にコミットすることを辞め、精神的なストレスを手放した彼らにとっては、ベネフィットを与えることもなく、無限にクレクレしてくる政治は依存的で厄介な存在だと受け止められている。
それを思えば、れいわが票を伸ばしたのもまた必然といえましよう。
有権者をこき下ろす「カシコぶりのアホ」
数年前からよくりっけんや共産の政党関係者やその支持者に「山本太郎(や、その後のれいわは)ポピュリズムだから」という言葉が聞かれました。
彼らがれいわを敵視するのは、それが維新に似たものであると感じているからですが、一部は当たっていますが、ではどの点が当たっていたのでしょうか。
批判的な野党支持者は、
・れいわはポピュリズム
・維新は反知性主義(その平易な表現としての「ヤンキー政党」)
という評価をしていたわけですが。
一般的な話として、政権担当経験のない政党にとっては、将来への期待感こそが票の源泉になります。これは先日自分のキャスなどでもご紹介した2004年の東大の研究でも明らかです。
そして、その期待感とは生活そのものの向上であり、少なくとも理念的で高尚なビジョンよりも優先される課題です。
れいわは一貫して生活を訴えました。
ワタシはれいわの、特に財源論に関しては全く信頼しておらず理論的には破綻しているとさえ感じています。でもよっぽど高尚なジェンダーや環境問題よりははるかに新型コロナと失業対策の方が身近で期待が持てました。
維新にしてもそうだったのです。彼らは既に大阪においては府政・市政を担う与党ですから、実績をアピールする必要がある。
それがどんなにかデタラメであっても「それっぽく聞こえて、有権者に納得感を与えること」が彼らのとれる唯一の方法論であり、実際にそうしたのです。
その方法論に対して、他の野党とその支持者はどういうわけか、支持者を上から目線でこき下ろしにいきました。
ワタシなられいわとは敵対せず、自党に近い人ほど、そうした発言をしないよう引き締めを図ったでしょう。
すべては結果論だという批判を承知で言いますが、この💩パターンは自分が見る限り、2016年の都知事選以降もう5年は続いているのです。
維新に対しては、ワタシならば支持者は批判せず、事実をもって政党へのカウンターをし続けたでしょう。むしろ今回はその手法は維新の方がやっていましたね。
そもそも、りっけん、共産、社民(社大含む)の選挙を仕切ったと言っても過言ではない「市民連合」が用意した争点とやらに、その他の政党は全く乗ってきませんでした。
野党の多くは一人相撲で土俵から落ちたのです。
結局何が敗因なのか
結論として、この選挙における野党、特に立憲民主党と共産党の敗因は明らかです。
・そもそもの課題が何であるかを見誤った
・そして、解決されるべき課題の主語をも見誤った
これが敗因だとワタシは考えています。
テレビのコメンテーターやカシコな学者さんたちはいろいろいろいろ言っていますが、ワタシから見てこれほどチャンスだった、争点のわかりやすい選挙はなかったと考えています。
しかし、何をするにせよ登るべき山を間違えていては目的を達成することは不可能です。富士山に登ることを宣言しながら、天保山のある大阪を目指してもどうにもならないでしょう。
政治が変えるべきもの=政治の目的は、有権者の、国民の、市民の、生活上の困難です。
そしてその課題は経済だったり、今なら新型コロナだったり、誰かにとってはジェンダーの問題だったりします。
つまり争点はこちらから「これである!」と言ったところで必ずしも、というかほとんどの場合は争点にはなりえません。
争点の生まれるところはどこなのか
なぜ、こちら側からしかけても多くの場合で争点にはなりえないのでしょうか。
まず、そもそも第一に、争点は有権者のニーズから生じます。
ジェンダー平等やら環境問題やらが第一になっていた野党共闘、そしてその旗振り役となった市民連合は、まず、そこからしてはき違えていたとしか考えられません。
イニシアチブは常に、主権が民衆にある限り永遠に、有権者にあるのです。広告代理店がCMを打つようなやり方で正しい争点を教えてやれば勝てると思っているのなら、それは完全に間違っています。
また選挙では必ずと言っていいほど敵対する他者が存在しますから、彼らの戦略に対する対処もしていかねばなりません。
すなわち第二に、現実には敵対する相手の持つテーマとの類似性を踏まえつつ、有権者のニーズから生じる争点を、差別化を図りながら訴える
ということになります。
自民であればそれは経済対策や国防、そして「反共勢力との闘い」でした。公明は、新型コロナ、経済対策が優先されました。
維新は新型コロナと反共勢力、そして「古い政治権力(自公を意味する)」との闘いでしょう。
一応本人たちはどちらも「経済に強い政党」または「国民に寄り添う政党」をアピールしています。
しかし、明らかに。そのどれにも野党はカウンターらしいカウンターができないまま終わってしまいました。
また、れいわの場合、大いなるミスリードを引き起こした市民連合主導の野党共闘政策は個々の候補者が部分的に取り入れるにとどまりました。あくまで自分たちの日頃からの主張を軸に据えて選挙を戦ったれいわは、必然的に他の野党との差別化が実現することになりました。
刺さらない人にはまったく刺さらないれいわの政策は、刺さる人にはしっかり刺さっていたといえましょう。
「主導権はこちらにある」などと言って見せる愚者こそ、自らの振る舞いを反省せねばなりません。
さいごに。心に残った街宣について
唐突ですが福岡4区の社民の方の街宣が良かったです。途中ゴリゴリ感MAXでしんどい部分もありましたが、昔懐かしい労働者の党としての社民の街宣でした。
全ての人が生まれて良かった、生きてて良かったと思える社会に。
当たり前のことだけどいいスピーチでした。
その原点に立ち返ってはいかがでしょうか。
誰のための何のための政治なのか。
もう一度考え直してはいかがでしょうか。
とはいえ、ワタシは今回選挙に行きませんでしたので、何を偉そうに言ったところでどうしようもありませんよね。人によっては全く受け入れられないでしょう。そういう人は今まで通りやっていけばいいと思います。
今までの上手くいかなかったパターンをこれからも踏襲し続けるのか、それとも、自分が聞きたくない話も聞いてみて、考えてみて、違ったやり方を試してみるか、それは情報の受け手が決めることですから。
ただ、今からとても大事なことを言いますね。もう記事も終わるのでそれだけは良かったら持ち帰って考えてみてください。
この解放感は癖になりそうで怖いです。
とても心理的に摩擦がない。
投票に行かないことが、こんなに楽だとは思ってもみませんでした。
投票に行かなくなった人がこの解放感に抗って再び投票に行くのは至難の業に思えます。
そうした心理的な摩擦を生まなくて済むにはどうすればいいのか。
次の選挙まではそれを自分の課題として、政治と付き合うことになりそうです。
※編集の記録
2021.11.2 引用した論文の掲載年を2014年→2004年に修正
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
