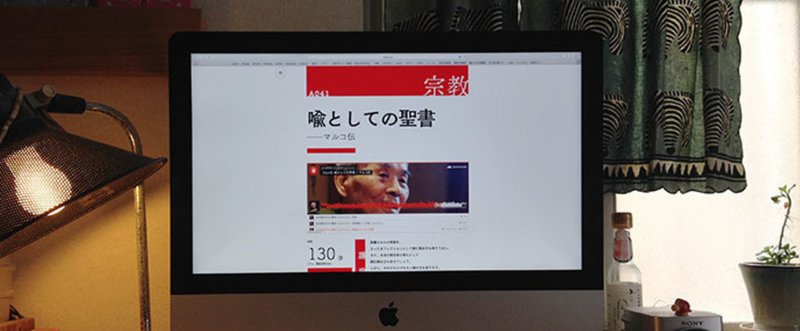
第9回 全部の領域を踏まえて
【吉本隆明さん講演『喩としての聖書−マルコ伝』を、日々、ほんのちょっとずつ聴きすすめております。ほんじつは「第9回目」です〜。前回noteはこちらです〜。】
どーも、こんにちはっ。
前回では、「近親者としての人間」「公の人間」「自分自身としての人間」というこれらは「ある場合には互いに相矛盾する。」と、吉本隆明さんお話ししておりました。
ここから、さらにつづけられるのは、
ひとりの人間の中でも相矛盾します。そして、(チャプター3 / 聖書のすぐれた洞察_8:09〜)
それらは、人同士のお互い、だけじゃなくって、「ひとりの人間の中」でも「相矛盾」する。そして、
人との関係の、他者との関係の中でもそれは矛盾したり、それから対立したりするわけです。それは、ひとりの人間としても対立しますし、他(た)から見た人間としても対立的に見える。つまり、まったく正反対に見えるっていうことは、人間の中に在るわけです。
「ひとりの人間の中」だけじゃあなく、「他者との関係の中」でも、「矛盾」したり「対立」したり「まったく正反対に見える」っていうことは、人間の中に在る。
という、ここのところは、ちょっとぼくにはややこしくて。。。
あっ! んでもさ、前回noteで引用しました久保ミツロウさんの漫画『モテキ』4巻でね。小宮山夏樹から「100人いたら100人の頭の中で見える私って全部違うのよ」そして「自分の思ってもいない方向に進む人生が好きなの」と言われた主人公・藤本幸世が、
「やっと 気づいた」
ってこころの中でおもうのはさ。なんてゆうか、吉本さん仰るこの「相矛盾」について藤本自身が「気づいた」んかもしれない、とおもったの。小宮山夏樹のことばを、藤本が「聞いた」ことによって・・・
講演をつづけます。
つまり、それはけっして偽善者であるから、そうなんでもなければ。ごまかしてるから、そうなんでもなく。ごまかしもなく正直にふるまったとしても、
それは「偽善者」であるからとか「ごまかしてる」から、そうなのではなくって。たとえ「ごまかし」もなく「正直にふるまった」としても、、
公共的人間、公の人間としてふるまった人間っていう場合のその人って言うのと、その人間と、それから近親者としてから見たその人間っていうのと。あるいは、自分自身が自分に問うている、その、自分の内面に問うている場合の自分自身がこうだと思っている自分自身もまた、
「公の人間」と「近親者から見たその人間」と「自分自身」も、また、
互いに対立したり、互いに異なったり、互いに矛盾したり、っていうことは、どんなに正直にふるまおうとありうることなんです。つまり、人間っていうのは、ひとりの人間の精神的な領域っていうのは、言ってみれば、そういう全部の領域を踏まえて立っている、っていうことなんです。
たがいに「対立」したり「異」なったり「矛盾」したりするのは、あり得ること。そして、ひとりの人間とは、それらすべての領域を踏まえながら、立っている。。。
あ、あのぉ、さきほど申しました漫画『モテキ』で言いますとん。
『モテキ』ってば、主人公・藤本幸世のおもっている「心の声」がたくさん描かれていて。それはね、もしかしたら吉本隆明さんおっしゃる「(自分が自分へ問いかける)自分自身としての人間」の「声」なのかもしれない。
そこから、人生で初めて「他者(小宮山夏樹)の声」を「聞く」ことができて。つまり、吉本さんの言い方ですと「自分の領域」以外を踏まえて「立つ」ことができた。だから、感動的で。。
(ドラマ版『モテキ』最終回のこのシーンも、ほんとにすてき〜。)
「対立」や「異」や「矛盾」を、藤本が、ちょっとだけ受け入れることができた、的な?! なんだか、たぶんだけれど『モテキ』とはそーいうふうなストーリーだったんじゃないかって感じたの。
そのことを例えば、あの、そのことを、そういう言い方では無いですけれども。思想として見ると「聖書」っていうのは非常によく取り出しているって言うことが、僕には非常に見事だって思えるところで。感銘が非常に大きいところなんです。
吉本さん曰く「これらのことが『聖書』では非常によく描かれている。」とのことで。ぼくは「聖書」のことはまったく存じあげませんが、でも『モテキ』のことを思い出したので、書いてみました〜。
ほいでは、また次回へつづきます。きょうで「チャプター3」が終わりましたので、次回noteより「チャプター4 / 聖書の思想のいちばん大切なこと」を聴いてまいりますっ。きんようび、晴れたっす。
2016年6月17日
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
