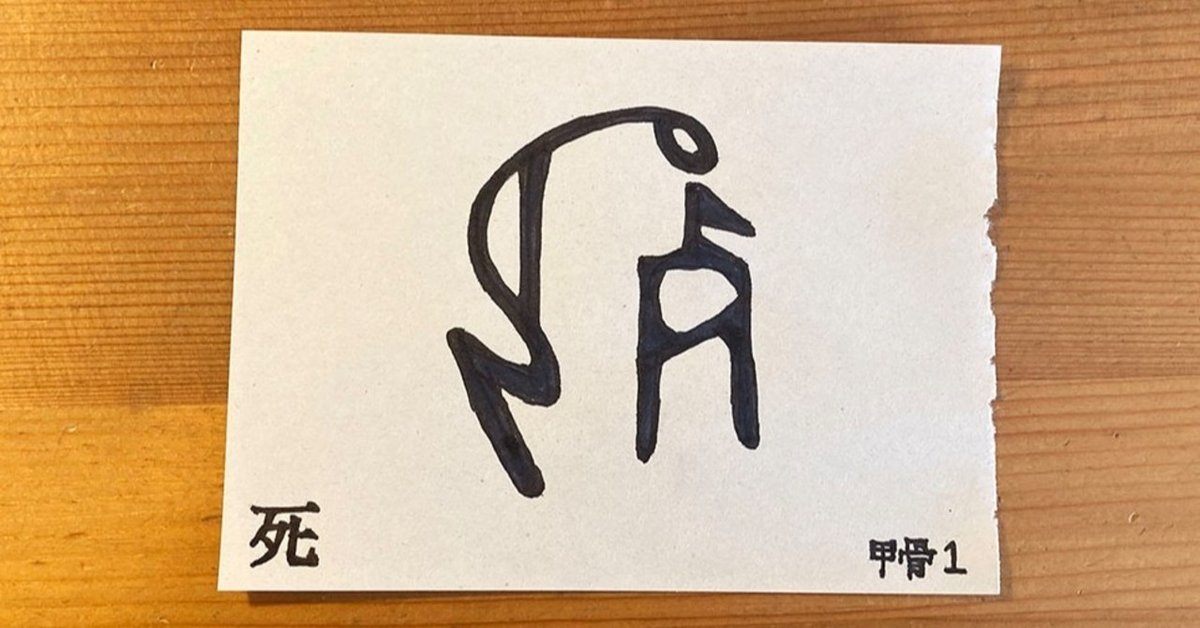
【死】について。
毎月13日更新、
漢字について調べてみる
「リッシンベン調査団」のこと。
こんかいは、
先日、ぼくの父が亡くなったこともあり、
【死】
という漢字を見てゆきたい。
ほかのどの漢字でも、
そのあらゆる形は、なにかしら、
特色があるような感じがするのですが。
あらためて、
【死】という漢字とは、
不思議な形だなあとぞんじます。
たぶん、よく言われるのは、
片仮名の「タ」と「ヒ」が並んでいる。
その上に、一本、線がのっている。
みたいな。。。
この【死】の字を、いつものごとく、
白川静先生の『常用字解(第二版)』にて
調べてみますと、、
【死】 シ/しぬ・ころす
歹(がつ)と人(匕(ひ))とを組み合わせた形。歹のもとの形は(註・変換できない形のため省略)に作り、死者の胸から上の残骨の形。古くは死体を一時的に草むらに棄て、風化して残骨となったとき、その骨を拾ってほうむることを葬(ほうむる)という。このような埋葬形式を複葬という。拾い集めた残骨を拝み弔う形が死で、「しぬ、ころす」の意味となる。
まずは、
片仮名の「タ」だと思っていたのは、
【歹(がつ)】で、
死者の胸から上の残骨の形。そして、
【匕】のほうは、
「人」の意味なのだった。
つまりはさ、
漢字の【死】とは、
亡くなった人の「骨」の形なのでしょうか。
また、
お葬式の【葬】という漢字にも、
真ん中に【死】が入っているのだった。
白川先生の『常用字解』によれば、
かつての埋葬形式では、
死体を草むらに棄て風化した骨を拾いほうむる、
ということもあったそうで。
その「草むら」より、
【葬】の偏が「くさかんむり」なのでしょう。
さらには、
【亡】という漢字も
『常用字解』で見てみますと、
【亡】とは、
手足を折り曲げている死者の骨の形で、
屈肢葬の形。あるいは、
草の間で白骨した屍(しかばね)ともみられる。
とのことで。はたまた、
頭髪の残っている屍が、
草野に棄てられている状態を【荒】という。らしい。
「亡命」のように「にげる」の意味、
「滅亡」のように「ほろびる」の意味として、
用いられる。
とのことでして。
【亡】の漢字も、
【死】と同様に、
「骨」の形なのだった。
【亡】とは、
手足を折り曲げた屈肢葬の形、あるいは、
草のあいだで白骨した「屍」の形。
この【屍】という漢字にも、
【死】が入っているのね。。。
父へ、
拝み、弔う。。。
令和2年11月13日
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
