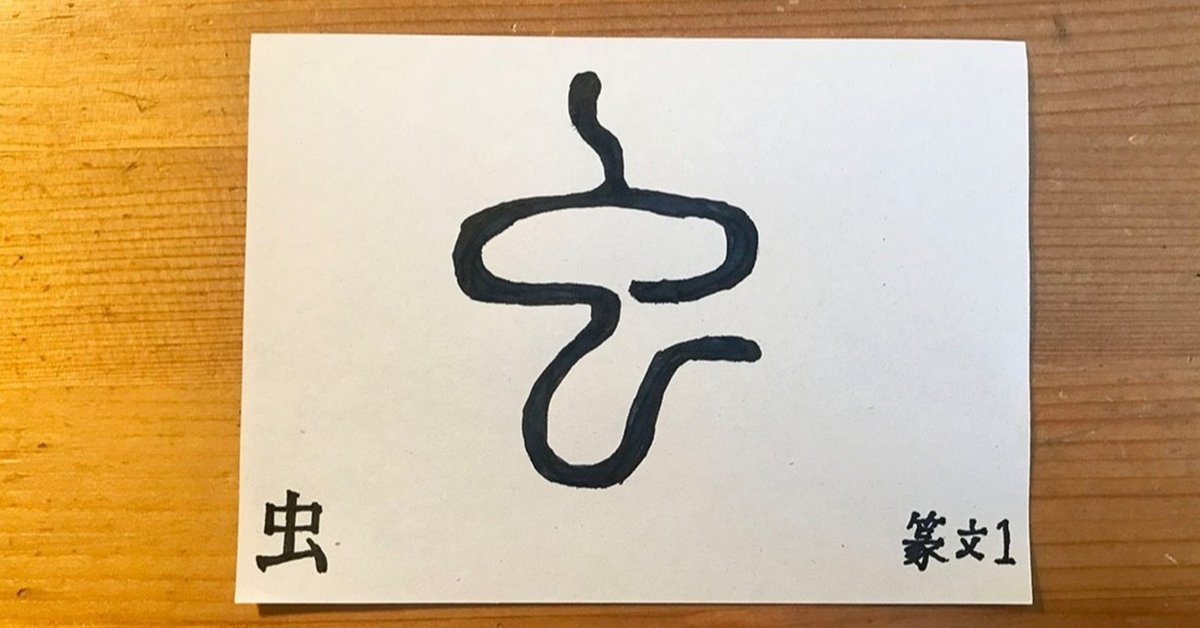
ちいさな【蟲】も、爬【虫】類も。
前回noteでは、
【春】という漢字についてブログ書きましたが。
そのなかでね、【春】の下に「虫」が二つついた
【蠢】という漢字のことも書きまして。
「うごめく」と読むこの【蠢】ってば、
やっぱり、形がすごい。
見るからに、もう、
とっても「うごめく」の感じがある。
そういうふうに言えば、
この【蠢】だけでなくって、たとえば、
「蠱惑的」という語句の【蠱】の字には、
「虫」が三つもついていて。
これもまた、形がすんごい。
シズル感がある、というか。
ことばの意味は『広辞苑(第七版)』によれば、
「人の心をひきつけ、まどわすこと。」
とのことなんですが。
もう、そんなにも「まどわす」虫って、
どんなやねん! と想う。
よっぽど、艶かしい「虫」なのでしょう。。。
ってなるとさ、
この【虫】という漢字が、どんな意味なのか?
ってのも気になってくる〜。
なので、こんかいも白川静先生の
『常用字解(第二版)』で調べてみました。
【虫】 チュウ・キ/むし
もとの字は蟲に作り、虫(き)が三つ集まっている形。蟲の常用漢字として用いる虫(ちゅう)はもと蟲とは別の字で、虫(き)と読む。虫(き)は蛇(へび)など爬虫類(はちゅうるい)の形、また、蝮(まむし)をいう。䖵(こん)は、[説文(せつもん)]十三下に「蟲の總名(そうめい)なり」とあり、蟲(虫)は昆虫のように密集する小さな「むし」をいう。(‥‥後略)
【虫】のもととなった字は、
「虫」が三つの【蟲】であって。また、
「虫」が二つの【䖵】という形もある。
そして、
【蟲】のほうが本来の「虫」の意味で。
【虫】は蛇などの「爬虫類」の形。
という、言われてみれば「爬虫類」のことばにはさ、
【虫】の字が入っているし。
「蛇」や「蝮」という漢字は、
「むしへん」だったんだなあ。
これまでとくに気にしたことなかったから、
あんまり知らなかった。
この【蟲】が、だんだんと、
爬虫類だけでなく、現在のような
「虫」の意味になっていったのでしょう。。。
それにしてもさ、やはり、
『常用字解』で書かれているように、
「虫」が三つの【蟲】という形は、
小さな「むし」が密集している感じがあるなあ。
そのほかにもね、たとえば、
「犇めく」とか、「轟く」とか、「囁く」とか、
「傀儡」とか、「贔屓」とか、「磊落」とか、
「脅かす」という漢字は、
おんなじ形が三つ重なっていて。
それらにはそれぞれの感じがある気がするなあ。
調べてみれば「磊落」だけは、
けっこう想像とちがっていたけれども。
そんなことをね、きょう、
ぼくは「綴」っている。
おそばを、啜りたい。。。
令和2年4月4日
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
