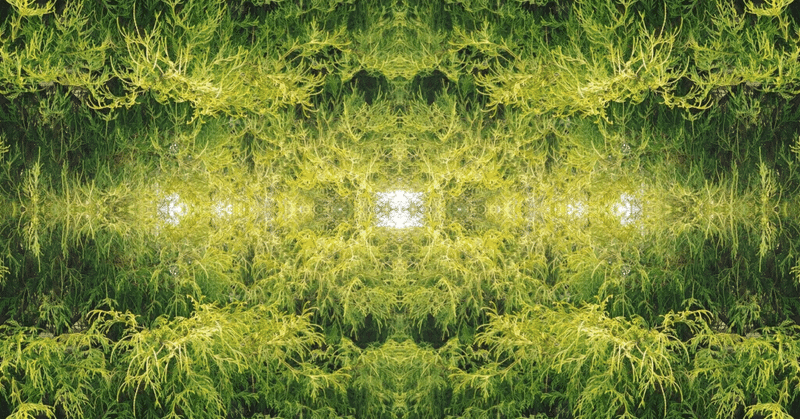
石山さんの読書会 田原さん『出現する参加型社会』
2021年4月17日、渋ドラでお世話になっている石山輝久さんに誘われて、ある読書会に参加させていただいた。
『出現する参加型社会』
田原真人さんの新刊を記念する読書会である。恥ずかしい話だけれど、僕はこの本を買わず読まずで参加させていただいたのだった。一応のこと、自分で自分のことを研究者だと名乗っている手前もあり、読書会の冒頭に設けられた自己紹介の時間にアマゾンでポチり、「先ほど購入させていただいたのですが・・・」と、なんとか面目を保つことに成功したのだった。
参加者の方々も多種多様で驚いた。クラシック歌手、アナウンサー、マーケター、美術家、、、。皆が皆、そうそう会えないような方ばかりである。司会者の方も誰もが恐ろしく聡明で、読書会はさながら国連か何かのサミットのような様相を呈していた。
「ボブさんみたいになりたかったんです。ボブさんって、本物のファシリテーターだと思ったから」
田原さんがそう話し出した。2015年に出会ったボブさんのようになること。田原さんの参加型社会の原点がボブさんにあった。僕は、意外なところで告白を聞いてしまったかのような気がして、すっと田原さんの話に引き込まれていった。
「ボブさんって、積極的に言葉を発しない人ですよね」
司会のたまこさんがそう言う。
「ええ。でも、最低一人でも自分の言った深い本音の言葉を受け止めてくれそうな人がいる。そんな場所だと、自分の深い本音を発することができる。その場を作れるのがファシリテーターだと思ってるんです」
「弱くても間が抜けていてもなんでもいい。弱さをジャッジしない。ジャッジしてしまうと、参加者がその場に即した良さそうなことを言うようになってしまって深い本音の言葉が出てこない」
「ただ、それってある種危ないというか、、、」
「ええ。なんでも言っていいって言ったけど、とはいえ、、、ってところが出てくる。ファシリテートしていて、流石にここまで外れた発言はマズイとか。ただ、そこから出てくるのが自分の生の本音なわけですよ。それが大事なんじゃないかなぁ」
僕が田原さんのお話に深く共感したのは、エフェクチュエーションと呼ばれる起業理論を理解する上で極めて参考になったこともある。エフェクチュエーションでは、ルールや計画ではなくて信念を重視する。ルールや計画というものは、人がそれに合わせねばならないものだけれど、信念は人が自身で使うためのものだ。この理論は人を人に回帰させる。
「僕はカオスって大事だと思っているんです。僕自身、パートナーと対立をして、その方との関係性を守るようにした時、アイデンティティが壊れてしまった。ただカオスから、今まで手に伸びなかった情報に手が伸びるようになったんです。それが自分を作っていった」
田原さんは因果論や機械論と、生命論とを対置させて考えていた。ルールや計画に従って社会を築くことも大切だけれど、人と人とが話し合って、ぶつかって、自然発生的に生じるコミュニティがなければ、僕たちから人間味が失われてしまう。
C.Gユングは、コンステレーション(星座のような布置)という概念を提出しているけど、人と人が話し合って、ぶつかって、を繰り返していると、いつの間にか必要な人が必要な場所にいる人間らしい社会が成り立つのだ。
「かつて消費者は一方的に商品を押し付けられていました」
マーケターの平賀さんが話し始める。
「今はCGMとかUGCとか、消費者主導のマーケティングが注目されています。consumer generated media(消費者主導によるメディア)、user generated contents(ユーザー生成コンテンツ)の略語で、アマゾンの書評とか、フェイスブックをみんな楽しみにしてるわけですよ」
かつて大学時代に読み耽ったアルビン・トフラーの『第三の波』に、「情報化が進むと消費者自らが生産者に回帰してゆく」とあった。そんなことを思い出していた。トフラーはそれをprosumer(プロシューマー)と呼んでいた。プロデューサー(生産者)とコンシューマー(消費者)を合わせた言葉である。人は再び自分自身で生産し始めたのである。
ここから、生産者の立場が極めて低いという話に移ってゆく。
「でもですね。宮城県の気仙沼なんですけど、農業従事者の給金は驚くほど低いんです。ただ生産に回帰すると言ってもそれは・・・」
「たしかにこれは極めて不思議な話だと思っていました」
もう耐えきれなくなって、僕自身も話に入れてもらった。
「僕、二宮尊徳が好きなんですけど、彼は『全員が農業に従事しても国は発展する。武士や商人ではそうはいかない。ただ、国の根幹であっても社会の基礎となるものゆえ、虐げられている。国の基礎となるものとは、大抵そういうものだ』って言ってるんです」
「今のエッセンシャルワーカーの人もそうですけど、なんでこれだけ大切なものが大切にされないんだろうって」
「それって支配者の信念体系だったんではないですかね」
司会のたまこさんがそう言ってくれた。
「自分たちで勝手に生きていかれると困る。だから支配者の信念体系に合わせた価値基準になってしまっているのではないかと」
たしかにそうだ。ルールや計画は、支配者の作るものだ。
M.ウェーバーは、
「資本主義以来、人は皆、王様や貴族になる機会を与えられた。王や貴族になろうとして絢爛に身を飾ろうとする意思が資本主義を形作った」
こう言っている。
「『食っていかれればなんとかなるよね』って意識に落ち着けば、なんとかなるんですけどね」
王ではなく、親になろうとする。成熟した社会とはそういうものだろう。ウェーバーも指摘しているが、いつしか人は、神や王になろうとしていた。その辺りに人類の悲劇があった。
「資本主義の魂とは、強欲そのものである」(M.ウェーバー)
そこでは愛が失われてしまったのだ。
「1次産業、2次産業、3次産業に進むにつれ、価値が高くなるとされています」
平賀さんがそう言ってくれる。
そう、そうだった。マルクスは労働にかかる時間によって、モノの価値が決まると話している。だから生地よりもスーツの方が高いのだと。それゆえ、計画やルール重視の社会にならざるをえないわけだ。時間のかかるものを組織して作らねばならないから。
経済学者の岩井克人氏が、週刊東洋経済のマルクス特集でこう語っていた。
「今、何の価値が下落しているかといえば、お金の価値なんです。人はお金で買えないものを重視するようになっている」
参加者のどなたかが、それからこう話してくれた。
「わたし、レールとかルールとか計画の中で暮らしているから、価値と自分とが切り離されてしまったような気がするんです」
ルールや計画は、それに人が合わさねばならないものだけれど、信念は人が自分自身で使ってゆくものである。それゆえ人が人に回帰するためには欠かせない。
エフェクチュエーションは因果論ではなく縁起論を説く。計画を敵視し、話し合いとかぶつかり合いから生まれる市場機会を重視するのだ。事業計画通りに進める起業というものは、起業素人が陥る間違いだとされる。そのために何が大切かと言えば、「あなたはいったい誰なのか」という個人の哲学なのである。それが対話を可能にさせるからだ。
哲学は成功と失敗とを超える。「ドン・キホーテがなぜあんなめちゃくちゃなことをしでかしたかと言えば、彼自身のことを彼自身がよくわかっていたからです」。エフェクチュエーションの生みの親、サラス・サラスバシーはそう語る。
起業家もそうだ。自分がどうしてもせねばならないことがある。だから何かをするのであって、カネのために行動している起業家は意外に少ない。ニーチェは『善悪の彼岸』で、哲学を持って動く人は、成功と失敗の基準から自由になると語っている。成功も失敗も、善悪ですら、他人が決めた基準に過ぎないのだと。
起業というと、ジョブズやザッカーバーグのように、一兆円稼ぐことをイメージされるかもしれない。人は600万円あれば家族を養ってゆける。700万円以上稼いでも、稼いだ効用はほとんど感じないという研究すらある。だから僕は、一人一兆円稼ぐ起業ではなくて、一人600万円稼ぐ起業社会を作りたいのだ。
社会は因果論から縁起論の時代に移った。
神や王になるのではなく、人として冒険し、恋をし親になり、子を作る。そしてまたその子が冒険に出る。
ある祭り好きの生徒が微笑ましくもこう豪語したことがあった。
「俺は神になる!」
僕はこう返した。
「お前ね、神になろうってやつと、神さまに頭を下げて祭りを盛り上げるやつと、どっちが格好いいんだよ」
「そりゃ、神さまに頭を下げて祭りを盛り上げるやつだら!」
人は神ではなかった。しかし人には人の役割があるのだろう。鈴木大拙が、「この世はあの世の奥の院」だと語ったというが、われらには祭りを盛り上げる役割があるのかもしれない。
「なにかワクワクすること、本当はやりたいんですよね」
最後、読書会はそんな参加者の言葉で締め括られたが、その通りだと思う。
なんとも得な役回りではないか、人というものは。

お読みくださいまして、誠にありがとうございます!
めっちゃ嬉しいです😃
起業家研究所・学習塾omiiko 代表 松井勇人(まつい はやと)
下のリンクの書籍出させていただきました。
ご感想いただけましたら、この上ない幸いです😃
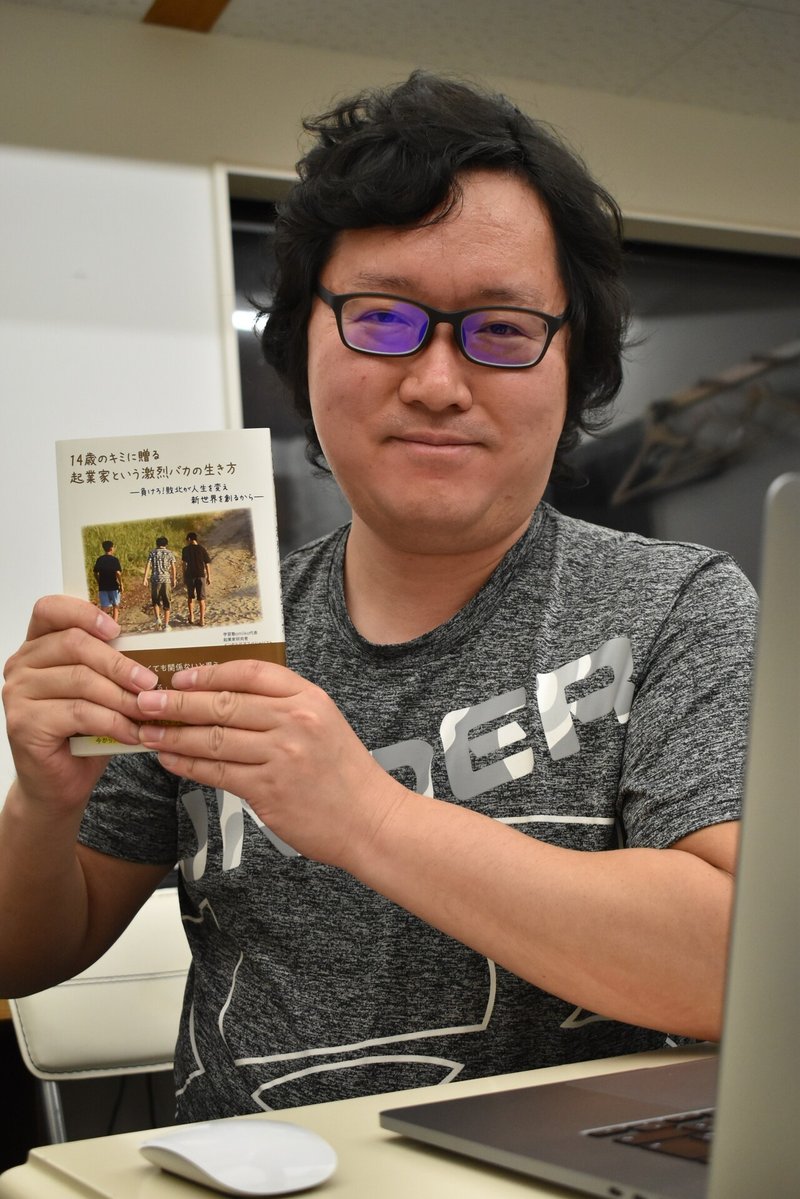
サポートありがとうございます!とっても嬉しいです(^▽^)/
