
ドローンで見た富士山頂火口の形成過程
この記事は、静岡県富士山世界遺産センターが2023年3月25日に刊行した富士山学3号に掲載した論文の提出原稿である。noteを利用して横書きで執筆したが、富士山学に印刷されるにあたって編集過程で縦書き処理された。編集される前のかたちで横書きでここに置いてある。富士山学では紙面に限りがあって写真と図を厳選したが、noteではそれがないので写真4枚と図4枚を追加した。すべての写真はクリックすると拡大する。とくにドローン写真は拡大して細部をじっくり観察することができる。
要旨 富士山頂火口縁からドローンを飛ばして火口内外の地層と地形を撮影した。それをじっくり観察して山頂火口の形成過程を次のように考察した。3140年前までは、富士山頂火口は西にいまより150メートル広い円形をなしていた。そのあと火口内側が次第に埋め立てられる過程で南西縁に剣ヶ峰ができた。2900年前に東側山腹が大きく崩壊したとき火口縁の東側5分の1が欠けた。崩壊した直後から山頂噴火を繰り返して、欠けた東縁に伊豆岳スコリア丘を構築しつつ火口内に金明水溶岩湖を湛えた。持続的な噴火は2300年前で終わったが、溶岩湖が冷却する過程で1800年前に大爆発して滝沢火砕流を北東に流した。火口内には大内院の大穴が残された。その後の噴火はすべて山腹から起こった。富士山頂火口は1800年間沈黙している。
0 はじめに
富士山頂火口は植生被覆がなく岩石と地層が全面に露出していて地質観察に最適な場所だが、意外にも研究は少なくてその形成過程がよくわかっていない。高地であることと積雪に覆い隠される季節が長いことによる調査困難がそうさせているのだろう。今回、ドローンを飛ばして山頂火口内外を隈なく写真撮影して、その形成過程を考察した。
1 ドローンの利点
富士山頂火口の形成過程を調べるときドローンを使うと、次に挙げる4つの利点が活用できる。
(1)航空機ほど高い位置からではなく、地上からわずか数十メートルだけ上昇した低空から観察できる。これは地形を見るのにもっとも好都合な高さである。大きな地層断面には、空中に浮かんで好きなだけ近づいて望むところを観察できる。
(2)麓から望遠鏡でのぞいても山頂火口内は見えない。火口縁まで登山しなければ観察することができないが、3700メートルの高所にある富士山火口縁の空気中酸素濃度は平地の3分の2だから、歩き回るとすぐ息が切れてしまう。ドローンを使えば、一か所に留まって移動することなく全域を望みの方角から接近して離れて観察できる。ドローンを火口底ギリギリまで下ろして観察することもできる。
(3)酸素が薄いと人の脳はうまく働かない。3700メートルの現地で深く考察するのは難儀だ。火口内をドローンで隈なく撮影してしまえば、平地に戻ってからゆっくり観察して考えることができる。
(4)球面パノラマ機能を用いて空中の一点から自動ですべての方向を隈なく撮影しておけば、あとから上下左右思い通りを観察することができる。
ドローンを飛ばすには、雲がなくて空気が澄んだ風がない日を選ぶ必要がある。この条件を満たす日が、2019年10月10日に訪れた。当日は、埼玉県の自宅を4時に出発して、富士宮五合目を起点終点とした日帰り登山を実行した。山頂火口には10時35分から2時間滞在した。バッテリーを4本持参したのでドローンを4回離陸させることができた。合計の飛行時間は68分だった。富士山頂火口全体をとらえた写真を1と2に示す。使用した機材は DJI 社の Mavic 2 Pro。4つのプロペラを持つ折りたたみ式ドローンだ。10月だったから積雪はすっかりなくなっていたが、日陰になった崖には大きなつらら氷が何本も垂れ下がっていた。


この論文を執筆しながら富士山頂火口の形成過程を考察していたら、もう一度山頂まで登ってドローンで撮影したい箇所、そして自分の目で直接確かめたい箇所がいくつか出て来た。天候を選んで、2022年9月16日に今度は吉田五合目から往復した。今回も無風快晴。山頂火口縁に10時05分に立って4時間滞在した。火口を一周する御鉢巡りもした。携行したのは新型ドローンDJI Mini 3 Pro。ズボンのポケットに入る大きさで249グラムと小型軽量だ。それでいて飛行時間は37分と長い。山頂の最高気温は15度で、この年一番暑い日だった。
2 山体崩壊は火口縁まで及んだ
富士山頂火口縁のうち東側5分の1区間(中心から見て75度の弧)は、2900年前の御殿場崩壊で失われて、そのあとすぐ再構築された。山腹斜面はこの方角だけがなめらかで、西山腹に刻まれた大沢や北山腹に刻まれた吉田大沢のような深い谷の切込みがない(写真3)。富士山の東山腹は、形成されてから時間がたっていない若い斜面なのである。

宮地ほか(2004)は、山頂に届かない東山腹斜面が崩れたと考えた。しかし、崩壊後に山頂火口から流出した大量の溶岩で馬蹄形凹地がすっかり埋まってしまったことを考えると、山頂火口を巻き込まずに崩壊したとみるのはむずかしい。もし山頂火口壁が手つかずだった場合は、どちらの方角が崩壊したかを富士山は知らない。崩壊した東側だけに向けて山頂火口縁から溶岩をせっせと流すことはできない。東が崩壊したことを富士山は知っていたのだ。崩壊は山頂火口縁まで及び、東縁が欠けて低くなった。そこから大量の溶岩が流れ出して山腹を下った。
富士山には山頂が二つあったが、2900年前の崩壊で東のピークが失われていまの整った円錐形になったとするツインピークス説(小山2013)もある。二つあったピークのうち、東のピークが崩壊したのに大量の溶岩は西の現存ピークから流出したとするのは不自然だ。火山が大規模に崩壊したあと大量の溶岩を流すのはよくあることだが、そのとき溶岩はいつも崩壊してできた馬蹄形凹地内の最上部に出現して地表を流れ下る。富士山の場合、東山腹の溶岩流はすべて山頂火口を出発点としている。途中にコブや段差は認められない。2900年前の崩壊は山頂火口まで及んでなければならない。
崩壊壁が山腹のどこを通るかを正確に決めるはむずかしい。その後に流出した大量の溶岩で馬蹄形凹地がほぼ完全に埋められてしまったからだ。それでも、小富士から望むと北側の崩壊壁がおおむね特定できる。須走口登山道は、崩れ残った古い山体の溶岩の上をよじ登るが、下山ルートは南にシフトして馬蹄形凹地内を流れ下った新しい溶岩を覆う厚いスコリアの上を駆け下る。砂走りだ。厚いスコリアに覆われた新しい溶岩の上は雪なだれが発生しやすくて地表が毎春更新されるため、樹木がまだ侵入できていない。山頂を極めた登山者は、地表にむき出しになった細かな厚いスコリアにかかとを踏み込んで愉快に駆け下る。
馬蹄形凹地の中の標高2000メートル地点に獅子岩と呼ばれる長さ600メートルのキプカ(新しい溶岩に囲まれた島)がある(写真3)。獅子岩は崩壊前からあった古い溶岩である。崩壊せずにその場に残った。溶岩裸地に囲まれながら東先端だけが樹林におおわれていて、典型的なキプカの様相を呈している。溶岩の傾きはいまの山腹斜面と調和的だから、この少し上にかつて東のピークが存在したとするツインピークス説は受け入れがたい。獅子岩のすぐ南の谷壁にも古い溶岩が小さく露出している。

崩壊で発生した御殿場土石なだれが残した堆積物の上には、噴火で降り積もったスコリアと火山灰がレス(風塵)を挟まずに何枚も厚く重なる(写真4)。レスは1000年で10センチ堆積するから、崩壊と噴火開始の時間差はとても短かった。富士山は、崩壊後ただちに噴火を繰り返して傷跡をすみやかに修復してしまったわけだ。この降下スコリア(群)は、宮地(1988)のテフラ層序で S-17, -18 あたりに相当するが、彼はスコリアの間に挟まれる複数の火山灰層を非噴火時に堆積したレスだと解釈したようだ。崩壊直後からしばらく富士山がひっきりなしに噴火したイメージを持たなかった。実際には、富士山は2900年前から600年ほど溶岩を休みなく流し続けて、2300年前までに傷跡をほぼ修復してしまった。2300年前は湯船第二スコリア(S-22)が噴火したときである。


欠けた山頂火口縁の北端と南端をドローン写真で特定してみよう。北端は、吉田口登山道が火口縁にたどり着いたまさにそこにある。浅間大社奥宮久須志神社の真下だ(写真5)。吉田口の山小屋群は、崩壊後に出現した伊豆岳スコリア丘最上部をなす溶結した赤いスコリア平坦面の上に建っている。南端は、伊豆岳と成就岳の鞍部にある。ここは荒巻と呼ばれる。伊豆岳スコリアの下には新しい溶岩が、成就岳の断面には古い山体が、それぞれ露出している(写真6)。伊豆岳のスコリアは成就岳の表面も薄く覆っている。
3 崩壊後にできた地層と地形
富士山は、2900年前に崩壊したあと馬蹄形凹地内の最上部からストロンボリ式噴火をしばらく継続して伊豆岳スコリア丘をつくった。いまの火口東縁はこれでできていて、火口内壁にスコリア丘の断面が大きく露出している(写真7)。中央に火道があって、左右両翼にスコリアが厚く積もっている。南翼(右手)のスコリアの下は崖錐に隠されるまですべて溶岩だが、北翼(左手)のスコリアの下の溶岩は薄く、その下に複雑な地層が露出している。黄・赤・青のパッチワークからなる部分は、できたばかりの不安定な崩壊壁から崩れ落ちた古い火山体だろうか。よく似たパッチワークが久須志岳と成就岳にも見える(写真7の左端と右下隅)。
伊豆岳スコリア丘の外側斜面を南東から撮影した(写真8)。スコリア丘の裾を3か所で破って溶岩が外に現れて斜面を流れ下っている。東山腹にできた馬蹄形凹地を埋め立てた大量の溶岩は、伊豆岳スコリア丘の成長とともに、こうやって裾から流れ下った。火口内壁に露出した伊豆岳スコリア丘の南翼が高いところまですっかり溶岩でできていることとよく符合する。溶岩の上にスコリア丘が乗る層序は、できた順番を意味しない。スコリア丘ができたあと、その下に溶岩が割り入ったとみる。


富士山は、江戸時代1707年も、平安時代864年も、山頂火口ではなく山腹斜面から噴火した。宮地(1988)は、山頂火口から起こった最後の噴火は2300年前の湯船第二スコリア(S-22)であって、山頂火口の南東半分にぽっかり開いた大穴である大内院はその噴火でつくられたと考えた。たしかに大内院の外形はくっきり角張っていて、最後の山頂噴火のとき地表近くにあった岩石を噴き飛ばしてできたように見える。この大穴ができたあと、富士山は山頂火口から噴出物をまき散らしていない。

今世紀になって、田島ほか(2013)が富士山北東斜面で新しい火砕流堆積物をみつけた。テフラ層序と放射性炭素年代測定によって、その噴火は湯船第二スコリアの500年もあとの1800年前に起こったことが明らかにした。彼らはこれを滝沢火砕流と呼んだ。吉田口登山道二合目と滝沢林道を結ぶ狭い林道脇で、私もこの火砕流堆積物を確認した(写真9)。滝沢火砕流は吉田大沢の「く」の字屈曲を無視して直進し、尾根をひとつ乗り越えて北東山腹に広がった。田島ほか(2013)は、吉田大沢が屈曲している標高3000メートル地点から噴出したと考えたが、そこに火口地形はない。もし屈曲点から噴火したなら、吉田大沢に沿って北に向かったはずだが、そうはならなかった。山頂火口から噴出して吉田大沢の屈曲を無視して直進したと考えたほうがもっともらしい。大内院はその爆発で噴き飛ばされてできた。滝沢火砕流は大内院から測って少なくとも8キロ流れた。その先は自衛隊の演習場になっているため調査がまだ不十分である。


大内院の西壁には溶岩湖の断面が大きく露出する。山頂火口が大きくくぼんでいた時代に、その中に灼熱の溶岩が満々と湛えられていた時代があったわけだ。深さは、露出しているだけで150メートルある。この溶岩湖は火山専門家の目をよく引くと思うのだが、これまで詳しく記載されたことはない。産総研の富士山火山地質図第2版(高田ほか2016)は、ここに溶岩湖を認めて荒巻噴出物に分類したに留まる。ここでは金明水溶岩湖と呼ぶことにする。すり鉢の底を挟んで南に孤立する虎岩も同じ溶岩湖の一部だ。
ドローンを火口内に下ろして金明水溶岩湖の断面を正面から撮影した(写真10)。真ん中に亀裂が垂直に走っている。亀裂の両翼ともに垂直な柱状節理が顕著だ。右端にある金明水も亀裂である。ここでは冷たい水が得られるそうだ。溶岩湖の冷却過程に複雑はなく、単純に一回で、そしてゆっくりと冷え固まったようにみえる。冷却に伴って若干収縮して地表がたわんでいる(写真11)。左手の剣ヶ峰に近づくにしたがって薄くなるが、上面の高さはあまり変わらない。溶岩が薄くなるのは上げ底による。溶岩に埋められる前の火口はすり鉢型をしていた。伊豆岳スコリア丘に連続するスコリアが均一の厚さで表面を覆っていて、その一部は溶結している。剣ヶ峰や白山岳の上にも乗っている。火口北西縁に鎮座する雷岩(写真12)もそうだ。宮地(1988)が見た湯船第二スコリアである。

金明水溶岩湖は伊豆岳スコリア丘と同時に形成されたと考える。2900年前に崩壊したあと、伊豆岳スコリア丘が徐々に成長して壊れた東火口壁を塞いだことによってすり鉢状の窪みができて、そこに溶岩が厚く溜まった。東山腹に出現した大きな馬蹄形凹地をほぼ埋め尽くすほど大量の溶岩が山頂火口から出たのだから、近くにもし窪みがあったら、そこを溶岩が埋めなかったはずがない。伊豆岳スコリア丘の南翼下半分をつくる厚い溶岩を再度よく観察すると、金明水溶岩湖とよく似た柱状節理が認められる(写真7)。 厚さ150メートルの溶岩が冷えるには100年単位の時間がかかる。2300年前に湯船第二スコリアを噴出したあと、地下からのマグマ供給が止まって溶岩湖が静かに冷却し始めた。温度が低下するに伴って内部の水蒸気圧力が高まって、500年後の1800年前に突然爆発して滝沢火砕流を出したのではなかろうか。金明水溶岩湖と伊豆岳スコリア丘の大きな断面はこの爆発で出現した(写真13)。

4 崩壊前からあった地形と構造
日本列島では火山の最高点が山頂火口縁の東寄りにあるのが普通だ。高空では西風が常時吹いていて噴出物が東側にたくさん積もるからだ。浅間山の最高点(2568メートル)は真東にある(図1)。羊蹄山の最高点(1898メートル)も真東にある(図2)。これに反して富士山では、最高点の剣ヶ峰(3776メートル、写真14)が南西にある。2900年前に山頂火口縁の東側5分の1を失う事件があったからだ。かつて東縁に剣ヶ峰より高いピークがあったが、崩壊して失われてしまった。



大きな円錐火山の山腹にできた馬蹄形凹地が、いまはほとんどわからないほどきれいに修復されたとするのは都合よすぎると思うかもしれないが、岩手山でも同様の修復が見られる。岩手山は6900年前に崩壊したが、馬蹄形凹地をほぼ完璧に修復して南部富士と呼ばれる整った円錐形に戻った。ただし、富士山ほどうまく修復されてない。山に近づいて山頂付近の地形をよく観察すると、東に開いた崩壊壁を北側に特定できる(写真15)。地理院地図の等高線にも屈曲として表現されている(図3)。


大円錐火山が山頂火口縁を巻き込んで崩壊したあと、馬蹄形凹地の最上部からただちに大量の溶岩を流して傷跡を修復することはめずらしくない。鳥海山は2500年前に日本海に届く大崩壊をしたあと、馬蹄形凹地内の最上部から溶岩を幾筋も流した。空中写真でよく観察できる。『日本三代実録』の貞観十三年四月(871年5月)の条に、二匹の大蛇が無数の小蛇とともに出現したとある。馬蹄形凹地の中を流れ下った幾筋もの溶岩を表現したのだろう。山体崩壊から1100年後だった。そのあと江戸時代1801年にも馬蹄形凹地の最上部に溶岩が現れた。いま新山と呼ばれるピークである。鳥海山の場合は溶岩の量がまだ全然足りなくて、馬蹄形凹地がその全貌をよく残している(図4)。

山体崩壊が及んで失われた火口縁はそこがもっとも低くなるから、地下から中心火道を上昇してきた溶岩は必然的に崩壊した方角に流れ下る。繰り返しになるが、もし山体崩壊が山頂火口縁に及ばなかったのなら、地表に現れた溶岩はどの方角の山腹が崩壊したかを知らない。その方角だけに溶岩を集中的に流して傷跡を修復することはできない。

大沢源頭部には不整合がある(写真16)。下位の地層は外側斜面と同じくらい急傾斜だが、上位の地層はそれよりずっと緩傾斜だ。外側斜面に層理断面が露出している。かつての富士山は、いまより大きな山頂火口を持っていた。西に150メートル大きかった。これによって山頂火口は直径820メートルの真円になる。いまの山頂火口は南北に長いが、優美な裾野を引く大きな円錐形を形成した中心火道が真円の開口部を山頂にもっていたのはたいへんもっともらしい。
富士火山地質図第2版(高田ほか2016)は、大沢に露出する幾重もの溶岩積み重なりをすべて須走-b期に塗色している。いまの富士山の整った大きな円錐形は須走-b期に形成されたと考えている。3500年前から須走-c期に移って、スコリアを空高く噴き上げるプリニー式噴火を富士山はするようになった。その最初期に噴出した仙石スコリア(3400年前)と大沢スコリア(3140年前)が大沢源頭部の不整合面を決定したのだろう。富士火山地質図第2版(高田ほか2016)によると、白山岳から久須志岳までに厚く露出する釈迦ノ割石アグルチネートが大沢スコリアに連続するという。大沢スコリアは山頂から噴出したとみてよさそうだ。このあとに続いた大室スコリア(3000年前)と砂沢スコリア(3000年前)は山腹から噴火したから山頂火口の形状に影響を与えていない。不整合面を覆う地層(剣ヶ峰を含む)は、それから2900年前までのあいだに起こった弱い噴火で積み重なった。
5 まとめ
富士山頂火口の地形と地質を図5に示す。大沢源頭部不整合が示す古い山頂火口の範囲をピンク線で、大内院の輪郭をオレンジ線で、示した。東に開いたパープル太線は2900年前に崩壊した範囲だ。山頂火口縁の5分の1を飲み込んだ。伊豆岳スコリア丘、金明水溶岩湖、虎岩、大沢、そして吉田大沢に着色した。

表1 富士山頂火口の層序
--------------------------------------------------------------------
1800年前 大内院 ⇒ 滝沢火砕流
金明水溶岩湖(冷却) = 虎岩
2300年前 ⇒ 湯船第二スコリア
伊豆岳スコリア丘
2900年前 山頂火口縁の東側5分の1が失われる
剣ヶ峰
3140年前 大沢源頭部不整合 ⇒ 大沢スコリア
3500年前 整った大円錐
---------------------------------------------------------------------
図5から富士山頂火口の形成過程を次のように読み取ることができる。表1に整理した層序を参照しつつ読んでほしい。いまの富士山の整った大円錐形は3500年前までに形成された。大沢源頭部不整合が示すそのときの富士山頂火口は、西にいまより150メートル広がった円形をしていた。不整合面は3140年前の大沢スコリア噴火で決定した。そのあと噴火の爆発力が弱まって大きな火口を必要としなくなり、火口内側に噴出物が少しずつ積み重なって剣ヶ峰を含む西縁ができた。
2900年前に東側山腹が大きく崩壊した。それは火口縁まで及んだ。崩壊後ただちに馬蹄形凹地内の最上部から噴火を繰り返して東側火口縁に伊豆岳スコリア丘ができた。伊豆岳スコリア丘の裾を破って大量の溶岩が東に流れ下ったが、一部は西のすり鉢状の窪みを埋めて金明水溶岩湖をつくった。その深さは150メートル以上あった。
馬蹄形凹地を溶岩で修復する噴火は600年続いたが、2300年前に湯船第二スコリアを出して終わった。そのあと金明水溶岩湖は静かにゆっくり冷え固まったが、500年後の1800年前に大爆発した。このとき滝沢火砕流が吉田大沢を下った。大内院の大穴はこの爆発でできた。そこにはいま金明水溶岩湖と伊豆岳スコリア丘の断面が露出している。
このあと富士山は、平安時代864年噴火で青木ヶ原溶岩を、江戸時代1707年噴火で宝永スコリアを、出した。どちらも噴出したマグマが10億トンを超える富士山最大級の噴火だった。この2回を含めて滝沢火砕流後の噴火すべてが山頂からではなく山腹から起こった。山頂火口は1800年間沈黙している。
引用文献
小山真人(2013)富士山 大自然への道案内、岩波新書、222p。
宮地直道(1988)新富士火山の活動史。地質学雑誌、94、433-452。
宮地直道・富樫茂子・千葉達朗(2004)富士火山東斜面で2900年前に発生した山体崩壊。火山、49、237-248。
田島靖久・吉本充宏・黒田信子・瀧尚子・千葉達朗・宮地直道・遠藤邦彦(2013)富士火山北東斜面の滝沢B火砕流堆積物の発生・堆積機構、火山、58、499-517。
高田亮・山元孝広・石塚吉浩・中野俊(2016)富士火山地質図(第2版)、産業技術総合研究所、地質調査総合センター。
付録 富士山頂火口の球面パノラマ。リンクをクリックすれば、あるいはスマートフォンでQRコードを読み取れば、上下左右を自由自在に閲覧できる。

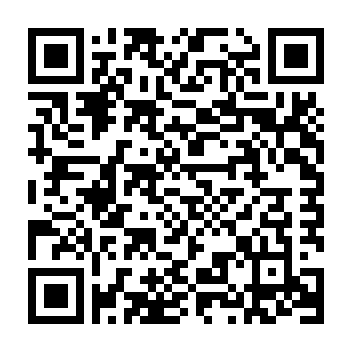
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
