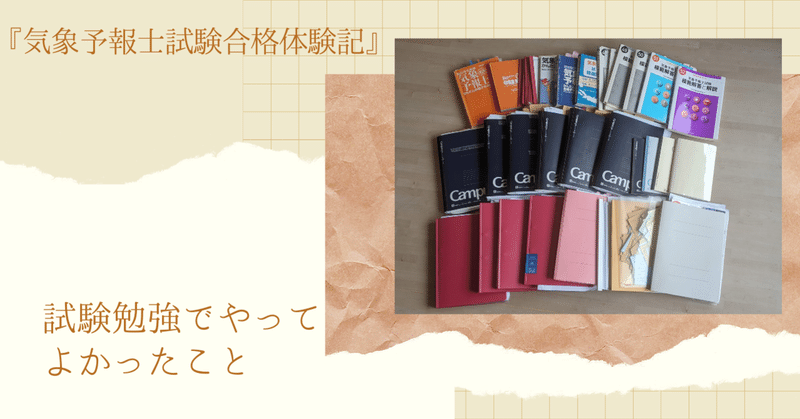
気象予報士になるために
2021年3月、3年間の勉強の末、4度目の気象予報士試験で無事に合格しました。気象予報士を目指す方にとって少しでも参考になればという思いで試験勉強でやってよかったことをまとめてみました。
気象予報士を目指すきっかけ
私は人道支援団体に勤務する30代の会社員です。普段は、海外で起こる自然災害に対し支援を検討したり、その広報活動をする仕事をしています。ときには日本国内で起こった台風災害などの対応にあたることもあります。近年では自然災害の規模が年々大きくなっており、残念ながら命を落とす方も大勢いらっしゃいます。
日本でも毎年梅雨時期になると毎年のように大雨災害が起こり、平成30年7月豪雨では死者数が250人以上となりました。こうした災害から人のいのちを守るためにはどうしたらいいのか、そしてそのために専門的な知識を得るにはどうしたらいいのか考える機会が次第に増えていきました。もちろん平時から備えることも重要ですが、人のいのちを守るために気象情報を正しく伝えたいという思いが強くなりました。それが気象予報士を目指すきっかけでした。
受験歴
過去の受験歴は以下のとおりです。なお私は理系の大学院を卒業しており、理科は比較的得意なほうで、計算問題にも苦手意識が少ないほうです。それを踏まえて以下読んでいただけると幸いです。
第51回 一般 〇 専門 × 実技 ×
第52回 未受験
第53回 一般 免除 専門 〇 実技 ×
第54回 一般 〇 専門 免除 実技 ×
第55回 一般 免除 専門 免除 実技 〇
一般・専門の勉強でやったこと
まず、気象予報士を目指す人がみんな登録しているといっても過言ではないめざてんサイトのメルマガ(メール講座)と本サイト内のめざてんメンバールームに登録をしました。定期的に気象予報士試験に必要な知識をメルマガで得ることができることと、10年以上前の過去問もダウンロードすることができるようになります。
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
