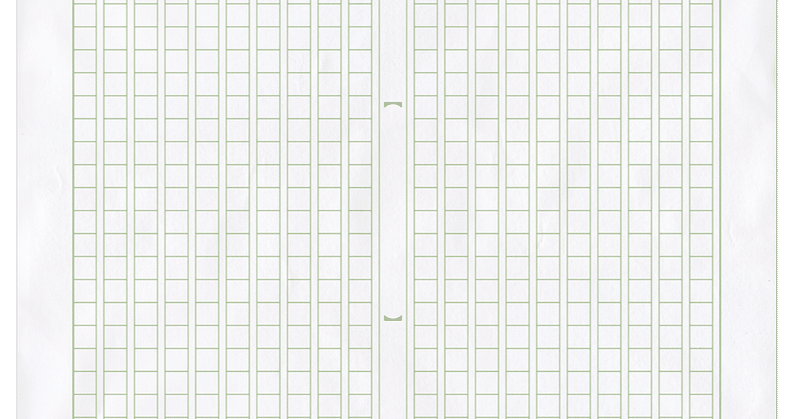
警察バディもの冒頭とプロット
公募に出そうとした短編の書き出しとプロットが残っていて、たぶんもう今後書かないやつなので、ここで「クソヘタでやんの」って笑って指さしてもらって供養します……ナム
2~3年前くらいでしょうか? 結構バティもの好きで、頑張って考えたと思うんです……でもいま読み返すと、ラブが少ないなってのは分かるので、少しは成長したのかなあ……タイトルも適当だなあ
すみません、以前noteに書いたことで嫌がらせ(?)されちゃったので、後半の恥ずかしいプロット部分は有料とさせていただきます。とはいえ、構成も萌えも全然ダメな内容です。こんなの書こうとしてたんだよオ~ってだけのプロットです。
タイトル「相棒はいらない」(4万文字程度を予定していたっぽい?
【書き出し】
髪を金色に染めたその少年は、F県警海原西署の門をくぐり自動ドアのエントランスに入ると、そこで手にしていた包丁を床に落とした。カーンという音ともに、包丁に付着した血液が白いフロアに飛び散る。居合わせた一般市民の女性の悲鳴が署内に響き渡った。少年はうつろな目で集まってきた署員に言った。
「人を殺してきました、たった今」
+++
「ノーヤンキー、ノーライフ! ヤンキー大好きミタカさんの薬物講座へようこそ……で、どう?」
F県警警察本部少年課のデスクで、同課の三鷹雪馬は同僚に演説の練習をしてみせた。26歳のわりには幼い顔をきらきらと輝かせて。
「却下。何だ、そのラーメン大好きナントカさんみたいなノリは」
スマートフォンをいじりながら、同僚の沖田が白けた視線を送ってくる。その沖田は突然「おっと、釣れた」と電話を取る。
「もしもし、ほのかちゃん? 今夜OK? ありがとう。えー警察? ナイナイ」
会話はまさに援助交際の交渉そのもの。彼はこうして出会い系サイトを使って18歳未満の少女を捜し、待ち合わせ場所のホテルで複数人で待ち構えて捕まえる、という『サイバー補導』を担当している。三鷹はと言うと、非行少年や引きこもりの支援をする少年育成指導官を務めている。今日の午後からは市内の教員を対象とした研修会で薬物乱用に関する講義を任されていた。
「ああ、緊張する」
後ろから「緊張されているところ申し訳ないが」と、薄毛の少年課次席がぬっと顔を出す。
「講義はいいからさ、今から二人で海原西署行ってくんない?」
沖田の運転で国道を飛ばしながら、雪馬は自分が持っている携帯ラジオを付けた。女性の声で臨時ニュースが流されている。
『17歳の少年は血痕のついた刃物を持参し「人を殺した」と自首してきたとのことです、海原西署によりますと――』
「17歳か。遺体は見つかってないんだろ? 猫とか殺したんじゃないか」
雪馬は海原西署からの応援要請ファクスを読みながら、そう希望的観測を口にしてみる。沖田も「そうだといいがな」と小さく返事をするだけだ。少年事件になると少年課が取り調べに立ち会わなければならない。今回は重要案件になる可能性があるとあって、署内の少年課ではなく、本部少年課へ応援要請が出されたのだ。海原西署によると、自首してきた少年は「殺した」という供述と、犯行場所、そして自分の年齢しか言わないという。
「俺の出番かな」
雪馬はファクス用紙を眺めながら、緊張と興奮の入り混じる気分を味わっていた。
海原西署に到着すると、同署の刑事管理官が迎えてくれた。取調室に向かいながら概要の説明を受ける。先ほど犯行現場に署員がかけつけ、倒れている男を発見し病院に搬送したとのことだった。
「すまない、被疑者は何も言わないし、うちの少年課には手に負えそうにないんだ」
「大丈夫です、ちなみに倒れていた男の容体は? そいつ何者ですか?」
雪馬が尋ねると管理官は少し躊躇したあと、こう漏らした。
「まだ息はあるが意識不明だ。名前は小倉文成――藤雲会の三次団体『雲竜組』のトップだ」
「ジーザス……」
藤雲会とはF県内にある指定暴力団の一つで、最も歴史の古い組織だ。その刺された男は、若くして三次団体の組長にのし上がったやり手だった。
「特捜は?」
沖田が、県警本部捜査四課――暴力団捜査担当の総本山――の応援の有無を尋ねる。管理官は「うちの署にいる特捜班は知らんぷり。未遂だし『少年課案件だろ』と言われたよ」と首を振った。「やだねぇ、タテワリ」と雪馬は苦い者を食べたときのような顔をして見せる。
「三次団体くらいじゃうまみがないんだろ、あいつらが虎視眈々と狙ってるのは藤雲会のトップ・野口だ」
沖田も同じように白けた表情を浮かべた。
詰め寄るテレビや新聞の記者たちを撒きながら、二階の取調室に上がる。署の二階はマスコミも含め、原則部外者立ち入り禁止なのだが一人だけしつこい記者がいて、沖田が対応するふりをして彼を足止めした。その間に取調室に入った雪馬は、マジックミラー越しに少年の様子を伺う。根元が伸びかけた金髪は痛んでいたが、細面のきれいな顔立ちをした少年だった。
灰色の壁に灰色の古い机、海原西署の少年課職員がほっとした表情を浮かべて雪馬に席を譲った。
「こんにちは」
雪馬は人懐っこい笑顔を浮かべ、その椅子を正面ではなく、少年の斜め前に移動させて座る。カウンセリングポジションと言われる位置だ。
「誰あんた、俺は何も話さねえよ」
金髪の少年は、古びた椅子の背もたれに寄りかかってキイと音を立てながら、ぞんざいにそう言った。
「今日はただの挨拶だよ。その恰好、お前『キタカン』だろ」
雪馬がそう何気なく言うと、少年は「なぜ知ってる」とでも言いたげに、背もたれから身体を起こした。『キタカン』とはこの一帯最大の暴走族『北関東爆走連合』の略。このあたりは暴走族がいくつもあり、少年育成指導官として非行少年と日ごろ触れ合っている雪馬は、反り込みの入れ方や目つき、髪型などで所属が大体分かるのだった。
「最近キタカンやってねーなと思ったら、走るのやめて暗殺集団にでもなったのか?」
無邪気な笑顔をわざと浮かべて、雪馬はそう煽った。
「キ、キタカンは関係ねえ!」
「だろ? ちゃんと話さないとキッチまで参考人で呼ばれるぜ?」
キタカンのトップである人物のニックネームを出して雪馬が頬杖を突くと、少年は「脅しかよ」と舌打ちをし、何かを言おうと口を開いた。
その時だった。取り調べ室の扉がノックもなしに勢いよく開く。そこから姿を現したのは、質のいいスーツに身を包んだ長身の男だった。切れ長の瞳に通った鼻筋――と一見美男のように見えるが、眉間には険しい縦じわが寄り、その殺気は明らかに堅気ではない。スーツを着ていてもかなりのトレーニングを受けてきたことが分かる、無駄な肉のない体つきだった。
雪馬はとっさに少年とその男の間に身体を挟み、両手を広げた。
「やめろ、こいつはこれからちゃんと裁きを受ける! やるんなら俺をやれ!」
暴力団のヒットマンが報復のために取調室に飛び込んできたと思った雪馬は、思わずそう叫ぶ。背後で少年が硬直しているのが分かった。
「は? 何言ってんだ」
長身の男が、冷ややかに雪馬を見下ろす「へ?」と間抜けな声を上げた雪馬に、刑事管理官が困ったように説明した。
「こいつ、うちの組織犯罪対策課の豊島。見た目はアレの人っぽいけど」
「アレってなんすか」
豊島、と呼ばれた長身の男はつまらさなそうにそうぼやくと、何も言わずに椅子に座り「今回の調べの担当の豊島です」と、にこりともせずにつぶやいた。
今回の事件は殺人未遂のため、本来なら強行犯を担当する海原西署の刑事一課が調べをするはずだ。しかし、現れたのは同署の、暴力団を担当する組織犯罪対策課(略して組対課)の捜査員。首をかしげる雪馬に、豊島が「被害者、俺が追ってた奴だったんでね」と不愛想に説明した。
雪馬はうなずきながら心で舌打ちをしていた。こういう見た目も態度も威圧的な捜査員がいると、非行少年の面談は非常にやりにくいのを経験上知っている。彼らは、今まで幾度も親や教師に押さえつけられたり裏切られたりしてきたため、そもそも大人を信じていないし、威圧的な大人に対しては相当のアレルギーを持っているのだ。
しかし、今取調室にいる少年の様子は違った。少し頬を染めて雪馬を見上げたかと思うと、照れくさそうに視線をそらし「聞きたいことがあるなら早く聞け」と口を尖らせたのだった。先ほどとは真逆の態度だった。
少年は筧淳と名乗った。父子家庭に育ったが、淳の中学卒業とともに父親は蒸発。北関東爆走連合のメンバーとなり、この1年半ほどは友人宅を転々としながら暮らしていたという。
「生活費はどうしてたんだ?」
雪馬の問いに淳は沈黙した。淳は使用した凶器や犯行状況などは詳しく供述するものの、被害者との関係や動機、そして今の生活費のように事件にかかわりそうな内容については黙秘を続けた。しまいには「刺せるなら誰でもよかった」と言い出す。
「あんな人けのない河川敷にヤクザが何の用で来るんだよ」
そんな不毛な押し問答が20分ほど続いたころ、ずっと横で黙って聞いていた豊島が、しびれを切らした。
「おい、いいかげんにしろよガキ……」
見目のいい人間のにらみとは、そもそもぞっとするものだが、この豊島という男は、本当に人を殺したことがあるのではないかと疑うくらいの強面なので、さらに凄みが増す。雪馬も淳も気圧され、案の定、淳は一言もしゃべらなくなってしまった。
「今日はこれくらいにしようか」
慌てて取り調べを切り上げ、豊島の背中を押しながら取調室を出た。そして、頭一つ分背の高い豊島を見上げて、詰め寄った。
「勘弁してくれよ、ああいう面談の仕方だと何もしゃべらなくなる」
「面談? 取り調べの間違いだろ」
豊島は鼻で笑って、こう続けた。
「どんなに優しくしても無駄だ。あいつらはしょせん社会の役に立たない極道予備軍だ」
その言葉に、雪馬はかっとなって豊島の、胸倉をつかんだ。といっても相手はびくともしていないが。
「お前に何が分かるんだよ、どいつもこいつも奴らを見下しやがって! これだから警察は嫌いなんだ」
「お前もその組織の人間だ」
「うるせぇ、俺は刑事でもなんでもねえ。少年育成指導官だ、肩書の通り奴らを立派な大人に育てるのが仕事なんだよ!」
雪馬は、つかんでいた豊島のスーツを放すと、律義にそのしわを整えてから、どすどすと足音を立てて取調室を去った。そしてそのまま刑事管理官のもとへと急いだ。もちろん、取り調べの担当を豊島から別の人物に変えてもらうためだ。しかし――。
「すまん、組対じゃ豊島がエースなんだ。本部が来るのに署員にヘマはさせられないって、署長直々のご指名なんだよ」
あっさりと断られる。あきらめまいと口を開いたところで、後ろから襟首をつかまれた。その犯人は少年課同僚の沖田だ。
「ええ? おれ一人で?」
沖田だけは本部に戻るよう課長に命じられたという説明を受けた雪馬は、悲鳴に近い声を上げた。
「しょうがないだろ。うちは今サイバー補導でウハウハだから、この手が通用するうちに数字上げときたいんだよ」
沖田は、それに一人じゃないだろ、とロビーで腕を組んで仁王立ちしている男をちらりと見る。先ほどの捜査員、豊島だった。
「嫌だよ、あいつの目ぇ見た? 絶対3人は殺してるぞ」
「泣きごとを言うな、それでも警官か」
「俺は福祉職採用ですう」
泣きつく雪馬をハエのように追い払って、沖田は一人で県警本部に帰ってしまった。取り残された雪馬は、署の入り口で沖田の車を恨めしそうに見送る。すると、その横に豊島が音もなく肩を並べて、横目で見降ろしてきた。美形ではあるが、こうも仏頂面では取り付く島もない。雪馬は、ぞんざいで威圧的なこの男とうまくやっていく自信がみじんも湧かなかった。
「あんた……歳いくつ」
雪馬が口を尖らせながら訪ねると、25歳だと返ってきた。すると、雪馬はパッと表情を輝かせて、生意気そうな顔で豊島を指さした。
「はーい、俺の方が年上でしたァ! 敬えよ? 俺の言うこと聞けよ?」
突然先輩風を吹かせた雪馬に、豊島は小さくため息をついて「ついてこい」と署の中へ入っていた。
「命令するな、俺は先輩だぞ!」
しつけのなっていない犬のように吠える雪馬は、豊島の背中を追いかけながら拳を振り上げた。
+++
夕方にもう一度面談したものの、淳は何もしゃべらなかった。
「小倉のところに行ってみるか」
豊島がそう提案すると、雪馬は賛成しつつ「先に会いたい奴がいる」とスマートフォンの通信アプリで、ある人物と連絡を取った。
数十分もしないうちに、バイクの騒音が署の駐車場で響く。そのブォンブォンというエンジンの吹かし方を聞いて、雪馬は「今日は機嫌がいいな」と笑いながら駐車場へと向かった。豊島を取調室の裏に待機させて。
そこには、真っ赤な特攻服の男が、改造されたバイクにまたがっていた。
「久しぶり、三鷹サーン」
見るからに暴走族のその男は、サイレンサーのついていない直管マフラーで爆音を立てながら手を振る。頭には、申し訳程度に工事現場の「安全」と書かれたヘルメットをかぶっていた。
「おー、キッチ! 今日はヘルメットかぶってるじゃん」
雪馬が親し気に駆け寄ると、キッチと呼ばれたその男は「三鷹さんが困るかなと思って」と照れたように鼻の下を掻いた。
署の1階に職場を置く交通課から、マル走班(暴走族取り締まり担当)の白バイ隊員数人が出てきて「おい、あいつキタカンのアタマだ」と騒ぎ出す。豊島も、二階の窓から北関東爆走連合の総長と親友のように話している雪馬を見下ろして、無言で目を丸めていた。
雪馬は交通課の面子に、キッチが殺人未遂事件の参考人であることを告げて、彼を署の中へと案内した。
「おれ、パクられた以外でサツに来たの初めて」
取調室に入ると、椅子に座ったキッチがそわそわしだした。雪馬はキッチと向き合って口を開いた。
「いきなりで悪いけどさ、お前んとこの筧淳が殺人未遂で捕まったの知ってる?」
少し浮かれていたキッチが、表情を深刻なものに変える。
キッチの話では、筧淳は北関東爆走連合の中でも見た目の華やかさから人気のあるメンバーだったという。親の蒸発もキタカンの中では特に珍しい話ではなかったが、その割には金に困っていないのが不思議だったという。
最近変わったことがなかったか尋ねると、キッチは少し考えてから、こう漏らした。
「最近いきなりいなくなることが増えたんだよな。そんで不思議なのが、バイク置いていくんだよ。バイク預かってるやつがブツブツ言ってた」
雪馬は被害者である小倉の名前を告げてみると、キッチは椅子から転げ落ちそうなほどのけ反った。
「えっ、こ、小倉さん……!」
キッチの話では、小倉は非行少年に優しいと評判のやくざだった。
「煙草1コのパシリに万札出して『釣りはやる』って言うんだよ。家族がいない奴らには『俺を兄ちゃんか若いオヤジだと思って頼れ』って言うから、惚れこんでるやつらがうちにもいっぱいいるよ。なんでそんないい人を……」
キッチとはその後、簡単に世間話をした。彼女が妊娠したため、キタカンを引退するのと同時に籍を入れ、鳶職人の元に弟子入りするという。
「お前ならやれるよ。ピンチのときは連絡しろよ」
「俺、ミタカ学級も卒業だな」
ミタカ学級とは、雪馬がかかわった非行少年たちの誰かが言い出した名称だった。
「ばーか、学校じゃないんだから卒業なんてねえよ。いつでも連絡してこい」
そう言って、雪馬はキッチのリーゼントをぐしゃぐしゃとくずした。キッチはマジックミラー越しに豊島が見ているとは知らず、雪馬に本音を漏らした。
「小倉さんがさ、『兄だと思って頼れ』って言ってくれたとき、俺は三鷹さんの顔が浮かんだよ。俺の兄貴は小倉さんじゃない、三鷹さんだよなって」
「ははっ、俺か! 優秀じゃないかキッチ、百点やる!」
「学校じゃ取ったことなかったけどな、百点」
未就学児のうちに親が離婚し、引き取った母親から育児放棄されながらも必死に生き延びてきたキッチを知っているだけに、雪馬は笑いながら目頭を熱くした。
「今度は百点満点の親を目指せ」
「ああ、頑張るよ。お先に悪ぃな、独身の三鷹さん」
それがキッチ一流の照れ隠しだと分かっている雪馬は、「うるせぇ」と殴るふりをして見せた。
駐車場でバイクにまたがったキッチを見送りながら、雪馬はひとつ気がかりを口にした。
「お前、引退ってことはひと騒動やるのか?」
キタカンのトップが交代するときは大規模な暴走をすることを思い出したのだ。キッチは八重歯を見せて首を振った。
「静かに消えるよ」
「派手好きが珍しいな」
キッチが「喧嘩も走りも見た目も完璧」とあこがれている5代前の総長が、そうやって引退したのだという。
爆音を立てて海原西署を去るキッチを見送ると、いつの間にか雪馬の後ろに豊島が立っていた。雪馬は構える。どうせまた、キッチのことを悪しざまに言うのだろう。しかし――。
「あいつ、親になるんだな」
そう言って、豊島は爆音の響く秋空を眺めながら目を細めた。そして、雪馬に視線を寄越し、じっと見つめてくるのだった。
「な、なんだよ」
「別に。落ちこぼれかと思ってたが、案外まともに仕事してるんだなと思って」
無表情だった豊島の口の端が少し上がった。雪馬は、初めて見る豊島の表情の変化にわずかに気分を浮つかせながら、こぶしを振り上げた。
「そこは『別に』で終わっとけっ」
「はいはい。さっさと小倉のとこ行くぞ、車に乗れ」
先輩に命令するな、と幼顔を膨らませながら、雪馬は捜査車両に向かって歩いていく豊島の後ろを追いかけた。
++
(原稿はここで途切れている)
【プロット】
ここから先は
¥ 300
いただきましたサポートは、小説の資料購入などに活用させていただきます!!
