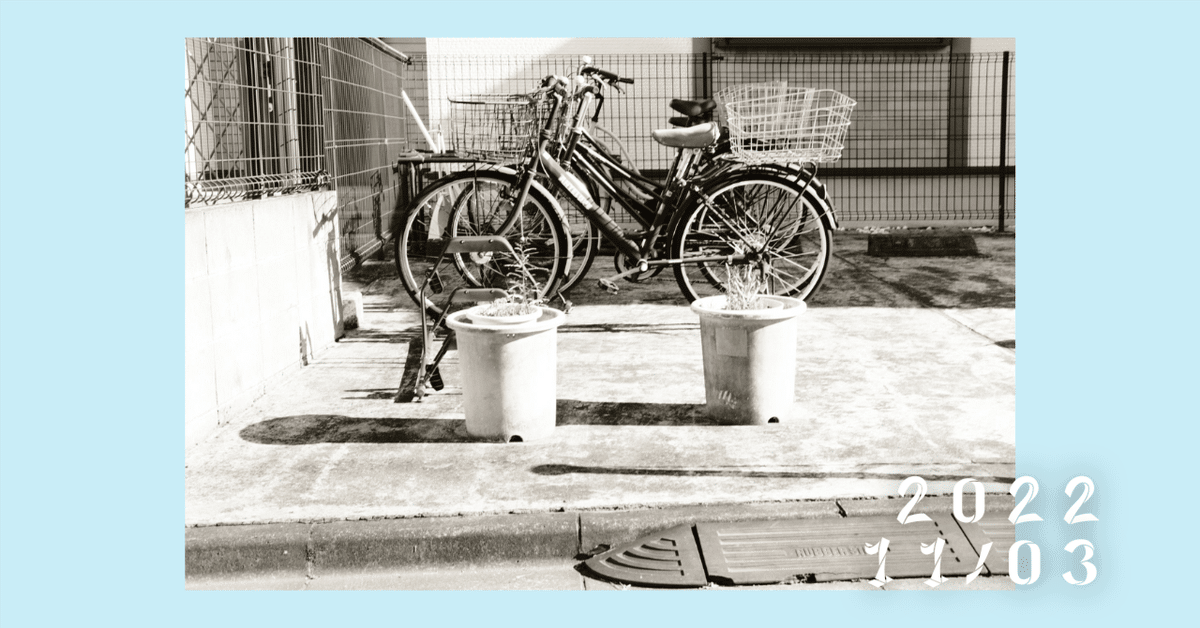
2022/11/03
アメリカで最初の大学であるイェール大学では、1764年に女性学・ジェンダー学学科が設立されました。1867年、米国議会で初めてマサチューセッツ州から女性が下院議員に選出される。1869年、マサチューセッツ州で初めて女性に州全体の選挙権が認められた。
1940年代後半、日本ではフェミニズムが影響力を持ち始めた。戦後の日本の女性や少女の世代は、社会における性の役割や女性の役割についての考え方を変え始めていたのです。1972年には、日本人の女性ノーベル賞受賞者が3人誕生し、25人以下だった女性の大学講師や研究者が1977年には16万人以上に増えていた。
1973年に制定され、1970年代後半から1980年代前半の自民党政権下で継続された日本政府の「女性活躍推進プログラム」は、アカデミックな場でのセクシャルハラスメントの問題に取り組み始めたのです。
戦後日本の女性の人権活動家として最も有名なのは、萩秋子教授である。彼女は1950年代から60年代にかけて、地方の大学都市で大学教授をしていたが、自らもセクシュアル・ハラスメントの被害者であった。1972年、彼女は法制度を通じて多くの事件の第一審で勝訴した。また、萩原は日本における反強姦運動の中心的な人物の一人である。
1973年に創設され、1970年代後半から1980年代前半の自民党政権下で継続された日本政府の「女性活躍推進プログラム」は、1980年にアカデミックな場でのセクハラ問題への取り組みを開始した。このプログラムは、少数の学者と学生で構成される「指導委員会」が、新任の教員や学生の研修に取り組むことから始まった。フェミニスト運動の影響もあり、このプログラムは、セクシャルハラスメントの問題を含め、大学キャンパスにおける男女の分離の問題にも焦点を当てました。このプログラムは、より多くの女性がアカデミックなキャリアに就くことを奨励することを目的としていました。また、このプログラムは、大学におけるセクシャルハラスメントや男女隔離の問題に対処することも目的としていました。
女性の平等とセクハラをめぐる議論は、1982年の「踊る女教授」事件に代表されるように、時に強い反米主義を特徴とした。セクハラ問題の根本原因をアメリカの「リベラリズム」に求める学者もいて、日本の女性教授の多さを非難していた。(本号の「日本の女性人権活動家のセクハラ闘争とジェンダーの政治学」参照)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
