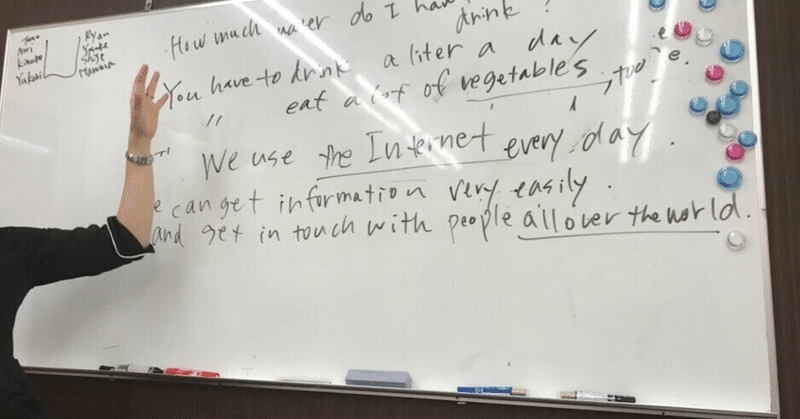
鉄緑会 〜AとBの違い〜
こんにちは!今回は鉄緑会のクラスの違いについて紹介します!鉄緑会については以下のリンクをご覧ください。
鉄緑会のクラス
鉄緑会にももちろん実力によるクラス分けが存在します。大阪校では上からSA、A1、A2、A3、Bとなっています。科目によってはAの中での違いはないものもあります。クラスは年に2回行われる校内模試で決まり、そのほかのテスト結果は一切加味されません。
大阪校のシステムは東京校と異なるようですね。東京校はレギュラーとオープンなんだとか。
今回は大阪校のクラス分けについてお話しします。東京校は全くわからないのでね。
B帯
BクラスというのはA帯(後程紹介)未満の人のクラスです。週に8クラスほどありますが、レベルは同じです。京都校ではKクラス、西宮校ではNクラスと呼ばれます。
SA
SAは鉄緑会の最上位のクラスです。SAは私もなったことがないのでわからないのですが、話を聞く限り、化け物の集団です(良い意味で)。鉄緑会の中でも飛び抜けてできる人が行くところです。このクラスにいる人は余裕で京医や理Ⅲに受かります。羨ましい。
また、鉄緑会の講師は大体SA出身のようですね。…当たり前か
A
AはSAの次にレベルの高い人が集まり、SAも含めて鉄緑会の上位層のことをA帯と呼びます。時たまにそこまで賢くないのに校内模試で奇跡的に良い点をとり、A帯に入ってしまう人がいるのが特徴です。SAにはそんな人は絶対にいませんが。
授業・宿題の違い
まずは、授業の違いについてです。B帯では、2周目の単元であっても、基本事項の確認から入ります。そして、例題の解説を丁寧に行い、授業が終了します。その一方で、A帯では。基本事項の確認はもはやされません🤣「これくらい常識だよな?」の一言で終わらされます。初っ端から例題。例題は解き方を解説されて答えは出してくれないことも多々あります。以下略みたいな。
そして、A帯の1番の特徴が居残り課題です。正解するまで帰れません。22:00になったら解放してくれる先生もいますが、22:30くらいまで残らされることもあります。鉄緑生は10時コースと言ったりします。先生は先生で早く帰りたいので前で「早くしろー簡単だろー」と言っているのですが、普通に難しいです。
次に、テストの違いです。B帯は基本的に復習テストは35分、計算テストは10分で行われます。A帯の復習テストは45分、計算テストは5分(ときには3分)です。計算テストの問題はAとBで共通ですが、復習テストの問題はAとBではかなり違います。Bは宿題となる問題集や例題からの出題がメインですが、Aでは、入試の過去問からの出題が主だったりします。数Ⅲの積分を初めて習った時の復習テストが東大の入試だったのには驚きました💦
最後に宿題の違いについてです。使用する問題集は同じですが、Aでは、大量の追加プリントが出されます。その量のまあ多いこと。
校内模試の平均点
鉄緑会のクラスは校内模試のみで決まります。それでは、各クラスの平均はどれくらいなのでしょうか。(120点満点)
数学
SA→99.6 A1→75.8 A2→75.6 A3→63.9 B帯→大体40くらい?
英語
SA→93.6 A1→84.5 A2→81.8 A3→75.4 B帯→大体58くらい?
やはりSAとA、AとBの間の点差はとても大きいですね。学年が上がるごとに点差は開いていくようです。SAのメンバーはほぼ固定、A帯もほとんど固定になるので、BからAに上がるのは相当頑張らないとダメだということを示していますね。
こうしているとAクラスが天才の集団のように思えてきますが、実は一学年の約25%がAクラスです。こう考えるとAクラスに行けそうな気分になりますよね。頑張ってください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
