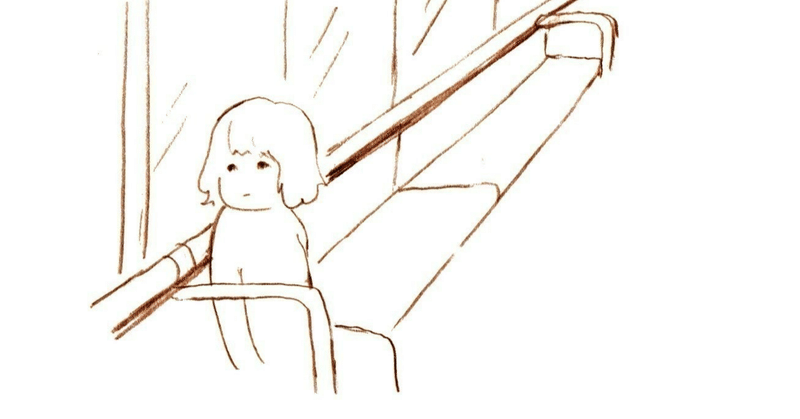
認知症を知ることが入院中の高齢者を救う!せん妄の発症について解説
第一人者が教える 認知症のすべて】
せん妄は、突然発症する精神機能の障害のこと。高齢者に特に多く、一般的な医療機関に入院した70歳以上の高齢者では、3分の1がせん妄を経験。その半分は入院時点でせん妄となり、残りの半分は入院中にせん妄を発症するといわれています。何かひとつの因子が関係しているというより、複数の因子が関係して引き起こされます。このせん妄、認知症との関連性が強く、双方に関連しています。つまり、せん妄があれば認知症になりやすく、また認知症がせん妄を生じやすくするのです。
せん妄とは?
せん妄は、精神機能の突然の障害であり、高齢者に特に多い症状です。70歳以上の高齢者の3分の1が、一般的な医療機関に入院した際にせん妄を経験するといわれています。その半数は入院時点でせん妄となり、残りの半数は入院中にせん妄を発症するとされています。せん妄は、単一の原因ではなく複数の因子が関連して発生します。また、せん妄は認知症と密接に関連しており、双方に関連しています。つまり、せん妄があると認知症にかかりやすく、また認知症があるとせん妄を生じやすくなるということです。
フィンランドの後ろ向きコホート研究によれば、せん妄がある人は認知症の発症リスクが高く、重症度とも関連しています。また、せん妄の既往がある群は、認知症の検査「MMSE」のスコアが年間1点以上多く低下するという結果も報告されています。MMSEは1問につき正解1点で、30点満点中27点以上取得すれば「問題なし」とされ、それ以下の場合は「軽度認知症疑い」「認知症疑い」となります。
イギリスの後ろ向きコホート研究によると、せん妄は2年後の認知症の有病率の増加と関連しています。
せん妄は複数の因子が関係しており、そのリスク因子は「素因」と「促進因子」に分類されます。素因が多いほど、促進因子が少なくてもせん妄を発症しやすくなります。高齢はせん妄素因のひとつであり、若い人では問題ない促進因子でも高齢者にはせん妄を引き起こすことがあります。
せん妄のリスク因子には、「素因」と「促進因子」
素因は、せん妄を引き起こす原因となる要因であり、高齢や慢性疾患の存在、遺伝的素因などが含まれます。高齢者は、脳の構造や機能の変化があるため、せん妄の発症リスクが高くなります。また、慢性疾患を抱える人は、病気による身体的負担や薬剤治療の影響によって、せん妄を発症する可能性が高くなります。遺伝的素因に関しては、脳の機能に関連する遺伝子の変異がせん妄の発症リスクに影響することが報告されています。
一方、促進因子は、素因に加えて、せん妄を引き起こすトリガーとなる要因です。例えば、感染症、手術、薬剤治療、外部の刺激、睡眠不足、過度なストレスなどが挙げられます。これらの要因が素因に加わることで、せん妄の発症リスクが高まるとされています。
また、素因や促進因子以外にも、食事、運動、ストレスの管理などのライフスタイル要因もせん妄のリスクに影響することが知られています。適切な栄養や十分な運動、睡眠などを維持することで、せん妄の発症リスクを軽減することが期待されます。
せん妄の予防が認知機能低下の予防につながる
せん妄とは、意識や注意力、認知機能、感情、睡眠-覚醒周期に影響を与える精神機能の障害のことを指します。精神疾患の国際的な診断基準「DSM-5」では、「意識と注意の障害」「認知の全体的な障害」「精神運動障害」「睡眠-覚醒周期の障害」「感情障害」が程度に関係なく起こるとされています。
せん妄の症状としては、ぼんやりとした状態、幻覚や妄想、注意力の散漫、夜間の興奮、睡眠-覚醒周期の障害、感情の不安定さ、入院中に点滴やチューブを自分で抜いてしまうなどが挙げられます。ただし、これらの症状はすべてが必ずしも現れるわけではありません。
せん妄と認知症は密接に関連していますが、現在認知症ではない場合には、せん妄と認知症を区別する必要があります。せん妄の促進因子を除去することで、せん妄を予防し、認知機能低下につながることを回避することが望まれます。
せん妄と認知症の違いとしては、まずせん妄の発症が急激であること、初期症状が幻覚や妄想などであり、認知症の記憶障害とは異なることが挙げられます。また、せん妄は夕刻から夜間に発症することが多い一方、認知症ではそういった変動は少ないです。さらに、せん妄の症状は一過性で、数時間から数日で治まります。改善した後は、発症前と同じ状態に戻りますが、認知症の場合はそうではありません。
せん妄には、過活動型、低活動型、混合型の3つのサブタイプがあります。過活動型は、24時間のうちで運動活動量が増加し、活動コントロールが障害されます。一方、低活動型は、24時間のうちで、活動量や発語量の低下、活動速度や発語速度の低下などが見られます。混合型は、過活動型と低活動型の両方が見られることがあり、急速に変動することもあります。
せん妄の素因や促進因子を除去することで、せん妄を予防したり、改善することができます。具体的には、感染症や薬剤の過剰摂取などを避け、適度な運動や十分な睡眠をとること、ストレスを避けること、規則正しい食生活を維持することなどが挙げられます。また、せん妄が発生した場合には、その原因を特定し、適切な治療を行うことが必要です。
最近では、せん妄に対する認識が高まり、予防や早期発見に取り組む取り組みが進んでいます。例えば、せん妄の発症リスクが高い高齢者に対して、病院内の環境を整えることでせん妄を予防する取り組みが行われています。また、せん妄を早期に発見するために、病院などでの定期的な認知機能検査や、医療従事者への教育・トレーニングなども行われています。
総じて、せん妄は高齢者に特に多く発生する精神機能の障害ですが、適切な予防・治療を行うことで、認知機能低下やその他の合併症を回避することができます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
