
わかりやすい!中医学の基礎Vo.17〜病邪について〜
今回までで、『気血津液』と『五臓』についての説明が終わりました。
中医学は、その昔、今のような検査方法もなく、人体の生理機能などもわかっておらず、ウイルスや細菌などもその存在が明確にはされていなかった時代に、なぜ人が体調が悪くなったりに重い病になったりするのかを、豊な想像力で説明し、養生法、治療法を経験の中から見出してきたものです。
『気血津液』も『五臓の役割』も、そう考えるとうまくいったという積み重ねのもとに考えられたものです。
現代に生きる私たちは、西洋医学の恩恵を多大に受けていることは否定できませんが、西洋医学では治しきれない症状が漢方薬で軽くなるということも多く見られます。
人のからだには、検査や規定の治療法では説明できない自然とのつながりがあるのでしょう。
今回からは、私たちのからだがバランスを崩す原因となる『病邪』について学びましょう。
病邪の分類
病邪には、大きく
①外因性(季節性のもので自然環境ではあるが、時として私たちのからだが不調になってしまう原因となる)
②内因性(私たちの感情としてあるものが、時として行き過ぎた場合に私たちのからだを不調にさせる)
③その他(生活の乱れや過労、環境の変化など私たちの日常生活に関係するもの)
があります。
外因性:六淫の邪
外因性のものは『六淫の邪』とも呼ばれ、
1 風邪
2 寒邪
3 暑邪
4 湿邪
5 燥邪
6 火邪
の6つに分類されます。
1 風邪
風邪は、『百病の長』と言われ、全ての病気の元となったり体内に他の病邪が侵入するきっかけとなるものです。
発病が急で、鼻・口・喉などの上部を侵しやすく、
また、病の位置が固定せずにあちこち変わる(蕁麻疹などで出るところがあちこち違う、痛いところがあちこち変わるなど)
という特徴があります。
今の病気に当てはめると、急性の上気道炎や急性蕁麻疹などが該当します。
2 寒邪
寒邪が体内に侵入すると、体内を温めるための『陽気』を損いやすく強い冷えを感じます。鼻水や尿が無色透明になることが特徴です。
また、患者は、凝滞(とどこおること)の性質を持つため冷えて血行が悪くなり『しもやけ』などができやすくなります。
また、収縮の性質もあるため、毛穴が縮んで汗が出ずブルブルと震えるといった風邪の初期にも該当します。
3 暑邪
夏の暑い日などに体内に侵入し、病気を引き起こす邪気です。
からだが熱くなり、汗が多く、心臓がドキドキする、喉が乾く、
全身の倦怠脱力感 尿量が少なく色が濃いなどの熱中症の症状などに該当します。
4 湿邪
梅雨のジメジメした時期に体内に侵入しやすい邪気で、湿度が高い環境に長くいた場合や、居住地が多湿の場合にからだに不調を及ぼします。
体が重だるい・手足がだるい・口の中がネバネバする・おりものが粘っこい・足のむくみ
などを引き起こす邪気です。
日本は、湿度が高い環境が続くことが多く、湿邪による体調不良が多く見られます。
5 燥邪
晩秋の乾燥する時期にからだに侵入しやすい邪気で、鼻や喉の乾燥・空咳(痰は出ないが咳が続く)・口が乾きやすい などの症状をひき起こします。
6 火邪
上炎の性質を持ち、他の病邪とくっつくことが多い邪気です。
例えば、悪寒よりも発熱・高熱が目立つインフルエンザや急性扁桃炎などは、風邪と火邪によるものです。
ひどくなると、精神症状(心煩、不眠、せん妄)や口内炎・目が腫れる・尿量が少なく黄色いなどの症状が表れます。
何の邪がからだの不調の原因となっているのか?を症状から推測することは、漢方薬を選ぶ上でとても重要となります。
まとめ





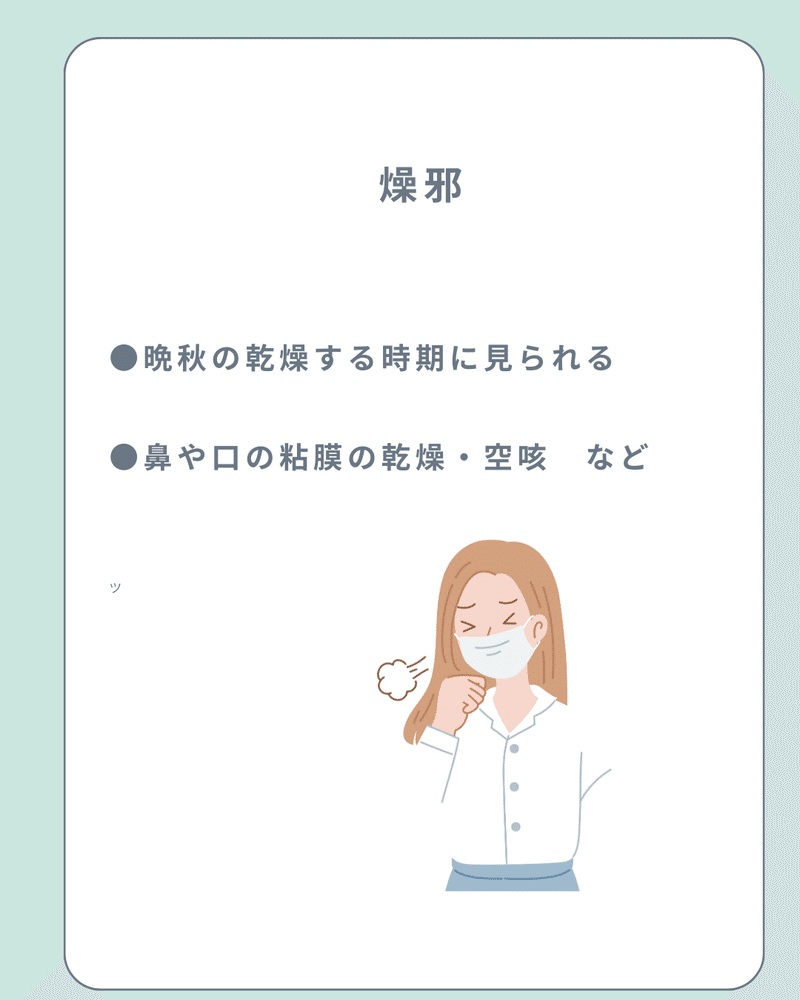

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
