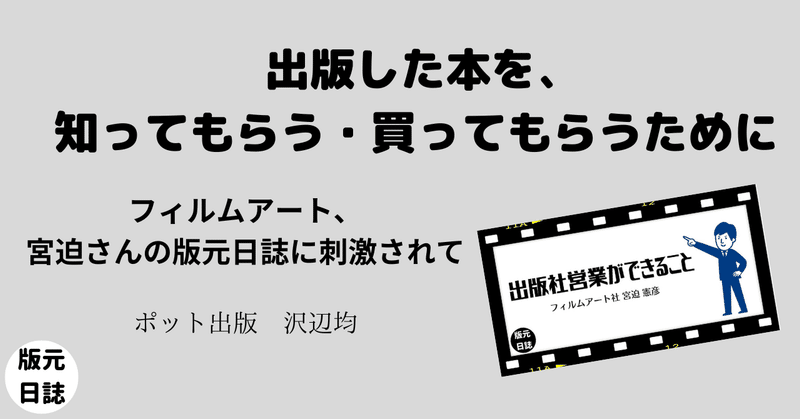
出版した本を、知ってもらう・買ってもらうために フィルムアート、宮迫さんの版元日誌に刺激されて
ポット出版 沢辺均
この「版元日誌」は版元ドットコム会員社が、毎週、あいうえお順の交代で書いてる。
会員社が増えて500社くらいになったので、一度書くと10年まわってこないことになる(500社÷52週=約10年)。実際には、ちょうど忙しかったりして辞退するする会員も多いので数年でまわってくるようだけどね。
先々月の2022年10月19日の版元日誌でフィルムアート社の宮迫さんが書いた「出版社営業ができること」にはいろいろ教えられたんでそのことについて書いてみる。
宮迫さんは、大手チェーン書店で西日本のお店に10年近く働いてから、版元・フィルムアート(東京)で「ひとり京都支社」的に働いてるそうだ。
なんと2017年からは、京都市内で小さな書店(副業)を経営もしてる。
宮迫さんの版元日誌には、その書店は書いてなかったけど、勝手に調べたらこんな記事もでてきた。
https://rurubu.jp/andmore/article/15483
宮迫さんは、版元日誌のなかで、「出版社の営業マンとして書店とどのような距離感の保つのがよいのかを考えながら」「本屋を経営している立場から出版社に期待すること」を書いてる。
それは次の三点だ。
・情報をしっかりと届けてほしい(知る)
・商品情報を充実させてほしい(興味をもつ)
・発注しやすい環境を整えてほしい(買う)
いずれも書店が、版元に提供してもらいたいことだ。
思わず膝を打ったな。
本の存在を、知ってもらわなければ、読む/読まない、買う/買わない、という選択すらできないもんね。
読者だけじゃなくて、書店にも知ってもらわなければ、その本を仕入れる/仕入れない、の選択もできない。
読者に知ってもらうのは、TwitterとかのSNS、新聞・雑誌・WEBメディアなどの書評、広告とか、いろいろある。
だけど、いまだに書店の店頭も読者に知ってもらう、大きな「きっかけポイント」だ。
だって文字モノの本の7〜8割は、ネット書店などではなく、本屋の店先でうれてるんだからね。
書店の店先に並べる本に選んでもらうのは、書店員にまず「知って」もらわないといけない。
書店員に知ってもらう=情報を届ける方法は、ファックス・郵送DMとかあるけど、安く、簡単にできるのはネットワークに情報を存在させることだ。
これは最低限のことだ。
広告とかDMとかはカネのかけ方によってできる/できないがあるけど、版元ドットコムサイトに掲載するのは会員社になればいいだけだ。
会員になるのは、発行点数10タイトルまでなら、会費は千円/月。
版元ドットコムのサイトは、書店員や読者がアクセスしやすいモノに日々改善しているのだ。
それぞれの版元のサイトで、出版してる本の情報を公開することも、とっても必要だけど、日本の出版業界のほぼすべての本を掲載されていれば、そこに探しに来てもらいやすいからね。
版元ドットコムのサイトは、現在 約140万/月のページビュー。
いろんなネット書店にここから誘導された売上は 年間5万冊/1億円程度になっている。読者が版元ドットコムサイトから本を買う、という動線ができているのだ。
一定の書店員にも利用されていて、宮迫さんの言う「・情報をしっかりと届けてほしい(知る)」に答える事ができていると思う。
「・商品情報を充実させてほしい(興味をもつ)」というのも大切だ。
内容は? 著者はどんな人? デザインは(書影やためし読み)? 書評にとりあげられたりしてるの? 売れ行きは(重版してるの)? ためし読みできない?、、、。
こうした情報(書誌情報・書影)を充実させられるように版元ドットコムはつくってる。
情報を充実させるのは版元ドットコム会員社それぞれの取組みなので、こうした書店員の声に応えて、内容紹介、著者紹介、書影、ためし読み、書評掲載情報、重版情報を更新するのが大切だと思う。
そして、「・発注しやすい環境を整えてほしい(買う)」というのを、最近版元ドットコムで力をいれているところだ。
発注しやすい環境とは、もっといい流通システムをつくることと、今の流通システムのなかでどうすればその本を、書店が注文・入手できるかわかるようにすることだ。
細かいことをはぶいて書くが、版元→取次など→書店の流れには、さまざまな「特例」が存在している。講談社・小学館・集英社といった大出版社、中堅出版社は、この「特例」を整備していて、本屋の側から注文先がわからない、ということはほぼない。
小規模出版社、「ひとり出版社」などにこの問題は多い。
版元ドットコムでは、発注はどこに・どうすればいいか、という版元それぞれの情報をオープンにすることに力を注いでる。
実はこのあたりの版元ドットコムの取組には、元書店員のすずきたけしのいろんな「希望」が随所に活かされている。彼の事務局への参加で、書店の現場の「こうならないの?」を直接聞けることになったのがおおきい(本人、事あるごとに「ほめて伸びる子」を強調してるんで、ほめとくw、伸びておくれw )
書店員に、この本は
取次に注文して入荷するのか? 直接取引なのか? とか
注文・在庫確認とかしたいけど電話は? ファックス番号は?
いざ返品しなきゃならなくなったときに、引き取ってくれるの?
といった情報を講談社・小学館をはじめとして数千社の情報の整備にとりくんでいる。
もちろん、版元ドットコム会員社は、さらに大幅に詳しく会員システムから登録し、サイト上に明示できる。明示できるのは、個別の本の詳細情報のページの左側の書影のしたにある「書店員向け情報」の欄だ。
例)ポット出版 取次ルートあり https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784780802368
例)ポット出版プラス トランスビュー扱い https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784866420196
書店で働いた経験をもとに、フィルムアート社の営業として働きながら、本屋も経営する宮迫さんが、出版社にのぞむ情報提供としてまとめた三点は、版元を営む上で、最も基本的な「営業活動」だとおもう。
まずこの三点を、最低限のこととして、網羅的に取り組むのが、版元の役割だと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
