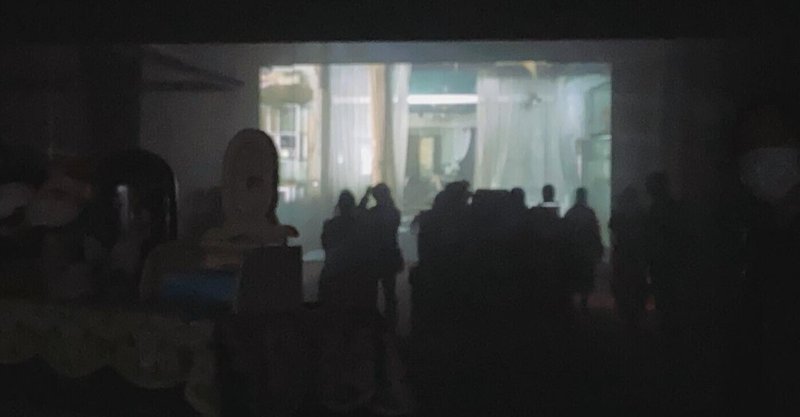
冨安 由真:漂泊する幻影
重たい扉を開くと、永遠にも感じられる廊下が姿を現す。
でも、それは永遠ではない。目線の先は鏡があると2回目の瞬きで気が付く。
-----この時点で既に現実と虚構の境界線がぼやけてきているな。
そんなことを思いながら、幻影が待ち受けているであろう部屋への扉を開き、足を踏み入れた。
暗闇。視界の隅に微かに感じる光。
最初に感じた情報が少なく、少し不安を覚えてしまうが、徐々に目が慣れてくると、オブジェの位置がだんだんと把握できるようになってくる。
と、天井から光芒が差した。
光が暗闇から浮かびあげたのは、倒れた椅子と机と椅子とその近くに佇む鹿。
暗闇からぼうっと現れたオブジェに人々がそちらに流れるのを見て取って、私も近づく。鹿も机も現実にある動物・物体であるはずなのに、どこか知らない世界からやってきたもののように思えた。
そうしてまじまじと眺めていると、光は徐々にか細くなり、あたりはまた暗闇に戻った。
思わずあたりを見回す。
おぼろげな光を頼りに観察すると、部屋は思っていたよりも大きく、広間のような場所だった。光の乏しい空間でなんとか構造を把握しようとする。
------次はどこが照らされるのだろう。
再度、頭上から光。光の先はさきほどと同じ机と椅子とリスのような生き物と鳥。名前も分からない動物の出現に、私の意識はますます現実から遠のいていく。そうしているうちに、また光は消えていき、暗闇が辺りを満たす。
頭上から差し込む光。暗闇から浮かび上がるピアノ。楽譜置きの周りにはクリスマスプレゼントと思われるようなおもちゃや時計などが置かれており、音が奏でられるようには感じない。
光はそのままピアノを照らす。
じっとピアノを見ていると、ひかりは徐々に消えていく。
暗闇。
光が蘇る。
部屋の角に設置された、ソファを中心としたダイニングを模したかのようなスペースが浮かび上がる。
食器棚もソファもテーブルも埃をかぶっていたり破損しており、いずれもそのものたちの生命を感じなかった。
そしていくつかの間。
暗闇。
光が指す。
今度は部屋の前方(といってもどこが前方かはっきりと分からないが)を照らす。
と、スクリーンに映像が映し出される。
今いる施設ではない、別の建物が移されている。
映像は建物の中を静かに、ゆっくり進んでいく。映し出される建物は、壁も家具もボロボロになっており、まるでここにあるオブジェたちのよう。
映されている場所がどこなのかも分からないまま、視点は進んでいき、終着点が見えないまま、映像は光と一緒に消えていった。
そして暗闇。
---
------
--------------
部屋の中は、オブジェを照らしたり映像を映し出すことを繰り替えしていた。だが、同じようで、光が照らす場所や、光の色、映像は僅かに変化しており、ますます世界に取り込まれしまう。
そうやって、現実を感じさせないオブジェたちが光の中からぼんやり現れるのを見ている度、これが漂泊する幻影か、と思ったが、ふと遠くからぼんやり部屋全体を眺めてみると、光に照らされるオブジェたちの方が現実味が強く、そこに集まる私たちの方が幻影なのではないかとさえ思えてきた。
まさに現実と幻影の世界の区別が分からなくなったのは、ピアノが光に照らされ、ピアノの後ろにぼんやりと自分の姿が映し出された時だった。
-----あれは、誰?あれは、もう一人の自分?現実の自分?
今ここに立っている私の方が虚構?
暗闇は私を不可思議な世界に容易に溶け込ませており、不確かな光が映し出す自分の姿が、鏡に写った自分だと気づくためには随分時間かかった。
----ここにいると、現実を忘れられそう。
ずっとこの空間にいたい気持ちが生まれるも、そっとしまいこみ、私は暗闇の部屋を出るため、扉を開けた。
扉の先にあったのは、先ほど通ったのと似たような廊下だった。ただひとつ違ったのは、ぽつんと置かれたその場に似つかわしくない、ほこりの被った車椅子だった。
恐怖と名づけるには弱々しい違和感が心の隅をちりっとかすめる。
その違和感を煽るように、廊下の電球は不規則に、いや規則的とも取れる点滅を繰り返す。
----この通路はいわば現実と虚構の境目なのかもしれない。
浮かんだ考えを受け入れるように、私は次の部屋へ続く扉の取っ手をつかみ、引きよせた。
次の部屋も光の少ない部屋だったが、先程の得体の知れない暗闇とはまた違っていた。
天井から指す光芒は、1枚ずつ、あるいは2枚の絵画を照らしていく。
そこに描かれているのは、先ほど広間のスクリーンに映し出されていた、"ここにはない場所"の風景。
光が消える。
しばらくの間。
次は映像の中でみた建物の廊下の絵画が映し出される。
そうやって暗闇の中から絵画が浮かび上がる度、あの映像の場所は幻想ではなく存在していたんだ、と同時に、あるいは"あの場所はやはり幻想であったんだ"、とも感じされられた。
-----次はどの絵画に光が当たるのだろう。
注意深く全体に目を向けていると、不規則的に(あるいはやはり規則的に)指していた光が、ぱっとすべての絵画を映し出した。
現実に一斉に現れる虚構たち。
いや、もはや光に照らされた風景たちはその存在感を増し、現実世界のものとなっていた。
1つずつ丁寧に照らされる絵画を見ながら、前方(と思われる方へ)進んでいく。そして部屋の先頭(と思われる場所)まできたとき、ふいに後方で光が降ってきた。と思うと、これまでの静寂な空間を裂くように、光芒は頭上から地面を突き差しながらこちらに近づいてくる。そしてとうとう光が私を貫くと、あたりはまたほのかに光が漂う静かな空間に戻った。
-----これがこの空間の終わりなのかもしれない。
最後の光をそう解釈した私は、虚構から(あるいは現実から)背を向けて、出口への扉を開いたのだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
