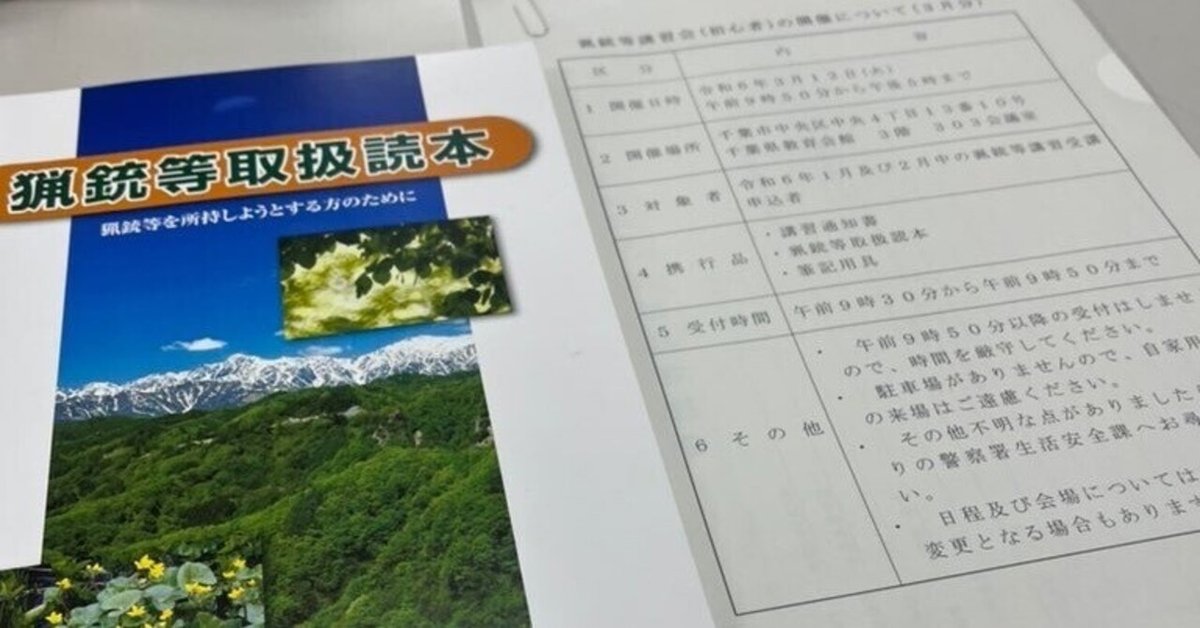
猟銃等講習会(初心者講習)①
前回の記事では、まず猟銃を取ろうと思ったら銃砲店に行ってみることをおすすめしました。
銃砲店で申請書の原紙を貰う、またはインターネットでファイルをダウンロードして記入・印刷をしたら、住所地を管轄する警察署へ行きます。
初めての猟銃取得を目指す人は、初心者講習会(猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会)を受講します。
受講に際して必要な書類や申請期間は、前回の記事でも貼っていますが、千葉県警のホームページを参照してください。
さて、ここで講習を受けるだけだと考えていた私は、講習開催前々日に非常に焦ることになりました。今までの社会人生活で建設業に従事してきた私は、いわゆる講習というものを舐めていました。
世の中にある技能講習等の"講習"と名の付くものは、基本的に申請者を合格させるための講義を行い、最後の考査については"1日を通して真面目に話を聞いていれば、まぁ合格するものである"という認識でいたのです。
ところが、銃刀法はそんな甘いものではありませんでした。
インターネットで調べていたら、猛勉強とは言わないまでもそれなりに勉強しておかなくては落第するとの事だったのです。
そりゃぁ基本的に世の中で禁止されている銃というものを手にするのですから、ある程度ふるいにかけようとするのは当然。
焦って勉強を始めたのが講習前々日の21時という有様でした。
焦った私は急ぎamazonで初心者講習対策テキストをその場で買い、購入したその日は警察署から申請時に貰える猟銃等取扱読本を2週読みこむのでした。
なお、その際に購入したのは下記のテキストです。
余談ですが、ここで私は救われたことが一つあります。
趣味の一つでサバイバルゲームをやっていたこと、そしてその中で気を付けていた事が知識のベースとして非常に役立ちました。
猟銃の取扱いにおいて、法令関係は当然一から覚えるしかないのですが、そもそも銃というものは何を目的としていて、どのような仕組みで動作し、どのような取扱いが危険で、どのような安全管理を行わなくてはならないのかといった事が、エアガン・エアソフトガンと呼ばれるものと共通していたのです。
まさか、遊びがここで役に立つとは・・・!
私の場合は、上記の通り銃というものの基礎知識があったため、6時間ほどのテキスト読書と4時間ほどの過去問によって、無事講習合格へと行きつきます。
前回の記事でどのような要件が欠格事由にあたるかという話をしようかと考えていましたが、テキスト内で明確に記載されているので、猟銃を持とうとする方は必ず覚える知識の一つとして出てきます。
考査で出てきた問題とか、覚えてるうちに書き出しておこうかな~。
※なお、千葉県の初心者講習考査は、ざっと周りを見た感じでいうと合格率8割といった感じでした。講習中に居眠りする方もおらず、恐らく皆さんしっかり対策していたのだろうと思います。
逆に考査に通っていなかった方は、50~60歳ぐらいの方が目立っていたように思います。
年齢を重ねると新しい勉強に対しての記憶力が落ちると聞きますし、猟銃を取りたい方はなるべく早く挑戦した方がいいかもしれません(何事にも共通しますけども)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
