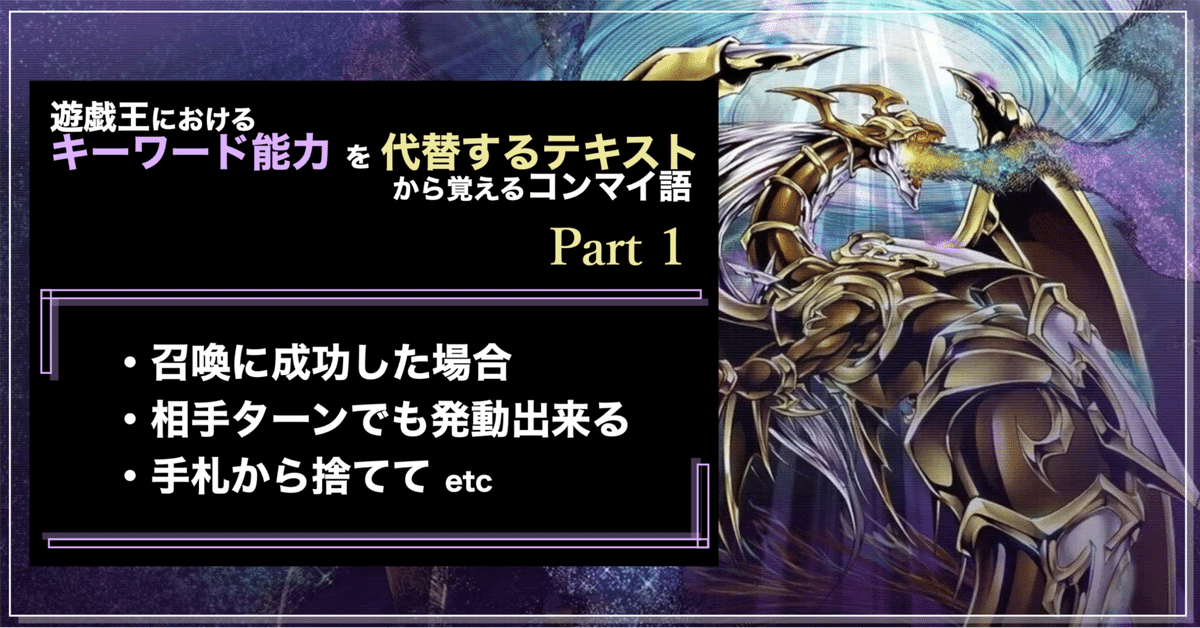
【遊戯王】「時と場合」「対象に取る取らない」の次に覚えるコンマイ語解説
皆さん、こんにちは
マスターデュエルをきっかけに遊戯王を始め既に1年以上。
マスターデュエル君に丸投げしてきた遊戯王のルールもとい、コンマイ語の勉強をすべきだと思い立ち、遊技王wikiを覗くと情報の津波。あびゃーと言って溺れていくこと数回。
同じような経験をしたことがある人はきっといるでしょう。
私と同じような目に遭った人の一助になる為に
実戦で使える部分に絞り、環境で見かけることの多いカードを例にとって直感的に理解しやすいようにまとめたコンマイ語解説になります。
とはいえ、遊戯王のテキストは複雑で、漠然と解説していくには無理がありすぎるので、遊戯王におけるキーワード能力(を代替するテキスト群)を軸にしてまとめていきます。
遊戯王にキーワード能力ってあるの?
キーワード能力とは“このカードは召喚されたターンにも攻撃できる”という効果を一々書いているのは面倒だから“疾走”という一単語で表してしまおう、というシステム。
カードゲームにおける圧縮言語の事。
キーワード能力は多くのカードゲームに採用されており、例を挙げると
デュエマの「スピードアタッカー」や「W・ブレイカー」
バトスピの「激突」や「粉砕」
シャドバの「守護」や「疾走」
MtGの「飛行」や「速攻」
などなど、有名所のカードゲームが。
しかし遊戯王には明確にキーワード能力と称されるシステムは存在していません(でもポケカもこっち側だから仲間はずれではないよ)。
しかし遊戯王にもキーワード能力を代替するテキスト群は存在していると筆者は考えており、その代表例が「時と場合」,「対象に取ってと選んで」,「このカード名の①の効果は1ターンに1度しか使用できない」辺りでしょう。
チラッと見えただけで「嗚呼、なるほどね。んで本命の効果は?」となる共通テキスト達。
短いテキストにこれでもかとルールを詰め込んだ圧縮言語であり、遊戯王におけるキーワード能力と言っても過言ではないでしょう。
こういった多くのカードで使われているお約束のテキストとそれにまつわる日本語からは読み取れないルールをまとめていこうと思います。
注意事項
テキスト例は場合の効果で表記。
9期以降のテキスト整備がなされたものを基準に取り扱います。
「このカードが召喚(・反転召喚・特殊召喚)に成功した場合に〜〜発動できる」
〜〜の部分にはフィールドのモンスターを対象に取ってなどの条件が入り、効果の内容はこの後ろに書かれる。
〜〜の部分がない場合も多い。

召喚時効果があることを示すテキスト。
このテキストにおける“召喚”というのは通常召喚のことだけを指し示しており、「通常召喚・反転召喚・特殊召喚の全てに対応しているよ」という訳ではないので注意。
“成功した場合”とあるように神の宣告などの“召喚を無効にする”効果で邪魔された場合は召喚失敗となり、効果は発動できない。
これは理解しやすいのだが、頻出するわりに解りにくい召喚失敗がある。それがチェーン中の特殊召喚とフィールドからの除去である。
チェーン①にサンダーボルトの全体破壊、
チェーン②にスプライトエルフで墓地のスプライトブルーを蘇生した場合。
ブルー特殊召喚→サンボル効果で、ブルーは特殊召喚されるがその直後に破壊される事になる。
この場合でもブルーの召喚成功時の効果は発動できない。
詳しい理由はさておき、「チェーンの途中で特殊召喚された場合は、チェーン処理が終わるまで生き残らないといけない」というのは、このテキストにおけるコンマイ語要素なので覚えておこう。
「(自分・)相手・お互いのメインフェイズに〜〜発動できる」
「〜〜この効果は相手ターンでも発動できる」
前者はメインフェイズ以外のバトルフェイズやエンドフェイズ表記でも同様。

チェーン2以降でも発動できる効果にかかわるテキスト群。
このテキスト群がある効果はスペルスピード2で、速攻魔法と同じくチェーン2以降でも効果の発動が可能になる。
当然、条件がある場合はその条件を満たしてから発動が可能になり、条件がなかったり緩かったりするものはプレイヤー間ではフリーチェーンと呼ばれることが多い。
「召喚直後の着地狩りしたいけど、あのカードってチェーン2以降で動けたっけ?」となったらこのテキスト群を探すと良い。
前者の「(自分・)相手・お互いのメインフェイズに~~発動できる」のテキストには1つ落とし穴があり、
「相手メインフェイズに〜〜発動できる」
「自分・相手メインフェイズに〜〜発動できる」
「お互いのメインフェイズに〜〜発動できる」
はチェーンを組んで発動できるテキストなのだが、
「自分メインフェイズに〜〜発動できる」はチェーンを組んで発動できないスペルスピード1のテキストになる。
後者の「~~この効果は相手ターンでも発動できる」方についてもコンマイ語要素があり注意が必要。
「この効果は相手ターンでも発動できる」と書かれているが、相手ターンだけでなく自分ターンでもチェーン2以降で動けるコンマイ語仕様。
「このカードの発動後〜〜できない」
「このカードを発動するターン〜〜できない」
〜〜には縛りの内容。
金謙のダメージ半減など“できない”以外の縛りの場合もある。

どちらも発動に伴って、なんらかの縛りが発生するテキスト群。
一見すると同様の効果を示したテキストに見えるが、全くの別種。
前者の「このカードの発動後〜〜できない」は発動前であれば何をしていても許される。
例えば天底の使徒は
“このカードの発動後、ターン終了時まで自分はEXからモンスターを特殊召喚できない”
であり、融合やシンクロ→天底の使徒の順であれば使うことができる。
後者の「このカードを発動するターン〜〜できない」は発動前であろうと許されない。
例えば強欲で謙虚な壺は
“このカードを発動するターン、自分はモンスターを特殊召喚できない”
であり、特殊召喚しまくった後に使うことはできない。
よく読めば意外と日本語通りである。
9期以降の最新のテキストにおいては
前者は効果テキスト(①〜〜 ②〜〜の部分)に記載され、
後者は効果外テキスト(①とかが付かない、名称ターン1とかが書かれてる部分)に記載されている。
*旧テキストだと後者も効果テキストに記載されていたりする。
「手札から捨てて発動できる」
「手札(・フィールド)から墓地へ送って発動できる」

主に手札誘発でよく見るテキスト群。
日本語的には同じに見えるが、コンマイ語的には微妙に別物。
ほとんどの場合において同じ挙動をするが、次元の裂け目やマクロコスモス下においては
「手札から捨てて発動できる」は発動できるが、
「手札から墓地へ送って発動できる」は発動できない。
発動コストかつ墓地を指名している場合に起こる現象らしい。
どっちがどっちだか分からなくなる効果筆頭だが、「テキスト内に"墓地"と書かれているものが"除外"されるのはNG」と覚えれば大丈夫。
「発動を無効にする」「効果を無効にする」

効果の無効化にかかわるテキスト群でコンマイ語案件が複数あるテキスト群。
「効果を無効にする」の中には更なる区分があったり、無効の発動条件による処理の違いなどもあるそうだが、あまりにも難しくて分からなかったので、今回は発動無効と効果無効の違いだけとする。いずれリベンジする予定
1.名称ターン1にかかわる違い

「このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できない」の名称ターン1をもつ三戦の才を例に考える。
手札に三戦の才が2枚あり、1枚目に対して無効を打たれた場合
発動無効だと2枚目の三戦の才が使えるが、
効果無効だと2枚目の三戦の才が使えない
という事が起こる。

もう一例、「このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない」の名称ターン1をもつ灰流うららで考える。
手札に灰流うららが2枚あり、1枚目に対して無効を打たれた場合
発動無効と効果無効の両方で2枚目の灰流うららが使えない
という事が起こる。
実は一般に名称ターン1と呼ばれる効果にも「発動できない」と「使用できない」の2種類があり、
発動無効は「発動できない」に対しては不利な効果になっている。
発動を無効にした場合、「発動はしていないけど、使用はしたよ」という扱いになるのは日本語通りな気はする。
効果無効は両者に対して有利な効果であるので、名称ターン1に関しては効果無効の方が優れているといえる。
2.ダメージステップにおける発動の有無
ダメージステップに発動した効果に対して
発動無効はダメージステップに発動できるが、
効果無効はダメージステップに発動できない。
理由は知らない。そういうものらしい。覚えよう。
発動無効はダメステ有利で効果無効は名称ターン1有利と、この2つは一長一短の関係性にある。
3.「このカードを発動するターン〜〜できない」と「このカードの発動後〜〜できない」
前の項目で取り扱った「このカードを発動するターン〜〜できない」(強欲で謙虚な壺)にこれら無効を打つと
発動無効は〜〜できないが適応されないが、
効果無効は〜〜できないが適応される。
「このカードの発動後〜〜できない」(天底の使徒)に関しては
発動無効と効果無効の両方で適応されない。
頭の片隅のどこかにあれば、役に立つ……かもしれない位の項目。
無理に覚えなくてもいいと思う。
後書き
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
この記事が参考になったと思っていただけたのなら、いいねしていただけると喜びます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
