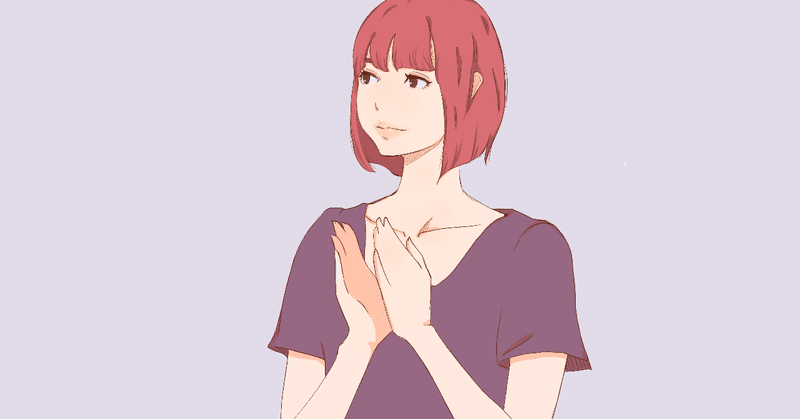
2019年に読んでおもしろかった本
2019年に読んだ本のベスト10みたいなものを書いてみよう、と珍しいことを思い立ったのだけど、ちょうど2019年から読書記録を付けるのをやめていたので、どれが今年読んだ本なのかわからなくなってしまった。新刊ばかりを読んでいるわけではないし(むしろ少ない)、もはや年月の経過するスピードも認識できなくなっているため(25歳になったあたりから自分の年齢も正確にはわからなくなっている。それがかなり昔のことだというのはわかる)、10冊を選ぶ作業に非常に難儀した。難儀したというか、最初の3冊を思い出した時点でやめた。この3冊が意外と密接な関係にあるというか、どの本も他の2冊の副読本として機能すると思ったから。
ジャレット・コベック『くたばれインターネット』
チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ『なにかが首のまわりに』
カート・アンダーセン『ファンタジーランド 狂気と幻想のアメリカ500年史』
『くたばれインターネット』はトルコ系アメリカ人、ジャレット・コベックによる長編小説。「アメリカのウエルベック、現代のヴォネガット」という最高の触れ込みに惹かれて手に取ったのだけど、読んだ感じ、それほど近い印象はない。極端にあけすけな物言いだったり、皮肉や風刺の強度なんかは似ているといえば似ているけど。ウエルベックやヴォネガットの小説から新鮮なビジョンや詩的な空気みたいなものを取り払って、ユーモアと攻撃性だけを大幅に増強したような設計になっていると思う。強烈なパンチラインだけで小説を構成しようと目論んでいるかのような執念深さは、三者に共通しているかもしれない。
『くたばれインターネット』には、登場人物のひとりが、さまざまな実在のセレブをギリシアの神々になぞらえていくシーンがある。たとえはスティーブ・ジョブズは冥府の神ハーデスとみなされている。
「ハーデスは人であれば必ず関わらざるを得ない神だ。この神が人に対して示す約束は単純だ。我々には選択権が与えられているというものだ。醜く愛されぬまま死ぬか、さもなければ高めに価格設定されたパソコンとかiパッドを買って初期のボブ・ディランに耳を傾け、そうやって輪廻の輪から逃れるかという二択である」(p.249)
『くたばれインターネット』(原題『I hate the Internet』)は、その名の通りインターネット、とくにSNSがこの世界に及ぼした負の影響をめちゃくちゃに批判した小説だ。ほとんど罵詈雑言といって良い。けれど、読みながらその罵倒に何度も笑い、何度も頷いてしまう。
前述のように実名でさまざまな有名人を腐しているし、
「ネットって本当変な世界よね。誰もが何に関しても我こそは道徳の十字軍みたいに振る舞うでしょ?」
というセリフや、
「ネットがアメリカの文化を様変わりさせ、新たな表現手段となったのだという話は耳にタコができるほど聞かされてきた。しかし結局は一層多くの人々が(ネットで)テレビの話をするようになっただけだった」
という文章にも、作者の立ち位置が見て取れる。
といってもこの本は、「ネットがない時代は健全だった」的な、老人の老人による老人のための長く無意味な回顧を聞かされる感覚とも無縁だ。むしろまったく逆の印象を受けるはず。インターネットをユーモアまじりに強く批判することで、社会全体にはびこる性差別、人種差別、ポピュリズム、広告の不全、搾取や格差の問題、といったものを覆い隠す欺瞞を叩き壊す構造になっているからだ。
何かを笑いものにすることによって問題を明らかにしたり、問題の本質を暴いたり、果てしなく傷口を広げて見せて、誰もが罪人であると突きつけたりする。それがユーモアの効能のひとつだと思う。すべてのユーモアは必ず攻撃性を含んでいる。誰かの傷を癒す表現は、同時にどこかで誰かを傷つけている。「誰も傷つけない笑い」などというものは存在しない。「誰も傷つけない笑い」だと言われているものは存在するが、それは「進歩的な集団には差別が存在しない」というのと同じくらい雑なものの見方だ。誰かの突拍子もない言動を優しくフォローする、という構造の笑いにだって傷つく人はいるし、赤ちゃんの無邪気な失敗を笑うことにだって傷つく人はいるのだ(だから人を笑いものにする表現はやめるべきだ、といっているわけではもちろんない。でも傷つけていることに自覚的ではあるべきだろう。かすり傷ひとつ負うことなく生きていくことはできない。だとしたらそれがどういう傷で、自分のどこが傷ついていて、どんな言動が他人を傷つけていて、その傷に対処する方法は何なのか、ということを知るべきで、それを教えてくれるもののひとつがユーモアなのだ。そういった種類のユーモアは、ワクチンのように多少のウィルスを含んでいる場合もある。反ワクチン運動の無知と、「過激な表現」に対する無知は似ていると思う。もちろん、表現する側が無知であったために人を傷つけ、そういった古くさい表現が蔓延し、時代を後退させる場合もある。そうならないために整備されるべきものがポリティカル・コレクトネスなのであって、これらのすべては共存することができるはずだ。ポリティカル・コレクトネスだって、全知全能の神によって運営されているわけではない。グレーゾーンを含んだ、常に変化し続ける緊張状態の中でしか、正常な人間関係や芸術的な表現といったものは維持できない。ところでこの文章、なんか怒りすぎてない? 偉そうだし、途中から改行もないし、カッコ内なのにぜんぜん閉じないし……怖~)。
いわゆる「文学」、といったイメージに忠実な「善い小説」が、国の支援を得て長年もてはやされたことで、「アメリカ文学は技術革新のテンポにまるっきり追いつけなくなってしまった」という一文が『くたばれインターネット』にはある。この本の根底には、その苛立ちがあると思う。これに関しては、アメリカ人でもそんなことを思うのか、と新鮮な気持ちになりましたね。しかし本作は自費出版からスタートして、結果として12か国語に翻訳されている。海外にはこんな極端な小説の市場がきっちり残されているんだな、とうらやましく思ってしまう。
『くたばれインターネット』は、作中で示される「善い小説」ではない。ろくでもない小説だ。だけど、ろくでもない小説でなければリーチできない領域というのも確実に存在するのだ。この本に書かれているすべての悪辣な表現は単なる冗談であり、しかし本気の本気でもあり、やっぱりただの冗談にすぎない。だけど……。というような小説ではないだろうか。非常にシンパシーを感じます。まあ、筋立てはないに等しいし、独特のユーモア感覚が合わないと読むのそうとうキツいだろうけど。地の文でキャシー・アッカーの『血みどろ臓物ハイスクール』を「偉大なる作品」と言っているし、比較すべきはウエルベックやヴォネガットではなく、そちらかもしれないですね(キャシー・アッカーほど極端な小説ではないですが)。
『なにかが首のまわりに』は、フェミニズムを基調としてさまざまな社会問題を複合的に扱った小説群を発表し、次世代の書き手と目されるチママンダ・ンゴズィ・アディーチェの短編集。というと、説教じみた小説と思われるかもしれないが、美しい描写に胸を打たれているうちに、いつのまにか世界の見え方が切り替えられてしまうような素晴らしい小説集です。
そもそも、ナイジェリア人で、黒人で、女性で、イェール大学やハーバードの研究所で学んだアディーチェは、現代文学の書き手としてすべてのカードを持っているとみなすこともできる(この言い方がすでに差別的だが)。
性差別、人種、格差、宗教、教育、医療、などなど、多岐にわたる問題を短い小説の形で、無理なく、押し付けることなく、広がりを感じさせ、読者のものの見方を変えさせ、なおかつ読んでいておもしろいという超絶技巧。シンプルなプロットなのに、ここまでの多重構造が可能なのか、と読んでいて恐ろしくなってしまう。
12本の短編すべてが最高水準だけど、とくに『先週の月曜日に』『震え』『結婚の世話人』の3本には、完璧、の一言しかないですね。
結局のところ、アディーチェは高い知性で「孤独」について書いているのだと思う。この本におさめられたほとんどの短編が、「すべての人は個別の人生を歩んでいて、すべての人は完全には理解し合えず、すべての人が寂しい思いをしている」ということを静かに突きつけてくる。最後におさめられた『がんこな歴史家』という短編だけが、一族の血のつながりや、家族というシステムにかすかな意味や希望を抱かせる内容になっている。それも、この方法でしか描けないだろうな、と思わされる細い道筋を通ったプロットで、本当に感心させられる。
そのうち小説はAIが書くようになり、それだけで事足りるようになる、という説があるけど、そう主張する人たちがそろいもそろって「小説イコール、おもしろいプロットと読みやすい文章」としか認識していないのには悲しくなってしまう。それはレトルトカレーのパッケージに書かれたカレーのようなもので、皿に盛られた、実際に食べられるカレーの話を誰もしていない。AIは限られた人生を生きていないし、固有の人生も生きていない。その制限のなさが逆に足かせとなって、この本のような広大な背景を持つ小説を書くことができない。AIに小説を書かせるなら、根本的にやり方を変えないといけないのではないかしら(多少バズるくらいの本なら今の技術でも可能だと思うし、その程度の小説しか望まれていないのは寂しいことだと思います)。
『ファンタジーランド 狂気と幻想のアメリカ500年史』は、簡単にいうとアメリカの歴史を、「大衆が何を信じ、何を支持してきたか」という観点から振り返った本。
僕は高校生くらいまで、将来は歴史学者になりたいなーと純朴なことを思っていた純朴な歴史マニアだったのだけど、アメリカの歴史にはわりと冷淡で、受験勉強以上のことは学ぼうとしなかった(ホームステイしてた時期はある)。アメリカはん? たかだか500年で歴史? そら可愛らしいどすなあ……とエセ京都弁のようなことを思っていたのだ。振り返ってみると、僕は単に古代から中世にかけての歴史が好きなだけの、戦記物から入ったありがちな歴史オタクにすぎなかったわけですね。本当になりたかったのは歴史学者ではなく、天才軍師だったのかもしれない。可愛らしいどすなあ……。今は歴史オタクですらない。
そんな僕も最近、アメリカ史を学び直すことが重要だと思っていて、関連本をいろいろ読んでいます。そのうちの一冊がこれ。
非道な方法で先住民をむりやり追い払って、広大な土地にイチから国を作ったアメリカの短い歴史は、人類が太古の昔から繰り返し行ってきたすべてのことの、コンパクトな見本市になっている気がする。
この本では、マーク・トウェインの「歴史は繰り返さないが、韻を踏む」という発言が繰り返し引用されている。その通り、歴史は繰り返さないが韻を踏むし、いま日本で起こっている問題は、すべてアメリカで起こったことの押韻ではないかと思わされる。
この『ファンタジーランド』という本は、アメリカという国を、そもそもの成り立ちから徹底的に洗い直している。新大陸発見より以前、ルターの宗教改革、さらにはルター本人の気質にまでアメリカの起源を遡る徹底ぶりにはちょっと笑ってしまうけど。
「この国は、一攫千金やユートピアや永遠の命などの幻想を入れる空っぽの容器として始まった」
という大胆な記述があるが、結論ありきでアメリカの現状を批判しているわけではなく、自分の考えが万能ではないことを作者が認め、どの時代、どの局面についても、常に思想的なバランスを取ろうと苦心しているのはうかがえる。
全編を通して主張されているのは、人間にとって必要な「幻想」の領域を認めつつも、社会の運営は理性によってコントロールされるべきだ、という当たり前のこと。現代芸術やポップカルチャーの分野に関しては、キース・ヘリングの絵を「ノートに書いた落書きのような」と、いちばんよくある、平凡なあしらい方をしてたりもするけど。
科学が進歩し、神を信じる人が減ったからと言って、大衆が神秘的なものを盲信するのをやめたわけでも、理性的になったわけでもないということが、さまざまなデータから本書で明らかにされている(それでもアメリカは「神の存在を心の底から信じる」人の割合がそうとう高い)。いまだにポピュリズムは有効だし、それどころか現代の最も重要な悪とも言える。日本と同じように、アメリカでもニセ科学やフェイクニュースは横行しているし、あらゆるハラスメントは健在だ。日本の政治、科学、医学、その他の「理性的であるべき」分野に起こっているような惨劇は、先進国(不愉快な名称だけど)と言われる国であっても、そうでなくても、すべての場所で現在も起こり続けている。世界中の歴史で何度も何度も繰り返されてきたように。
日本だけがひどい、とか、海外にはこんな差別やニセ科学やいい加減な報道は存在しない、という意見はすべて間違っている。日本の特定の地域に住む人は差別的だと発言することも、北欧のどこそこの国には差別が一切ないと言うことも、どちらも同じくらい嘘だし、同じくらい差別的な物言いだろう。日本の特定の地域に存在する差別意識は東京のど真ん中にも、想像上の北欧の楽園にも、世界を牛耳る進歩的な企業にも、ハリウッドにも、PTAにも、コンビニの棚にも存在している。
ここで紹介した3冊が、それぞれ他の2冊の副読本として機能すると書いたのは、どの本も現代の不穏な空気と、その背景について書いているから。
『くたばれインターネット』と『ファンタジーランド』は、どちらもアイン・ランドの名前を繰り返し登場させて、その特権階級的なエゴイズムを批判している。
『くたばれインターネット』と『なにかが首のまわりに』は、どちらも黒人として生きることについてのリアルな最新の感覚を描いている。
『なにかが首のまわりに』に収録された「震え」という短編は、ペンテコステ派の知識がなくても充分に楽しめるけれど、ペンテコステ派のおおまかな概要や歴史を知っていれば、また少し見方も変わるだろう。ペンテコステ派のおおまかな概要や歴史は『ファンタジーランド』を読めばわかる(まあウィキペディアでもわかると言えばわかる)。
『ファンタジーランド』のメインテーマでもある「理性を捨て、幻想と現実の区別がつかなくなり、自分の信じたいものしか信じなくなった人々」は、『くたばれインターネット』の世界にも登場する。すなわち、僕たちの住むこの世界にも登場している。
良い本でも悪い本でも、読めば読むほど良いと思う。同じ傾向のものばかり読んで、自分の主張を強めるためだけの読書は良くないと思う。本を読んで何かに疑いを持ったり、何かの疑いが晴れたりするのを繰り返すのは良いことだと思う。1冊の本、1人の作者を盲信しすぎるのは良くないと思う(単純な娯楽であれば別ですが)。
本を読んで現実と戦う力を身につけるのも、本を読んで現実逃避するのも、どちらも素晴らしいことだと思う。僕はあほですが、読書の年輪みたいなものを少しずつ丸く大きくすることで、多少なりとも社会と接点を持つことができているのかもしれない。
この文章をここまでほぼ読み返していませんが(2020/01/03現在)、非常に青くさく、幼稚なことを書いてしまったのではないかと恥じております。恥ずかしがり屋なので。TOO SHY SHY BOYなので。
今年はもっとおもしろい小説を書きたいなー、と思っています。よろしくお願いします。
『くたばれインターネット』
Pヴァイン
著者 ジャレット・コベック
翻訳 浅倉卓弥
『なにかが首のまわりに』
河出書房新社
著者 チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ
翻訳 くぼたのぞみ
『ファンタジーランド 狂気と幻想のアメリカ500年史』
東洋経済新報社
著者 カート・アンダーセン
翻訳 山田美明/山田 文
