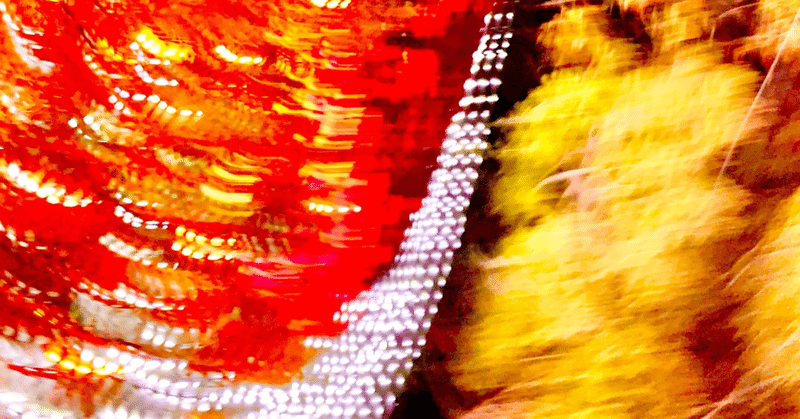
BFC5落選展感想64~66
BFC5落選展の感想です。リストはkamiushiさんによるまとめ「BFC5落選展」をお借りしました。
LIST64 「悩むよりまずはクリニック」阿蒙瞭
出先でお腹が痛くなると「どこでもドアが欲しい!」と思う。家のトイレに直行して、またすぐ元の場所に戻ればいい。ああ22世紀が待ち遠しい!
でも、どこでもドアの技術に危険性があることは明らかです。カーナビだって近くまで来たら「だいたいこのへんです」って止まるのだから、位置関係を間違って屋根とかでドアが開く可能性がある。
社会問題にも発展しえます。犯罪者は喜んで使うでしょう。一般人にとっても、通勤時間がなくなるのは一見いいようでいて、「いつでも帰れるんだから残業していいよね?」という状態が蔓延しそう。
その点、本作に登場する技術は流行っても公共の害にはならなさそうだなと思った。医師も「生き易くなる」と言っているし、きっとその通りだろう。が、あくまでパッと思いつく限りの話です。長期的に観察しなければ、本当のところはわからない。
◇「悩むよりまずはクリニック」あらすじ
肉体のある部分を切除するためにクリニックを受診した「私」。一般的には思春期に切除するものなので三十代の「私」は少々恥ずかしい。しかし医師は「年齢のことは気にしなくていい」と励ましてくれ、手術の日程はとんとん拍子に決まった。
ある部分とは、「自意識」である。「私」は思春期の頃、恋人を周囲に自慢したくて自意識を切除せずにいたのだ。
思い出すと恥ずかしい過去だ。しかし切除の前、看護師にそのことを打ち明ける「私」は愉しげだった。間もなく手術が開始する。医師は「手術が終わると、とても生きるのが楽になっていますよ」と言った。
「自意識」というが、鏡に映った自分を自分と認識するための「自意識」ではなく、自意識過剰という意味で使われるような「自意識」のようだ。ライトな話として割り切るなら、見栄といったほうが適切かもしれない。ただ、見栄は張るものだから人体の一部という感覚がないんですよね・・・。
作中に恥ずかしがる「私」と医師の構図が出てくる。「私」は自意識があるからめちゃくちゃ恥ずかしい。医師はというとこんな感じです。
私は気恥ずかしさを憶えて、視線を医師の目線から外して下に落とした。白衣の下に薄ピンクのシャツを着ているのが透けて見えて、なぜか目が離せない。
服装がいいですよね。変ってわけじゃないけど、エッて思っちゃう。本人は別に気にしていない。年は「四十代半ばぐらい」「彫の深い顔立ちで恰幅のいい医師」という設定です。つまりは堂々としているということなのでしょう。思春期に自意識を切除したか、もともと気にしない性格なのかもしれない。いずれにせよ、設定が文章に溶け込んでいると思いました。
わりと寓話的な話です。さらっと書くこともできたと思うのに、背景描写がリアルで良かった。
心の中で葛藤した結果、恥ずかしくても意を決して手術を受けることにした以上、とにかくここで話を進めたかった。天井の白色光LEDが少し眩しいぐらいの光を周囲に降り注ぎ、ちょうど真下の机の上に置かれた太い胴体をした旅客機のフィギュアに直接当たって、白飛びさせていた。
深読みすると、つまり旅客機のフィギュアはミニチュア化した「私」のことなんじゃないかと思った。飛行機ではなく、旅客機と書いているのがポイントで、本来はたくさんの人を乗せて大空を飛ぶことができるけれど、クリニックの眩しい光の元ではそのもののかたちを把握することができない。光に目がくらんで、本来の自分を見失っているとかそういうことなのかなあと思いました。
◇ぜんぶ脳の問題
春Qは、この技術が開発されたらぜひ自意識を切除したいと思う。本作もそのこと自体を否定しているわけじゃないように感じる。
「お辛いんですか」
「そうですね。つまらないとわかっていても会社の同期との出世の差に屈辱を感じたり、仕事の評価が低いと、正当に扱われてないと苛立ったり。そもそも自分が何者でもないとそろそろわかってきて、堪らない気持ちになるんです」
ここ、たぶん「私」が問題にしているのは、屈辱を感じる、苛立つ、という感情の動きでしょう。「私」は(ま、こんなもんだよな)と感じたいのです。余計な自意識がなければ(だから、今は○○をしよう)とか(だから、この点に関しては諦めよう)とかの切り分けができる。
ただ、この文章だけだと「私」が自意識をなくした結果、どういう未来を期待しているのかがわからなくて心配になる。ちょっとヤケを起こしてて、「モウ心ナンテイラナイ……楽ニナリタイ……」と思っているんだとしたら、ちょっと話が変わってくる。
大丈夫です、わかってますよ。いや、そういうシリアスな読み方をするような箇所ではない。もっと軽く捉えていいんだと思う。
しかし完全にライトな読み方をするとなると、先に挙げたような繊細な背景描写が引っかかってくる。あの意味深な旅客機のフィギュアを見ていると、私はなんだかよくないことが起ころうとしている気がするんだ・・・ッ! 事故・・・みたいな・・・。
まとめます。
ストレスの多い世の中です。自分で自分の機嫌をとるとか、アンガーマネジメントとか、ネガティブな感情を自己処理することが当たり前の社会。それは確かに当たり前なんですけど、本当はあなたの感情を良いとか悪いとか決めることなんて誰にもできないはずだ。
しかし今、それらの感情は現実に生きづらさのもととなってしまった。成熟し、病んだ社会の中で私たちは自意識を切除して生きてゆかざるを得ない。私たちは懐かしくて恥ずかしい思い出を惜しみながら、いまだ見たことのない未来へと歩んでいくのだ。裸の自分ともう一度向き合うために。
そういう話として読みました。
LIST65 「逆迷彩蝸牛」黒谷知也
お店屋さんで働いていた時、店にキモい虫が出たことがありました。私はマジで役立たずな店員でしたが、なんの抵抗もなく虫を殺せたので、その時だけは仲間たちに感謝されました。そのキモい虫は二度とあらわれず、お店屋さんは商業ビルごと潰れてしまいました。で、私は田舎へ帰った。・・・これらの出来事に因果関係を感じるのは、物語の読みすぎでしょうか。
本作では殺されるためだけに生まれたような虫が登場します。人間が不快害虫などというレッテル張りで虫を虐殺するのはあるあるですが、殺さずにはいられないナニカを虫のほうが放っている設定は非常に斬新でした。
◇「逆迷彩蝸牛」あらすじ
伊豆半島の一部地域に生息するアカカタツムリ。個体数が異常に多く、家の中にも侵入してくる。人間や動物はアカカタツムリを見ると踏み殺さずにはいられない。踏み潰しても嫌な思いをするのだが、その衝動に抗うことができないのだ。地元では梅雨時の恒例行事だが、移住者には受け入れがたいようだ。何十年かに一度、アカカタツムリが大量発生すると地域は真っ赤に染まり地獄の様相を呈する。人間は体力が尽きるまでアカカタツムリを虐殺しつづけるのだ。
作品は10のchapterに分かれている。それぞれのchapterは1~7行で構成されていて、独特な間が生まれるのが面白い。たぶんchapterの存在がなくても文章として成立はするんだけど、雰囲気を出すにはこっちだろうな、と思った。あと読む側としてはありがたい。
読者側としては、文章が短ければ短いほど能動的に情報を拾いにいくのかもしれない。はじめに『ドン!長い文章です、じっくり読んでくださいね』となると、逆にボエ~ッと読んでしまう。イヤただただ私の話です、ごめんなさい。読書はともかく何度も読むようにしてます・・・。
それが意味深に「chapter01」と書かれた1ページを見ると、何かしらと思って拾いたくなる。ほうほう、短いけれど意味の通る文章だ。横を見ると「chapter02」がある。そのままスラスラと「chapter03」まで読んで「chapter04」で(あえっ!?)という展開が来る。
ところが、何故か人間を含め他の生物たちは「どうしてもアカカタツムリを潰さずにはいられない」という不可解な情動を喚起された。
noteの引用では反映できないのだが、本文には鍵カッコ内に傍点が付いている。強調に強調を重ねた表現、「何故か」「不可解な」という言葉選びには、語り手の価値観が反映されているように思う。といっても、キャラクターとしての語り手がいるわけではないのだけど・・・『本当になんでなんだろう?まったく不思議なことです』と驚いている印象がある。
でもアカカタツムリに同情しているわけではないようだ。「不可解な情動を喚起された」という言葉の堅さには、公平感がある。語り手は人間、他の生物、アカカタツムリのいずれにも肩入れしていない。ミステリにありがちな信用できない語り手とは真逆ってことだ。
そういう理由で、chapter07、08も、読んでてクスッとした。chapter6で地元の子供たちがアカカタツムリを踏みつけて遊ぶことが書かれたあと、こうくる。
chapter07
もちろん、生命を弄んで面白がっている大人もいる。
chapter08
犬や猫や鳥や家畜などは潰すだけでなく、そのまま食べたりもする。
几帳面な語り手だ。『子供たちだけじゃない、大人もだ』とchapterを変えて書き加え、さらに『いや動物たちは潰すだけに留まらないんだ、食べることもあるんだ』と付記する。特に「犬や猫や鳥や家畜」と、アカカタツムリを加虐する動物たちが具体的になんであるかも列挙しているあたり律儀で、とても好きだ。
◇アカカタツムリを踏みにいらっしゃい
たぶん、アカカタツムリが虫だから(うひょ~、やべぇ~)くらいの感覚で読めたのだ。鳥や動物だったら(ウッかわいそう)と思っていただろう。私はあんまり虫が好きじゃない。別に喜んで殺すほどではないが。そういう微妙なスタンスのひとは多いんじゃないか。
さらにアカカタツムリには絶滅の恐れがないことも示唆されている。該当地域のいたるところにいて、何十年かに一度は大量発生している。私は『さあ殺せ、殺しに来い』と語りかけられている気がした。観光促進PRではないが、そのおもむきがある。
そういう意味では食を前面に押し出した観光ポスターって、わりと猟奇的な側面があるんですよね。「牛が美味い!」「カニを食べに来て!」「鮎釣りイェーイ!」・・・まあ、人間本位ではある。観光するのは人間なので。
だから、アカカタツムリを通して人間の秘められた暴力性を明らかにしようとしているとか、そういう安易なことではなくてさ、倫理と道徳に則って殺戮する。そのための舞台を整えたのが本作なのだと思う。
だって、アカカタツムリを踏み潰した感覚って、ちょっと気持ちよさそうだものな。靴が汚れてイライラしそうでもあるけど。
殻をぱきっと踏み抜くと、そこからはみ出した体液のぬるぬるとした感触が伝わった。また、体液は溝の汚水にバニラミントを混ぜたような匂いがした。
このご時世に「虐殺」という言葉をみるとドキッとするし、(いいなっ、私も今年はアカカタツムリを踏み潰しにいこうっ!)とはもちろん思えない。しかし、老いも若きも気が狂ったようにアカカタツムリを踏みつけている、その景色は一生に一度の絶景だろうなと思いました。
LIST66 「罪の装い――〈つけぼくろ〉シリーズ全レビュー」稲田一声
※作品が閲覧できなくなったため、感想は差し控えます。
次回更新は5月24日の予定です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
