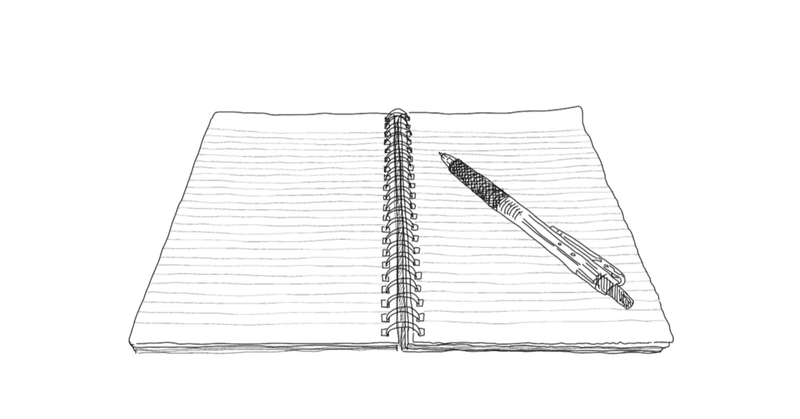
4. 病気は運。そう考えることにしたⅡ〜病気はバツやバチではない
父は運のいい糖尿病
オオタさんの死は、予想以上に大きな衝撃だったと言えます。「あんなに努力をしても報われないなんて……」。そう思うと、自分の努力まで否定されるような気持ちになりました。
その後も内科病棟には、糖尿病の患者さんが入院しましたが、その経過は、オオタさんよりはるかにましに見えました。
40代以降に発症し、多少食事に気をつければ、70代以降もそこそこ元気に暮らせる。そんな経過の人も、たくさんいたのです。
身近なところでは、私の父・宮子勝治(1927〜2000年)も65歳から糖尿病を患いました。そもそも糖尿病の原因は、長年の飲酒が原因で繰り返された慢性膵炎。飲酒をやめる気はさらさらない、不良患者でした。
カロリー制限が無理と判断した私は、主治医と相談し、早めにインシュリンを導入。今思うと、それも血糖コントロールには良かったのだと思います。
父は、若い頃一時獣医になる勉強をしていたため、「注射は大丈夫。牛や馬で実習した」と、全く抵抗感はないようでした。いや、これも運というか。人間、何が幸いするかわからないものです。
ただ、糖尿病については、運が良かった父ですが、その後患った肝臓がんについては、ちょっとした不運もありました。
糖尿病がわかった時、父は超音波検査で肝臓に怪しい影が見つかりました。以後、毎年血管造影検査を行ってきたのですが、たまたま父の予定と主治医の予定が合わない年があり、「まあ、大丈夫だよね」とみんなが思い、1年飛ばしてしまったのです。
そして、2年ぶりに行ってみると、父の怪しい影は、しっかりがんの顔つきになり……。結局はこの遅れが、完治の可能性を無くしたとも言えるのです。
父には肝臓がんである事実とともに、この1年の空白についても話しました。すると父は、「いや、あの検査はつらいから。やらなければやらないに越したことはない。気にしなくていいよ」。
本気でそう言っているように見える父は、先々の不安よりも、今の楽しみを大切にするタイプ。その後の父の経過については、また別のところでお話しします。
いずれにせよ、不摂生を絵に描いたような父の糖尿病がそこそこコントロールされ、ストイックに自己管理していたオオタさんがあのような経過だったのは、なんとも申し訳ない気持ちにさせられました。
偶然受けた胸部CT検査でがんが見つかったオクヤマさん
病気の経過が違うのは、もちろん糖尿病に限った話しではありません。がんなどは、発見から完治するかしないかの転帰まで、あまりにも多くの分かれ道があります。
私が働き出して数年後、病院の建て替えが進み、病棟が再編成されました。私が勤務していた内科病棟は、呼吸器内科病棟に。呼吸器疾患の患者さんが集まり、これまで以上に肺がんの患者さんをみるようになりました。
今、当時の患者さんたちを思い浮かべると、病気が見つかる段階から、運の善し悪しがあったように思えます。
その中で、最も運がいい人を思い浮かべると、大酒を飲んで路上を放歌しながら歩いていて転倒したという、オクヤマさんという男性が、思い出されます。
オクヤマさんは、この転倒で、胸部を打撲。肋骨骨折と気胸を起こしてしまいました。そして、現場近くの病院に運ばれ、気胸の治療をするために撮った胸部CT検査で、早期の肺がんが見つかったのです。
オクヤマさんは私が勤務していた病院での治療を希望し、まずは入院して呼吸器内科病棟で精査。外科に移って肺の一部を切除。完治に至りました。
オクヤマさんの何が幸運かと言えば、とにかくあのタイミングでのCT検査です。肺がんは、胸部レントゲン写真で発見されても進行している場合が多く、早期発見にはCT検査が欠かせません。
残念ながら、現在通常の健診で行われるのは、胸部レントゲン検査。この検査の目的はがんの発見ではなく、あくまでも結核の検査なのです。
レントゲン検査でも、肺がんの死亡率を下げる効果はあるのですが、やはり1㎝以下の腫瘍や、血管や心臓と重なった位置にある腫瘍は見つけられません。
肺がんを早期に見つけるためには、胸部CT検査にするべきなのですが、公的な検査では未だレントゲン検査が行われています。これは、1にコスト、2に被爆の問題があるからでしょう。
肺がんはごく早期であれば5年生存率8割の病気になっていますが、一方で、進行がんを含めた肺がん全体での5年生存率は2割程度です。たまたま撮ったCT検査で早期にがんが見つかったオクヤマさんが、いかに幸運か。この値を診ると、よくわかると思います。
オクヤマさんは、外科に移って手術をして完治できました。一方で、呼吸器内科病棟でそのまま治療を受ける人は、皆進行した肺がんの人ばかり。完治は難しいのが現実でした。
丸呑みした梅干しに助けられた母
運が味方してがんが見つかった例と言えば、私の母も、まさにその好例でした。
母は、70代で大腸がんの手術をしています。発見時、がんは漿膜という腸の一番外側の膜に達する寸前。親しかった病理の医師は、切除部位を検査し、「もう少し遅かったら、漿膜からでて、腹膜に播種するところだったよ」と、教えてくれました。
がんとわかるまでの経過は、かなり急な変化だったようです。
母はある日突然、外出先で水様便が止まらなくなり、私にすぐ連絡。それまでの便の状態を聞くと、「この数日、絵の具のように細い便が出る」というので、その時点で私は大腸がんを疑いました。
その後は私が勤務する病院で大腸内視鏡の検査を受け、がんと判明。全身のCT検査で転移も見つからず、すぐに手術が行われました。
そして、手術後。執刀した主治医は術後の説明で、実にオカシナことを言いました。「お母さまは、梅干しを丸呑みするクセがありましたか?」。
なんと、母の腸からは、大きな梅干しの種が2つ出てきたとのこと。後から本人に確認すると、当時母は芋がゆに梅干しを入れて食べるのに凝っていて、ついつい丸呑みしたかもしれない、と言うのです。
母のがんは、S状結腸という場所で、比較的症状が出にくい位置でした。しかし、がんに梅干しの種が2つひっかかって腸の内腔が細くなったことで、症状が急に強く出たのでしょう。
だから、急に便が絵の具のように細くなったのも、突然激しい下痢に襲われたのも、全て梅干しの種のおかげでした。
かゆに梅干しを入れてかき込んで丸呑みする。いかにも面倒くさがりの母のやりそうなこと。飲み込みが悪ければむせてしまうし、すでに慢性呼吸不全の状態だった母には、してほしくない食べ方です。
けれども、そんなよろしくない食べ方をしていたからこそ、母はがんがあのタイミングで見つかった。これもまた、事実だと思うのです。
病気は運次第と思うと……
オクヤマさんも、母も、なんというのか………。病気が見つかるきっかけは、ほめられたものではありません。けれども、オクヤマさんの転倒、母の梅干し丸飲みがなければ、かなりの確率で、2人のがんは発見が遅れていたでしょう。
結局のところ、病気のなりゆきや、そもそもの発症は、運次第。結局私は、ここに行き着いてしまうのです。
もちろん、なかには患者さんの行動と病状が、関連している場合もあります。いわゆる依存症の人などは、その典型。飲まなければいい酒を飲んで身体を悪くする。これもまた事実ではあります。
けれども、実際依存症の人を見るようになると、そうそう事態は単純ではないとわかってきました。まず、人間は、生まれる環境、どのような人間に生まれるかを選べません。
その人の意志の強さや病気に関する理解力も同様の面があり、「たまたまそのように生まれついた」「たまたまそのような環境に生まれたから、そのようになった」と思える例もたくさんあるのです。
一方で、こうした考えを受け入れるのは、実はかなり恐いことでした。例えば、「病気になるのは、生活態度が悪い人だ」とすれば、生活態度を改めれば、病気にならない。そんな希望が維持できます。
ところが、病気が運次第ならどうでしょう。もう、これは防ぎようがありません。防ぐ手立てがないとなったら、いつ何時病気になるかもしれない。これはとっても恐ろしいことでした。
やっぱり、病気になるのは、その人自身に責任がある。そう考える方が、不安から逃れられるのは事実です。
生活習慣病という言葉
私が看護師をめざして看護専門学校に入ったのが1984年。この間世の中も大きく変わりました。
この仕事に関連して強く感じるのは、世の中全体が今、自己責任を声高に問う風潮であること。病気の人はそのやり玉に挙げられているように感じます。
かつては成人病と言われた病気が生活習慣病と名前が改められたのも、この傾向に拍車をかけたのではないかと懸念しています。
生活習慣病とは、「食習慣・運動習慣・休養・喫煙・飲酒等の生活習慣が、その発症や進行に関与する疾患」。具体的には、以前は成人病といわれた、脳卒中、がん、心臓病などを指します。
生活習慣病という言葉は1996年頃から使われていますが、この用語への転換に際し、厚生省(当時)は、以下のような注意喚起を記しています。
<但し、疾病の発症には、「生活習慣要因」のみならず「遺伝要因」、「外部環境要因」など個人の責任に帰することのできない複数の要因が関与していることから、「病気になったのは個人の責任」といった疾患や患者に対する差別や偏見が生まれるおそれがあるという点に配慮する必要がある。> (厚生労働省,生活習慣病とは,https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/metabolic/m-05-001.html)
現状を考えると、こうした配慮が本当に行われていたのか。改めて振り返る必要があるのではないでしょうか。
もちろん、食事は食べ過ぎず、塩辛くない方が、煙草は吸わない方が、健康に良い。これは当たり前のことです。これである程度は病気になる可能性を減らせるのは事実でしょう。
しかし、だからといって、病気になる可能性をゼロにはできません。そうである以上、病気の原因を、生活習慣にばかり求めるのは間違いなのです。
予防のための方策と、病気になった原因は、分けて考える必要があります。
公正世界仮説とは
病気の人と関わる仕事を長く続けてきて、私自身の中にも、病気を何かのバツやバチのように見たくなる傾向を自覚してきました。
先にも書いたように、病気を運だと考えると、どんな病気も人ごととは思えなくなります。なぜなら、その病気になるかならないかは運次第。そう思うとなんとも言えない不安に襲われました。
そして、病気になるのは患者さんに何らかの落ち度がある。そう考える方が、この不安から逃れられるのは明らかです。
このような心理についていろいろ考えていくうち、「公正世界仮説」という考えに行き当たりました。

この考え方については、日本心理学会のサイトにとても分かりやすい資料があります。題して「人はなぜ被害者を責めるのか 公正世界仮説がもたらすもの」(https://psychmuseum.jp/show_room/just_world/)。
私たちは、世界に安定と秩序を求め、以下のような世界であってほしいと願います。
l 善人は幸せになり、悪人は不幸になる
l 努力は報われ、努力しなかった人は報いを受ける
l 悪いことをしたら必ず罰せられる
世界にこのような安定と秩序を求める考え方が、公正世界仮説です。これを信じるよい点としては、心の安定を得られ、未来に向かって努力することが出来ます。
しかし、この考えには、世界が公正であると信じたいがために、不運な目に遭った人を、不当に非難してしまう可能性があります。善人が病気になったり、努力しても病気が良くならない人がいては、世界の秩序と安定が信じられなくなるからです。
この概念を知って以降、私は自分の中にこのような傾向があることを自覚し、「待てよ」と自制できるようになってきました。
病気はバツやバチではない。私はこのことを常に肝に銘じたいと思います。

※今回から、第4水曜日の投稿も無料にすることにしました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
