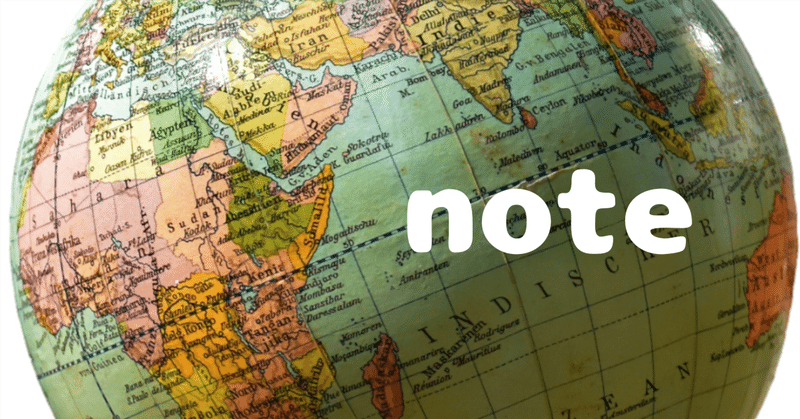
教育/学びの侵襲的な性質について
変化をもたらす
教育とは何か?
ある人間を望ましい姿に変化させるために、身心両面にわたって、意図的、計画的に働きかけること。知識の啓発、技能の教授、人間性の涵養(かんよう)などを図り、その人のもつ能力を伸ばそうと試みること
望ましい姿とは何だろう?万人が合意するような理想的な望ましい姿、というのは絵に描いた餅であるから、実際には教育を施す者が想定する、個別の望ましい姿が必ずあるということになる。すると、教育とは、教育を施す者が思い描く望ましい姿に、変化させることである。
教育と洗脳の違いはなんだろうか?
その人の主義や思想を根本的に改めさせること。「—されて組織に入る」
語義の点では、"知識の啓発、技能の教授、人間性の涵養" を図るものが教育であり、"主義や思想を根本的に改めさせる" のが洗脳である、という違いはある。しかし、そのような意味であるのならなおさら、教育という行為はときに一種の洗脳を伴うものであると言える。なぜなら、"知識の啓発、技能の教授、人間性の涵養" を図るために、"主義や思想を根本的に改め" させなければならないことがあるからだ。
不快を伴う
"知識の啓発、技能の教授、人間性の涵養" というのは、大雑把に言ってしまえば、成長だ。
成長には、不快や苦痛が伴うことが多々ある。成長できたことを実感したときには快感やら喜びやらが感じられるけれども、その手前にたいてい何らかの苦労や我慢、忍耐などがあることは、誰しもよくご承知の通りだろう。
単純に机に座って何かを勉強している時間が苦痛であるということ以上に、新しく何かを学ぶ行為には、独特の不快、苦痛がある。
この不快、苦痛は、薬指だけを動かそうとするときの感じに近い。実際にやってみていただくと、脳がイライラするというか、背筋がざわざわするような、妙な不快感を感じられることと思う。多分、ある種の成長痛なのだ。
今までできなかったことをできるようにする時に、脳や身体には相応の負荷がかかる。その負荷が無いと新しいシナプスは形成されないのだろうと、私は考えている。
まとめ
教育/学びは、侵襲的な性質を持つ。
生体の内部環境の恒常性を乱す可能性がある刺激全般をいう。投薬・注射・手術などの医療行為や、外傷・骨折・感染症などが含まれる。
侵襲というのは医療の用語なので、ここではあくまで比喩として侵襲的と言っている。おおむね以下のような内容を指していると考えていただければ私の考えと一致する。
教育は、学ぶ者の精神に非可逆的な変化をもたらすことを目的とする。
教育は、学ぶ者の精神に負担を与える。
何かを学ぶときには、自身が変化することを恐れてはならない。というより、変化しないのなら何も学んでいないのと同じだ。変化するために学ぶ。だから、学ぶときには積極的に変化を志向するほうが良い。極端に言えば、今までの常識や慣れ親しんだ自分なりのやり方はとりあえず一度捨ててみることを検討するべきだ。
また、ある程度の成長痛は受け入れなければならない。成長痛を感じるまさにその時にあなたは成長している、と考えるのが良いだろう。新しいことに挑戦するときに生じるストレスは、成長している証拠と言っても良いかもしれないくらいだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
