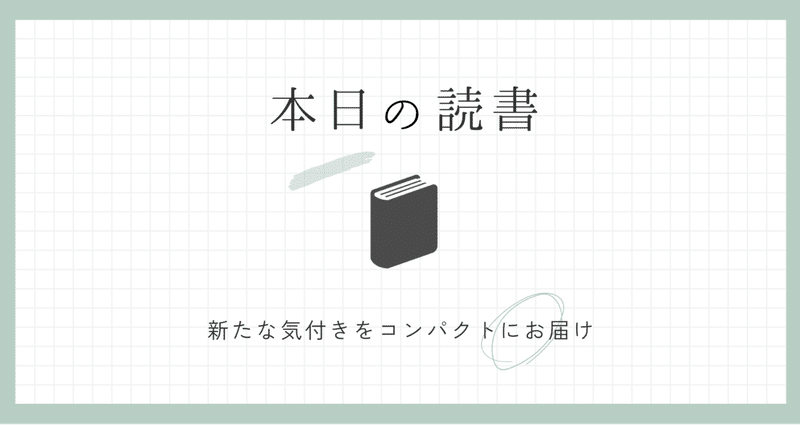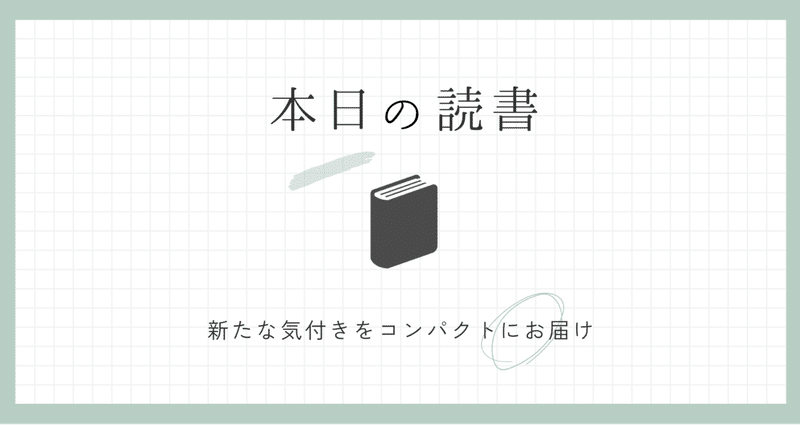本日の読書 #033 「スマホを無視することの難しさ」
参考書籍:『スマホ脳』 アンデシュ・ハンセン
第四章 集中力こそ現代社会の貴重品 より
スマホを無視することの難しさ。
本書の主要なテーマの一つだ。
スマホがただそこにあるだけで、集中力が阻害される。
直感的には「目に見えてなければ大丈夫」「電源を切ってあれば大丈夫」などと思いそうなものだ。
しかし著者によればサイレントモードだろうがポケットにインだろうが、スマホの存在そのものが集中力を落とすらしい。
これは脳の構造を考えれば確かにそうで、脳にとってスマホはドーパミ