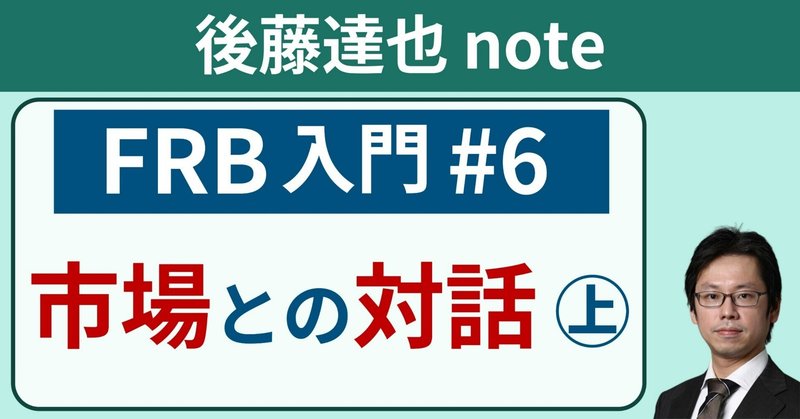
FRB入門 #6 市場との対話 ㊤
日本時間あす7/28(木)未明にFOMCがあります。直前の「FRB入門」のテーマは「市場との対話」。アメリカの金融政策を読み、そして楽しむうえでの醍醐味ですが、その意味合いのコンパクトな解説はあまり世の中にないように思います。
今回は大きなテーマなので、㊤㊥㊦にわけます。【㊤】はこの1年ほどを振り返りつつ、FRBの説明の変遷を確認。【㊥】はあすのパウエル会見という鮮度の高い題材を「市場との対話」という切り口で分析。【㊦】は㊤㊥の事例も踏まえたうえで、少し俯瞰して「市場との対話」を考え、そのおもしろさを感じていただければと考えています。
㊤を流し読みするだけでも、この1年の「FRBと市場のドラマ」を体感できると思いますし、あす未明のFOMCがグッとおもしろくなると思います。では、はじめましょう。
◆ まず1年前の7月
まず1年前、2021/7/28のFOMCでのパウエル議長の記者会見の発言を振り返りましょう。
・経済回復が完全なものとなるまで、いまの金融政策を続ける
・資産購入の変更(テーパリング)の時期は今後の(雇用などの)データ次第。まだ見極めるべきことがある。雇用の「進展」はほど遠い
・インフレは今後数カ月は加速を続け、その後緩やかになりそうだ。
・供給制約は予想以上に大きいが、こうした一時的な供給要因が収まるにつれ、インフレは2%に向かって低下すると予想する
・利上げを検討するのは時期尚早だ
・経済再開は前例のないもので、インフレが予想より高く、長引く可能性も高まっている
2020年春にコロナがアメリカを襲いました。20年夏ごろから段階的に経済が再開され、21年7月には経済活動はかなり正常化していました。とはいえ、コロナ危機からの回復途上です。FRBは経済・社会の正常化を最優先し、全力で金融緩和を続ける姿勢を示していました。
当時はFRBも、金融市場も利上げはほとんど関心外でした。金融緩和の修正という点で注目されていたのは、大量の資産購入を緩やかに減額する「テーパリング」でした。その議論では、物価よりも雇用の改善状況のほうが重視されていました。つまりコロナ危機から雇用の正常化が十分に進めば、テーパリングの議論を進めるという整理です。
インフレはあくまで「一時的(transitory)」と繰り返し、利上げは「時期尚早」としていました。本心ではもっとインフレリスクや利上げの可能性を意識していたかもしれませんが、この時期に利上げの思惑が広がってしまうと、長期金利上昇や株安を招き、経済再開に水を差す恐れがあったためです。つまり、こんな感じです👇

ただ、FRBをかばうわけではありませんが、1年前にいまのようなインフレがを予測した人はエコノミストはほとんどいませんでした。コロナ危機、そこからの経済再開はFRBがいうように前例のない事態で、過去の経験則から予測するのが極めて困難でした。だからこそ、上記の会見にも「インフレが予想より高く、長引く可能性も高まっている」とヘッジをかけています。
◆ 急転換の難しさ
そして、下記が当時の想定と実際のインフレ。

「一時的」としてきたインフレはむしろ加速し、国民の不満・不安も一気に高まりました。こうして秋ごろから「経済正常化 > インフレリスク」を急速に修正せざるをえなくなりました。
しかし、「市場との対話」で発言の急転換はなるべく避けたいものです。発言が急に変わると、金融市場にサプライズとなり、好ましくない金利急上昇や株価急落を招きかねません。
そしてなにより信認が揺らぎかねません。日常生活でも言うことがコロコロかわる人は信用できませんよね。中央銀行だとなおさらです。「インフレは一時的、利上げは時期尚早」といった翌月に、「インフレが深刻、利上げが必要」とひっくり返されると、今後の発言も信用されなくなってしまい、コミュニケーションが機能しづらくなります。
もちろん経済もマーケットも日々動くので、発言を頑なに保つ必要はありません。しかし、中央銀行は将来も見据えて、慎重に言葉を選ぶ必要があります。発言を修正する際も無理のない範囲で段階的に修正していくのが王道です。
◆ 発言の変遷
その後のパウエル議長の発言と政策変更をごくコンパクトに振り返ります。ざっと読み流しでも結構です。
【2021/8/27 ジャクソンホール会議】
・「資産購入の減額は年内が適切」
・市場は11月ごろのテーパリングを意識
・「テーパリングは将来の利上げ時期の直接的なシグナルではない」
→ 利上げの思惑が強まらぬよう念を押す(まだ経済正常化>インフレリスク)
【2021/9/21 FOMC】
・「経済順調ならテーパリングは11月のFOMCで決定」
→ 8月の地ならしに続き、テーパリングを「予告」
・「来年中頃のテーパリング終了が適切となる可能性」
・「利上げのタイミングに関する直接的なシグナルではない」
→ 8月発言を踏襲し、利上げの思惑をおさえる
【2021/11/4 FOMC】
・テーパリング決定。月150億㌦ずつ減額
・インフレ、「加速しているが大半は一時要因」「2022年半ばにかけ低下と予想」
・「利上げは経済次第。必要なら躊躇しない」
→ 9月より踏み込んできました
・供給制約は「予想以上に長期化」
※ この間にバイデン大統領がパウエル議長再任の意向を示しました
【2021/12/15 FOMC】
・テーパリングを加速
→ 前回会合で決めた政策変更を早々に修正するのは異例
・インフレ「一時的(transitory)」の表現を声明から削除
・「幅広いモノ・サービスでインフレ」
・「資産購入終了で適切な政策対応が可能に」
・2022年の利上げ見通し「3回」に引き上げ
→ いろいろかわり、一気に利上げモードになってきたことがわかります
【2022/1/25 FOMC】
・「利上げがまもなく(soon)適切に」
→ 事実上の3月利上げ予告
・利上げのペースは「現時点で決めていない。経済次第」
・資産圧縮(QT)は利上げ後に開始
・テーパリングは3月に終了
→11, 12月の急な地ならしのうえで「利上げ予告」。ただし、いまのような大幅利上げの言質は与えていません
【2022/3/16 FOMC】
・0.25%利上げ
・一時は0.50%利上げ観測もあったが、ウクライナ戦争も影響し、0.25%に
・年末の政策金利見通しを1.75-2.00%に引き上げ
・QT開始を示唆
・「供給面の混乱は予想以上に大きく、長引いている」
・「高インフレは深刻な苦境」
【2022/5/4 FOMC】
・0.50%利上げ=通常の2倍
・インフレは「あまりにも高い」
・6, 7月FOMC「0.50%利上げが議論されるべきだとの考えをFOMCで共有」
・(Q: 0.75%利上げの可能性は?)「積極的に検討しているものではない」
→実際は6,7月とも0.75%利上げとなりそうです
・量的引き締め(QT)開始
【2022/6/15 FOMC】
・0.75%利上げ
・インフレ「再び上振れ、驚かされた」
・年末の政策金利見通し「3.25~3.50%」に引き上げ
・7月FOMC「0.50%か0.75%利上げの可能性が高い」
・「考えはできる限り、明確に伝えていく」
いかがでしょうか。急激な変化とともに、FRBの苦労もわかるかと思います。この流れを踏まえると、7月FOMCの見え方ももっと多層的になりますし、年末にかけての政策も少しイメージしやすくなると思います。
◆ 最後にマーケット
最後に市場も振り返りましょう。先日お伝えしたように2年債は今後2年間の政策金利予想とほぼ同じです。下の青い線、2021年6月ごろまではほぼゼロ。つまり「今後2年は利上げはないだろう」とみていたわけです。それが21年秋ごろから一気に上昇しました。そして、株価も急激な調整に見舞われました。

こうしたチャートも、きょうみてきたようにFRBの発信とあわせて振り返ると、金融政策・金融市場との関係がより深みをもって理解できます。そしてなにより壮大な経済ドラマであるともいえます。
【注:以下、㊥㊦を配信後に上書き】
㊥は7月FOMCのパウエル議長の記者会見をケーススタディーとして読み解きながら、「対話」の難しさとおもしろみを伝えています。㊦は「市場との対話」の意味合いを俯瞰してまとめています。(下記リンク)
こうした話題は分厚い教科書を詰め込むように学ぶよりも、リアルタイムで起こっていることを解きほぐす方が関心を保ちやすく、理解が進みやすいと思います。これからも鮮度の高い話題を起点に、本質的な話に掘り下げていければと思っています。いくつかの記事を読んでいるうちに話がつながっていき、立体的に経済や金融市場がみえるようになるよう、がんばって編集していきます。
後藤達也
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
