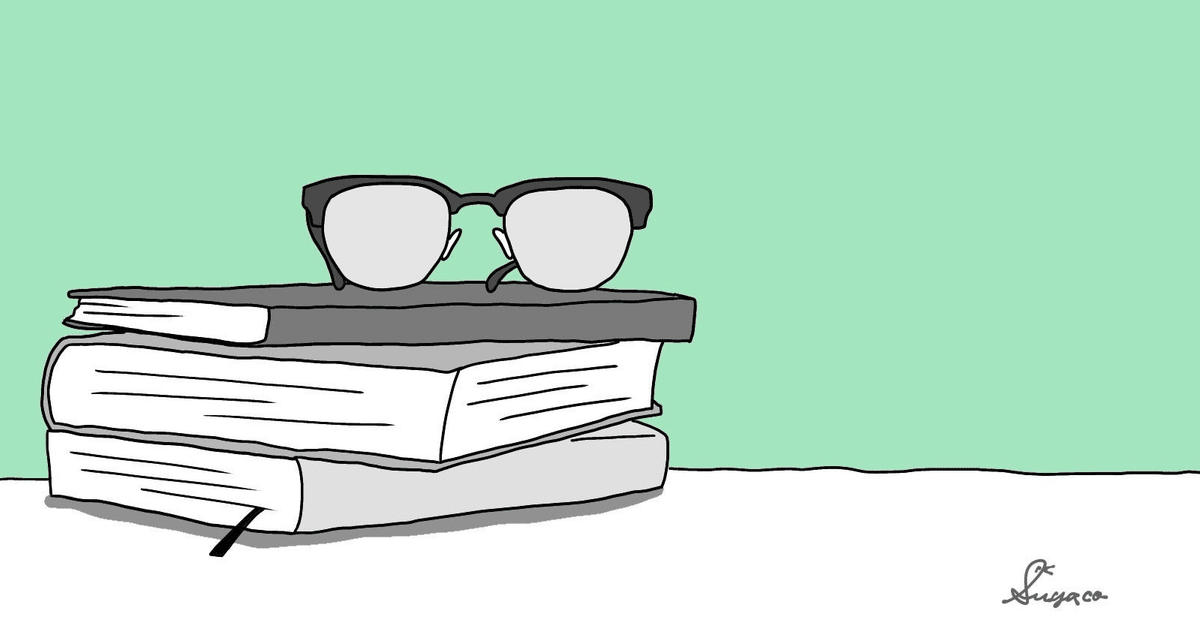
今の子供達のペットには鷹を推奨したい
両眼性複視と言うのは、両目で見ると、1つのものが2つ3つにぼやける症状です。
左右ともに片目だけで物を見る時は問題ないのが乱視との違いです。
私は三年位前から、この複視の症状に悩まされています。パソコンなどで仕事をする時、目の調子が良ければプリズム眼鏡(めちゃ重い)を使いますが、それでも見えないときは、単眼視するために眼帯のようなものを使っています。ビジュアル的には海賊、もしくは厨二病をこじらせたような感じです。痛(涙)。
今回は、
「結論から言うと私の眼はタイムマシンがないと治せないという事がわかった」
というお話です。
最初に目の不調を感じて近くの眼科に行った時のこと。
遠くの文字を見てみる。あ、普通にちゃんと読める。次にネコのカレンダーをを見てみる。あれ?ネコは1匹なのに、2、3匹に見える。
先生曰く「猫ちゃんや人間はねぇ、増えやすいんですよ。」とのこと。
そんなことある?!と思ったけれど、体験してみて分りました。そうなのです。
特に制服やスーツ等、同じような服を着た人たちが数人いると、全く数えられません。
多分もう野鳥の会には入れません(涙)。
両眼性複視は、眼球そのものではなく、視覚情報を映像化する脳の問題なのだそうです。
看板の文字などは、認識の方法が違うので増えにくいのだとか。
人間の脳って面白いですよねえ。
そのうち段々、色々なものが増えるようになりました。
見え方は自分の体調や物との距離にもよるのですが、公園の噴水がピタリと真ん中で重なって2つに見えた時は、キレイすぎて感動しました。
あと、マジカルアイってご存知ですか?目の焦点をずらすと、イラストに隠された文字や、画像が浮かび上がって見えると言うアレ。
試しに見てみたのですが、ちゃんと焦点をずらして、隠された画像を浮かび上がらせることができました。が、それもきちんと2つ重なって見えました!!
どういう理屈かわからないのですが、焦点をずらすことによって浮かび上がるその映像も2つ見える。これ、世界中でも見たことある人少ないんじゃないかなぁと思いました。
そんな複視ライフを送っていたわけですが、
脳や血管に問題があるとしたらちょっと心配。
でも複視はMRI等調べても原因が分からない事が多いと聞きます。
そんなとき心療眼科医である若倉雅登先生の
「健康は"眼"に聞け」
という本に出会いました。
本に記載されていた症例を読んで「まさに私これかも!」と思い、何も考えずに著者である若倉先生の診察を予約しました。
実は先生は、東京お茶の水の井上眼科病院の名誉院長で有らせられ、偉い方だというのは後で知りました(汗)。
でも飛び込み患者の私を、とても親切丁寧に診察して下さいました。
そして私の症状もズバリ先生の仰る「窮屈病」である事がわかりました。
強度近視によって眼軸が伸び、眼球が収まるべき頭蓋骨の中(眼窩)でパンパンになって動けず、問題が生じていたのです。
詳しく知りたい方は若倉先生の著書またはコラムをどうぞ。
(自分で上手に説明出来なさすぎて(すみません)ググったら見つけました。)
ええと、結論から言うと、私の複視は治りません。
先生曰く「数十年前に来てもらってたら、治せた」とのこと。
右目と左目は見えているものが違います。それを頭の中で調整して物を見ているんですよね。
その力が「視力」なのだそうです。
動体視力や空間把握など「視力」と言うのは、絶対音感や言語等と同じで、視力が発達する子供の時に鍛えないとダメなのだそうです。
「視力」とは、ドーナツみたいなアレの上下右左の切れ目が当てられるかどうかだけの問題じゃなかったのです!!!
例えば外科手術で眼球の内転をコントロールし、外見的に斜視などを治すことは出来たとしても、その目で捉えた物が正しく見えるかどうかは「視力」の問題で、大人になってから「視力」を身につけることはもう出来ない。
うわーん、確かに私本ばかり読む子供だったし、ドッヂボールとか超絶苦手だった〜〜。
時は戻せないので、せめて私の周りにいる良い子のみんなには、
外で遊んだり、遠くを見たり、
いっそペットに鷹とか飼ってみない?と勧めたい。
こんなに近くの強い光ばかり見る時代は今がピークなのかもしれませんが、人間が成長過程で「視力」を伸ばせる時期は限られているのです。
ああ、テックフリーが一周まわるまでは、あえて鷹を飼えと言い続けたい。
昔友人が「小笠原に行ったとき、鯨を見たすぎてずっと遠くを見ていたから目が良くなった」と語っていたのを思い出しました。
私の目(本当は脳)も小笠原に行ったらちょっとは良くなるのかなあ。
今日はここまで!
若倉先生のコラム一覧です。
心療眼科医・若倉雅登のひとりごとhttps://yomidr.yomiuri.co.jp/column/wakakura-masato/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
