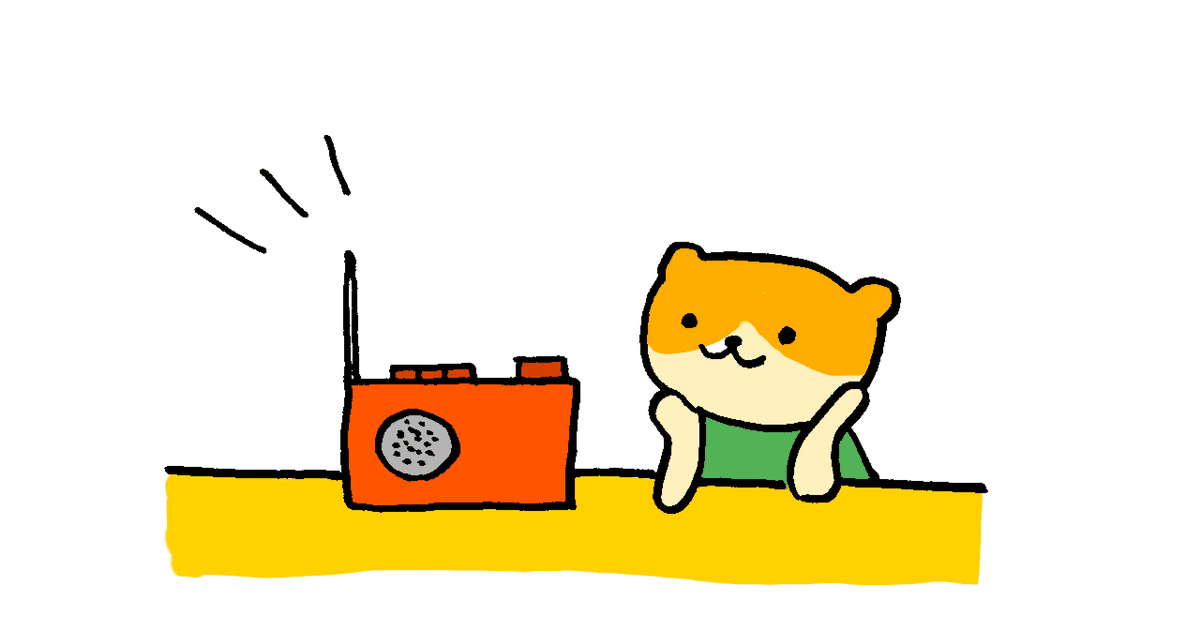
自分に合った推し活を見つけた2023年
近年定着してきて耳馴染みしてきた「推し活」という言葉。現在大学3年生の私ですが、高校生の頃から推し活というものを始めました。小学生の頃からお笑いが好きで、バラエティー番組を見ることが好きでした。
40〜50代おじさん芸人しか見てこなかった私が、なんとHey! Say! JUMPというアイドルグループにハマり、CDやアルバムを買って満喫していました。同じ年に、星野源とあいみょんの音楽性に感銘を受けすっかり沼に落ちました。
今までの推し活
私にとっての推し活とは、見せること・語れること・課金できたら課金することでした。特に、語れることには力を降り注いだつもりです。初めてSNSアカウントを作り、同じ界隈の人と繋がったり、共感できる推しに対する呟きをいいねしたりしていました。お笑い界隈とアイドル界隈とアーティスト界隈でアカウントを別にしてアカウントを3つ作りました。さすがに3つのアカウントの使い分けに疲れてしまって、お笑い界隈とアイドル界隈のアカウントだけ残して、見る専のアカウントを作りました。
しかし、納得いく推し活ができず、何度かアカウントを変えてきました。何が満足できなかったのか自分でもよく分かりませんでした。
ニセ明(星野源)の言葉
私は、普段から星野源のオールナイトニッポンを聴いているのですが、その中で好きなコーナーがあります。「ニセ明のオールナイトニッポン」というミニコーナー。星野源扮するニセ明がリスナーのお悩みを解決してくれるんです。
ちなみに、ニセ明というのは、星野源が生み出したサングラスをかけた謎の歌手のキャラです(名前は布施明に寄せています)。英語訛りなクセの強い喋り方と艶のある長髪が特徴です。
実は、このニセさんのコーナーに届くお悩みが真面目なものが多いのです。ニセさんの砕けた喋り方と徐に寄り添ってくれる真剣な言葉が刺さるのだと思います。だからこそ、誰にも言えないような悩みだったり心の奥で思っていることを打ち明けられるのかもしれないです。
2023年に放送された回で、私の推し活に対する考えが変わりました。
その回で読まれたお悩みが、「自分の"好き"をSNSで発信することに満足できていない、どうすればいいか」というようなものでした。
ニセさんは、学生時代は自分の"好き"を周りの人と話し合える環境にいなかった、と話します。今の若者はSNSというものがあって、気軽に推しについて語り合うことができて羨ましい。でも、今思うと自分が誰にも話せなかったのは良いことだったのかもしれない、と話し始めます。SNSが身近なものだと、好きでいることより発信することに力が入ってしまう。本当に推しのことが好きなのか、はたまた推しのことが好きな自分のことが好きなのか。
このお悩みを送った方に対するニセさんの答えはこうでした。
「一旦SNSでの推しツイートや投稿をやめてみる。できれば1年くらい。自分の心の中だけで"好き"を発信する。1年経ってみてそれでも好きなら、本当に推しのことが好きということだから、またSNSを使って投稿してみてもいいんじゃない」
読まれたお悩みが、まさに自分が感じていた謎のモヤモヤと通ずるものがあり、ニセさんの答えにビビッとくるものがありました。そこから、推しに対する投稿や呟きをやめてみました。いいなと思ったり好きだなと思ったことはできるだけ自分のノートに書き留めてみました。ポケットプリンターで推しの写真を印刷してペタペタ貼ってみたり、絵を描いてみたり。ニセさんの言うように、心の中で楽しみました。
数ヶ月間続けてみると、お笑いやアーティストに対する"好き"が強くなっていました。お笑い番組の感想を紙に書き出すことが増えました。逆に、アイドルオタクをやめるきっかけにもなりました。私はSNSアカウントを使って、着飾ってアイドルオタクをしていたんだな〜と気づかされました。別に嫌いになったわけではないけど、離れることでちょうど良い距離になったように思います。
今の私の推し活
今はお笑い界隈のアカウントだけ使って、たまに投稿しています。月に数回くらいのペースなので本当に少ないです。推し芸人の出演する番組の投稿をリポストすることが多いです(笑)M-1とかキングオブコントのような賞レースの感想は全部自分のノートに書き起こしています。今の私にはこれが一番合っているみたいです。
見る専用のアカウントも継続して使って、そちらでは好きなアーティストやデザイナーさんをフォローして楽しんでいます。インプットとアウトプットを上手く分けること。自分の心のうちで楽しむこと。この2つが私の推し活には大事だと気づくことができました。これもニセ明さんのおかげです。ありがとう、ニセさん。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
