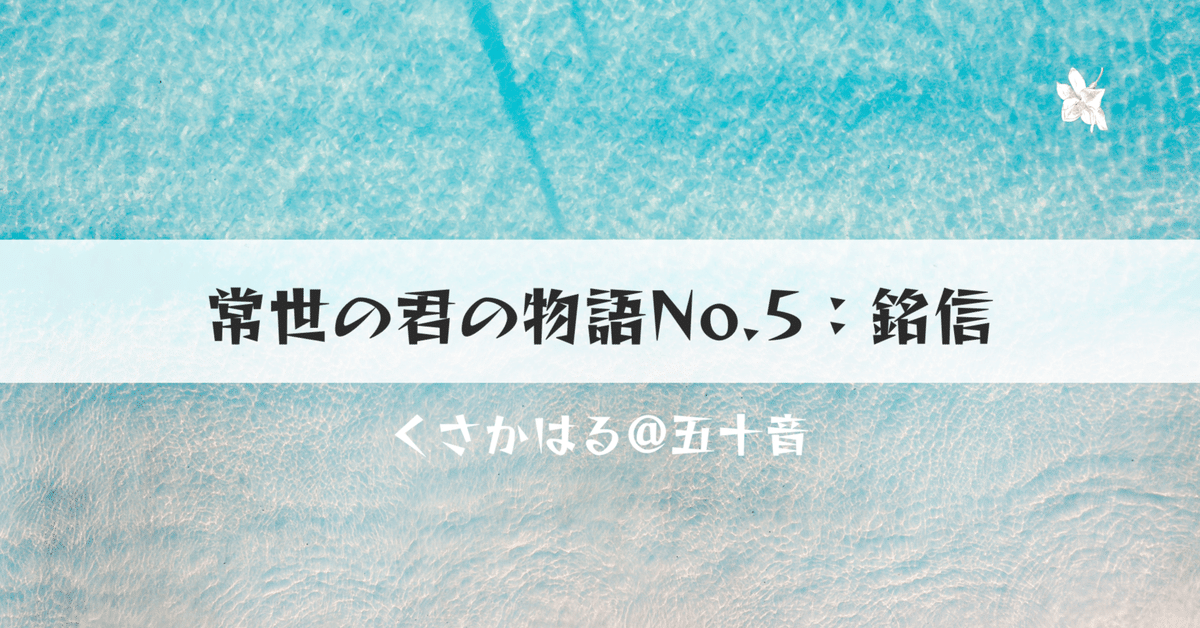
第二章:九星
九朗は、舞に見とれて動かない兄をほっぽって、長門の町はずれのある廃寺まで足を延ばしていた。
午後の一番暑い最中、太陽はいよいよ勢いを増し、それにこたえるかのように方々の木々から蝉の声がこだましている。
陽炎が立ち揺らめく中、九朗は廃寺の入り口に立った。
「きゅうせいさーん」
廃寺の中は、折からの大飢饉による死者であふれかえっていた。
九朗のいる廃寺の入り口付近にも、瘦せさらばえた死体の山が、うずたかく積まれている。
夏場にあって、そこここの死体にはうじがわき、野良犬と烏が競うようにそれらを漁っている。
「九星さーん」
あまり長くはいたくはない場所なだけに、九朗は声を張り上げる。
「はぁい」
九星と呼ばれた、既に老年ともいってよい女人は、手ぬぐいで両手を拭きながら玄関口に現れた。
その面には深い皺が刻まれ、笑うといっそう、それらが目尻に濃い影を落とすのであった。
「あらあら、九朗。今日は、お兄さんは?」
一人で立っている九朗をいぶかしがり、九星が問う。
「今は女に夢中。つまらないから遊んでもらいに来た」
「あらあら。こんなぶっそうなところへ一人で来るだなんて」
手ぬぐいで頭上に影をこしらえながら九星が言う。
「今は町じゅうに死体があふれてるだろ。どこも一緒だよ」
九朗はこともなげに言ってのけた。
死があまりにも身近な時代、それでも、血気盛んな子供の目には、それはどう映ったろうか。
子供は親の影響をよく受ける。
死が間近にあり、親が弱っていれば、子も弱る。
一方、親の元気な銘信や九朗のような子供の場合、死がいくら身近にあろうが、食うに困らぬ身である以上は、それは他人事である。
「九星さん、今日も、行くの?」
「行く」とは、九星の日課のことであった。
九星は、一年ほど前からこの町に住みついている。
身よりのない独り身の尼僧が、あてもなく流れ着いたといった方が合っている。
はじめは知り合いなどどこにもいなかった。
町はずれの廃寺にひとり居を構え、近辺の者たちの施しを受けて暮らしていた。
しかし折も折、巷を飢饉が襲った。
九星は方々で死体に経をあげてくれと頼まれるようになった。
懸命に勤めている間に、徐々に知り合いも増えていった。
そうして今では、町では知らぬ人はいないほどの有名な尼僧となっていた。
そんな九星のここのところの日課は、町へ繰り出して、そこここに転がる死体の額に文字を記すことであった。
九朗がついていきたいと言っているのは、この練り歩きのことであった。
「楽しくは、ないわよ」
九星は、言う。
「死者の魂を送ってやるんだろ、分かってる」
このあいだした説明を、九朗は覚えているようであった。
九星はにっこりと笑みを返す。
「じゃあ、一緒に行きましょうか」
「うん」
二人は連れ立って、まだ日差しの降り注ぐ暑い最中を、足元に濃い影を落としながら町の方へと歩いて行った。
「九星さん」
「九星さん、うちの母ちゃんにも、文字を」
ゆくりゆくりと歩いていると、方々の路地から九星を呼ぶ声がする。
それは身内をなくした者たちが、遺体の額に文字を書いてくれとせがむ声であった。
「はいはい、ただいま」
九星はどんなか細い訴えにも、快く応じてゆく。
九星が路地裏に入り、死体の横に膝をつき、懐から墨壺を取り出し筆をつけ額に文字を書くのを、九朗はつぶさに見つめていた。
幼い目には、九星の仕業がことごとく物珍しく映る。
「九朗は、暑いのに一緒に歩いて、立派ね」
九星は九朗をそのようにして時折褒めた。
「九星さん面白いから」
子供ながらの残酷さなのか、九朗はそのように返す。
「九朗は、離れておいでねぇ。病の者もいるから。うつったら大変」
口に布をした二人は、肩で息をしながら死体の中を練り歩いてゆく。
「ねぇ、九星さん」
「なぁに、九朗」
「俺も死んだら、額に文字を書いてね」
「まぁ、九朗ったら」
子供の時間間隔が、九星には懐かしく感じられた。
己以外の者が、己の成長とともに永遠にあるかのように思える時期――。
九星にも、そのような時期があった。
九星は、瀬戸内は伯方という村の生まれであった。
幼い頃より他人の世話が好きで、十六になる頃になると村の子供たちを一手に引き受けていたほどである。
その村に、ある日、海賊が押し寄せてきた。
今でもはっきりと覚えている。
九星は、その一件で仲の良かった一太という友人を亡くした。
九朗は、どこかその一太を思い起こさせる。
仲の良かった一太。
けれど一太が死んだとき、九星は「ざまぁみろ」と思ったのだった。
一太が死ぬ直前に喧嘩をしていたからである。
死んでしまった者に対して、なんということを思ってしまったのか。
いたたまれなくなり村を出て、長じてからは四国の讃岐という村でやっかいになったこともあった。
そこで九星は、無残にも子供が殺されたり自ら死んでゆくさまを立て続けに見ることなった。
そこでも九星は、「言わんことではない」といった気持ちを抱いたのだった。
彼らが死ぬ直前に言葉を交わし、言い分を受け入れられなかったからであった。
死者に対し、なんということを――。
そんな己を、九星は恥じた。
そうして、己には、たとえ子供であろうが、自らの言い分を聞き届けさせたい性分がある――。
強くそのことを自覚した。
自覚してから、九星は尼になろうと考えた。
僧であれば、日々普通に勤めを行っているだけで、他者から尊敬され、言い分を聞いてもらえる存在となることができるから。
まさか目の前の九朗は、九星がそのような算段でもって死体の額に文字を書いてまわっているとは思わない。
九星は知っていた。
己の浅はかさを。
しかし、どうにもならないその思いが、九星をして今日も日々の勤めへと走らせているのであった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
