
中原中也の詩「僕が知る」の狂気と現識
■■■
「僕が知る」は
「坊や」と同じ日に制作され
「中原中也追悼号」となった
「文学界」昭和12年12月号に掲載された作品です。
死亡後の発表ということで
「生前発表詩篇」には分類されません。
詩人は
この作品を
生きているうちに
読むことはなかったのです。
◇
僕が知る
僕には僕の狂気がある
僕の狂気は蒼ざめて硬くなる
かの馬の静脈などを思わせる
僕にも僕の狂気がある
それは張子(はりこ)のように硬いがまた
張子のように破けはしない
それは不死身の弾力に充ち
それはひょっとしたなら乾蚫(ほしあわび)であるかもれない
それを小刀で削って薄っぺらにして
さて口に入れたって唾液に反発するかも知れない
唾液には混らぬものを
恰(あた)かも唾液に混ざるような格構をして
ぐっと嚥(の)み込まなければならないのかも知れない
ぐっと嚥み込んで、扨(さて)それがどんな不協和音を奏でるかは、僕が知る
(一九三五・一・九)
◇
「狂気」についての詩ですから
すぐさま思い出すのは
「狂気の手紙」ですが
こちらは手紙の形を借りず
直(じか)に
僕の内にある狂気、
僕という狂気を見つめます。
それは
蒼ざめて硬く
馬の静脈を思わせたり
それは
張子のように硬く
張子のようには破けない
それは
不死身の弾力があり
乾鮑(ほしあわび)みたいなものかもしれない。
小刀で削って薄くして
口に入れても唾液に溶けないかもしれない。
唾液に混ざらないものを
熱心に混ぜようと頑張っても
ぐっと飲み込まなければならないものかもしれない。
飲み込んでも、その後、体内に容易に溶け込まないで
おなかの中でゴロゴロしていることは
僕がよく知っている。
◇
僕の狂気は
僕がよく知っていることで
あんたにゃ言われたくない! とでも
言いたかったことがあったのでしょうか。
特別な事件があったというより
詩人が
そのことを常々考えている詩そのものとか
死とか生とか
永遠とか
人間そのものとか
生身の生存とか
肉体であるとか。
ひょっとして
現識とか。
名辞以前とか。
かつて「夕照」(「山羊の歌」所収)で歌った、
かかる折しも我ありぬ
少児に踏まれし
貝の肉。
――の「貝」と同じものであるとか……。
◇
馬の静脈
張子
乾鮑
……。
狂気の実体が例示されていますが
ほとんど了解できるようでいて
何だか分からない
抽象化すれば狂気としか言いようにない。
名辞以前や現識を
狂気と言い換えてみたのかもしれない。
◇
簡単に分かってたまるかと
詩人は言いたかったのかもしれない
最終連、
唾液には混らぬものを
恰(あた)かも唾液に混ざるような格構をして
ぐっと嚥(の)み込まなければならないのかも知れない
ぐっと嚥み込んで、扨(さて)それがどんな不協和音を奏でるかは、僕が知る
――の4行が突き刺さってきます。
僕しか知らない、と。
◇
今回はここまでです。
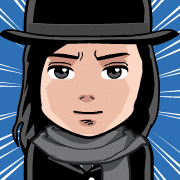
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
