『源氏物語の結婚-平安朝の婚姻制度と恋愛譚』 工藤重矩 中公新書
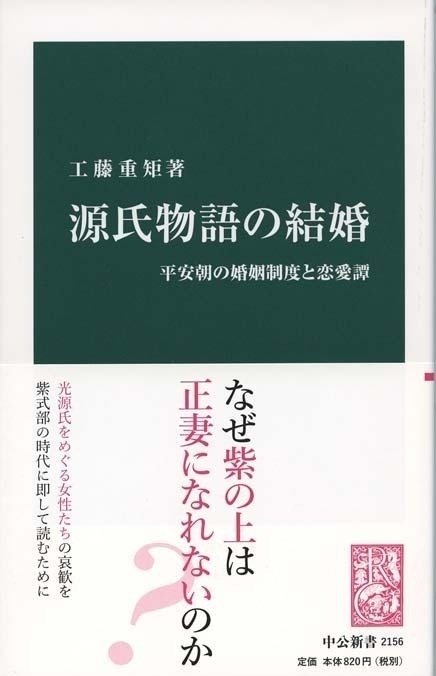
しばらく前に読んだのだが、予定外の本に手を出してしまった。きっかけは、「家族を規定したのが「なるちゃん憲法」」で紹介されている天皇家が、いかにも軽く里子に出していたかという史実だった。当時、その年のNHK大河ドラマは、「平清盛」で、久しぶりに興味深くこの物語を毎週楽しみに観たが、色恋ものの風情がいまいちピンとこなかったため、本書を読んでみた次第。
「源氏物語」は、日本最古の小説として、あるいは世界最古の長編小説としての評価と、平安期の貴族社会における優雅な恋愛物語という視点が強固で、古典中の古典として見られている。それだけに、異なる視点や新たな解釈を寄せ付けない傾向もある。
中学や高校の古典で読まされ、結構ウンザリした。理由は、古典が好きじゃなかったというのが大きな理由だが、年もとって視点も変われば、これほど面白いものはないと言える。
この面白い視点は、著者が文学者ではあるにも関わらず、平安の法制史を軸に、当時の結婚制度と社会文化に基づいて源氏物語での人間関係の構造を解明していくところにあると感じた。
高校の古典の授業で、平安期の日本は一夫多妻制で、通い婚だったという前提で読んでいた記憶がある。源氏物語の他にも、蜻蛉日記や落窪物語などがあった。
ところが、これは間違いで、平安時代でも日本は法律上一夫一妻制で、夫と正妻は一緒に住むのが基本だったとわかる。光源氏にとって、正妻とは葵の上と女三宮の二人のことで、残るヒロインたちは妾か愛人という立場だった。この点は、学校教育でも正妻として教えられたが、他の登場人物が非法的な男女関係であることまでは教えられなかった。今から思うと、未成年への当時の教育者の立場ということだったのか?なんか、そういう時代だったのだ。
つまり、紫の上はお妾さんで、六条御息所は愛人だったということ。ここでは妾と愛人の違いには触れないことにする(機会があったらどこかでまた)。このことを推理するのが難しかった理由に、それぞれのヒロインには社会的地位やその背景があったためだとは思うが、正妻になれない理由や正妻の座をめぐる葛藤があった。本書が面白いのは、こういった部分に、当時の法制度や社会文化に対する見解が加えてあり、その理解だろう。当時の背景を知れば知るほど、プロットの緻密さや物語の完成度に驚かされる事になる。
疑問の数々
光源氏がなぜ左大臣の娘である葵の上と結婚するはめになったのか。
葵の上が死んだ後、なぜ六条御息所と再婚しなかったのか。
紫の上はなぜ妾のまま正妻に次ぐ地位だったのか。
紫式部はなぜ葵の上に息子を産ませ、明石の君に娘を産ませたのか。
紫の上になぜ子どもをつくらせなかったのか。
これらの疑問が解けてくると、紫の上は親が押しつけた結婚ではなかったことが明快になる。
そこでああ、子どももいないのだから純然たる愛以外に光源氏との結びつきが存在せず、だからこそ儚かったのだと至る。因みに、個人的には「愛」は儚くはないが、「恋」は儚い終わりしかないと思っている。
逆に、光源氏の立場は厳しい物だったに違いない。
臣下として生きていく以上は、政治的な後ろ盾が不可欠であり、桐壺帝が後見になれない以上、他の有力者の支援を得なければ、朝廷での出世や生き残りは難しかった。政略的に、年上の左大臣の娘を娶る他なかったわけだが、それは親同士の取り決めで今で言うところの「お見合い」であって、本人の気持ちは別のところにあったと言える。
衝撃を受けたわけじゃないが、正妻とは和歌のやりとりなんてしないという点。当然だが、同居している正妻と一々和歌をやりとりする必要などあるわけがない。和歌とは、想う人への恋心を歌うものであるという認識も確固たるものになる。愛情を注ぐ愛妾が離れ他場所に住んでいる、という物理的要因故に和歌を託すもの。
「源氏物語」を理性的に分析すると味気なくなるからか、あまり評価は芳しくないらしい。
和歌が不倫メールという認識に立ってみると、「源氏物語」の今日的な価値も高まるかもしれないと感じた次第。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
