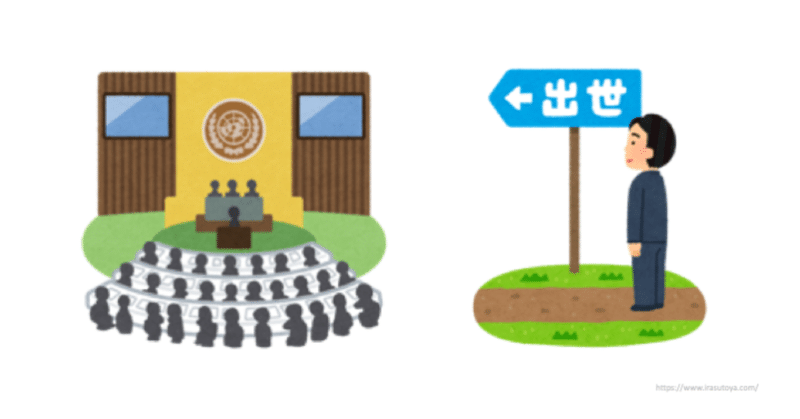
WHO「本部」で活躍できる人材とは?
諸事情がありWHO本部から某国の国事務所に異動することになった。その詳細についてはおいおい触れるとして、今回の一件はWHO本部に向いているのはどんな人材か?について深く考えさせられた。あくまでも私の経験に基づいた話で一般化できないかもしれないが、これから国際機関を目指す日本の若者の参考になるかもしれないので以下にまとめたい。
WHOの役割・機能を理解する
FrenkとMoonは、WHOを含むグローバル・ヘルス・システムの機能を4つに分類している。
1. Production of global public goods (例:国際基準やガイドラインの作成)
2. Management of externalities across countries (例:公衆衛生危機対策)
3. Mobilization of global solidarity (例:途上国への技術支援・資金供与)
4. Stewardship (例:決議や条約の制定)
私もこの分類は正しいと思うのだが、もう一声、深く掘り下げた方がよいと思う。特にWHOでは、本部-地域事務局-国事務所の3層で上記の4機能をどう分担しているか理解することが重要だと思う。それを個人的な主観に基づいて勝手にまとめたものが以下の図である。

例えばガイドラインの作成等は本部が中心となって行われるのに対して、国に対する技術協力等は国事務所が中心となる。StewardshipはグローバルレベルではWorld Health Assemblyが、地域レベルではRegional Commiteeがある。こうした3層の違いを理解すると、自ずと本部に向く人材・向かない人材が明らかになる。
WHO本部に向いている人とは?
上記を踏まえた上で、WHO本部で活躍できそうな人材の特徴を以下にいくつか列挙してみた。尚、WHOの求人のJDを集計してみても以下の特徴が傾向として浮かび上がってくる。こちらも参照されたい。
1. 研究者>>実務家
まぁ部署にもよるのだが、WHO本部のPスタッフは国支援に携わる機会は少なく、チャンスがあっても出張ベースになりがちである。一方で規範的業務が占めるウェイトは大きい。したがって研究志向が強い方がフィットするだろう。研究者としてある程度自立している、つまり博士号を持っていたり、修士に加えて相応の研究実績がある人材が向いているだろう。WHO本部では修士取り立ての若者はコンサルタントに甘んじており、P2~3のポストは限られるので、正規職員に成り上がるのは容易ではない。
逆に実務志向で国支援をしたい人がWHO本部にうっかり勤務してしまうと、フラストレーションが溜まるだろう。本部からPスタッフを国に派遣するには、原則として国事務所からの要請が必要である。当然お声がかかるのはシニアスタッフが多く、JPOのようなひよっ子にはなかなかチャンスが回って来ない。
2. 専門性が既に確立している
上記1とも関連しているが、保健分野の専門機関であるWHOの中で最も専門性が要求される本部で働くのだから、専門性がそれなりに確立してから入職した方が生存しやすいだろう。自らの専門分野で成果を出し、それが上司に評価され、より大きな仕事を任されるようになり…という具合である。
逆にWHO入職と同時に新しい分野に挑戦しようとすると、なかなか辛い状況に陥る。例えば私は今まで臨床をやってきて、いきなり保健ガバナンス・財政の分野に飛び込んでしまった。受け入れ側にしてみたら「え、医者?…で、お前は何ができるの?」状態である。例えば所属先部署のあるスタッフに、あなたの分野の仕事に興味があるから手伝わせて欲しいと相談したことがあった。しかし「でもあなたは(その分野の)学位がないでしょ?」と、けんもほろろに断られてしまったことがあった。JPOは国際機関にとってタダの労働者なので、やりたいと希望すれば別の部署の仕事でもやらせてもらえる…と言う訳では必ずしもなかった。
3. 金を引っ張ってこれる
どんな組織も金がなければ活動できないので、ドナーとの繋がりが強くて拠出金を引っ張ってこれる人材はありがたがれる。まぁ日本の場合は、WHOへの拠出金は厚労省からの出向者が管理しているので、JPOには関係のない話だが。そもそもJPOという立場で、大きな金を引っ張ってこれる人はいないだろう。
WHOは歳入の7割近くがイヤーマークされている。これはWHO内で特定の国・団体から特定の部署・チーム・人に資金が流れることを意味する。こうした技術的な部署において資金の用途について影響力を持っているAward Managerは、江戸時代に例えるなら(徳川将軍をDGとするなら)大名のような存在になれる。そう、実はWHOの組織ガバナンスは封建的なのである。Award Managerは自らの給料の出どころを心配する必要はないし、人を雇う等の決断も容易だろう。
4. 社内政治が苦ではない
まぁ国際機関全般に言える話ではあるが、社内政治をうまく乗り越えられる人材は生き残れる。三層どのレベルでも社内政治はあるが、人が多いぶん本部の社内政治は酷い。これはピュアな開発ワーカーが国際機関を避ける理由の1つかもしれない。ちなみに私自身は、今まで小さな組織にしか所属したことがなかったので、こうした社内政治は未だに慣れない。
途上国経験はどうなのか?
途上国でのフォールド経験が大事だと言う話は至る所でされるし、JPOの同僚でJICA協力隊経験者等は多い。一方で途上国経験に乏しい技術的職員が特にWHO本部では散見される。まぁ同じ2年間なら協力隊に費やすのと博士課程を2年早く終えるのでは、後者の方がキャリア形成に有益かもしれない。医療者だって専門研修を積んでいたら、いつの間にかアラサーになってしまう。フィールド経験と専門性構築がトレードオフになってしまうのは悩ましい。
とは言え、途上国で住んだことも働いたこともない職員が、口では「途上国のため」と言い仕事をする現状が健全なのかと言われると疑問符が残る。こうした観点から、私は職員のMobilityには概ね賛成である。
もし記事の内容が役に立ったと思ったら↓ボタンをポチッとお願いします!
