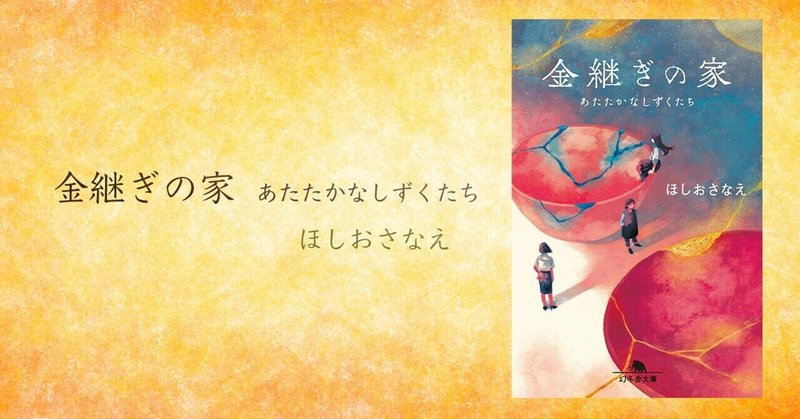
金継ぎを教わって…祖母の過去をたどる感動の物語 #4 金継ぎの家
高校生の真緒と暮らす祖母・千絵の仕事は、割れた器を修復する「金継ぎ」。進路に悩みながらも手伝いを始めた真緒はある日、漆のかんざしを見つける。それを目にした千絵の困惑と、故郷への思い。夏休み、二人は千絵の記憶をたどる旅に出る……。ほしおさなえさんの『金継ぎの家 あたたかなしずくたち』は、癒えない傷をつなぐ感動の物語。その始まりを抜粋してお届けします。
* * *
「成績はどうだったの?」
祖母が訊いてくる。

「うーん、二学期とあまり変わらず」
わたしの成績は、総合するとクラスのちょうど真ん中くらい。平均のやや上とやや下を行ったり来たりしている。だが、英語があまり良くない。いつも平均以下で、得意な国語で補っている感じだ。
「英語は?」
「二学期と同じだよ。お母さんに怒られるかなあ」
昨日の夜、母から電話があった。進路のことを話したあと、明日は成績表をもらったら、写真を撮って送るように、と言われた。
高二になれば受験のことも考えなくちゃならない。そのせいか、最近母はかなりうるさい。とくに英語だ。英語は日々の積み重ね。将来なにをするにしても、英語はできた方がいい。口癖のようにそう言っている。
母は学生時代から語学が得意で、いまはホテルでコンシェルジュの仕事をしている。日本語がわからない外国人観光客からの複雑な要望もあるので、ホテルスタッフのなかでもとくに高い語学力が求められるらしい。
「まあ、結子の要求水準は高いからね」
祖母はふふふと笑う。
「そうなんだよ」
わたしはちょっと憤慨したように言った。
「真緒のことを心配してるんだよ、きっと。いつも言ってるよ、真緒は将来どんな仕事をして、どうやって生きていくつもりなのか、って」
「わたしだって考えてるよ。けど、なにをしたいのかなんて、まだ全然わからない」
大学の学部だってまだ決められずにいる。わたしの得意科目は、理科と国語。数学と社会はまあまあで、英語がダメ。理系とも文系とも言えない、中途半端な成績だ。
「まあねえ。結子はそう言うけど、先のこと考えて生きてる高校生なんて、そんなにいないよねえ。おばあちゃんはそう思います」
祖母が笑う。
「高校生はね、まず、いまを楽しまないと」
わたしも笑った。
「青春だもんね」
とはいえ、そんなことをしていたら、競争から脱落してしまうかもしれない。クラスのほかの子たちの話を聞いていると、ときどき不安になる。
「ともかく、明日から春休みでしょ。真緒さんはなにをするおつもりですか」
祖母がちょっとおどけた口調で言う。
「なに、って……。とくに計画はないんだけど……」
ふとさっき見た祖母の作業場が頭をよぎる。
「そうだなあ。ちょっと、おばあちゃんの金継ぎの仕事を見てみたい」
思いつきで言うと、祖母は小さく、え、と言って、目を丸くした。
「金継ぎを?」
「うん。前から気になってたんだよね。直したものは見たことあるけど、直してるとこを見たことなかったなあ、って」
なんの気なしに言い出したことだったが、言葉にしてみると、ほんとに前々から気になっていたように思えてきた。祖母の棚を見るたびに、修繕された器のうつくしさに目を奪われた。罅の形の筋。縁の欠けたところに埋められた金や銀やいろいろな色。
何度ながめても飽きることがなかった。
「じゃあ、真緒、金継ぎ、ちょっとやってみようか」
「え、わたしが?」
「こういうことは自分でやってみないとわからないものだから」
祖母の目が笑っている。
「わたしでもできるの?」
「できるよ。最初から上手にはできないかもしれないけど、自分で直した器には愛着が出てくるものだよ」
なぜか少しどきどきした。
「じゃあ、やってみる」
答えてから、身体がぶるっとした。
「そしたら、さっそく今日からはじめよう。おばあちゃんもね、いまは仕事がたまってるんだ。前は真緒がお休みの時期は仕事をお休みにしてるんだけど、最近は量が増えてね。だから真緒が手伝ってくれたら、すっごく助かる」
「ほんと?」
「じゃあ、これを片づけたらはじめようか」
祖母の言葉にうなずき、器を流しに運んだ。
3
片づけが終わり、二階にあがる。
「そこの椅子に座って」
祖母が部屋の真ん中にある机を指す。以前は食卓に使っていたテーブルだが、いまは作業机になっている。机の上には割れたり欠けたりした器がいくつかならんでいた。欠けた部分に黒いものが埋められている茶器に、割れた部分がテープでとめられている大皿。
「割れたのを直すのはちょっとむずかしいから、まずは欠けを埋めてみようか」
祖母が棚の前に立ち、ならんだ器をながめる。
「お客さまの器をまかせるわけにはいかないからね」
そう言って、小さな湯呑みを手に取った。見覚えのある湯呑みだ。
「これ、うちの……」
六客そろいだった白い磁器の湯呑みだ。シンプルだが整った形で、母が気に入っていたのだが、この前ちょっとしたはずみで欠けてしまった。
「まずはこれを直してみよう」
祖母はわたしの前を片づけ、湯呑みを置く。
「こことここを埋める。本来は欠けに漆を入れて、乾燥させて、削って、と何回かに分けて作業するんだけど、このくらいの小さな欠けだったら、インスタントの直しもできる。ちゃんと直したものより強度も見た目もちょっと落ちるけど」
湯呑みを手に取り、欠けた部分を見た。ひとつは五ミリ程度、もうひとつはそれより少し大きい。

「まずは、直す部分を洗う。破片が残っていたりすると、うまくくっつかないからね」
祖母が部屋の隅の水道を指す。
「どのくらい洗えばいいの?」
流しに立ち、祖母に訊く。
「断面のざらざらしたものが取れれば大丈夫」
水を流し、欠けた部分を洗った。
「うん、それくらいでいいよ」
祖母に言われて水道を止める。布巾で器をよく拭き、もとの場所に置く。
「次は、水道でこの布を湿らせる。そしたら、さっきの椅子に座ってね」
七、八センチ角の布を手渡された。水を含ませて絞る。席に戻ると、祖母がわたしの前に四角いタイルやへら、爪楊枝などの道具を置いた。
「これが砥の粉。水を加えて練るんだよ」
小皿に出された粉にスポイトで水を垂らす。いっぺんにたくさん水を入れてはいけないらしい。少しずつ水を加えながら、へらで練った。
「どれくらいまで練るの?」
「そうねえ、へらで固めるとなんとかまとまるくらいの感じ」
なんとかまとまるくらい? わかるようでわからない。祖母に何度か練り具合を見てもらい、ようやくOKが出た。
「次が生漆」
祖母が絵の具のチューブのようなものから、どろっとした黒いものを絞り出す。
「漆?」
――よく金継ぎって言うけど、金で継ぐわけじゃ、ないんだよ。ほんとは漆で継ぐんだ。
そう言っていたのを思い出した。
「じゃあ、これが接着剤?」
見たところそんなにねばねばした感じじゃない。
「そう。これをさっきの砥の粉と混ぜたものが『錆漆』。接着用のペーストみたいなもの。漆工芸でも表面を盛り上げたりするときに使うんだよ。生漆に砥の粉を少しずつ混ぜて練って……」
「どれくらい?」
「さわっても指にくっつかない硬さになるまで」
最初は生漆の水分の方が多いので混ぜやすかったが、砥の粉の量が増えるにつれ、硬くぽろぽろしてきた。
「もっと力を入れないと混ざらないよ」
祖母にそう言われ、ぐいぐいとへらで練る。
「これくらいでいいかな」
何度か指で確かめたあと、祖母がうなずいた。
「じゃあ、埋めていくよ。まず、指で欠けの形を確かめて。錆漆が欠けからはみ出さないようにね」
祖母は練ったものを爪楊枝で少し取り、欠けに盛った。
「少しずつ、少しずつ、埋めていく」
「わかった」
祖母から器を受け取る。
「作業するときは必ず、さっき濡らしてきた布で、指を湿らせるんだよ。漆はかぶれる人もいるからね。でも、湿っていると、漆は指に直接くっつかなくなる」
かぶれる、と聞いて、少し怖くなった。
「指の腹はもともとかぶれにくいからね。あとで油で拭いてよく洗えば大丈夫。かぶれるのはたいてい顔や首なんだよ。だから、漆をさわった手で顔や首をさわってはいけない」
「かぶれるとどうなるの?」
「腫れる。大変なことになる人もいる」
「大変、って?」
「顔がふくれて、真っ赤になる人もいるよ。瞼が腫れて、目も開かなくなったり……。それが二週間くらい続くの。そのあいだはとにかくかゆいらしいね」
「二週間も?」
「漆は水で洗っても完全に落ちないんだよ。漆をさわった人が使ったタオルで顔を拭いてかぶれちゃった、なんてこともあるらしい。すぐに症状が出るとはかぎらなくて、次の朝とか、一週間後とか、いろいろみたい」
ということは、いま出てなくても、これから腫れることもあるってことか。
「かぶれちゃったらどうしよう」
「そのときは、金継ぎはあきらめた方がいいかもね」
祖母が笑った。
「けど、漆のかぶれは悪いものじゃないんだよ。熱が出ることはあっても、それで死んだ、って人は聞かない。治るときはあとを残さずきれいに治るしね」
「そうなの?」
「かぶれるかぶれないは、そのときの体調にもよるみたい。漆職人でずっとかぶれなかった人が、あるとき突然かぶれるなんてこともあるそうだよ。わたしはこれまでかぶれたことはないんだけどね」
じゃあ、わたしも大丈夫だろうか。
「まれにいつでもかぶれる人もいるみたいだけどね。漆アレルギーの人。手袋して長袖着て完全防備してもダメなんだって。かぶれを起こすウルシオールっていう成分は揮発性だから、漆を使ってる部屋にはいっただけでかぶれる。生の漆の木の近くを通っただけでかぶれたって話も聞くよ。ウルシ科の果物でかぶれる人もいる」
「ウルシ科の果物?」
「マンゴーとか……」
「じゃあ、そういう人はマンゴー食べられないの?」
「そう。真緒はマンゴー好きでしょう? だからアレルギーではないと思う。けど、さっきも言ったみたいに、漆をさわったあとは必ず油で手を拭くこと」
「わかった。でも、漆って器に使うものでしょう? 大丈夫なの?」
「完全に乾けばかぶれないの。固化してしまえば、ウルシオールは揮発しなくなる。むかしの職人のなかには、漆に慣れるために生漆を飲んだ人もいたんですって。薬として飲むところもあるっていうし。ミイラになるときに防腐剤として飲んだっていう話も聞いたなあ。ほんとかどうかわからないけどね」
かぶれるかかぶれないかはわからない。でも、とにかくいまは目の前の器を自分で直してみたかった。
◇ ◇ ◇
連載はこちら↓
金継ぎの家 あたたかなしずくたち

