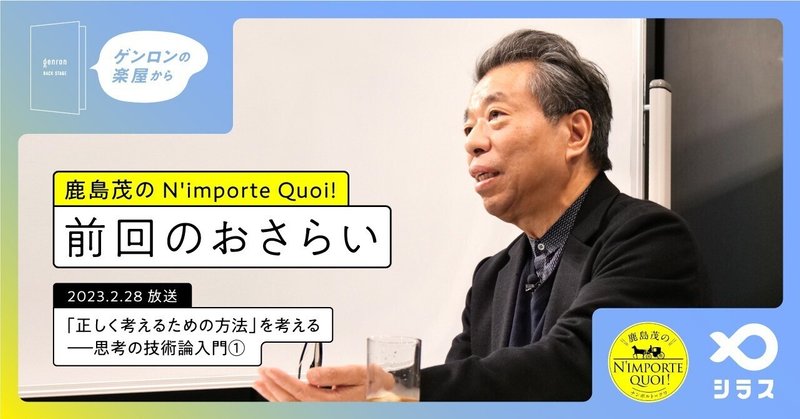
「考えること」を考えてみる──鹿島茂のN'importe Quoi! 前回のおさらい
こんにちは、ゲンロンスタッフの野口です。
2023年1月から2年目に突入した「鹿島茂のN'importe Quoi!」。第1シーズンとしてお届けしてきた「家族人類学入門──トッド理論の汎用性」の講座に一区切りをつけ、2月28日から新しい講座「『正しく考えるための方法』を考える──思考の技術論入門」がはじまりました。
新講座の第2回放送を前に、しばらくお休みを続けていた「前回のおさらい」もひさびさの更新です。本日19時からは第2回を放送。どうぞお楽しみに!

1.「考える」ことについて考え始めた17世紀
さて、この「『正しく考えるための方法』を考える」で出発点となるのは近代哲学の祖といわれるルネ・デカルト(1596-1650)の『方法序説』。あまりにも有名な「われ思う、ゆえにわれあり」の一節はもちろん、歴史の授業などで名前は聞いたことがある!という方も多いかと思います。
「Q.「大陸合理論」を打ち立てたフランスのデカルトに対して、イギリスでのちに「イギリス経験論」と呼ばれる理論を打ち立てたのは誰か?」
なんて出題、なんとなく覚えがありませんか?
ところでこの『方法序説』、なんの「方法」の「序説=前置きの論説」だったのでしょうか?岩波文庫版の『方法序説』を開けば答えはすぐに書いてあります。
「理性を正しく導き、学問において真理を探究するための」方法序説
つまり、「理性を正しく使って考えるための方法」の前置きが展開されている、と言えるでしょう。
そもそも「考えるための方法」としては、デカルトの時代からさらにさかのぼり、アリストテレスがまとめた「論理学」や「修辞学」までさかのぼることができます。ヨーロッパを暗黒の中世が覆っていたころ、これらの学問はイスラム圏で咀嚼され、さらに深化。その後、十字軍やレコンキスタ、ルネサンスを経て、デカルトが生きた17世紀にも学ばれていました。
デカルトが生まれたのはフランス・ロワール地方。1589年にアンリ4世によりブルボン朝がはじまり、1598年に「ナントの勅令」によって国内のカトリックとプロテスタントの融和が図られていた……そんなタイミングです。そのバックグラウンドとなるもう少し前の時代はどうだったか、というと、15世紀末から16世紀半ばまで続くイタリア戦争などで、フランスはハプスブルク家と長い戦争を続けてきました。この戦争による財政難を乗り切るため、フランソワ1世による官職売買制度の大々的な導入が行われ、それをきっかけに官職を手に入れた「法服貴族」とよばれる人々が新中間層として台頭してきた頃でもあります。
彼ら「法服貴族」は「帯剣貴族」と呼ばれるような従来の貴族層と対抗するために学ぶことに積極的に取り組みます。イエズス会やオラトリオ会などさまざまなカトリックの宗派が運営する、現在の「リセ」と呼ばれる教育機関の前身ともいえるような寄宿学校で、彼らは学びました。
比較的詰込み型の傾向があったというこれらの学校でも、アリストテレスの論理学は学ばれていました。しかし、ここでいう論理学の特徴はあくまでも「与えられた問題を解く」ということ。ギリシア世界で打ち立てられた論理学は、当時のキリスト教神学的な世界と接触し、「神の作った完璧な世界で新たな問いを立てる必要はない」という発想の下で、自らの問いを立てることは行われていなかったのです。
こういった寄宿学校で学んだデカルトは、その後オランダ・アムステルダムへ。当時のオランダは、ヴェネツィアやフィレンツェなどとならぶ学問や工業の先端地でもありました。ここでさまざまな学者たちに学んだデカルト(当時は有名な学者のもとへ直接訪ねていく、という習慣があったそうです)は「すべてを疑う」ことを決意します。
「すべてを疑う」とは、つまり自ら問いを立てることとも言えます。「神はこの世界を完璧に作った」というテーゼを考えるにあたって、「いや、そもそも完璧とは?」「なぜ神は世界を作ったのか?」と疑いを立てていく……行き着くところはそう、「神は存在するか?」という問い。しかし1633年のガリレイの地動説に対する異端審問の例を挙げるまでもなく、当時のヨーロッパ世界で大っぴらにこの問いを考えることは、なかなか難しいものがありました。そこでデカルトが取ったのは「『すべてを疑う』ために、現実の世界の中では疑うことをやめる」という方法。あまり面倒ごとに巻き込まれそうなところへはいちいち絡まない、ある種の「生活保守」の態度があったと言います。

なにはともあれ、与えられた命題を解くことを主眼とするこれまでの論理学=旧論理学に対して、自ら問いを立てること、疑いを立てることを掲げたデカルトの発想。このあとデカルトには様々な批評(クリティック)が寄せられるわけですが、「問いを立てる」ことが重要である、というその1点については、批判が寄せられることはなかったといいます。
2.方法序説で述べられていること
さて、先ほどもご紹介した通り、「理性を正しく使って考えるための方法」がまとめられていた『方法序説』。本書を通して説明されている4つの原則を、鹿島先生は以下のようにまとめます。
①すべてを疑おう
どんなことでもいったんは疑ってかかる!すべてを疑ってから、疑った挙句に「明証的に真」であると認めざるを得ないもの以外には真と認めないという思考態度。この「明証的に真」をどう判断できるかに、デカルト的な大陸合理論と、ロックのイギリス経験論の議論がある、ともいえるでしょう。
②分けて考えよう
問題を解決するには、それを分けて考えるのがよい、しかも、できるだけ多くの小さな部分に分ける、という方法。「分析的方法」と呼ばれる。
③単純から複雑へ
必要な最小部分に分けた結果、単純になり認識しやすくなったものから始めて、より複雑なものへと階段を上がるようにしてさかのぼる。「総合的方法」。
④見落としをチェックしよう
見落としがないか、問題点を枚挙・列挙して最終的なチェックを行う。
これらの4原則のなかには、②と③のあいだに「最小単位を認定する」という行為が必要なのではないか、あるいは、方法序説で宣言されている理性の使い方には、旧論理学的な発想も前提にあるのではないか……といった分析が鹿島先生から示されるのですが、このあたりはぜひ放送でお楽しみください。
3.これから考えていくこと
他方で「本講義で何を考えていくのか」については、その参考となる考え方が『方法序説』の冒頭に記されています。
良識はこの世でもっとも公平に分け与えられているものである。というのも、だれも良識なら十分身に具わっていると思っているので、他のことは何でも気難しい人たちでさえ、良識については、自分がいま持っているもの以上を望まないのが普通だからだ。(中略)正しく判断し、真と偽を区別する能力、これこそ、ほんらい良識とか理性とか呼ばれているものだが、そういう能力がすべての人に生まれつき平等に具わっていることだ。だから、わたしたちの意見が分かれるのは、ある人が他人よりも理性があるということによるのではなく、ただ、わたしたちが思考を異なる道筋で導き、同一のことを考察してはいないことから生じるのである。というのも、良い精神を持っているだけでは十分ではなく、大切なのはそれを良く用いることだからだ。
つまり、デカルトは良識や理性はあらゆる人に平等に与えられており、それをどう用いるかが重要だといいます。さらに、この理性の用い方は伝達できるスキルとして学ぶことができるのだ、と続けていきます。
ということで、本講義ではこの考え方に基づき、「理性の用い方」について学んでいきます。デカルトの考え方だけではなく、それに寄せられた批判の内容や、その妥当性についても触れていくことになります。
そこでポイントになるのは、あくまでも形而下の範囲にとどめるということ。あらゆることを疑う、そのための方法を学びこそすれ、なぜ疑うのか・何を疑うのかといった哲学的な問題については深入りしすぎない、という方針でこれからの講義は展開されていく予定です(それこそこの講義で学んで、それぞれで考えていくのがよさそうです!)。
前回の講義の中で僕が「面白いな~」と思ったのはフランスにおける「デカルト」という書き手の「存在感」です。
フランスも含む旧ラテン語圏の地域は、そこから崩れた国民言語がその国の言葉として定着するようなきっかけとなる作家がいる。例えばイギリスにおけるシェイクスピア、イタリアにおけるダンテ。そしてことフランスにおいては、デカルトがその存在にあたる、というお話がありました。
デカルトはフランスのシェイクスピア、と考えると、その発想法や考え方を学ぶことは、まさに「フランス」ではどのように考えるのか、という根本に触れることに近いのかも……そんな風に考えると、もう一つの「パリの歴史」に関する講座や、そのフランスから出発しているトッドの考え方にも近づきそうな予感がするのでした。

と、いうことで次回の放送は3月28日(火)19時~。ぜひ皆さんと一緒に「考えること」について考える時間を過ごせたら、と思います。放送でお会いしましょう!
↓番組はこちらから↓
本講義で取り組む内容にご興味を持たれた方は、講義のサブタイトルにもある『思考の技術論』と題された、鹿島先生の新著であるこちらもおすすめです。3月28日現在、僕もまだほとんど読めていないのですが(!)、目次を見ているだけでも、これまでの鹿島先生のさまざまな研究につながるトピックスが並んでいて、ワクワクします。ぜひ講義のおともにお手に取ってみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
