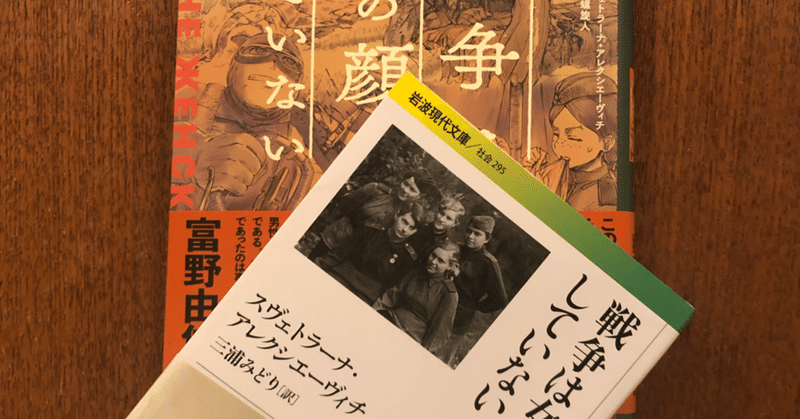
『戦争は女の顔をしていない』コミカライズ版を読んで考えたこと
最近、Twitterの一部で議論になっていたスヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ『戦争は女の顔をしていない』(三浦みどり訳、岩波書店)とそのコミカライズ版『戦争は女の顔をしていない』(小梅けいと著、速水螺旋人監修、KADOKAWA)を読んだ。
アレクシエーヴィチの原作の感想は読書メーターに書いたので参照されたい。ここでは小梅けいとによるコミカライズ版を原作との比較で語る。先述したTwitterでの議論の内容に触れることはしない。というのもTwitterで議論の的になったのは某ジャーナリストがコミカライズ版に寄せたコメント(一部で言われているように書評ですらない)についてであり、そこには文学作品の「誤読」をめぐる根深い問題の一端が垣間見えもしたが、それは本稿に直接関係しない。
コミカライズ版の感想を一言でいうなら、独ソ戦の知識に乏しく、原作を読んでも理解できないかもしれないと憂慮する人は、まずこちらを読むといいかもしれない。漫画表現にあまり詳しくない私からすると、小梅けいとの絵はいささか繊細すぎるきらいがある。原作の悲惨さ、残酷さの描写はかなりおさえられているが、そこは全年齢向けコミックの制約上、しかたないところだろう。
ただアレクシエーヴィチの原作は、既存のどの書物より戦争と生活の細部に焦点を絞っており、そうしたディティールの描き方はコミカライズ版も非常に上手かった。特に洗濯係の少女たちが、自分たちを嘲笑した兵士たちの前でダンスに興じるあたり。生き生きとしていて、原作にもある一瞬のユーモアを絶妙に切り取っている。
とはいえ私としては、ぜんたいに拭いがたい違和感をおぼえるコミカライズ版であった。その違和感について、以下、二点に絞って考える。
違和感のひとつは、エピソードの抽出の仕方について。
原作では、コミカライズ版のように、第×話……という話の枠におさまる証言は多くない。その多くはある場面、ある印象について、きわめて断片的なかたちで語っている。原作者のアレクシエーヴィチ自身、こうした生の証言をまとめるにあたって、彼女なりの編集作業を余儀なくされているが、それをビジュアルで、より情緒的に読ませる漫画という形式にアダプテーションする際には、やはり物語的な起伏がある、もっと言えば漫画的に「映える」証言を優先して採択せざるを得ない。
原作にあった無数の声のせめぎ合い、ポリフォニックな混沌が、コミカライズ版では捨象されている。
もうひとつは、女性たちの表象について。
原作とコミカライズ版の最大の違いは、言うまでもなく前者にはない女性たちの顔が、後者では描かれていることだ。問題は、彼女たちがいわゆる漫画的な美少女として見目よく描かれているところにはない。そうではなくて、顔なき声として表象されていた彼女たちの存在を恣意的に引用し、読者の情動を揺さぶるために都合よく泣き、笑い、怒る顔を無遠慮に与えてしまうその態度に、私は、語り得ない者に対する暴力的なまなざしを感じる。
語り得ない者について、語り得る立場にある者が語る(代弁する)行為がすでにして支配乃至所有の一形式であり、原作者のアレクシエーヴィチですらその構造からは逃れられていない。
その語り得ない者に、語り得る者の側から一方的に顔を、それも異国の読者が感情移入しやすいようデフォルメされた顔を与える。ここにはやはりいくばくかの暴力性が内在しているのではないか。
更に言えば、彼女たちの体験を読み、知ることができる読者もまた、両者の力関係において上位にある。畢竟、読者たる私たちは、語り得ぬ者たる彼女たちの体験を所有する立場にあるといえよう。この自覚を抜きにして、残酷だ、悲惨だ、あるいはまた感動的だ、泣いた、という単直な感慨を述べることは、持てる者の欺瞞と見做されてもしかたない。
ただし、これまで書いてきたことがコミカライズ版『戦争は女の顔をしていない』の欠点であると、ただちに断ずることはできない。
私自身、語り得ぬ者と語り得る者の所有の関係性について、コミカライズ版を読むことなしには気づけなかっただろうし、それによって原作がもともと抱えていたナイーヴな問題点や読者による受容の態度が浮かび上がり、多面的に作品を論じることができるようになったはずだ。批判は非難の謂ではない。原作を読んだ人はコミカライズ版を、コミカライズ版から入った人は原作を手に取り、より広く深い議論を交わしていくことが必要だろう。私は前者の順番で読んだので、後者の人の意見も是非聞いてみたい。きっと私とはまた別様の印象を受けるにちがいない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
