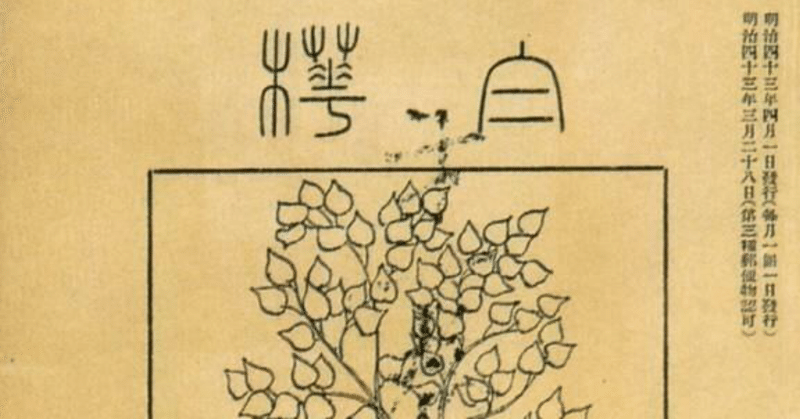
夏目漱石と志賀直哉 恩と済まなさ
スーパースター同士の交流というのは、ファンにとって心温まるとともに、興奮を感じるものである。
同世代のライバルという関係も熱いが、一時代を築いた覇者が、次世代のエースと出会い、お互いにリスペクトしているという関係も素晴らしい。
イチローと大谷翔平がグラウンドで一緒に練習していたり、荒木飛呂彦が手塚治虫に褒められていたり……。
夏目漱石(1867-1916)

は、明治後期から大正にかけて当時にしては個性的な小説を驚くべきペースで、発表し、沢山の門下を持った近代文学の第一人者の一人である。彼の残した作品は没後百年を経ても忘れ去られるばかりか、常に新しい読者を獲得し続けている。日本人としての自我の問題、芸術家として生きることの苦悩など、ユーモアと普遍性を兼ね備えた作品群を想像した文豪だ。
志賀直哉(1883-1971)

は、文芸誌「白樺」同人の代表的作家として文壇に登場し、その後数十年に及んで文壇の高峰に立ち続けた。冷徹な視点で現実を見つめる文体は「心境小説」とよばれ、凡庸な私小説とは一線を画し、日本語散文のお手本として多くの文学青年に支持を得た。彼の文体の特徴としては、修飾を省いた簡潔性であり、彼の表現の特徴としては、その根底にある自我の絶対的肯定をあげられる。
漱石が東京帝大講師を退任する最後の年に、志賀直哉は大学に入学した。ほとんど講義に出なかった志賀だったが、漱石の講義は例外で、内容にも感銘を受けていた。
教師と生徒という関係であった二人だが、その後志賀の友人であり白樺派を代表する作家の一人である武者小路実篤(1885-1976)を通して、交流が生まれる。
「白樺」の創刊号は1910年の4月に出た。この雑誌はトルストイなどのヒューマニズムに影響を受けた新しい世代の作品が掲載されているが、それと同時に当時最先端の西洋美術が輸入紹介される場であった。ロダンやセザンヌなどがこの雑誌で紹介された画家である。
また余談だが、武者小路はヨーロッパでピカソにあったことがあるそうである。とても小柄で驚いたと書いている。
「白樺」創刊号には、志賀の短篇「網走まで」、そして武者小路の評論「「それから」に就いて」が掲載された。
これは自然との調和について論じたものであり、自然のまま生きて社会から逸脱するか、それとも社会に迎合して心を空虚にしてしまうか、このジレンマのなかを生きること、という漱石文学の主題の一つについて論じている。
武者小路はこの雑誌を漱石に贈り、それが漱石によって激賞され、交流がはじまる。
漱石と志賀のパイプは、武者小路によってつなげられる。
1914年、自らが専属している朝日新聞に『こころ』を連載していた漱石は、その次に連載する小説を志賀直哉に依頼する。
その時志賀が書いていた作品が「時任謙作」である。
ところが、これが完成しない。完成しないまま、漱石と約束を交わした朝日新聞の掲載は断ることになる。
尾道から松江に移動し書き続けていた原稿の依頼を断るために、志賀は上京し、牛込に住む漱石を訪ね、謝罪する。漱石は考え直すように説得し、「書けないなら書けない気持を小説に書けないか」などと提案する。
夏目さんには敬意を持っていたし、自分の仕事を認めてくれた事ではあり、なるべく、豆腐のぶつ切れにならぬよう書くつもりでも、それまでが白樺の同人雑誌で何の拘束もなしに書いて来た癖で一回毎に多少の山とか謎とかを持たせるような書き方は中々出来なかった。
(中略)
私の出すべき長篇小説の空地はその頃の私位の若い連中の中篇小説幾篇かで埋める事になったが、義理堅い夏目さんに迷惑をかけた事を大変済まない事に感じ、何時かいい物を書いて、朝日新聞に出そうと思ったのが、他にも理由はあったが、それから四年程何も作品を発表出来なかった原因の一つであった。
──志賀直哉「あとがき」
その直後に漱石は亡くなる。
なお、この「時任謙作」は「父との不和」というテーマから、「過酷な運命に直面しながらも強い意志で生きる」という謙作の姿を描くことに方向転換し、26年の歳月を経て完結する。その長篇こそ『暗夜行路』であり、現在でも版を重ね続けている志賀の代表作となっている。
なおこの暗夜行路の巻頭には、
「武者小路実篤兄に捧ぐ」という言葉が掲げられている。武者小路は志賀より二年年下であるが、志賀が留年したため大学では同級生であった。また、志賀の妻である康子は、武者小路実篤の従姉妹である。
参考文献
志賀直哉『暗夜行路』新潮文庫
『志賀直哉随筆集』岩波文庫
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
