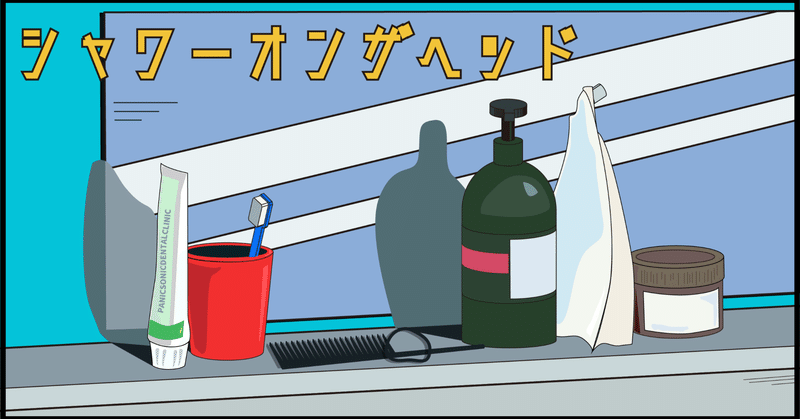
シャワーオンザヘッド
このまえ会った友達の友達の名前はなんだっただろうかとか、明日必ず出してと言われていたデータの定義が足りないだとか、しんしんと降り落ちる水の中で思い返すことはどの箱に入れるかも決める以前のテーマばかりである。頭上で雑多に浮いているそれらが水滴と共に脳みそに落ちてきて、そしてそれを流れに任せるように受け止め消化していく。自分でも思いがけないようなテーマを与えられて、足元が冷たくなっているのにいつまでも暗い浴室から出られずに時間が過ぎていくとき、このままこの緩い水流に溶けて一緒に排水溝へ吸い込まれてしまえば解放されるのだろうかと子供のような発想に逃げたくなる。こうしたシャワーとの関係性が始まったのがいつだったか。
私と母とで構成される我が家は、いわゆる母子家庭だった。夜働きに出る母と、託児所に預けられる私。この生活が幼稚園生の間は続いていて、夜中に迎えにくる母のドレスから香るのがシャネルのチャンスだと知ったのは大学生になってからだったが、それより先にこれが強かに生きる女性のための香りであることは理解していたように思う。深夜にタクシーの後部座席で頭をグラングラン揺らしていた4歳の私を見た運転手さんが「こんな遅い時間に可哀想だ」と言って、ヒステリックに怒った母の姿がとても好きだった。ひとしきり怒って泣いたあと、コンビニの蛍光灯から崩れたアイメイクを隠すようにサングラスをしてピザまんを買ってくれた。誰に対しても感じる必要がないはずの罪悪感を母の手元から受け取った。小学生になると託児所でも預かってもらえなくなり、私はオルスバンをするカギッコになった。朝は、まだ寝たばかりの母を起こさないようにそうっと布団から抜け出して学校に行った。学校から帰るとメイクをしている最中の母がいて、作ってあるご飯の温め方を説明をしてもらったりする。ちょっとでも長く居させようと何度も生玉子のレンジの仕方を確認して母を苛立たせた。
留守番中は酷いものだったと思う。頼まれた洗濯物畳みや洗い物は、23時近くになって慌ててするから雑な仕上がりだったし、テレビを見ててもCMの時間が苦痛過ぎてリモコンを片手に、サスペンスとバラエティとドラマを同時視聴していたし、2リットルのペットボトルに口をつけてファンタグレープを飲んだりした。その中でもいちばんの苦行はお風呂に入ることだった。テレビの音も聴こえない異様に白いあの空間で、目を瞑って頭を洗うなんてそんな背中がゾクゾクする恐怖を毎日乗り越えていた子供の頃の自分に、今の自分からライナスの毛布を贈りたい。シャワーどころか浴室とさえ仲良くなれずにいたけれど、私たちの間柄が転換したのは小学4年生になって、母との間柄も大きく転換した頃だった。託児所にも終わりが来たように、鍵っ子生活にも終わりが来て、その代わりに祖父母との暮らしが始まったのだ。さすがにいつまでもお留守番は良くないというのと、祖父母が田舎の港町でやっていたBARの先行きも見えなくなってきたのとで、2人は九州の陸の孤島から埼玉の陸の孤島へとやってきた。
金子國義の絵が表紙の文庫本や四谷シモンの人形集が飾られていたシックなリビングも、半年後には青々としたチェックのテーブルクロスを中心にプラスチックとダンボールに溢れた居間に様変わりした。母も1、2年は一緒に寝食していたはずだが、気がつくと都内に単身者用の部屋を借り、たまにこちらの家に帰る程度になっていた。明日から12進法になりますと言われたらものすごい違和感だと思うけれど、母は顔を見せる間隔を上手に広げていった。
母が我が家に入るときに放つ言葉が「ただいま」から「お邪魔しまーす」になった辺りで、私は思春期に差し掛かり、おじいちゃんおばあちゃん特有の古い考え方や図々しさに反発し始めていた。母が家を出たお陰で4.5畳の自室がもらえたけれど、そのドアに鍵はなく「入るよー!」の「は」のところでもうドアを開けるようなおばあちゃんと暮らしていては、個室であって個室でないのと同じだった。整理できない若い情緒の数々を、シャワーが流してくれた。冬場は冷えた脱衣所に戻るのが億劫なのも相まって、1時間近くシャワーを浴び続け、湯水の如く湯水を無駄使いしたりした。実をいうと、ほとんど同時期にトイレとの仲も深まっていた。漫画や本を服の下に忍び込ませてトイレに入り、長時間便器の上に篭っていることがよくあったけれど、さすがにこの習慣は大人になってから手放してしまった。ただただ、成長過程の子供が鍵のついている空間を求めていたということなのだろうけど、シャワーとの関わり方はどれだけ成長しても身体に馴染んだままで、近くなり過ぎることもなくそこに在った。自己肯定が難しくなりそうなとき、何を手にして明日の自分を迎えたいのか見失いそうなとき、水道代を自分で払えるようになった私は、今や堂々とシャワーに埋もれる。
そうして今日も外側が温まっていくのと反比例して、内側はしんとクールダウンしていくのを感じていた。と、急に水圧が強くなりホースが生き物のようにぐるんと翻って、あっと思ったときにはシャワーヘッドがフックを飛び出すのが見えた。勢いそのままに、コツンと頭を打たれて、私の人生に起きた全てが虚構だようと言われた気がしたけれど、私はそこまで鈍感じゃないよと小さな声で言い返す。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
