
『山へよする』の広告:竹久夢二『山へよする』研究①
1 『文章倶楽部』第4巻第3号の「新刊紹介」と巻頭広告
『文章倶楽部』第4巻3号(大正8年3月1日)には、『山へよする』の広告と、新刊紹介、それに夢二による自作紹介記事「自画自賛 (『山へよする』より)」が掲載されている。
『文章倶楽部』は新潮社刊で、『山へよする』と同じ版元であり、自社新刊の広告に力を入れているということを示している。
まず、巻末の「新刊紹介」では、次のように紹介されている。
◉山へよする 竹久夢二作 夢二の歌と夢二の絵はいかに甘く悲しく快きかは、諸子の夙に知るところ、ここに繰返すまでも無からう。稀有の美本、挿画二十葉、短歌二百四十首。(定価一円 新潮社)
「稀有の美本」というところにこの本の詩画集としての側面があらわれている。
次に、巻頭の1ページ広告を見てみよう。
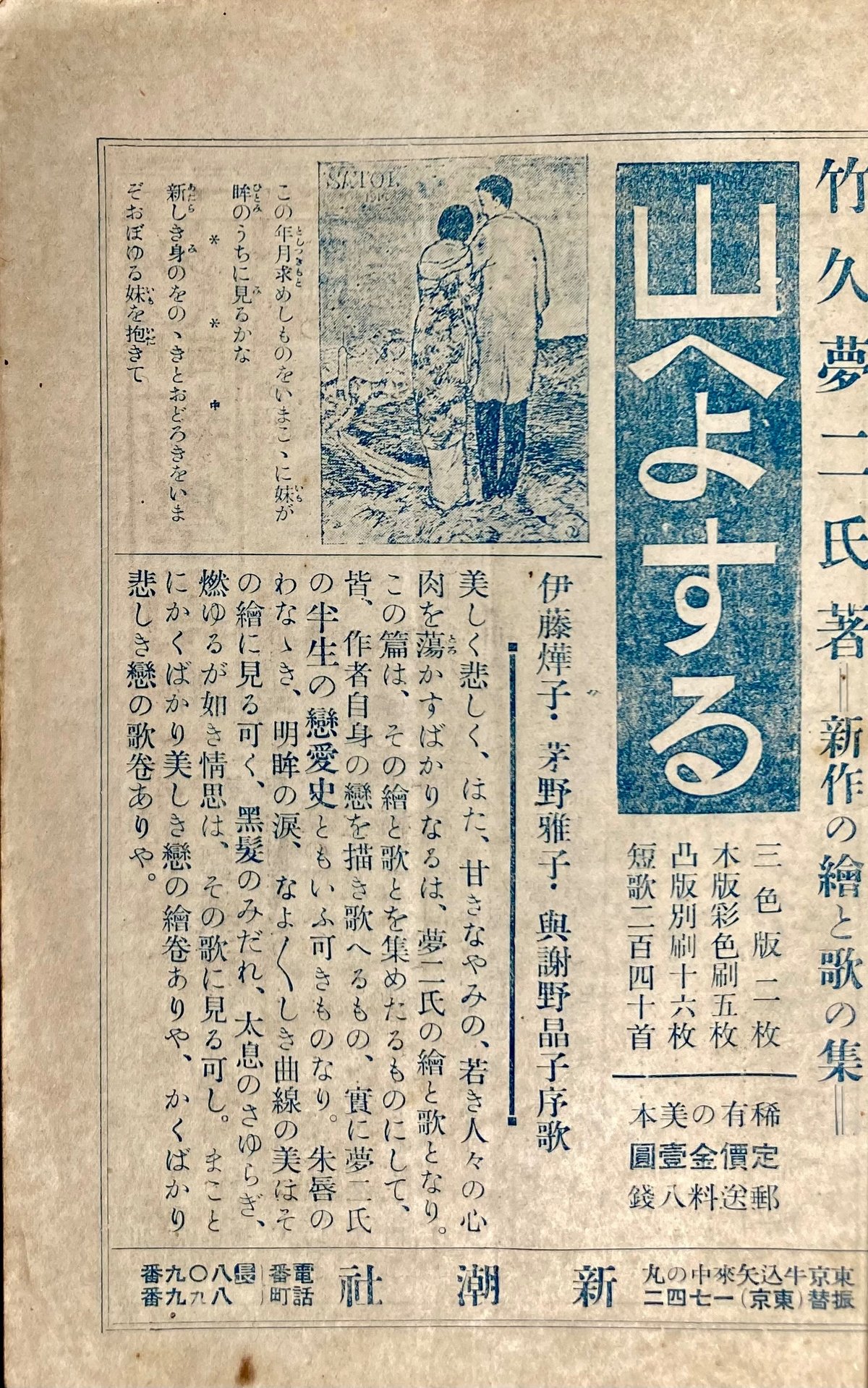
最初に「竹久夢二氏著=新作の絵と歌の集=」とあり、絵と短歌を組み合わせた書物であることがわかる。挿絵の版式と歌数にについては、「三色版二枚/木版彩色刷五枚/凸版別刷十六枚/短歌二百四十首」とある。その下に「稀有の美本/定価金一円/郵送料八銭」とある。
『山へよする』では、短歌は題をつけて数首から十数首をまとめてある。配置は時系列の順序ではない。
「伊藤燁子・茅野雅子・与謝野晶子序歌」とあるが、3人の女性歌人が2首ずつ序歌を寄せている。歌集としての『山へよする』の内容を踏まえた歌を含んでいる。
宣伝文は次のとおりである。
美しく悲しく、はた、甘きなやみの、若き人々の心肉を蕩かすばかりなるは、夢二氏の絵と歌となり。この篇は、その絵と歌とを集めたるものにして、皆、作者自身の恋を描き歌へるもの、実に夢二氏の半生の恋愛史ともいふ可きものなり。朱唇のわなゝき、明眸の涙、なよなよ(引用者注-「なよなよ」後半の「なよ」は原文では「く」の字型の繰り返し記号)しき曲線の美はその絵に見る可く、黒髪のみだれ、太息のさゆらぎ、燃ゆるが如き情思は、その歌に見る可し。まことにかくばかり美しき恋の絵巻ありや、かくばかり悲しき恋の歌巻ありや。
広告のための文章であり、美辞麗句に満ちているが、「夢二氏の半生の恋愛史」という部分は、作者の恋愛についての告白を含むことを示している。だが、その対象が笠井彦乃という一人の女性であるということまではわからない。
上段の挿絵《SATOI》は、本では亜鉛凸版であるが、広告では写真銅版である。そのため画面にかすれとしてのノイズが出ている。男性の風貌は竹久夢二を彷彿とさせるので、この本が告白文学の側面を持つことが示されている。《SATOI》は金沢の湯涌温泉での彦乃と夢二を描いている。「里居」の章の13首は恋愛歌の頂点をなすものである。
紹介されている歌は2首。
この年月求めしものをいまこゝに妹が眸のうちに見るかな
新しき身のをのゝきとおどろきをいまぞおぼゆる妹を抱きて
2首とも、「逢坂山を越えて」の章からとられている。12歳年下の彦乃という恋人を得た喜びが伝わってくる。
「逢坂山」は見開きの扉にローマ字書きで示された和泉式部の和歌にも関連している。恋の関を越える、すなわち世間的には認められにくい恋愛の領域に踏み込むという暗示が「逢坂山」という語に込められている。
2 「自画自賛 (『山へよする』より)」
夢二自身の記事は「自画自賛 (『山へよする』より)」という題で、本に収録された4首の短歌について金属版のイラストと解説文を付して、見開き2ページで構成されている。

この見開き2ページに絵と文を組み合わせるという構成は、『文章倶楽部』に連載されている「名作絵物語」の形式を踏襲している。ちなみのこの号の「名作絵物語」では、菊池寛の『無名作家の日記』が取りあげられている。「名作絵物語」は、原作の一部を引用しながら、いくつかの絵をつけて、見開き2ページで作品の概要を示すという形式であった。
挿絵はいずれも本の方には収められていない。
3 父の恋仇
「父が家へ君をおくるとたちいづる戸のもはいまし春のくれがた」という1首は「港屋懐古」の章の最終歌。
夢二は次のように解説している。
これはあんまり秀れた歌ではないが、女は女の父に許されずに男のもとへ来て、逢つたらあゝも話さう、かうも言はうと考へて来は来ながら、さて逢つて見ると言はでもの事ばかりであつた出された茶も飲みたくはない。ただだまつて手の指をいぢりながら相対してゐれば、充ちたらふ心であつた。
これはおそらく、当時、落合村丸山の夢二の家に父の目を盗んでやってきた彦乃と逢瀬を楽しんだ後、日本橋本白銀町の家に帰らせる時のことを詠んだ歌である。
彦乃と交際が始まった大正3年秋から大正5年11月、京都に向かうまでの夢二の住居の変遷は次のとおりである。
大正3年10月1日 日本橋呉服町2 港屋絵草紙店開店
大正3年11月 神田区千代田町28
大正4年4月 落合村丸山370
大正4年6月 高田村雑司ヶ谷大原
大正5年10月 渋谷伊達跡1836
裏取りができていないので断定はできないが、挿絵が郊外の様子を示しているので落合村の家の可能性が高い。高田村の家は写真が残っていて2階建てである。ただ、高田村の家の時期は、彦乃が外出禁止になっていた頃であり、5月に2人が結ばれたのは落合村の家だとされているので、やはり落合村の家の可能性が高いだろう。
先の引用に続いて、彦乃とかわされた次のような会話が記されている。
「相変らず詮議きびしい?」
「えゝたいへん。まるであなたを恋仇にしてゐるのよ。」
「さうらしいね。だが父親が自分の娘を、異性として見るやうになつたのは悲惨だね。
その父の家へ女をかへすのは男には辛かつた。戸の外へ出ると、|夕靄《ゆふもや
》が立ちこめて麦の畑のエメラルドが柔かに流れて、すべての物のたゝずまひをおぼろにし、物の調子を弱々しくやさしくしてゐた。春の暮れ方にふさはしい情景である。
『絵入恋愛秘語』(大正13年9月10日、文興院) にも同趣旨の自歌自注がある。『山へよする』の「果実篇」には解説がついていて、その一節に「「青麦の青きをわけてはるばる(引用者注-「はるばる」の「ばる」は原文では「ぐ」の字型の繰り返し符号)と逢ひに来る子とおもへば哀し」 これはその頃詠んだ歌である。そのやうに青い麦畑の中を、下町の方から通つて来た。」とあるので、これも落合村の家だったと推定される。
さて、彦乃の父が夢二を「恋仇」としてみているという言葉を受けて、夢二は「自分の娘を異性として」見ているのだと応じている。
このくだりは、夢二が恋愛を個人同士のやりとりだと考えていることを期せずしてあらわにしている。父宗重の立場に立てば、一人娘の彦乃の恋愛は家を壊すという危険をはらむものであった。宗重が彦乃を溺愛したのは、養子をとって笠井商店を継がせる心算があったからである。夢二には、笠井家という家の問題は見えていない。
夢二の本名は茂次郎で次男であったが、兄は夢二の生まれる前に亡くなっている。夢二は相続の筆頭人であるが、実家が明治39年に岡山県邑久郡本庄村から、福岡県遠賀郡八幡村に転籍していることもあって、家の意識が希薄であったのだろうか。
4 父と娘、笠井商店
ここで、笠井宗重と彦乃について整理しておこう。「父が家」というのは日本橋本白銀町にあった、笠井宗重が紙業を営む芙蓉笠井商店のことである。
彦乃及び笠井家の来歴については、坂原冨美代『夢二を変えた女 笠井彦乃』(2016年6月、論創社) が詳しく記述している。坂原氏は、明治44年に彦乃の実母そうが亡くなったあと、宗重の後添えとなった河西定代を母とする千代の娘である。

*『日本橋』平成19年3月号(通巻336号)より
笠井宗重は山梨県南巨摩郡中富町(現身延町)西嶋の出である。西嶋は和紙の産地で宗重は紙業を始める。苦労を重ねて宗重は明治36年、日本橋本銀町に芙蓉社笠井商店を開店した。
彦乃は明治29年3月生まれ。9歳まで西嶋で暮らした。明治42年、日本女子大附属高等女学校に入学。明治44年に母、そうが亡くなっている。
坂原氏は笠井商店について次のように記している。
父宗重は創意工夫の人で、 商売熱心なやり手と同業者からも一目置かれ、宮内省御用達商となって家業も順調だった。 紙をロール状に巻き取る新技術が導入され、宗重はいち早くそれを応用して紙テープを発明した。 船の出航の際、船と埠頭で別れを惜しむ時に投げる、あの紙テープである。店頭には西嶋特産の半紙や画仙紙などと共に、桜紐と名付けた色とりどりの紙テープが並べられていた。
坂原氏によると、この紙テープは大正3年開催の東京大正博覧会で金牌を受賞している。
荒川太郎 編『国産展覧会報告概要』(大正5年、国産奨励会)には笠井商店の「紙製テープ及同品捻出器」の出品記録が残されている。
紙テープ(商標は「桜紐」)があたって、笠井商店は順調であったが、長女彦乃は家を継ぐべき立場にあった。
地域広報誌『日本橋』平成19年3月号(通巻336号)が「永遠のひと・日本橋の女笠井彦乃」という特集を組んでおり、そのなかの「紙テープを発明した笠井宗重」という無署名のコラムに次のようなことが書かれている。
諸外国では商品をしばるのにリボンが用いられていて、紙テープの需要はなかった。「桜紐」という商品名の笠井商店の紙テープは、大正4年のサンフランシスコ万博に出品された。当地でデパートを営んでいた森野庄吉は、テープを買い取り、船の出航の際の「別れの握手」に使うという需要を創出したというのである。
『日米年鑑』第8号(明治45年1月、日米新聞社)には、森野が経営する近江屋商店の広告が掲載されている。近江屋商店はサンフランシスコのサウスパーク130番地にあり、港のすぐ近くであった。
森野は『在米日本人人名事典』(大正11年、日米新聞社)に立項されている。それによると、森野は滋賀県の出身で、明治33年に渡米、当時人家もまばらであったサウスパークに、雑貨小間物を扱う店を開いた。夜間に店を開き、昼間は東洋汽船の桟橋で働いた。移民排斥運動があり、苦労を重ねたが、大正3年には事業を拡張し、旅館と湯屋を併設して繁盛したという。おそらく、桟橋で働いていた経験から、出航の際の「別れの握手」として紙テープを使うことを思いついたのだろう。
5 彦乃と夢二の交渉史
他の歌にふれる前に、彦乃と夢二の交渉の経緯を整理しておくことにしよう。
港屋での出会い 大正3年10月〜大正5年2月
最初の妻岸他万喜と夢二は明治42年に法的に離婚していたが、彦乃との恋が始まる大正3年秋頃にも他万喜とは関係が続いていた。
離婚した他万喜の経済的自立のために、大正4年10月1日、日本橋呉服町2番地に絵草子店港屋が開店した。場所は、彦乃の実家笠井商店のすぐ近くであり、10月に開催された第1回港屋展覧会を見た彦乃は、足繁く港屋に通い、夢二に絵の指導を請うた。
当時、彦乃は日本女子大附属高等女学校の生徒であった。夢二は31歳、彦乃は19歳で、ちょうど12歳の年齢差である。彦乃との交際のはじめの時期は、前妻他万喜との関係が断ち切れずに葛藤が生じていた。
たとえば、大正4年2月、夢二は嫉妬から他万喜を富山泊海岸に呼び寄せ、刃傷沙汰をおこしている。

*富山泊海岸での他万喜との諍いを描いている。コロタイプ印刷
大正4年4月、夢二の勧めもあって彦乃は日本美術学校日本画科選科3年に編入学する。5月22日に、落合村の家で、夢二は彦乃と結ばれた。なぜわかるかというと、夢二の記憶している百首の短歌にイラストを合わせた『絵入歌集』(大正4年9月、植竹書院) の最終ページに二人が結ばれたことを示す日付入りの絵が提示されているからである。

*1915年5月22日の日付が入っている。
短歌は、斎藤茂吉『赤光』(大正2年10月、東雲堂書店)の恋愛歌「おひろ」から採られた「たまきはる命ひかりて触れたれば否とは言ひてけぬがにもよる」という一首である。
体に触れると「いけない」といって消えてしまうような風情ではあるが、こちらに体を寄せてきたというのである。絵は時空を分割した前衛的な表現であることが目を引く。光と闇の裂け目に2人の接吻が描かれている。
先妻他万喜との複雑な関係が続き、彦乃とは結ばれたが父宗重の厳しい反対があり、人目をしのんで愛を育むしかなかった時期である。大正5年2月には、他万喜に三男草一が生まれた。
京都へ 大正5年3月〜大正6年4月
大正5年3月に彦乃は卒業制作の絵画《御殿女中》を完成し、女子美術学校を卒業した。
大正5年11月20日、夢二は他万喜との関係を完全に解消するため、京都の友人堀内清のもとに向かった。ところが、12月に他万喜が不二彦、草一の養育を放棄して失踪する。
次男不二彦は京都の夢二のもとに向かい、三男草一は養子先をさがすこととなった。後、草一は新派の女形河合武雄の養子となり、栄二郎を名のり俳優となった。
夢二は清水二年坂から高台寺南門鳥居脇に住居を移し、彦乃の上洛を待った。大正6年に入って彦乃は雑誌の表紙画や口絵を描き始めた。4月に彦乃は絵の師栗原玉葉の支援もあって、絵の修業を名目に上洛し、夢二、不二彦と住むことになった。不二彦を含めた3人の疑似家族としての生活が始まった。
旅と病 大正6年8月〜大正7年10月
大正6年8月から金沢に滞在し、9月に金沢市金谷館で「夢二抒情小品展覧会」を開催した。彦乃も「山路しの」の名で数点出品した。
夢二、不二彦、彦乃は9月24日から10月まで湯涌温泉の山下旅館で平穏な日々を過ごす。湯涌での滞在は、不二彦を加えた疑似家族の生活を営んだ安息の日々であり、『山へよする』の「里居」の章にそれがあらわれている。
夢二が諸方に旅をしたのは、地方の支援者を頼って展覧会を催し、作品を販売し、生計の資を得るためであった。
大正7年に入って1月に、後援者の医師大藤昇がいる岡山で「竹久夢二作品展覧会」を開催した。
3月に彦乃の父宗重が上洛し、彦乃を東京につれもどすことになった。
4月、京都府立図書館で「第2回竹久夢二抒情画展覧会」を開催する。支援者の仲介によって会期中に突然彦乃が姿を見せた。
8月に夢二は不二彦とともに九州に出かけ、彦乃は別府で合流するが、病状が悪化し、9月に別府の病院に入院する。9月下旬、3人は京都に戻り、彦乃は東山病院に入院する。
10月、夢二と、彦乃の父宗重が病院であらそい、決定的な対立関係となり、夢二は彦乃に面会ができなくなる。
終末へ 大正7年11月〜大正9年1月
11月7日、夢二は東京に戻る。11月27日頃から『山へよする』の原稿を書き始め、12月10日に脱稿する。
12月26日に彦乃は京都を発ち順天堂医院に転院した。
大正8年2月、『山へよする』が新潮社から刊行され、3月5日に夢二が属していた春草会の主催により、神田万世橋のミカドで出版記念会が開催された。会の後で夢二は高橋しづとともに彦乃を見舞った。
『山へよする』の後記(12月25日の日付が入っている)に次のような記述がある。
「山へよする」一篇は、千九百十四年十月より千九百十八年十二月まで五年間に渉る HEとSHEとのの記述である。また彼等の愛の祈りである。
1918年、すなわち大正7年12月で、大正3年10月の港屋の出会いから始まった夢二と彦乃の関係は一区切りをむかえたととらえられている。こうした区切りは愛の終わりを明確につげていることになり、そこに酷薄さを見る見解もある。(注1)
しかし、大正7年9月、京都に戻る帰路、岡山で夢二の後援者で医師である大藤昇の診察を受けて、彦乃は自分の病状の深刻さを明確に認識していた。2人の愛の記念である『山へよする』を、生きているうちに病床の彦乃に届けたいというのが、夢二の切なる願いであったろう。
大正8年2月以降、夢二はどれほど病床の彦乃を見舞うことができたのだろうか。坂原冨美代氏は、「笠井彦乃・竹久夢二略年譜」(坂原冨美代『夢二を変えた女 笠井彦乃』2016年6月、論創社)の大正7年12月25日の項に「以後夢二は彦乃の従弟達の手引きで時々彦乃を見舞っている」と記している。
大正9年1月16日、順天堂医院で彦乃は亡くなった。
大正8年の空白は、本が出ても彦乃の衰弱は進み、死は避けられないという現実の酷薄さを示しているようだ。
6 空鳴りの鈴
さて、自著広告「自画自賛 (『山へよする』より)」に取りあげられた残りの歌を見ていくことにしよう。
「わがゆきて鈴はひけども空鳴りのいでずば人にまた逢はめやも」という一首。本では「港屋懐古」の章に収められている。
夢二は次のように解説している。
これも女の歌である。その頃男は二階立の青い部屋に一人住んでゐた。寝台のわきに鈴を下げておいた。女が訪れてきて扉口でその鈴の緒を引くと内から扉をあけて入れる習ひであつた。男はその頃よく、青い部屋を明けて外を出歩いたので女は空しく鈴を引くことが度々あつた。その度に「もう再びと来まい」と思つて怨みながら帰つても、いつかまた足はひとりでに青い部屋の方へ向いた。この頃は男にも女にも危険な時代であつた。
留意しておきたいのは、この歌には発話を示す「」がもともとついているということである。つまり、彦乃の発話そのものが歌にしたという形をとっている。こうした歌は何首かある。吉井勇や石川啄木が明治40年代に試みている。
「逢はめやも」は逢うことがあるだろうか、いやそんなことはない、という反語的な表現であるが、夢二の解説は、それでもまた女の足は「青い部屋」に向かうとしている。
「危険な時代」という表現は、結ばれたが、安定しない二人の関係を示している。前妻との関係は断ち切られていないし、女の父の反対もゆるんでいない。2人は未来を容易に想像することができない状況にあったのである。
7 唄ひ女の歌
「寂しさが身をおとしめて唄ひ女の歌に涙をこぼすたそがれ」は「竹絲哀傷」の章頭歌である。夢二は次のような解説を添えている。
運命は待たれてゐる時来なかつたり、与へようとする時、人が背を向けてゐたりするのだ。愛し合つてはゐがら、確実に二人が結びつくのは、やはり「時」だ。何といふ原因もなくこだわつたり、そびれたりするのも、恋の経過だ。男は寂しい寂しい(引用者注-原文では「寂しい寂しい」の後半の「寂しい」は「く」の字型の繰り返し符号)と口癖に言ひながらたつた一人の、その女から求め得られるものをも求めずに、わるくこぢれて、ある夜、紅燈の巷に唄女の下等な歌にさそはれて涙をながしたといふのである。すべては寂しさがさせたのだといふ言開きに、この男の弱い性格と子供らしいはにかみがある。
寂しさゆえに「紅燈の巷」に足を踏み入れたという言い訳に「この男の弱い性格」があらわれているという解説は、『山へよする』の重要な一面を言い当てている。『山へよする』は佳人薄命の悲劇であるとともに、〈弱い男〉の告白自伝でもあるのだ。
夢二が足を踏み入れたのは待合茶屋で、芸妓の歌に心を動かされたということだろう。待合茶屋は客と芸妓が遊興する場所であったが、売春も盛んに行われていた。「言開き」「弱い性格」といった表現から、音曲だけではなく、夢二が花街の女性の身体をもとめた可能性は否定できないだろう。
夢二は、笠井宗重の干渉によって彦乃に会えない時期が続いた大正4年9月の日記に「童貞へ」という題をつけている。この題は、彦乃と会うことができない間に「紅燈の巷」には行かないという意味が含意されている。(注2)
8 愛憐の幸不幸
「愛憐が恋の寝椅子によりそふを嬉しとぞおもひかなしとぞおもふ」という一首は「永遠の猶太人」の章の最終歌。本では「愛憐」は「あはれみ」とかながきになっている。
夢二は次のような解説を付している。
相愛の日が経るに随つて男も女もすべての好い所ばかり見せ合つてはゐない。時とすると甘えるやうな我儘から、お互の悪い性格をすら打つけ合ふものである。この性格や境遇の不幸を感じある愛憐の心が大きな運命のまへにへりくだつてある時は不幸だか、お互同志の愛憐に変るときは幸幅でなかつたといふのである。
解説文の「不幸」と「幸福」のどちらかに誤植があるのではないだろうか。原文のままでは、どちらの場合も不幸ということになり、対比する意味がないからである。
私解を示しておこう。「愛憐」はいつくしむ心を示している。互いの悪いところをぶつけ合って、「愛憐」の気持が「大きな運命」の前に「へりくだって」いる、すなわち、謙虚でいるときは不幸である。なぜなら、「愛憐」の気持が十分お互いに向けられることがないからである。しかし、「愛憐」の心がお互いに向けられるときは不幸ではない。
そのように理解すると、「お互同志の愛憐に変るときは幸幅でなかつた」の「幸福」は「不幸」に直すべきだろう。
9 広告と『山へよする』のずれ
さて、広告は『山へよする』の内容をすべて伝えているわけではない。広告には選択がはたらいており、実際の書物の内容の一部を取りあげている。
夢二の自著広告「自画自賛 (『山へよする』より)」では、彦乃と自身の恋愛が焦点となっている。
しかし、『山へよする』では、彦乃にとっては血のつながっていない不二彦を加えた疑似家族としての生活や旅、夢二の不二彦への思いも大きな部分を占めている。また、夢二・彦乃の、絵を描くもの同士としてのかかわりも重要なポイントである。
まず最初に広告を取りあげたのは、読者に夢二と彦乃の関わりの概要を知ってもらうのに、都合がよいと考えたからである。
次回から、『山へよする』の装幀や挿絵の画像分析、短歌表現の読解に歩を進めていくことにする。
(注1)林えり子『愛せしこの身なれど 竹久夢二と妻他万喜』(昭和58年1月、新潮社)は、他万喜の心理にそった小説体の記述であるが、『山へよする』の「後記」について、「前年十二月で彦乃との仲が終わった」、「夢二は愛人を病魔に奪われ、彦乃は残酷な訣別を一方的にいい渡されたのだ」と記している(200頁)。これは岸他万喜に引き寄せた理解で、本文中に記したとおり、夢二も彦乃も、彦乃の余命が長くないことは明確に理解していた。
(注2)夢二が吉原がよいをしていたことについては、東郷青児に証言がある。東郷青児は中学を出る少し前から夢二の神田千代田町の家に出入りしていた。大正4年2月の富山泊での刃傷沙汰は、夢二が東郷と他万喜の仲を疑ったためであるとされている。東郷は「夢二の家」(1956年、『いろざんげ』河出書房)というエッセイで、他万喜との不倫について否定しているが、夢二が吉原の角海老楼のさんごという娼妓をひいきにしていて、描きあげた屏風を車に積んでさんごのもとに運んでいたと記している。大正3年秋以降、大正4年頃のことと推定される。
*引用文のルビについては適宜取捨した。
文・木股知史
【編集履歴】
2024/07/15 笠井彦乃命日の誤記訂正 大正9年1月11日→大正9年1月16日
*ご一読くださりありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
