
経営学は何のために?(2) 理論の社会実装、そして失敗
先稿にリアクションいただいた方、ありがとうございました。「おもしろかった」「続きが気になる」から、「頭に入ってこない」まで、たくさんのコメント・リアクションをいただき、勉強にもなり、励みにもなりました。全ての読者に応える発信というのは不可能で、どういう読者を意識するのか、は発信者にとってめちゃくちゃ大事なことです。ただ、あんまりスタンスは決めておらず、とりあえずは、前回のように「友人に向けて」書いてるような気分です。
ちなみに、友人氏はこういう↓リアクションをくれました。彼は昔からこんな感じの人です。あと、「めっちゃ長文だったけどコロナで暇なの?」とも訊かれました。私は断じて暇ではありません。
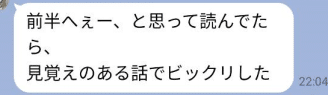
学問の社会実装
さて、前回の問いを改めて挙げましょう。
理論上正しいって同意されてるなら、なんで現実では使われないの?
理論って、現実ではそうならないし役に立たないんじゃないの?
また前回の投稿について、神戸大学の宮尾先生から、Facebookに以下のようなコメントをいただきました(宮尾先生のご研究はとても面白いので皆さんぜひ読んでみてください。『説得』『根回し』など一般的語彙をときに用いつつ、『技術の社会的形成』に関するご研究を多数発表されています)。
面白いですね。役に立つとはどういうことか…工学とか農学だと理論は実践では使えないなんて言わないんですよね。
工学も農学も(一括りにできないほど多様であることは前提として)、いわゆる「実学」色の強いものです。役に立てるために研究するような学術領域では、そもそも役に立つ論争など起きないかもしれません。役に立つという表現が不適切だとすれば、「社会実装することを前提としている」くらいが的確でしょうか。つまり、研究が何らかの形で現実世界に利活用されることを、強く念頭に置いている。基礎研究や応用研究とかの括りはあれど、研究の出口として社会実装があることは、およそ疑いなく合意されている。
対して、哲学や文学はいわゆる「虚学」に位置付けられており、こういう学問はあんまり社会実装するという意識がない(部外者の古典的イメージなので、実際は違うかもしれません)。京大はかつて「虚学の雄」と呼ばれていたとか。西田哲学などのイメージからそう言われていたのでしょうが、色んな意味で現在はそういう空気は感じません。
さて、じゃあ経営学はどうなのかというと、ちょっと微妙というか、実は自身から何らかのスタンスをはっきり表明しているわけではなさそうです。理由は色々あるでしょうが、社会実装という意識が薄めだという他に、工学や農学ほどに実装スキームが確立されていない、という点が重要に思えます。つまり、学者が理論をやって、それを現場に持っていって、フィードバックを貰って…みたいなサイクルがない(ここの検討も、note数回ぶん必要なくらい大事なテーマです)。現代において、優れた工業や農業に工学や農学が必須である(と私は勝手に思っている)一方で、優れた経営者が必ずしも経営学を修めていない、といった事情もあるかと思います。
ちなみに社会実装を強く意識して活動されている方もいます。経営学の映像授業を提供されているWATNEYの長地さんは、経営学を社会実装するという意識をかなり強く持たれています(リンク先参照。私も映像授業を提供させていただいています。これはただの宣伝です)。京大の伊藤智明さんとビジネスリサーチラボの伊達洋駆さんは「臨床経営学」というコンセプトから、経営学の社会実装を目指されています。ただ、これらはあくまで限定的な例だというのも事実だと思います。
理論の失敗
ところで、みんなが知ってるような有名な、理論が社会実装された例はあるのでしょうか。私の知っている有名な例を二つ挙げたいと思います。
まず、前回に続き経済学の、ファイナンス理論に関する例。MM理論から始まったとされるファイナンス理論の系譜において、金字塔とされる研究があります。ブラックさんとショールズさんによる「ブラック=ショールズ方程式」と呼ばれる研究(1973年)です。この研究が注目されたのは、学術理論として、現実への応用可能性が非常に高かったからです。ちなみに同方程式はオプションの理論価格を導出する方程式です(何のことかわからないかもしれませんが私も専門家でないので敢えて詳説を省きます)。とりあえず、社会実装できてかつ非常に有用な理論が金融界に出現したのです。ブラック氏は夭逝しますが、ショールズ氏と、同方程式を精緻化させたマートン氏(『官僚制の逆機能』のマートンの息子さんらしいです)は後に同方程式に関してノーベル経済学賞を受賞します。
この研究が革命的であったのは、まず、数学をバックグラウンドとする学者による研究だった点です。ブラックは数学で博士号を取得した、「数学屋さん」です。彼ら以降「金融工学」と呼ばれる一大潮流が出来上がり、数学を経済学やファイナンス理論に応用する流れが決定的になります。数学で博士号を取ったような人でないと使えない高度な数学を用いてモデルを作り、現実の金融に実装し、「理想の未来」を予測する、というスキームが構築され、金融工学ならびにヘッジファンドなどの金融機関が世界を席巻します。
さて、スゴイ理論が出現し、数学を現実の金融に応用する流れが加速していったのですが、それが00~10年頃にいかなる帰結を迎えたかは多くの方がご存知だと思います。まず、アジア通貨危機やリーマンショックといった、世界中を巻き込む金融危機が起きました。ファイナンス理論に絶対的信頼を置いた結果、世界がまるっと危機に晒されることになりました。また、ショールズとマートンが取締役を務めるヘッジファンド「ロングターム・キャピタル・マネジメント」社は、90年代後半に巨額の損失を出して経営破綻します。彼らがノーベル賞を受賞してから僅か1~2年の出来事でした。なお、これらの一連の流れはNHKドキュメンタリーの「マネー革命」に詳しく、本も出ていて、わかりやすいです。
まとめると、数学や統計学など最先端の学術を駆使した理論が、主に金融の世界で活躍し、多くの「現世利益」を生み出し、そして世界規模の危機をも招いた。ノーベル賞を受賞するような学者が会社を経営したら破綻させた。こういうことが、金融まわりでは起きたのでした。
もう一つ紹介します。こちらはわりと純粋な経営学の話です。「社外取締役」という制度があります。「株式会社の業務を執行せず、かつ、当該企業およびその親会社、子会社、経営陣等との間に一定の利害関係を有しない取締役」(出典:BUSINESS LAWYERS)のことで、端的には、「全く第三者の立場から、企業の監査や評価を行う役割」のことです。コーポレート・ガバナンス論の領域において、企業の不祥事が止まないことを問題意識として、こういう役職があれば不祥事はなくなるだろう、ということで生まれたと言われています。専門家ではないので詳細な経緯はさておき(お前、だいたい専門家じゃないな)、「このような役割を設置すればこういう効果が期待できる」といった理論的設計のもと現実世界に広がっていったという意味で、理論発の概念であると考えられます。社外取締役は画期的な制度として、出現当時は学術界でもおおいに持て囃されていたそうです。
さて、社外取締役は現代日本でも確実に広がっており、ますます普及して当たり前のものになっています。一方で、かつてエンロン事件―2001年時点で米国史上最大の負債を抱えて経営破綻したエンロン社を巡る事件―なる出来事がありました。簡単に言えばエンロン社は経理不正を行っており、それが明るみになって破綻したのですが、なんとエンロンは社外取締役を積極的に導入した企業の一つだったのです。破綻直前の98~00年、エンロンは常時20名前後の取締役を設置しており、そしてケネス・レイとジェフ・スキリングという2名(この2名は企業不祥事を主導したとみなされています)を除く全員が社外取締役でした。社外取締役は企業の不祥事を抑制するために有効だ、と多くの人が信じていたにも関わらず、社外取締役を20名も起用していたアメリカ有数の大企業が、不祥事のすえ破綻してしまった、というわけでした。一体なぜでしょう。
ところで私は2020年の授業で、こんな質問をすることがありました。「組織不祥事は、どうやったら防げるでしょうか」。お目付け役を置けばいいのでは?というアイデアを出した学生に端を発して、こういう答えが出てきました。「組織内部の人間は不正に加担するか、抑圧されて反対できないので、組織外の第三者がチェックすればよい」とか。「一人だけだと客観性や公平性が担保できないから、複数人でそういう役割を担った方がいい」とか。「シロウトじゃ仕方ないから、企業経営の経験者など、実績や社会的地位のある人の方がいい」とか。どれも一理ある、いい答えに思えます。ちなみに、エンロンの社外取締役は、これらの条件を全て満たしていたのですが。エンロンは、「理論上完璧な」社外取締役制度を備えていました。それがエンロン事件の凄いところであり、怖いところでもあります。

上記はエンロンの取締役会メンバーです(出典:丸山,2006)。錚々たるメンツを揃えつつ、エンロンは不正経理をやってのけます。
理論の失敗をどう捉えるか
さて、今回は、経営学は役に立つのか?という大きな問いから、学問領域によって社会実装志向がかなり異なること、経営学は今のところ社会実装についてコンセンサスがなさそうなこと、理論が大々的に失敗した例があること、について触れました。ここだけ読むと、ああなんかやっぱり理論って役に立たないんかな、と思えてしまいます。
しかし、こうした失敗例を根拠に「経営学は使えない」と言ってしまうことも早計である、と断っておきます。その理由は二つ考えられます。
一つ、理論はそもそも失敗するからです。
二つ、長期的な視野を欠いて要不要を論じることは危険であるからです。
次回は、この二つについて書いていこうと思います。
本当はもっとコンパクトにまとめるつもりだったんですが、書いてたら色々書きたくなってきて長くなっています。気長に読んでいただけますと幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
