
2023年5月以降にnoteにおいて発表してきたエッセイや短編小説・クイズ・言語に関する練習問題などをまとめてみました。
当noteにおいて発表してきた文章のジャンルは社会言語…
¥1,000
- 運営しているクリエイター
#ことわざ

日常生活でよく使う「これだけは覚えておきたい『ことわざ』『言い伝え』『故事成語』」(第20回)- - -「一年の計は元旦にあり」
Ⅰ「一年の計は元旦にあり]ということわざの成立過程・意味・用法について 「一年の計は元旦にあり」(いちねんのけいはがんたんにあり)ということわざは、日本の伝統的な言葉であり、成立過程や意味、用法について以下に説明します。 成立過程: このことわざは、元々中国の古典文学である「孟子」に由来しています。孟子(もうし)は、紀元前4世紀の中国の哲学者で、儒教の重要な思想家の一人です。彼の著作の中に、「一日を亡くす者は多いが、一年を亡くす者は少ない」という言葉があります。この言葉
有料
100
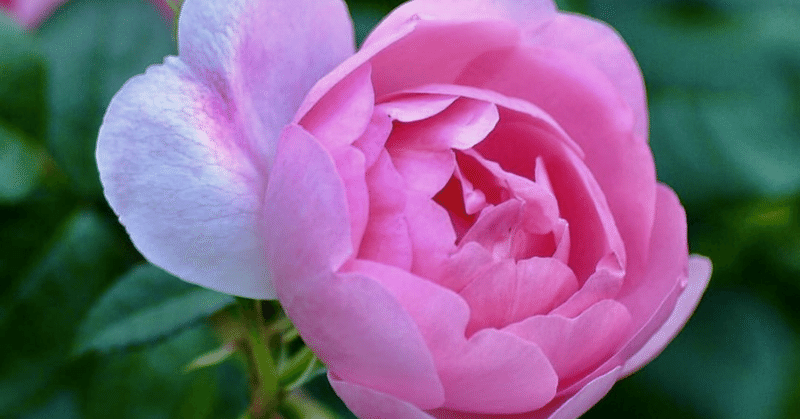
日常生活でよく使う「これだけは覚えておきたい『ことわざ』『言い伝え』『故事成語』」(第14回)- - -「縁の下の力持ち」
Ⅰ「縁の下の力持ち」ということわざの成立過程・意味・用法について 成立過程: このことわざは、江戸時代にさかのぼります。江戸時代は、社会が厳格な身分制度に基づいており、上流階級や目立つ存在が重要視されていました。しかし、その裏で、実際には目立たないところで働く人々が社会を支えていたことがありました。この文脈から、「縁の下の力持ち」という表現が生まれたと考えられています。 意味: 「縁の下の力持ち」の意味は、主に目立たないところで黙々と仕事をこなし、その結果として大きな影響
有料
200












