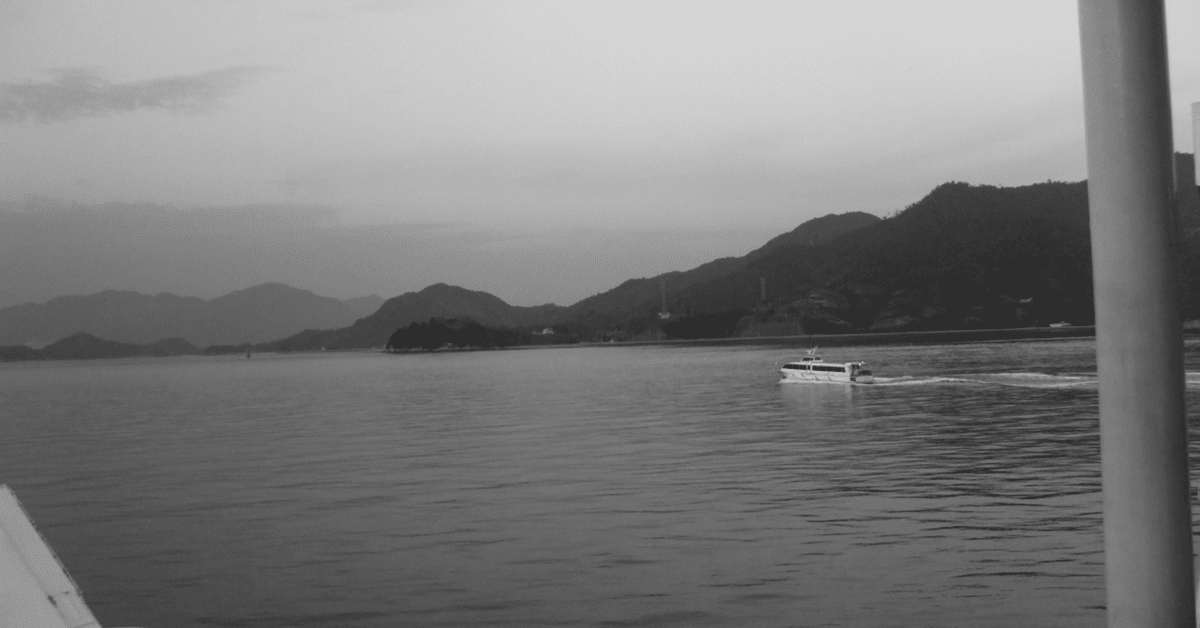
「焼畑の潜在力 アフリカ熱帯雨林の農業生態誌」 四方篝
昭和堂
ちなみに著書四方篝(しかたかがり)氏は女性。難しい字だなあ。篝火の字…
カメルーンの焼畑農業の本。焼畑といっても、火入れしない地域もあり「移畑」とか言った方がいいのでは?
カカオ生産地の中でカメルーン南東部のこの地域は、常食であるバナナと商品作物であるカカオを同時に森の中に植え、畑を変えて放棄する時でも単に放棄するだけでなく、そこに集まってくる食糧となる生きものなどは捕えるというやり方を取っている。生活作物と商品作物の共存がここには見られる。
(2015 11/09)
カメルーン焼畑農業。1000株もの様々な品種・時期のバナナを把握して、毎日主食のバナナを途切れることなく収穫する(バナナは日持ちがしない)のは、あの傍目にはジャングルにしか見えない畑も含めて、かなりの頭でないとできない(バナナ収穫は女性の仕事)。
(2015 11/09)
野生の多様性という言葉が結論の最後に出てくるが、このレヴィ=ストロースの言葉を利用した言葉は、アグロフォレストリーの管理された多様性と対にした言葉。後者のコートジボワールやガーナなどの森林破壊が問題となっているところでの農法と、この本で紹介されている農法とを同様に評価してはならない、というのが結論の一つ。
無理に森を飼い慣らそうとするのではなく、森に適度な刺激を与えつつ、そのダイナミックスの一部を利用するという、森と人の相互関係としての焼畑の潜在力が最大限に発揮され、人びとの生活を支えているプロセスなのである。
(p163)
例えばここのカカオ畑は、放棄されたバナナ焼畑に自然の二次遷移が起こる、その代わりにカカオを導入していこうという発想で行っている。
(2015 11/12)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
