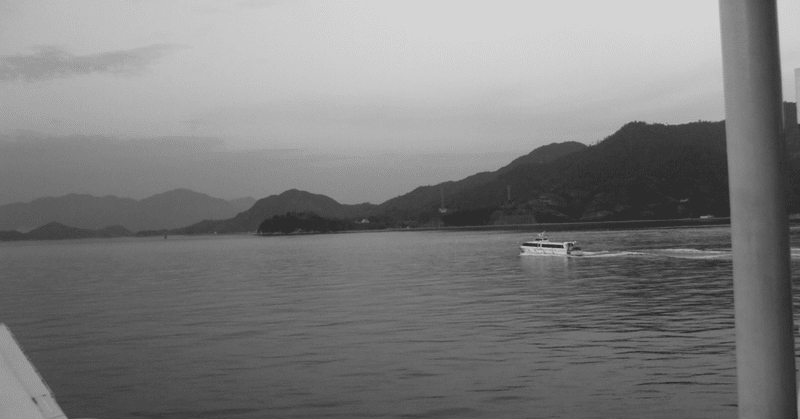
「アフター・ヨーロッパ ポピュリズムという妖怪にどう向きあうか」 イワン・クラステフ
庄司克宏 編訳 岩波書店
ヨーロッパ・ガラパゴス
序章を昨晩寝る前に読んだ。
序章冒頭がヨゼフ・ロートの「ラデツキー行進曲」で始まるように、このクラステフ氏、結構文学からの引用が好きな模様。この本を染めるテーマが「既視感」(EU分裂はソ連崩壊の再来?)なのだから、小説世界から引っ張ってこられるのは当然ということか。特にお気に入りはサラマーゴらしい。
現在では欧州が、自ら「ガラパゴス化」の瞬間に直面しているのである。欧州のポスト・モダンの秩序は、あまりにも進化しすぎて、周囲に対して独特なものとなったため、他の地域が追随するのは不可能であるということかもしれない。
(p11)
(というか、ここで例に引き出されている、日本の「ガラパゴス携帯」が技術的には進んでいたというのを初めて知った)
欧州の政治における主要な勢力として、脅えた多数派の台頭をもたらした。不安にかられた多数派は、外国人が自分たちの国を奪い、自分たちの生き方を脅かしていると恐れ、また現在の危機が、世界主義的な志向のエリートと部族的な志向の移民との共謀によってもたらされたと確信している。
(p17)
最初は読み飛ばしていたけれど、「共謀」という言葉に今気づいた。実際にエリートと移民が「共謀」していたわけではもちろんないことは普通に考えればわかりそうなものだが、それが見えなくなるくらい、この「多数派」は視野が狭くなっているのだろう。
(2021 11/29)
第1章「われわれ欧州人」
スラヴォイ・ジジェクは難民危機が欧州に与える影響を、エリザベス・キューブラー=ロスの「死ぬ瞬間-死とその過程について」の死の受容5段階説と似た経過をたどるという。
否認→怒り→取引→抑鬱→受容
ただし、ジジェクの難民の受容5段階説には最後の「受容」の段階が欠けている。
続いてはデイビッド・グッドハートの言葉から。
階級と経済的利益という古の分裂は消滅していないが、より大きくて緩やかな分裂にますます覆われている。すなわち、世界を「あらゆる場所」から見ている人々と、世界を「どこかの場所」から見ている人々の間の分裂である。
(p37)
p46にて紹介されている社会実験は、移民問題とは少し離れるが、直近未来社会を見る視点として重要な視座。
実験では、最長一年間、彼らに何の条件もつけずに毎月一〇〇〇ドルから二〇〇〇ドルを提供し、人々が生計を立てるために働く必要がなくなった場合に何をするのか調査する。職がない未来という展望は、知的かつ実存的な大きな課題である。
(p46)
後半は中東欧と西欧との分裂。及び中東欧での「同情の欠如」。それと反する?3つの現実。
1、20世紀、中東欧の人々は自身が大きな移民排出国だった。
2、現実中東欧諸国にはほとんど難民はいない
3、中東欧諸国は高齢化と人口流出で、実は移民の労働力が必要視されている。
ここからはクラステフ氏の母国であるブルガリアの事例が多くなる。
何十年もの間ひとりも子どもが生まれていない過疎の村で、地元の老人が難民の定住に抗議する場面をテレビで見ると、双方の立場の人間、つまり難民と、さらには自分たちの世界が消えうせていくのを目撃している高齢の孤独な人々に打ちひしがれる。一〇〇年後にブルガリア語の詩がわかる人は残っているのだろうか。
民族は、全能の神と同様に、死の概念に対抗する人類の盾の一つである。
(p54)
元々、中東欧では自国政府よりブリュッセル(EU)の指導者を頼りにしていたが、今では自国政府に多く傾くようになった。
(2021 12/02)
第2章「かれら人民」
欧州の共通通貨が生き残るためには、債務国の有権者は、政府を交代させる力を保持しているにもかかわらず、経済政策を変更する権利を剥奪されなければならない、という点である。
(p69-70)
選択肢のない民主主義、意味をもたない主権、正当性のないグローバリゼーションがもたらされるのである。
(p73)
ここから、3つのパラドクスに分けて説明される。
1、中欧諸国の世論調査による親欧州の傾向と、自国の政治には反EU政党が票を集める「中欧のパラドクス」
2、西欧での、汎欧州的・親EU的ポピュリスト運動の出現をもたらさなかった「西欧のパラドクス」
3、欧州人が能力主義で選抜されたはずのブリュッセルの「エリート」に憤慨している「ブリュッセルのパラドクス」
この説明から次回。
(2021 12/03)
人々はツイートで革命の火ぶたを切ることはできるかもしれないが、ツイートして政権を樹立することはできないのだ。
(p89)
今まで読んできた本では「デモのメディア論」も参照。ポーランド、カチンの森虐殺訪露での飛行機墜落事故に関しては、松里氏の「準大統領制」も参照。
(2021 12/05)
これら(ギリシャのスィリザやスペインのポデモス)の政党は、親EUの若者により構成されるが、、しばしばブリュッセルに反対することを土台にその正当性を作り上げる。
(p90)
つまりは支持層と政党の間に乖離が起きているのか。支持層が支持層たり得ない(若者の人口が少ない、若者が選挙に行かない等)のか。
能力主義的エリートから見れば、母国の外での成功は彼らの才能の証なのである。しかし多くの人々から見れば、まさにこの流動性こそが能力主義的エリートを信用しない理由なのである。
(p94)
能力主義的エリートはサッカーの一流選手みたいなものだという比喩はわかりやすい。国から出られない人々からすれば、どこかへ流れそうなエリートよりも、その国にずっといる人を信頼するのか(ただ、ポピュリスト政治家が本当にずっとその国にいるのかはわからないのだが)。
(2021 12/07)
国民投票は「独裁者と煽動政治家」の装置
(p99 マーガレット・サッチャーの言葉)
国民投票は複雑な政策事項を危険なほどに単純化し、しばしば辻褄の合わない政策へと導いてしまう。国民投票は諸問題を切り離して単一の争点を問うものであるから、人々は互いに矛盾するような複数の政策を承認する結果となってしまうかもしれない。
(p99)
国民投票(結果はともかく)とEU統合の同時化は、もっと言うと「経済統合」「国家主権」「民主主義」の三つをすべて同時に達成するのは不可能である(というダニ・ロドリクの仮説…訳者あとがき参照)…しかしブリュッセルのエリートも、ポピュリスト政党もこれが可能であるかのように振る舞っているという。国民投票の具体例として、イギリスのEU脱退についての投票のほか、イタリア・オランダ・ハンガリーのそれぞれ性格の異なる投票を取り上げている。
EUはこのまま分裂していくのか。著者クラステフはそうは考えてはいない。即興と妥協の精神で生き残っていくこと自体が必要であり、すべきであるという。
生き残るということは、詩を書くことに少し似ている。詩人でさえも、詩がどのように終わるのか、終わってみるまでわからないのである。
(p119)
(2021 12/08)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
