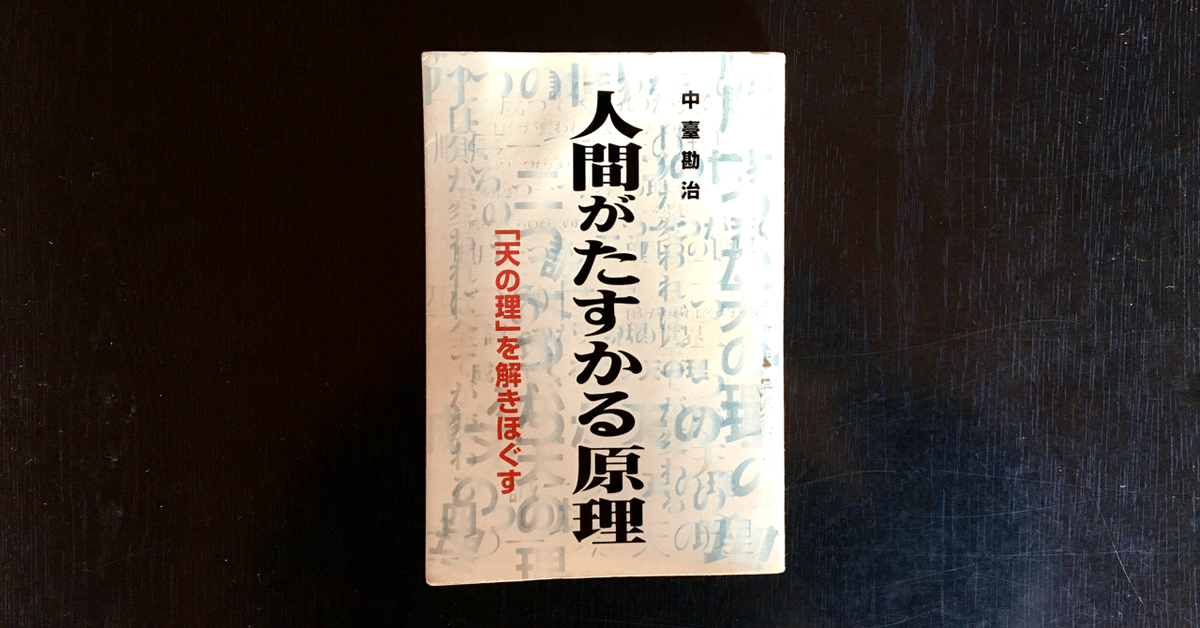
『人間がたすかる原理』
コアLv▶▶▷▷▷
こんにちわ、福之助福太郎です。
今日は中臺勘治さんの『人間がたすかる原理-「天の理」を解きほぐす-』(養徳社、2012年)を紹介したいと思いますが、初めての方はまずこちらをご覧ください。
教えについての分かりやすい説明や教理の一般的な解釈を載せるつもりの投稿ではないという事をあらかじめご理解いただければと思います。
今回のポイント
①誠一つが天の理
②二つ一つが天の理
③順序一つが天の理
④成ってくるのが天の理
いきさつと四つの「天の理」
四つの「天の理」について教祖が言われたかは僕は知りませんし、「おかきさげ」に出てくる場合もこの本で言われているような意味とは文脈的に違うと思いますが、一つの解釈として面白かったので今回取り上げることにしました。
まず著者がこの本で述べられる、四つの「天の理」による解釈に至るまでの経緯を紹介しておきます。
・二十歳(大学二年)の時、「なぜ人間は、この世に生まれてきたのか?」という問いに答えが見つからず勉強する気もなくなり何も手につかなくなってしまったが、お兄さんに「何でもいいから、神様の御用をさせて頂いたらいいよ」と言われ朝五時起きで教会の神殿掃除をするようにした。
・何日か続けるうちに心が明るくなって「おふでさき」を読むようになり、砂漠に水がしみ込むようにお言葉が心に入り込んできた。
・「人間は"陽気ぐらし"をするために生まれた」と小さい頃から聞いて育ったが、初めて聞いたような新鮮さを感じた。
・教会長として三十年以上、様々な病気や人間関係のもつれの"おたすけ"を通して、単に"陽気ぐらし"の教えだけでは解決できないことが分かった。
・さまざまな病気、家庭の問題には、「親神様の十全のご守護の理」が分かる必要があり、でなければ解決も表面的で核心を得ないものになってしまうと感じた。
・自分の信仰上解決しなければならない問題が出てきた。
①心から得心できて共感のできる人生観・世界観を持つ、深みのある信仰を持ちたい。
②なぜ理の親を立て親孝心の道を歩むことが大切か、自分なりの解決を得たい。
③たすかってもたすからなくても、どうでもこの道を歩むという信仰信念を持ちたい。
・大教会から<基本教理の修得>の大切さが全部内教会に呼びかけられている時、「お道とは"天の理"の教えではないか」とフッと浮かんだ。
・それ以来、大教会の青年部屋の張り紙に書いていた、
誠一つが天の理
二つ一つが天の理
順序一つが天の理
成ってくるのが天の理
という言葉がいつも心の中にあり、お道の教理が一つひとつ体系的にまとまっていくのに魅かれ毎月の教会報に書くようになった。
・教会長になってから「お道とは何か?」と行き詰っていたが、「天の理」が分かってくるに従って教理面と教会のあり方についての悩みが解消された。
以上の流れから、四つの「天の理」をもとにした解釈をされていきますが、ここまでの経緯とこの本の骨子は「はじめに」のわずか8ページでまとめられており、本文はその肉付け的な内容なので「はじめに」だけでも一読の価値があるように思います。
本文では『みかぐらうた』『おふでさき』『おさしづ』『天理教教典』『稿本天理教教祖伝逸話篇』などを引用し、体験談や関連するエピソードも交えて説明されているのでとても読みやすい印象でした。
目次
はじめに
第一章 誠一つが天の理
誠の心とは?
どうしたら誠の心になれるか
八つのほこり
をしいのほこり
ほしいのほこり
にくいのほこり
かわいのほこり
うらみのほこり
はらだちのほこり
よくのほこり
こうまんのほこり
うそ
ついしょう
ほこり(まとめ)
元の理からの誠真実
かしもの・かりものからの誠真実
誠一つが天の理(まとめ)
第二章 二つ一つが天の理
神様の働きは二つ一つ
どうしたら二つ一つになるか
親神さま
くにとこたちのみこと
をもたりのみこと
くにさづちのみこと
月よみのみこと
くにさづち・月よみ
くもよみのみこと
をふとのべのみこと
くもよみ・をふとのべ
かしこねのみこと
たいしよく天のみこと
かしこね・たいしよく天
いざなぎのみこと
いざなみのみこと
いざなぎ・いざなみ
十全の守護(まとめ)
二つ一つが天の理(まとめ)
第三章 順序一つが天の理
全てのものに順序・中心がある
順序の理の実践
人間の中心「心」
家庭の中心「親」
一日の中心「朝」
生活の中心「働き」
世界の中心「おぢば」
信仰生活の中心「教祖」
発想の中心「陽気ぐらし」
お金の中心「つなぎ」
物事の順序
グループの中心「リーダー」
宇宙の中心「神」
あとがき
目次を見るだけでも内容が分かりそうですが、それぞれの天の理についてのポイントとその関係について紹介していきます。また本文の中から印象に残った所もいくつか紹介します。
誠一つが天の理
・心の世界
・教理:「八つのほこり」(誠の心の反省)
・おつとめ:第一節
"あしきをはらうて たすけたまへ てんりわうのみこと"
〇人をたすける心が真の誠。たすける理がたすかるという。
〇それぞれも誠一つの理習えば、尋ねる理はない。
〇真実の心しだいのこのたすけ、病まず死なずに弱りなきよに
【印象に残ったところ】
・誠の心は簡単に治まるものではないが、だからこそ最後の切り札として教祖が「ひながたの道」をお残しくだされたのだと思う。
・アルフレッド・アドラー「人のことを考えられるようになったら、うつ病は二週間で治る。」
二つ一つが天の理
・神様の働きの世界
・教理:「親神様の十全のご守護」(二つ一つの中に親神様が身体をはじめ、この世のすべてを貫いて働いている)
・おつとめ:第二節
"ちよとはなし かみのいふこときいてくれ あしきのことはいはんでな このよのぢいとてんとをかたどりて ふうふをこしらへきたるでな これハこのよのはじめだし"
〇この世は、天地・夫婦・昼夜・左右・プラスマイナスなど、二つのものがお互いに補い合って一つになる中に本来の働きがある。
【印象に残ったところ】
・病気や悩みの原因や内容は単純化すると全て「二つが一つに治まらない」ということ。
・「二つ一つ」の元は「誠一つ」。
順序一つが天の理
・存在の世界
・教理:
「かしもの・かりもの」→人間の中心は心
「親孝心」→家庭の中心は親
「朝起き・正直・働き」→一日の中心は朝、心の中心は正直、生活の中心は働き
等々
・おつとめ:第三節
"あしきをはらうて たすけせきこむ いちれつすましてかんろだい"
〇宇宙では太陽を中心に地球が回り、地球を中心に月が回る。小さくは原子核を中心に電子が回り、原子を形づくる。存在するものは、中心がある中に調和を保っている。
〇各々が自らの立場と分を知り、小さな中心はより大きな中心を守る中に、守られ生かされる道がある。
〇中心とは元、根、親、土台。
〇混乱、崩壊、病み、災いは中心を失った姿。
【印象に残ったところ】
・「朝起き、正直、働き」の教えは、すべて生活に密接に関わる「中心」を守る生き方だと思う。
・どうしても中心ができない、順序が保たれず混乱がある場合は「二つ一つが天の理」が実践されているかを反省するのが要点だと思う。二つ一つの融和の中に中心・順序が現れてくる。
ex.)親がいるのに家庭の中で中心がなく問題が起こる場合、夫婦の二つ一つ・親子の二つ一つがうまくいっていない。
・世界中の宗教の聖地や本部の成り立ちと違い、「おぢば」は命のふるさと。"ぢばに一つの理があればこそ、世界は治まる。ぢばがありて、世界治まる"のご神言の意味をもう一度かみしめたい。
成ってくるのが天の理
・時間の世界
・教理:「いんねん」の教理
・おつとめ:第四節、第五節
〇無秩序と思える変化の中にも必ず原因と結果がある。それは「いんねん」として前生、今生、来生の流れの中に引き継がれている。
〇親神様が、全人類を陽気ぐらしにさせたいという「元のいんねん」と、それぞれの個人が過去にどんな種を蒔いてきたかという「個々のいんねん」があり、双方のいんねんが一体化して、成ってくる現象・姿となって現れてくる。
※「成ってくるのが天の理」については『天の理に沿う』(道友社、2007年)で詳しく書かれているそうです。
「天の理」の順序
それぞれの「天の理」の項目でも触れましたが、四つの「天の理」には成り立つ上で順序があり、それによって悩みの解決に向けてアプローチできるという解釈をされています。
①「誠一つ」:心の世界
②「二つ一つ」:親神様の働きの世界
③「順序一つ」:存在の世界
④「成ってくる」:時間の世界
・何か悩みがある時は、「天の理」のどこかが狂っているので、その狂いの判断の基準になる。
・最終的には「誠一つが天の理」(誠の心)が全ての悩みの解決につながる。
・全ての原因は自分自身の心で、「自分が変われば全てが変わる」という発想。
・"心一つが我がの理、たった一つの心からどんな理も出る"の意味が実に深いものとして迫ってくる。
として、誠の心が根本であるという点を改めて強調されています。
最後に
色々な教理を体系的にまとめるという、とても斬新な発想ながら分かりやすく面白い本でした。
個人的にはこの本で言われる四つの「天の理」を活用すると、
[〇:良い状態 / ×:良くない状態]
成ってくる姿が〇なら、順序〇→二つ一つ〇→誠〇
と言え、
成ってくる姿が×なら、順序×→二つ一つ×→誠×
もしくは、
成ってくる姿が×→順序×→二つ一つ〇→誠〇
のどちらかになり悩み事に対しては、
・心が誠ではない
・順序が守れていない
のどちらかだと言えるのではないかと思いました。
(自分の心の誠が〇なら、自分と何かの 二つ一つも〇 / 順序〇なら、成ってくる姿も〇 といえるため)
また、本で説明されている事も上記のように列挙すると理屈っぽくなってしまいますが、単なる理論上の話や教理の分析ではなく、著者が人だすけに専念する中で一つひとつ体系的に心に治まった解釈だという事が大切なポイントだと感じました。
最後に「あとがき」から紹介します。
"お道の教理は、どれもこれも陽気ぐらしを実現するための教理であるが、「八つのほこり」「十全のご守護」「かしもの・かりもの」「いんねんの教理」「元初まりの話」「教祖ひながたの話」。それぞれの教理がどういう関係にあるのかがわからないと、本当の力にはならないと思うのである。この「天の理」は、お道を考えるにも、悩みの解決にも、大いに役立つと思う。"(298-299頁)
お付き合いいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
