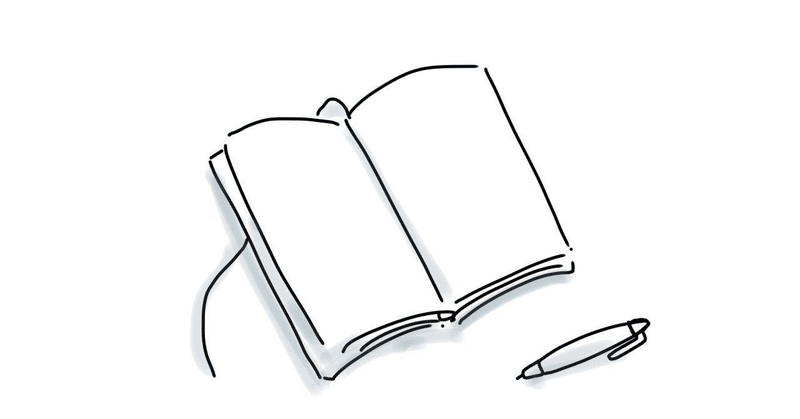
ゆる言語学ラジオとの話
動画解説記事を載せているように、Youtube「ゆる言語学ラジオ」に出演しました。改めて、堀元さんと水野さん、関係スタッフの方や、視聴頂いた方に感謝申し上げます。動画には励みになるコメントが多く、一生分褒められた感じがするのですが、驕らずこれからも謙虚に精進してまいります。
実はゆる言語学ラジオに出演するまでの話を聞きたいという声が結構あったので、今回はあらためて、ここに至るまでの経緯や、その最中で考えたことについて綴ってみます。
そもそもの始まり
始まりの記憶はちょっと曖昧ですが、なんとなくGoogleで何か調べ物していた時に、Youtubeに「ゆる言語学ラジオ」というチャンネルがあることを知りました。言語学をゆるく楽しく語るというコンセプトで動画を作成しているチャンネルということで、言語学に関わる人間としてとても興味を持ちました。このチャンネルは、以下の『「象は鼻が長い」の謎』が人気で視聴者数が急増したと聞いていますが、私が初めてこのチャンネルの動画を見たのは多分この動画が出たか出ないかくらいだったかなーと思います。当時の登録者数は1万人いない(むしろ2-3000人)くらいだったような...(うろ覚え)
私も、身の回りに普通にあり、何も意識せずに使用しているにも関わらず謎にあふれている言語というものを考える楽しさや奥深さを伝えることができればと思い自著を上梓したというところもあり、このチャンネルのコンセプトに共感を覚えました。コンテンツを作成・出演されているお二人は言語学の職業研究者というわけではありませんが、語り手の水野さんは、(どの動画でだったか失念してしまいましたが)「優れたコンテンツには二次創作がある」とおっしゃっていて、なかなか研究者コミュニティの外に出る機会の少ない研究の内容を非常に楽しくわかりやすいコンテンツに昇華させており、私が知らない内容も多かったため、通勤中や皿洗い中など、暇を見つけては楽しんで動画を視聴していました。私が兼任講師として受け持っている授業で受講者が100人超えのクラスがあったのですが、そこで「ゆる言語学ラジオって知ってる?」と尋ねると(オンライン授業だったのでチャットで)、そのうち5,6人、知っていると返ってきました。今のチャンネル登録者数はその頃の何倍にも増えていますが、当時から知名度が高く驚いた記憶があります。
ある日、雑談回を見ていると、途中から水野さんが神妙な面持ちで謝罪会見のようなことを始めました。どうやら動画で紹介したネタ本の内容が誤りだったとのことでした。
どの分野でもそうなんじゃないかと思うのですが、研究をやっていると、あまり迂闊に踏み込むと危ない領域みたいなのがあったりして(理由は様々ですが、巷でカジュアルに言及されているが原典はそう簡単じゃないとか、目を引く研究だけど実験の不備が結構指摘されているとか、その他諸々)、なかなか研究コミュニティ内にいないとそういうところを踏み抜かないように歩くのは難しいだろうなあとも思います。水野さんは大変真面目な性格の方で、動画であまりにも蒼白な面持ちで謝罪されているのをみて、これがきっかけでこの良質なコンテンツを閉じるということになったら残念だと感じました。
Twitterのチャンネルアカウントがあるということだったので、試聴が終わった直後にアカウント探し出し、楽しんで視聴しています、これからも一視聴者として動画の更新を楽しみにしていますといった感じの応援メッセージを書きました。このチャンネルは私が専門とするいわゆる「応用言語学」にはその時あまり触れていなかったのですが、彼らが動画内で「相談させていただける専門家の方がいらっしゃいましたら…」というようなことを仰っていたので、もし今後そこに関係する内容に触れる時は、お役に立てることがあればご協力しますといった内容も添えてお送りしました(後で知りましたが、現在監修として協力しておられる先生方は同じ感じで彼らに連絡をとった方が多いみたいです)。
私も自分の出した何らかのコンテンツにポジティブなフィードバックがあると嬉しいものなので、コンテンツ制作のモチベーションにしてもらえればというわりと軽い気持ちでのDMでした。
すると堀元さんから丁寧なご連絡頂き、「番組についてのご意見・ご感想を伺いたい」ということでしたので、とりあえず実際にお会いしてお話することになりました。恐縮なことにとてもご丁寧にご依頼いただきましたが、私としては愛聴しているチャンネルのYoutuberに直に会えるんだラッキーくらいの気分でした。
現実での出会い
実際にお会いしたお二人は動画内のままのイメージ(動画で見たイメージ唯一違ったのは、画角に入らない水野さんの足が超長かったということくらい)で、とても気さくで話しやすい方々でした。なおかつ動画で見ての通りとても博学な方々なので、次から次へと面白い話が出てきていくら話しても飽きず、そこではとても楽しい時間を過ごしました。
その中で、これから有志の専門家を募り、ゆる言語学ラジオの監修チャンネルをDiscordに作って、動画の事前確認などをお願いしようと思うが、そこに参加してもらえないかという旨の打診を頂きました。このような研究分野に興味をもってくださる人が増えるのはいいことだし、世に出るのであれば内容は正確であるにこしたことはないですので、私は研究のアウトリーチ活動の一環としてそちらに参加することにしました。
前述の通り私はこの分野の研究の楽しさや奥深さを色んな人に伝えたいという気持ちをこれまでも持ってきました。ただそれは、「この分野に従事する研究者を増やして分野を盛り上げたい」というのとは私の場合はちょっと違いました。僕はかつてあまりある時間を自由にできる大学生になった時に、図書館の新書コーナーに行っては好奇心の赴くままに本を手に取り、こんな世界があるのかと知的興奮を覚えたり、行き帰りの電車の中でその日に読んだ本の内容を反芻し、抽象世界と具象世界の間を頭の中で行ったり来たりしながら自分の生きるこの世界のことを考えたりすることに大きな楽しみと幸せを感じたものでした。そして自分も叶うならこのような体験を提供できるような者になりたいと思ったものです。研究者になれそうな要素が何一つなかった私が就職活動もせず大学院に進学し、そのまま大学教員を目指したことは、結果運良く上手く行ったから良かったものの無謀以外の何ものでもなかったわけですが、それは知的興奮に当てられた者が辿る、ありえた多くの帰結の一つでしかありません。つまりアカデミックな内容に興味を持つことと、自分がその営みに職業として主体的に加わることは必ずしもイコールではないと思います。ただ、こういったものに触れて私と似たような体験をした方々は多くいらっしゃるはずで、そのような体験は人生をひとときでも豊かにする素敵なものだと思っています。堀元さんが動画内で、「知識は人生を豊かにするね」としみじみ仰っておりましたが、本当にそうだと思います。
*とはいえ、これは私が研究者としてやりたいことの一つではありますが全てではありません。誰かに知的興奮を味わってもらうためのコンテンツを作るために自分自身が研究に従事しているかというとそんなことはないですし、娯楽コンテンツ的に楽しんでもらうために授業をしているかというと、興味を持ってもらうに越したことはないですがそれを主たる目的としているわけでもないです。また近年では「サイエンスコミュニケーション」の必要性がよく議論されるようになってきていて、科学の面白さ・興味深さを紹介しつつ科学をめぐる問題などを研究者ではない方々と広く共有していく必要性も強く感じているところでもあります。この辺の話は、機会があればまた追々。
監修チャンネル ー 出演オファー
さて、かくしてDiscordの監修チャンネルに入れていただくこととなったわけですが、最初はDiscordチャンネルにいる研究者は私一人だけで、しばらくして言語学の専門家の先生方が何人か参入されました。いずれの方々もお若いながらに研究にガッツリ取り組んでいる優秀な方々で、「ゆる言語学ラジオ」アップロード前の動画につくさまざまな視点からのコメントは私にとっても大変勉強になるものでした。というか今でも勉強になっています。言語に関係する他分野の方との交流はいつも刺激的です。
そして、監修者としてしばらく協力したのち、水野さんから、Youtubeに出ないかと打診されました。特に「いつか出てくださいよ〜」みたいな前振りとかがあったわけでもなかったのでびっくりしました。
楽しそうだなと思った反面、この時点では動画一つのビュー数がコンスタントに3万を超えるチャンネルになっていましたので、そこに出て多くの人に見てもらうことに心の準備ができていなかったし、「顔が生理的にムリ。。。」とか書かれたら立ち直れなさそうだし、どうしようかと結構迷いました。しかし、アウトリーチ大事とか言いながら人前に出たくないっていうのもなんだか言行不一致かなと思ったり、やはりせっかく自分の研究分野を広く知っていただける機会があるのなら...と思ったり、色々と思案した末、依頼をお受けする旨のお返事をしました。承諾した後も、今回はゆる言語学ラジオとしては初の「専門家コラボ」だそうなので、それをダメにしてしまったらどうしようとか、もっといい人いるのではないかとかいう気持ちが何度もよぎりました。
打ち合わせ ー 台本作成
第二言語習得研究は、広く言えば第二言語を対象にするほとんどすべての研究がその範疇に入ってしまうので、私もこの分野は専門といえどまったく素人になってしまうテーマもあります。そんな中で内容については水野さんから、あまり「英語教育」に寄せた内容にしないという方向性と、言語相対論とマルチコンピタンス周りのテーマでまとめるという企画案を頂きました。私も、意識と言語のインターフェイスを探るにあたっては言語相対論やマルチコンピタンスの内容は避けて通れない道だと思っていて、ちょうど今年度スタートした科学技術研究費補助金(科研費)のテーマがまさにこのあたりだったというのもあり、そのテーマを承諾し、そこに沿うような形で自分の出演回のアウトラインを考えました。
アウトラインを考えたといっても、自分がこれまで専門にしてきた意識的・無意識的学習と知識に関する内容から、だんだん意識内容と言語相対論の話に流れ、第二言語学習者のマルチコンピタンスに至るまでのざっくりとした流れを考えて、それに関係する実験研究や刺激文をリストアップしたものを手元資料として用意し、あとは流れに合わせて話そうという感じでした。ゆる言語学ラジオのお二人とお話していると話がどんどん脱線していくのは事前打ち合わせの段階から明らかだったので(ディスってはいません)、そのライブ感を楽しみながら喋る感じのほうが、講義っぽくならずいいかなと考えていました。実際、話に出そうと準備した実験は数にして半分くらいしか話さなかったのですが、結果的により専門外の人にも楽しんでもらえる内容になったと思いますし、そうなったのはひとえに私というより、編集に関わった方も含むゆる言語学ラジオメンバーの実力だと思います。
収録 ー その後
収録は堀元さんの自宅兼スタジオで行われました。スタジオの一角は見たことのある画だったけども、ビデオカメラの画角に収まっていない部分も含めてみると随分部屋の印象が変わって見えました。私が見ている前で第二言語習得回の私が出ていない二回分の収録も行われ(あの動画、水野さんと堀元さんの目の前のカメラが移っていないところで私はビーズクッションに乗ってゴロゴロしていました)、へー、Youtubeの収録ってこんな感じで行うのかと観て学んだうえでいよいよ自分も入って収録へ。自分の声をマイクにのせるのに苦労し(スタンドのマイクに向けてギターを弾きながら歌うっていう経験はありましたが、座った状態で固定されたマイクに向かって話すというのは初めての経験でした。結構勝手が違うものですね...)、またそれまでにある程度彼らとは打ち解けた関係を築けていたと思うので、それほど緊張を感じはしなかったのですが、それでも意外と緊張していたのか、お二人のイジりやギャグみたいなのにうまく返せていないような申し訳なさを感じたりしながら、収録が進んでいきました。動画の中でも言及されているように、結構長時間にわたる収録でしたが、正直あまり長くかかったと感じないほど楽しい時間でした。ただ、本収録を終えて疲れがどっと出たので雑談回は結構頭がまわらずふらふらしながら喋っています。収録を終えた後、夕飯を食べているときや、雑談回の初めと終わりで、「今日はどうでしたか?」と何度か尋ねられましたが、「楽しかったです(語彙力)」としか答えられていません。でも実際に、どう表現していいかわからないほど私にとっては非日常的で楽しい時間でした。人生でなかなかない経験ができたなと思います。
ただ収録を終えて帰宅してから、思い出すたびに「ああ、あのときこう返していればよかった」と思い直してイーッってなったり(こういうの良くありません?なんかいい名前あるんですかね)、収録中に出した例文を思い出して、あれ文法的におかしくなかっただろうかとか不安になったり(安心しようと同僚のネイティブの先生に尋ねて、「んーダメとは言えないかもしれないけどなんかちょっと違和感ある」といわれて不安がさらに増したり)、怖いコメントがついたらメンタルがもつだろうかと心配になったり、そもそもYoutubeで他人様の前に立つなど、なんていう性格に合わないことをしてしまったんだとか既に考えても意味がない余計なことを考えたりする日々を過ごしました。なぜか水野さんにめっちゃ怒られる夢を見たりもしました。公開日が近づいてくるころにはさすがに腹が決まったというか俎板の鯉みたいな気分になっていましたが、それまではなかなか色々葛藤がありました。
しばらくして編集が終わった動画が上がってきて確認作業をしたのですが、真っ先に内容より髪型が気になりました。その前の週に当てたパーマを手懐けるのにミスっていて、だいぶ前髪がキテる感じになっているように感じました(のちに動画を見たという友達とかから「ハゲじゃん。」というLineを複数もらいました)。ちなみにその後美容院に行って、動画のスクリーンショットをスタイリストさんに見せながら「こんな風になっちゃいました...」というと、「あっ、硬いワックス使ってます?元々髪質が柔らかい上にパーマあてて硬いワックス使うとこういう風になったりしますね」と言われました。速攻でムース買いに行きました。もうちょっと早く知りたかった…。
*ちなみに、「この動画、ゆる言語学ラジオっていうんですよ。月末に僕の出演回が公開されると思うので見てみてください」と紹介すると、パーマあてて放置している時間に「うんちくしりとりパンクランチオン」を閲覧されていて、楽しんでいらっしゃいました。また一人ゆる言語学徒を増やしてしまった。
動画が公開されてから、一気に緊張がMAXに達しました。3つの動画の公開が終わるまで、ずっとお腹の調子が悪かったです。やっぱり基本的にこういうのは自分には向いていないのでしょう。
ですが、リスナーの方のコメントや、流れてくるツイートをみていると、とても温かいコメントが多く、またとても楽しんで視聴していただけている様子が伝わってきて、本当に嬉しく思いました。ありがとうございます。心より感謝いたします。これからも頑張って生きようという活力になりました。
出演してから、身の回りの人、受け持ちの学生さん達に等にそのネタで話しかけていただくこともそこそこありました。「動画面白かったです!」「再生数めちゃめちゃ多くてすごいですね!」といったような。それはとても嬉しい反応ですが、(私が)勘違いしてはいけないのは、それはゆる言語学ラジオがすごいのであって、それに乗っかった私が何かすごいわけではないのです。私の出演回はあのチャンネルの再生数からいうと平均的なもので、ネタが提供できたのはもちろん嬉しいことですが、私が何か凄いわけではないです。ガイアが俺にあまり調子に乗るなと囁いている。
思いつくままに記憶を綴っていたら、ずいぶん長くなってしまいました。なんだかんだと、上述のように撮影前後や公開前後にさまざまな葛藤はあったのですが、やってよかったなとは心から思っています。少しでも視聴者の方に楽しんで頂き、言語研究に少しでも興味を持って頂けたら幸いです。
この場を借りて改めて、堀元さん、水野さんをはじめとするゆる言語学ラジオのメンバーに感謝申し上げます。「ゆる言語学ラジオ」の今後更なる発展を陰ながら願っております。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
