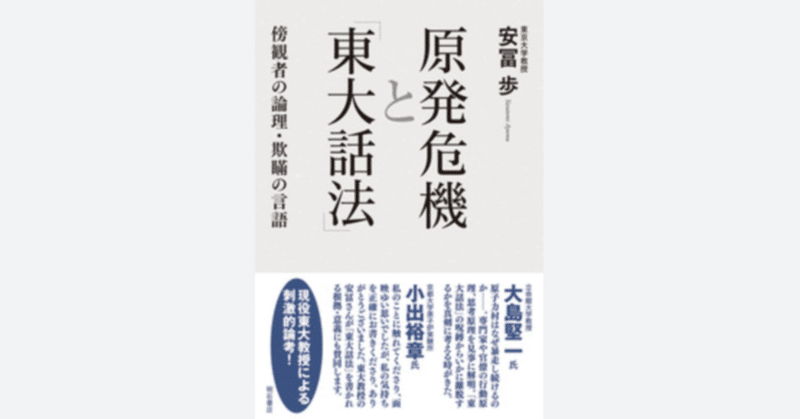
「傍観者の論理」の現在
『原発危機と「東大話法」 傍観者の論理・欺瞞の言語』(安富 歩)を読んだ(以下『東大話法』と略す)。率直な感想をいうと、新しい発見はあまりなかった。なぜなら、第一に事前情報として神保哲生さん、宮台真司さんがナビゲータとして進行する「ビデオニュース・ドットコム」に安富さんが出演されていた回を観ていたし、第二に冒頭に出てくる東大話法の規則については、Youtubeでやっている「一月万冊」でも度々取り上げられていたから。僕自身は原発事故の当時は高校2年の冬で確か部活動の最後の大会が終わって間もなくということもあり、受験勉強に本腰で取りかかる前の段階だったと想像する(正直にいうとあまり記憶がない)。当時は原発が爆発する様子や、津波で家々が流されていく様子にも、それほどのショックを受けることもなく、まったくの傍観者としてテレビを観ていたように思う。その後も原子力村に対する批判を展開している本をちょくちょく読む程度で、技術の破壊性について危惧する一介の工学系学生に過ぎなかった。技術の恩恵を享受しながら、その危うさ(生活そのものが破壊されてしまう危険性や、対人関係に及ぼす影響、世間で常識とされていることとの乖離)について身をもって体験しながら何とか破局的事態を避けているようなそんな生活だった。
以下『東大話法』の感想に入る前に、それ以前に読んでいた本から僕が念頭に置いていた問題意識を紹介しておく。
まず技術者の立ち位置について。
「技術者は技術的手段を考える人たちである。技術者は社会的な立場の条件を与える専門家ではない。問題解決の手段を担当する人間である。」-『ロバスト設計のための機能性評価―効率的開発の方法』(田口玄一)-
タグチメソッドを考案した田口玄一の言葉である。翻訳すれば、技術者は社会的条件を考えて問題設定を行う専門家ではなく、問題設定が行われた後でその問題をどう解決すればよいかの手段を考える専門家である、とでもなろうか。そして「その解決手段の良し悪しは社会的損失を含むコストで判定され、その中に価値判断は含まれない。」とされる。技術者のこの没個性・没倫理性が同時にその中立的立場を保証するわけだ。しかし、何らかの価値判断ぬきで判断を下したりできるのだろうかという素朴な疑問が頭を過ぎる。それは粛々と自分の仕事をこなすアイヒマンのような凡庸な悪とどこが違うのだろうか。自分が置かれている社会的状況やその構造、そして何らかの決定を下す際に帯びる政治性を忘却することが、何らかの悪に加担することになる、というのが第一次世界大戦の教訓ではなかったかと。
次に破局的事象について。
「臨界値に近づいているときに、コスト・ベネフィット計算はばかげたものとなろう。唯一意味があるのは、臨界値を決して超えてはならないということである。」-『ありえないことが現実になるとき-賢明な破局論に向けて(ジャン=ピエール・デュピュイ)』-
これはエコシステムの複雑性について述べられたものだが、破局という事象の特異性を理解する上で重要な指摘である。エコシステムはある臨界値を超えると質的に全く異なるシステムへと変貌する。つまり臨界値以前と以後でコストがぼぼゼロの状態(問題にならないレベル)から無限大(コスト計算不可能)へと一足飛びに跳ね上がり、コスト計算という手法そのものが意味をなさなくなる、というわけだ。そこではコスト計算での良否の判定が不可能となり、ひたすら破局へとつながる可能性を排除していくしか破局を予防する方法はないということになる。しかし、その過剰とも思える破局の予防が成功した際は、破局が本当に起きたのかどうかに対して答えることも原理的にできなくなってしまう、という厄介な問題がある。
「現実の可能性は現実に先行するものではないが、ひとたび現実が出現すればこれに先行したことになるだろう。」-『思想と動くもの(ベルクソン)』-
これは芸術作品についてベルクソンが言った言葉である。芸術作品はそれが出現した瞬間に初めてそれが可能だったことが事後的に証明される、ということを引き合いに出して「可能態はあらゆる瞬間に自らすすんで過去の中に入り込む」という性質を強調している。これは破局的事象にも当てはまり、破局は現実に起きて初めてそれが可能であったことがわかる、という構造になっているようだ。
さてやっと『東大話法』の話である。読んでみた感じたのは、ありていだが「ヒトは言語によって現実を歪めて認識する動物だ」ということである。これは通常考えられている以上に、おそらくそうなのである。現代では言葉よりも情報といったほうが分かりやすいかもしれないが、ホモ・サピエンスはどうやら日々摂取している食べ物が体を形作るように、摂取する情報によっていかようにも人格を変え得る、ということらしい。これは常々感じていたことなのでさほど衝撃はなかった。耳が痛かったのは「傍観者性」を批判している箇所である。現代の学術一般で広く受容されるに至った方法、『事前に設定された地平に沿って「意見」を集め、それを集計して全体像を描き出し、分類して代表的見解を取り出す』という整理の方法では決して「問題の切り取り方の変更」につながらず、「自分の物の見方を変える」ことにもならない、というのである。これはつまり真に学習していない、ということであろう。「知る」ということは、情報に触れることで良くも悪くも自分自身が変わってしまう、ということであると指摘した養老孟司さんと近い考え方ではないだろうか。「知る」というのは決して入れ替え可能な情報の取捨選択ではなく、その人が生きていくよすがとする信念を形作ること、その過程を生きた経験とするという思想である、と今は理解しているところだ。このような「知る」ということなしに、「傍観者性」を軸に思考を展開してしまう理由として安富さんは、日本人が自分が置かれている社会状況・社会構造を把握しようとせずに、ひたすら今置かれている「立場」という容れ物に適した「役」を果たすことで自らの身を守る習慣が、戦中の軍国主義に完成され、戦後は会社の中で温存されてきたためだと語る。そこで欠落しているのは、広い意味での「意味を問うこと」だろう。この仕組みはなぜ作られ、どのような役割を果たしてきたのか、現在も有効なのだろうか、社会的な影響はどうなのか云々。そういった問いを忘れて、ひらすら些末な役を果たしているうちに、足元の地盤が崩れ落ちる可能性は見過ごされてきたわけだ。
この本が書かれた2011年から10年が経過したが、「傍観者の論理」の現在はどうなっているだろうか。新型コロナウイルスの蔓延の中で露呈する日本社会の脆弱性は、そのまま傍観者の論理の脆弱性として、目を覆うほどになっている、といったら言い過ぎだろうか。国を運営している政治家たち自身が当事者性を欠いている状況であり、公的なレベルでの言語の崩壊も僕たちの現実認識を難しくしている。おそらく破局は避けられないのだろう。それでも生きていかなければいけないなら、破局の大波がくるのを覚悟しつつ、その後のよすがを育てていくほかに何ができるだろうか。そのためには閉じたくなる学習回路を開き、状況に適応していくしかないのだろう。たとえ微かなものでもいいから信念を保ち、育てていくこと。自己を見失わず、言葉を正していくこと。言葉を自分なりに再定義していくこと。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
