
【ふくしデザインゼミ 2023-24】講師やゲストの書籍リスト
※最終更新3月2日(3/3のゲスト書籍を追加しました)
2度目の開催となる「ふくしデザインゼミ 2023-24」は、初回に引き続き、多くの出会いやご縁をいただています。やはり講師やゲストのみなさんに興味をもったり、知っていたりして、ふくしデザインゼミと出会ってくださる方もたくさん。
このnoteでは、そんなふくしデザインゼミの講師陣、3/3(日)公開プレゼンテーション、そして12/3(日)開催のオープンフォーラムのゲストのみなさまの書籍をリストアップしてご紹介しています!
まずは、ふくしデザインゼミ2023-24の講師のみなさんの著書のご紹介です。
小松理虔さん(地域活動家)
『新地方論』(2022年、光文社新書)

そう、「自分なりの地方論」でいい。「都市か、地方か」の間に広がるそれぞれの都市論や地方論を、本書を手に取った皆さんにも自由に論じてほしい。(「はじめに」より)
『新復興論 増補版』(2021年、ゲンロン叢書)
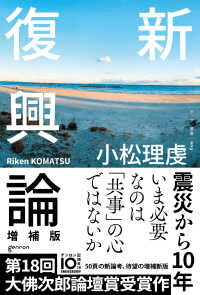
第18回大佛次郎論壇賞受賞から3年。
「本書は、ぼく、小松理虔が、この10年、いかに土地と交わり、思考を重ね、いかに震災と原発事故を血肉化してきたのか、つまり、ぼくがどのように復興してきたのかを記した『復興の書』である」。
——震災から10年、格闘し続けた福島のアクティビストは何を思うのか。外国人との交流、福祉施設への滞在、娘の成長。様々な出会いを通して、トラウマを受け止める「ナラティブ」にたどり着く。地域づくりから、心の継承へ。大佛次郎論壇賞受賞から3年、待望の増補新版。
『地方を生きる』(2021年、ちくまプリマー新書)

いま、余白がある「地方」にこそ可能性が広がっている。これまでの居場所を違った角度で見つめなおすと、新たな面白さ、そして課題と魅力が浮かんでくる。仕事、暮らし、苦労話まで、すべて洗いざらいお伝えします。
『ただ、そこにいる人たち』(2020年、現代書館)

障害のある人がどうしてもやってしまう行動を表現として認め、「いたいようにいる」ことで社会変革をめざすNPO法人クリエイティブサポートレッツ(静岡県浜松市)。当団体を1年かけて「観光」した、福島県いわき市在住のローカルアクティビスト・小松理虔さんによる旅行記的人文書。専門家でも支援者でもなく、あくまでヨソモノとして障害のある人と「ただ、そこにいる」ことで、自己と他者を理解するための扉が開く。東浩紀、國分功一郎両氏などの哲学のエッセンスも満載。
影山祐樹さん(編集者)
『ローカルメディアのつくり方』(2016年、学芸出版)

地域はローカルメディアの実験場だ。お年寄りが毎月楽しみに待つ『みやぎシルバーネット』、福岡にある宅老所の面白雑誌『ヨレヨレ』、食材付き情報誌『食べる通信』他、その地に最適な形を編み出し根付いてきた各地の試みを3つの視点「観察力×コミュニケーション力」「新しい形×届け方」「地域の人×よそ者」で紹介する
竹端寛さん(福祉社会学者)
『ケアしケアされ、生きていく』(2023年、ちくまプリマー新書)

ケアは「弱者のための特別な営み」ではない。あなたが今生きているのは赤ん坊の時から膨大な「お世話」=ケアを受けたから。身の回りのそこかしこにケアがある。
『家族は他人、じゃあどうする?』(2022年、現代書館)

42歳で父になった福祉社会学者、
ままならない育児にジタバタの日々(もうええ加減にしてや……)。
娘と妻との対話から「ケアとは何か」を考えるエッセイ。
「ぼくはいまだに、とっさに子どもをグイッと引っ張る癖がある」
「でも、ふと考えるのだ。なぜ、ぼくはそそっかしいままで、妻は注意深くあるのだろう?」。
自分のなかの「仕事中心主義」や「力ずく」のやり方(=男性中心主義)に気づき、ケアの世界にたどり着くまでの日々の記録。
ここからは、3月3日(日)開催の公開プレゼンテーションのゲストの著書のご紹介です!
安達茉莉子さん(作家・文筆家)
『毛布 - あなたをくるんでくれるもの』(2022年、玄光社)

「――いつも誰かの姿、誰かの言葉が
毛布になってくれていた。」
言葉と絵で「物語」を表現する作家・安達茉莉子の初エッセイ集。彼女は自らの望む道を模索する中で得た考えや感情を瑞々しく掬い上げた文章と、心にあかりを灯すような絵で確実に読者を増やし続けてきました。本書は自分自身を大切にすることが難しかったり、ふと立ち止まってしまったりした時にも「毛布」のように包み込み、心を温めてくれる一冊です。
『私の生活改善運動 THIS IS MY LIFE』(2022年、三輪舎)

「これでいいや」で選ばないこと。
「実は好きじゃない」を放置しないこと。
これは、ひとりよがりの贅沢ではない。--ひとの日常、ひとの営みが軽視される日々にあらがう、意地なのだ。 日常において、とても些細なことだけれど、気にかかっていること。タオルやシーツ、ゴミ箱、セーター、靴、本棚……。これでいいやで選んできたもの、でも本当は好きじゃないもの。それらが実は、「私」をないがしろにしてきた。淀んだ水路の小石を拾うように、幸せに生活していくための具体的な行動をとっていく。やがて、澄んだ水が田に満ちていく。――ひとりよがりの贅沢ではない。それは、ひとの日常、ひとの営みが軽視される日々にあらがう、意地なのだ。それが“私”の「生活改善運動」である。 手づくりのZINEとしては異例のシリーズ累計五千部を記録した大人気エッセイ『私の生活改善運動 THIS IS MY LIFE』を、5万字の書下ろしとともに再構成。待望の単行本化!
『臆病者の自転車生活』(2022年、亜紀書房)
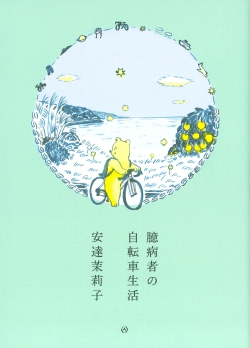
さよなら、「繊細すぎ」のわたし!
「どうせ無理」なんてもう言わない。
読めばじんわりと温もりが広がり、元気がどんどん湧いてくる、
ZINEで大人気の作家が贈る自転車エッセイ集。
----------------------
ふとしたきっかけで乗った自転車が、生活を、心を、大きく変えた。
心に怯えた犬を抱えて生きている著者が、電動アシスト自転車と出会って、小さな冒険を重ねていく。
横浜の街へ、鎌倉へ。
そしてロードバイクを手に入れて、真鶴へ、ついには海を越えて北海道へ。
──自分の「できない」を乗り越えた女性の、勇気の物語。
羽塚順子(編集者)
『ウェルフェア トリップ ー福祉の場を巡る旅ー』
(2021年、アノニマ・スタジオ)

次世代につなぎたい地域づくりのヒントは、
福祉の現場にある
障がい者や社会的弱者たちが働き、暮らしている、各地の福祉施設や共同体を紹介する一冊。そこは、「一般社会と壁を隔てた向こう側」ではなく、地域に根付き地域と交流し合う「福祉的な場」。人間同士が支え合いともに生きるという本来の在り方を伝えます。
そして最後は、12月3日に開催された「ふくしデザインゼミ・オープンフォーラム これからを見つける。~ふくしと、地域と、デザインと」のゲストのみなさんの著書のご紹介です!
磯野真穂さん(人類学者)
『他者と生きる リスク・病い・死をめぐる人類学』(2022年,集英社新書)

生の手ざわりを求めて――。
“正しさ”は病いを治せるか?
“自分らしさ”はあなたを救うか?
不調の始まる前から病気の事前予測を可能にし、予防的介入に価値を与える統計学的人間観。
「自分らしさ」礼賛の素地となる個人主義的人間観。
現代を特徴づける一見有用なこの二つの人間観は、裏で手を携えながら、関係を持つことではじめて生まれる自他の感覚、すなわち「生の手ざわり」から私たちを遠ざける。
病いを抱える人々と医療者への聞き取り、臨床の参与観察、人類学の知見をもとに、今を捉えるための三つ目の人間観として関係論的人間観を加えた。
現代社会を生きる人間のあり方を根源から問う一冊。
『急に具合が悪くなる』(2019年、晶文社)

もし明日、急に重い病気になったら――
見えない未来に立ち向かうすべての人に。
哲学者と人類学者の間で交わされる「病」をめぐる言葉の全力投球。
共に人生の軌跡を刻んで生きることへの覚悟とは。
信頼と約束とそして勇気の物語。
もし、あなたが重病に罹り、残り僅かの命言われたら、どのように死と向き合い、人生を歩みますか? もし、あなたが死に向き合う人と出会ったら、あなたはその人と何を語り、どんな関係を築きますか?
がんの転移を経験しながら生き抜く哲学者と、臨床現場の調査を積み重ねた人類学者が、死と生、別れと出会い、そして出会いを新たな始まりに変えることを巡り、20年の学問キャリアと互いの人生を賭けて交わした20通の往復書簡。
『医療者が語る答えなき世界』(2017年、ちくま新書)

医療現場にはお堅いイメージがある。しかし実際はあいまいで豊かな世界が広がっている。フィールドワークによって明らかにされる医療者の胸の内を見てみよう。
坂本大祐さん(デザイナー)
『おもしろい地域には,おもしろいデザイナーがいる』(2022年、学芸出版)
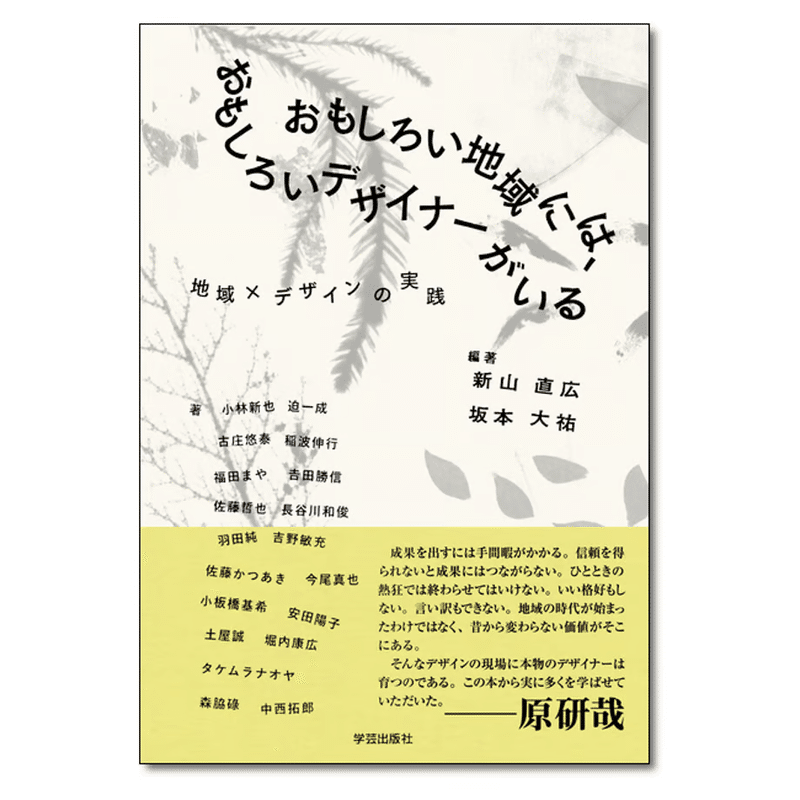
わずかな予算、想定外の作業、地域の付き合い。そんな状況をおもしろがり、顔の見える関係で仕事したり、自ら店に立ったり、販路を見つめ直したり。ディレクションも手仕事も行き来しながら現場を動かし、その土地だからできるデザインを生む。きっかけ、仕事への姿勢、生活の実際、これからの期待を本人たちが書き下ろす。
藤岡聡子さん(福祉環境設計士)
『社会的処方』(2020年、学芸出版)

認知症・鬱病・運動不足による各種疾患…。医療をめぐるさまざまな問題の最上流には近年深まる「社会的孤立」がある。従来の医療の枠組みでは対処が難しい問題に対し、薬ではなく「地域での人のつながり」を処方する「社会的処方」。制度として導入したイギリスの事例と、日本各地で始まったしくみづくりの取り組みを紹介。
ふくしデザインゼミ
『ふくしデザインゼミ』(2023年、ふくしデザインセンター設立準備室)

2022年8月から約8ヶ月にわたって、多様な分野を学ぶ学生13名とともに、「ふくしに関わる人図鑑をつくろう」をテーマに活動したプロジェクト「ふくしデザインゼミ」、その軌跡を記録した一冊です。人図鑑を軸に、ゼミ生の体験を綴ったエッセイや特別対談なども収録しています。
ご紹介は以上になります。どの本もとってもおもしろいので、ぜひ手にとってみてくださいね!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
