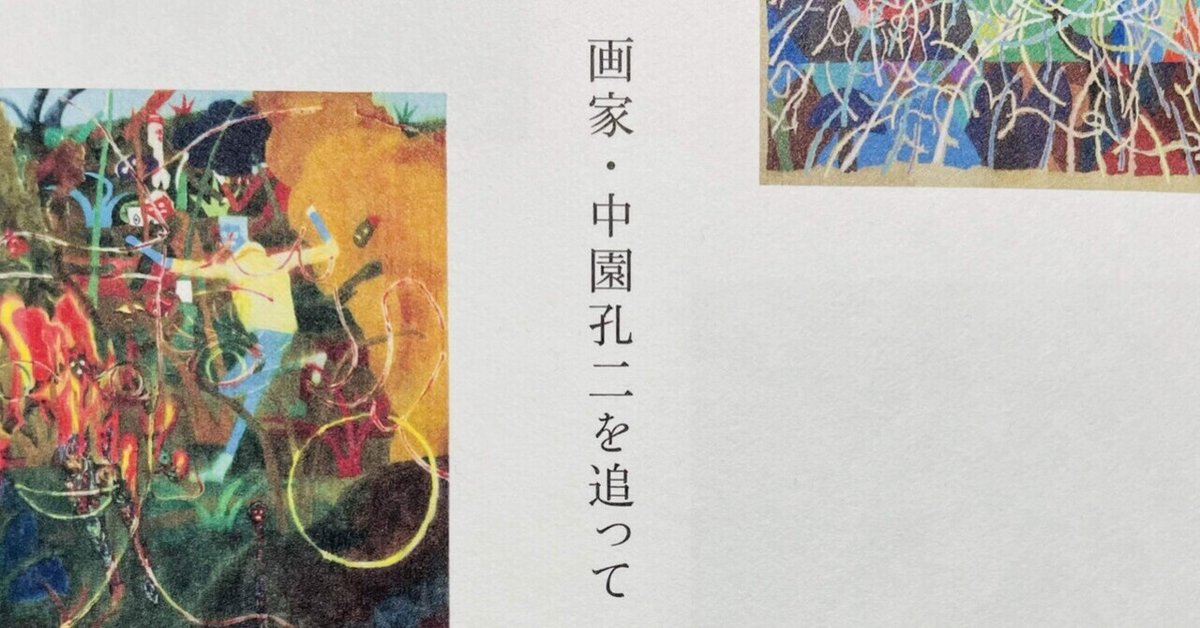
#48『穏やかなゴースト−画家・中園孔二を追って−』を読んで。
25歳の若さで逝去した画家・中園孔二の評伝が8月18日新潮社より出版されました。
タイトルは『穏やかなゴースト 画家・中園孔二を追って』。著者はノンフィクションライターの村岡俊也さんです。
著書をご恵贈いただいた村岡さんへの返礼として、また、中園の友人として思いを綴りました。
今回は文章のみの語りとなります。
書き手・大熊弘樹
少しの後悔
著者の村岡氏と会ったのは今から2年近く前だったと思う。中園のお母さんからの紹介で、新宿のカフェで中園の評伝を書くための取材を受けた。
中園が亡くなった時どう感じたかという質問に「悲しかった。でもホッとした」という常識はずれな回答をしたことは、今となっては少し後悔している。
だが、中園が亡くなりホッとしたというのは嘘偽りない本音だった。
それほどに中園の存在は自分にとっては大きく、誤解を恐れずに言えばいつでも中園の作品を恐れていた。
芸術新潮連載時、その発言が引用された回をみた中園のお母さんから「この発言は誤解を招いたりしないかな。大熊くんが嫌なやつに思われちゃうんじゃない?大丈夫?」と心配されたほどだったが、お母さんはこちらの真意を汲み取ってくれている様子だったので「こちら側としてはとくに問題ありません」と答えた。
それだけ中園の存在は大きかったということを話すと、「あの子はね、本当に普通の子だからね。」と少し重い口調で言われ、何か重要な見落としをしているような気がしてその時は黙ってしまった。
天才というレッテル
お母さんは中園が特別な存在として語られることに、違和感を持っているようだった。
そのような違和感は中園と近い関係の人には少なからずあるようで、本の中で書かれた同級生小川真生樹の「神格化して騒ぐなんて最悪ですよ」という発言は最後まで心に残った。
巷で語られる夭逝の天才画家中園孔二という人物像は、確かに中園を直接知っているものからすると違和感を抱かせることも事実だ。
そのような前提があってか、村岡氏の文章は全体を通じて抑制的な文体で書かれており、それは、死後膨らみ続ける中園像への抵抗のようにさえ思えた。
しかしながら、一つのわかりやすい物語に収束させないようにする配慮が、逆に中園の「普通でなさ」を多角的に照らし出し、結果としては彼の天才性をより強烈に浮かび上がらせるものとなっていた。
「天才というレッテルを引き剥がす試みは失敗に終わったらしい」
本の終盤そう語った村岡氏の文体はこの箇所だけ大変弾んでいるように思えた。
可能な限り粉飾せず「普通の」中園像を描き出そうとする試みが、逆に中園の天才性を浮かび上がらせる。村岡氏にはそのような確信が最初からあったのではないか。
天才という概念ほど便利でくだらないものはない。そう思っている。でも、そうした想いが本を読むにつれ崩れていく。どうしようもない天才はいる。
中園は天才だった。本を読み終えた今、てらいもなくそう形容できる。
そして、この本は中園にはなれなかった私のような人間に強烈なメッセージも放ってくる。
「自分が死んだらどれだけの人が何を語ってくれるだろう」
本を読んでいるとそうした疑問が常に付き纏ってきて、読み進めるのが辛くもあった。
慈しみの気持ち
しかしながら、村岡氏の丁寧な取材に基づいた文章は、中園の人生を追体験し、そこに私のこれまでの人生を重ねることも可能にしてくれた。
中園が関わってきた人たちの話を読む時、自分にも同じような人間関係とストーリーがあることを思い出す。
彼のように破天荒なものでもなければ、多くの人を惹きつけるようなものでもない。
でもそれはかけがえのないものだということに死んだ中園の物語を読みながら少しずつ気付かされていく。
意外だったことは、この本が中園の人生を描くと同時に、中園に関わった多くの登場人物の人生を映し出していることだった。
章の終わりはすべて中園に関わった人の発言で結ばれており、そのことで余韻を強く残す構成になっている。
語られたエピソードは、中園孔二というアーティスト像を形作るための一要素として消費されるのではなく、登場人物であるその人そのものを表す言葉として丁寧に切り取られ表現されている。
そのため登場人物たちのバックグラウンドまで想像することができ、その人物たちが輝いて見えるのだ。
この本は中園の人生を描き出すことを主軸としているが、中園とそれ以外の人たちという構図にはなっていない。文面には村岡氏の登場人物一人一人に対するリスペクトが満ちている。
そして、それは中園が他者に向かい合う時の態度そのものだということを本を通じて理解する。
誰よりも誠実で他者との関係性を重んじていた中園の評伝において、語られた話をパーツとして切り取るような書き方はもっとも回避しなければならない書き方だったのだろう。
いずれにせよ、そうして出来上がった本は中園の評伝でありながら、ある時期中園と関わった人達の群像劇でもあった。
私はなるべく中立的に中園についての話を提供したつもりでいたが、本を読んでみると、とんでもなかった。そこには自己顕示欲をなるべく隠そうとしながらも、中園を通じて自らの考えを語ろうとする私の姿が鮮明に書き出されていた。そうした浅ましさはいかにも私らしく、自分の性格の隅々まで見透かされている感じがした。しかし、不思議なことに、それを読んでもちっとも不快ではなく、むしろ感謝の気持ちでいっぱいになった。
この不思議な感覚の正体は何かと考え、ハッとした。それはまさに中園と対峙する時の感覚に近しいものだった。
思えば、中園にはこちらをバカにしているような態度を取られることがしばしばあった。だが、その時もそれを不快に思うことは一度もなく、むしろとても心地よい経験だった。
それはシンガーソングライターの桑原氏が本の中で語った「慈しみの気持ち」が前提にあったからに他ならないだろう。
中園が今もどこかで私たちのことを見ている。そんなことを思わせてくれる体験だった。
創作を司る"必然性"
私は中園と同じ年にプロとしての初個展を行った。出品した作品は当時20代の自分には信じられないような高値で取引され、その全てがはけていった。おかげで生活も安定したが、そこから3年も経つ頃には全てが嫌になっていた。
本の中でも書かれたエピソードだが、修了制作展を観にきた中園は私の絵を10秒と観てくれなかった。私にはそのことがずっと引っかかっていた。
中園の言う通り絵に「うそ」はつけない。
中園にとってはただただ見るに値しない絵だったというだけだろうが、私は、自分が完全にルーティンに埋没して、納得できない状態で絵を描いていることを見透かされたと感じた。
そんな絵を作り続けることには違和感しかなく、行き詰まっていた。
中園の訃報を聞いたのはちょうどそんな時だった。
それからほどなくして、納得する絵が描けるまでもう発表することはやめようと心に決めた。
納得する絵とは何か。それは描くことに必然性を感じる絵のことだ。中園の創作における逡巡もその必然性にまつわるものだということを本を読み知った。
そしてその必然性を形作るのは自分という主体ではなく、他者である。ということも確信させられた。
ここでいう他者は具体的な人物のことだけではない。
それは、中園の言葉を借りれば人間、社会、宇宙、そうした領域が重なる場所から発せられる一種のエネルギーのことだ。
それは、さしずめ精神分析家ジャック・ラカンの言う外密(Extimité)とでも名指すべき場所であり、そうした内でもあり外でもある亀裂のような場所から滲んでくるコーリングそのもののことだと感じた。
※中園はラカンの概念を援用している可能性があり、ここで言う人間、社会、宇宙はそれぞれ想像界、象徴界、現実界に当てはまるかもしれない。
また、外密と等価な概念として「異者としての身体=Fremdkorper」「不気味なもの=Unheimliche」「穴= trou」などがある。
作品は自分が自由にコントロールして作るものではないのだ。作品を形作るのは自分でもあり他者でもある。
「描かれる物語は僕が決めているのではない」
当時まったくわからなかった中園の言葉が、今はほんの少しだけ理解できるような気がする。
他者の声、複数の声
中園は死んで、私たちは生きている。
もちろんそのこと自体には何の意味もない。
でも、中園の死を頭の片隅に残しながら生きていく私たちにはなにか使命のようなものが託された気がしてならない。
それは具体的なものではなく、何か漠然と指し示される微かなもの。
村岡氏は作品を通じてその無言のコーリングを受け取り、損得を超えた感情でひたすらに取材に突き進んで行ったのではないか。
死者から生者へ何かが託されたと感じるならば、その感覚こそが創作の必然性を司る他者の声そのものであり、それは中園が夜の森で感じようとしていたものと同質のものなのではないか。
中園が最後に携えていたドストエフスキーの作品は、人間以外が主体となることの可能性を追求したものだ。中でも声そのものが主体となり肉を持つようになる過程を文芸批評家ミハイル・バフチンはポリフォニー(=多声性)と表現した。
中園作品の持つ多層構造は、無数の他者の声が肉をもち、決して一つに溶け合うことなく漂っている様子そのものだ。
そして、その作品からコーリングを受けた村岡氏が作り上げた今作も、他者たちの多声性で満ちている。(それは抽象的な意味でも具体的な意味でも)
そうした声に導かれて紡ぎ出された物語は、奇しくも中園の絵と同じ多層構造を作り、この上なく誠実な中園作品への応答になっていた。
おわりに
この本の中の登場人物の大半を直接知っているため、中園と関係した人たちの語りは生の声で再生され、一気に昔に引き戻された。
稲田さんとは昔取手駅にある食堂で一緒になり、その時ラーメンを分けてもらった。寺木南さんは夜のアトリエへの侵入方法を教えてくれた。島田さんとは介護体験が一緒でその時たくさんの話をした。
小川真生樹や神山くんのことは当時一方的に嫌っていたが、今会って改めて絵について話をしてみたい。
仕事にかまけて連絡が取れてなかったトコちゃん(小穴琴絵)とは毎年中園のお墓参りに行っていた。また一緒に行かなければいけない。
親友の富田正宣には今度『ちいかわ』の本を返す予定になっている。
たくさんの思い出や想いが万華鏡のように頭を駆け巡った。そうした読書体験は生まれて初めてのものだった。
中園が亡くなってから今年で8年になる。
この8年間ずっとあったモヤモヤがこの本を読むことで少しだけ解消された気がした。
そして絵を描き続けなければいけない理由も間接的に教えてもらったような気もした。
そして、何より中園にもう一度会えたような気がした。
このような体験を与えてくれた著者の村岡俊也氏には心より感謝の気持ちを伝えたい。
2023.9.23 大熊弘樹
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
