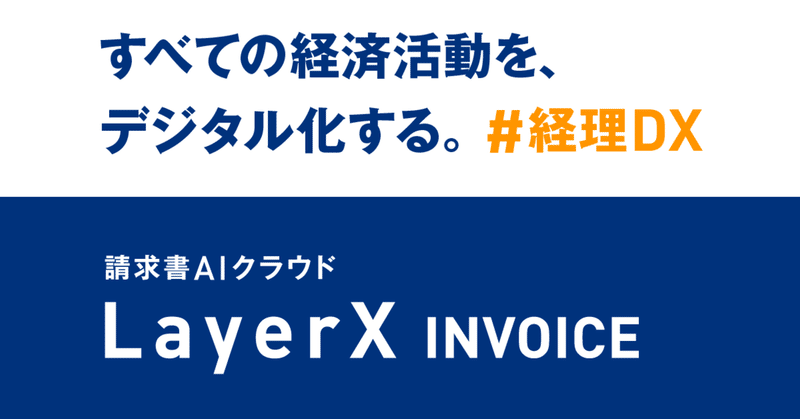
LayerXで経理DXプロダクト「LayerX INVOICE」をローンチします
LayerXは今何をやっているのか
LayerXはこの半年で事業領域と戦略を見直し、以下の3つの事業を展開しています。
1) 経済活動をデジタル化するに資する企業向けSaaSプロダクト開発
→ 請求書処理をデジタル化し、手入力ゼロを実現する「LayerX INVOICE」
2) 特定領域の事業アセットを保有する企業との、経済活動をデジタル化するに資する共同事業開発
→ アセットマネジメント領域における共同事業を行う合弁会社「三井物産デジタル・アセットマネジメント」
3) ブロックチェーンや秘匿化関連等自社テクノロジーのR&Dを活かしたコンサルティング及び事業インキュベーション
→ ブロックチェーンや秘匿化関連技術のR&D組織「LayerX Labs」

2や3に事業に関しては度々リリースを出しているのですが、今日は1の事業に関する発表をしました。
プロダクトのLP
プレスリリース
(日経にも掲載されました)
ちなみにこのプロダクト、かなりご好評いただいてまして、β版リリースして以来、すでに数十社近くトライアル利用いただいてます。
「LayerXだとエンタープライズが顧客」とイメージされるかもですが、1のSaaS事業に関しては、エンタープライズはもちろんのこと、加えてより小規模な会社も対象としてます。現在ご導入いただいてる会社のフェーズは上場前後のステージの会社が最も多いです。
今までデジタル化がほぼされてなかったところ(100社ヒアリングして100社アナログ処理でした)、コロナ禍でデジタル化待ったなしの領域のサービスですのでぜひお問い合わせいただければと思います。
LayerX INVOICE お問合せフォーム
さて本日はLayerXがこの3つの事業をどう考え、なぜこういう事業ポートフォリオにするに至ったかを書いていきます。
なぜこの3つをやるのか
一見バラバラに見える3つの事業ですが、LayerXとしては一貫した意味があります。
LayerXのミッションは「すべての経済活動を、デジタル化する。」です。
これを実現するためには3つの場が必要です。
- 課題とソリューションをドッグフーディングする場所
- 共通化した課題を展開する場所
- 来たるべき未来にむけてR&Dをする場所
の3つです。
さて一般的に様々な場面で言及されるDXですが、DX自体は「技術」「デジタル」の問題ではなく「プロセス」「意思決定」「組織構造」「事業構造」の問題です。なので実際に事業をし、事業者として課題を感じて、そこにソリューションを当て込む、ドッグフーディングする場所がDXの実現には絶対に必要です。
難しく書いてますが、要はその領域を当事者として「事業」として行わない限り、その領域の真の課題はわからないということです。
課題がわかれば、あとはそれをデジタルという道具を使ってどう料理すればいいか理解できます。DXとはデジタルを使うことではなく、自分たちのビジネスをデジタルに合わせて再定義することだからです。ですので、より効果的にDXに対して向き合うため、我々は「大企業との共同事業」と「SaaS事業」の両方を同時並行で持とうと意思決定しました。
実際に今は「アセットマネジメント領域」に絞り、共同事業を展開しています。そこでどういった形で、「大企業との共同事業」と「SaaS事業」が交わるのかの例を出してみます。
(当たり前ですが、)実際にアセットマネジメントの事業に関わることで、LayerXのアセットマネジメント事業への理解は日々深まってます。
またその中で、「アセットマネジメント業界の特有の課題」と「汎用的でいくつかの会社に共通で見える課題」というのも見えてきました。
共通化された課題の中にも、「金融領域の会社」として共通した課題や、より一般的に「統制が必要な会社」に共通した課題などいくつかの粒度にわけることができます。
課題があれば何でもかんでもプロダクト化するわけではありません。例えば三井物産デジタル・アセットマネジメントでは、電子契約にはDocusignを、会計ソフトにはマネーフォワードを、稟議にはKintoneを、といったようにすでに十分に使えるSaaSがあるところは既存のSaaSを導入しています。(※利用しているSaaSは日々の検討の中で変わる可能性はあります)
SaaSを導入した上で、デジタルに合わせた業務フローをつくっており、稟議→契約→会計までをデジタルで一気通貫に行えるようなちょっとした自社開発も行っています。おそらくこの業務が完全にデジタルで完結・効率化されてるアセットマネジメント会社は日本で唯一だと思います。
一方で既存のSaaSをどう組み合わせてもデジタル化できない領域があります。そういった部分は自分たちで開発し、SaaS化することで提供していこうというのが本日発表した「LayerX INVOICE」です。
「LayerX INVOICE」以外にも今後事業を進めていく上で様々な課題が出てきます。既存のSaaSで解決できないものはそこもどんどんプロダクト化していく構想です。

(実は布石として、5月にはこういったリリースも出していました。参考までに)
LayerXにとっての共同事業は、課題とソリューションをドッグフーディングする場所です。実際に当事者として事業をすることで業界の課題の理解を深ぼっていきます。もちろん課題理解だけでなく事業自体をデジタルスクラッチで作ることで、優位性の高い事業構造を作り、共同事業としての利益も取り込んでいきます。
SaaS事業は共通化した課題を展開する場所です。ここでストック収入を作り、自社のビジネスの基盤とし、長期投資の原資となる場にしていきます。
LayerX Labsは来たるべき未来にむけてR&Dをする場所です。短期的目線ではビジネス化が難しいが、5年10年単位で確実に来る大きな波を、沖にでて待つ場です。
ちなみにこのフェーズのベンチャーが、R&D組織を独立で持つことは稀かと思います。持たないという意思決定もできたのですが、デジタル世界における先端技術の圧倒的重要性・企業優位性につながることを私はエンジニアとして、経営者としてずっと見てきました。そのため会社の個性として、シードフェーズでもR&D組織を持とうと意思決定しました。(幸いLayerXは多額の資金調達をしていて、この長期目線をサポートしてくれる投資家の皆様に恵まれたという幸運があります)
LayerXの目指すところ
あらためて、LayerXのミッションは「すべての経済活動を、デジタル化する。」ことです。
こちらの記事でLevel1~4のDXという概念を提唱しました。

ざっくり、「ツール→業務→企業間・業界間・産業間」と最適化される対象が広がっていくイメージです。
請求書業務に例えると、
Level1だと請求書が「pdf化される、データ化される」が実現されるイメージです。
Level2-3が今回提供するLayerX INVOICEの範囲で、「手入力がなくなる・システム間の転記がなくなる・ミスや漏れなどを機械的にアラートする」など業務がデジタル化されるイメージです。
Level4が「請求書の標準化・規格化によってデータのやり取りだけで完結する、デジタルマネーと請求書が結びつくことで催促や担保の概念が変わる、IoTデバイスをトリガーに役務提供や実際に物が動いたら決済される」など、業界間や産業間をまたいだ最適化になるイメージです。
弊社が注力するブロックチェーンや秘匿化技術はLevel4のDXの根幹となる技術です。一方日本の産業界の現状はLevel1-2のDXで四苦八苦しています。
共同事業とSaaS事業はLevel1-2からスタートしLevel3に移行するように解決していきます。
Level4のDXは一足飛びにくるものではなくLevel1を超えたらLevel2の課題に、Level2を超えたらLevel3の課題に、Level3を超えたらLevel4の課題にというように順々に課題のレベルが上っていくと認識されるようなものだと考えています。
弊社としては時間軸が違う3つの事業ポートフォリオをもつことで、最終的にLevel4のDX実現を、(依然変わらず)目指していきます。
最後に宣伝
さんざん上でリンク貼ってますが、最後に諸々のまとめリンクをはっておきます。
サービスにご興味がある方はこちら(現在緊急事態宣言下での特別キャンペーン中です)
こういった世界の実現に興味がある方はこちら(エンジニア、BizDevともに積極募集中です)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
