
ぶいちゃ感謝祭(4) 演出のこと
私、Fujisawaは先日の2024年5月18日(土)、VRChatでのイベントとして「ぶいちゃ感謝祭」の主催行いました。イベントは大成功を収めることができたといっていいと自負しています。
イベントの様子はVRC放送局さんで生配信され、現在はYoutubeのアーカイブで見ることができます。
今回は、ぶいちゃ感謝祭での演出について考えていたことを話していきたいと思います。前回の記事はこちらから
ワールド作成
このイベントのクレジットで、私は、企画・主催・総合司会とクレジットさせていただいています。実はこっそりと、最後にワールド作成ということで、クレジットさせていただいています。ワールド作成以外にも、当日のカメラ制御や演出なども私が行っていました。

元ネタ「オールスター感謝祭」について
さて、演出について話をするとしたとき、元ネタのTBS様「オールスター感謝祭」(以下、本家)の話をしないわけにはいかないでしょう。
番組の何が面白いのかを考える
本家ではたくさんの芸能人の方がクイズやイベントに挑戦し、賞金を持ち帰るというのがコンセプトの番組です。この番組の面白いところはやはり、たくさんの芸能人が一喜一憂するところでしょう。
では、何に一喜一憂しているのか。それはクイズを正解したかどうか、ですね。更にいうと、その先にある賞金についてもありますが、クイズというものは正解しただけでも嬉しいものです。
そう、つまり、クイズはみている人も楽しめます。みている人もクイズに楽しみ、その結果を沢山の芸能人が一喜一憂し、その感覚を共有する。それがこの番組の面白いところだと思います。
演出の必要性
そこで、演出の優先順位を考えます……と、その前に。なぜ、演出を考える必要があったかについてなのですが……。
VRC放送局様での生配信
今回の企画なのですが、実は、VRC放送局様での特別番組を行うことが前提の企画でした。つまり、ワールドの作成時には生配信における演出も同時に考える必要がありました。

70人が同時にクイズに挑戦して優勝者を決めるという、今回のイベント。参加者は当然楽しい自信はありました。実は、私自身も過去にオマージュ企画を行っていたことがあります(点数システムなどは、その時の流用もあります。)その時の経験則からでもありますが、面白くないわけないじゃないですか。70人同時の早押しだなんて。
しかし、参加者が楽しくても、配信先で見てる人も楽しいかは別問題です。しかも今回は生配信なわけです。そこは演出を考える必要があります。
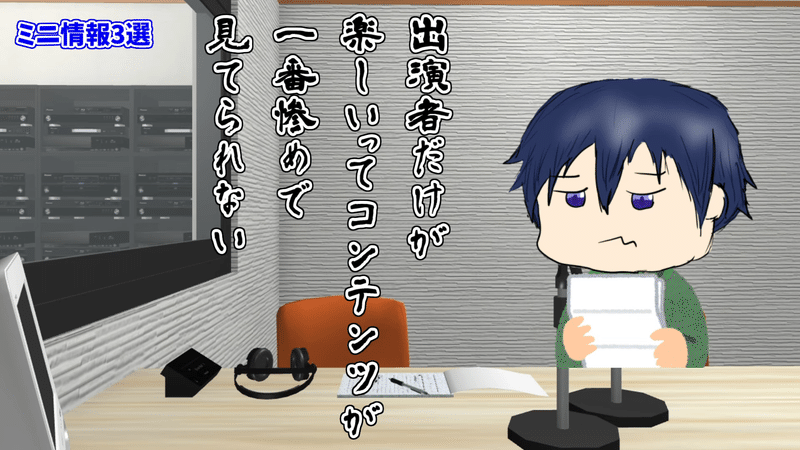
ぶいちゃ感謝祭独自の強み
さて、ネット上を検索してみますと、これまで本家様のパロディ、オマージュ企画は散見されます。前述の通り、私もオマージュ企画をやったことがあります。
今回のぶいちゃ感謝祭では、それまでの企画にはない独自の強みがありました。それは、VRChatというVRメタバース上で行うことで、参加者の生の反応を3Dアバターで届けることができるということです。これを生かさない手はないでしょう。
演出の方向性
さて、まとめますと、演出の方向性としては、70人と視聴者が同時にクイズに挑戦し、一喜一憂するリアクションを共有する。という方向性ですすめればいいかと考えました。
そこで、本家やオマージュ企画のいいところは残しつつ、変更すべき部分は変更し、そして、自分ひとりで操作をするため、ある程度自動化できる事を考えます。
すべてをワールド上で完結させる
演出はすべてワールド上で完結させ、配信状況は常に同期され、全参加者からモニタリングできるようになっています。

配信ソフト(OBS)での切り替えは最後の「ご視聴ありがとうございました」の表示だけです。
このようにすることで、参加者が常にどのような画面が配信されているか把握できます。
全員の音声が入るように
回答者全員の声がガヤとして配信に入るようにしています。
席の位置により声の大小はありますが、全員の声が入るようにはなっているはずです。
特にひっかけ問題などでのリアクションが場を盛り上げてくれました。

回答者カメラとマイクシステム
今回特にこだわった部分です。回答者一人ひとりを抜き(カメラを向け)、マイクのブーストをかけれるようになっています。
これは、マイクを向けられたのを表し、自分にマイクが向いているかどうかはマイクマークが現れるのでわかります。

回答者にカメラが向いている場合、目と名前のプレートが入るように自動的に画角が調整されます。
画角の調整方法やマイクブーストの大きさなど、問題はまだまだありましたが、概ねうまく動いていたのではないかなと思います。
全体カメラ
個別カメラだけではなく、ある程度全体も抜けるようになっています。
5色のグループ全体、および、それらの上段下段で15種類。これらは、抜いた人全員にマイクブーストがつくようになっています。

また、全員が映る画角が左から上から右からで3種類。左側半分が映る画角と、右側半分が映る画角。で、全体カメラは合計20画角作りました。
回答者がどのような状態なのかをわかりやすくし、視聴者と共有しやすいかなという狙いがあります。

ランダムでカメラを向ける
配信中、何度か正解者にカメラを向けているシーンがあったかと思います。これはボタンを押すだけでランダムな人に自動的にカメラを向けることができるシステムを構築しています。

右下の「生き残り」ボタンを押すだけで、順番に回答者が表示されます
なお、このランダムに表示されるシステムも、同じ人に連続でカメラが向かないように、そして循環して表示されるように制御しています。
例えば、ABCDの4人を表示させたい場合、ボタンを押すたびにB→D→C→A→B→D→C→A→…と、順番に表示されます。
このボタンを作ることで、回答者にカメラを向けやすくなり、視聴者と場の共有をしやすくできたかなと思います。
予選落ち(早押しワースト)とピリオドチャンピオン
この2つは絶対に必要だと考えました。なぜなら予選落ち(早押しワースト)もピリオドチャンピオンも回答者を抜いて(カメラを向けて)、リアクションを撮る見せ場となるからです。今回76問使ったということは、その見せ場が76回発生したということです。これを使わないわけにはいかないでしょう。

早押しワーストによる予選落ちとチャンピオンは、自動的にカメラが制御され、該当者を抜く(カメラを向ける)ようにしています。
早押しランキング
そしてそれらを彩るランキングシステムも必須でしょう。徐々に表示されるランキングは、回答者の皆さんの緊張感を高め、その後のリアクションへと繋がります。

小数点以下3桁まで表示しているのは、100FPS以上の環境のことを考えてと、同時チャンピオン/予選落ちを起きにくくするためです。なお、小数点3桁まで全く同じ時間の場合は、内部的に同時チャンピオン/予選落ちは発生しうるシステムになっています。(カメラは1人にだけ追従します)
予選落ちでも回答できるように
ぶいちゃ感謝祭では、問題のみをとにかく行います。過去、予選落ちルールのあった本家では予選落ちした場合、もうそのピリオドに答えることはできませんでした。
このシステムは、回答者に空き時間を作ることになるので、どうにか全問題に参加させたいという考えのもと、次の得点システムを考えました。

得点システム
本家で優勝の決め方は回によって変わりますが、ベースとなるのはクイズ正解数が多い人、そして、それが同じ場合は、かかった回答時間合計の短い人です。
では、生き残っていれば点数2倍、回答時間によって細かい点数が増減するシステムにすれば全員全問題参加しながら、クイズを楽しめるだろうと、構築しました。

なお、ピリオドチャンピオンの2500点は初期の本家がピリオドチャンピオンになったときのボーナス25万円から取ってます。そこをベースにバランスを取った形ですね。

こんな計算式になっているんです…
ボタンの高さと机の壁
ここで、私の作成した別のクイズワールド、V令和教育委員会と今回のぶいちゃ感謝祭のテーブルを比較してみたく思います。

V令和教育委員会とぶいちゃ感謝祭の違いとしては、ぶいちゃ感謝祭のほうが上半身が見える範囲が広いことと、そして、足が見えないことです。
上半身が見える範囲を広くすることによって、3点トラッキングやデスクトップの人でも大きくリアクション取れるようにすること。足が見えなくすることで、前の人のリアクションを邪魔しないようにすることを狙っています。

セットは簡素に
さて、今回のセットは、だいぶ簡素になっています。これは、私が過剰に豪華だったり、ビビッドなセットは好まないからそのようにしています(作れない/作りたくないというのもあります)。
演出の方向性の最初でも書きましたが、今回見せたいものというのは第1に出演者、第2にクイズです。セットは二の次で、むしろ過剰なセットは出演者を見にくくします。これでは本末転倒だと考え、出演者の状態が最低限わかる簡素なセットにしています。

他人の回答を見れるように(2024/06/01追記)
これは、見てる人はぱっと見でわからない部分です。回答者の操作盤には自分の押した番号や結果がわかるようになっているのですが、これは他の人からでも見ることができます。

カンニングという点では良くないシステムですし、隠すこともできますが、あえて見えるようにしてあります。その理由としては本家でも見れることが一つ。もう一つは、チームメイトや近くの人の回答を見てそれについて話ができるという点があります。

最後に
今思いつく限り、演出について考えていたことを書き並べました。
忘れてたことがあれば、また追記していこうと思います。
方向性にも書きましたが、基本的な考え方は、出演者第1です。出演者のリアクションをいかに画面に残して、視聴者と感覚を共有するか。それぞれの項目は、ほぼその方向を向いていることが、わかるかと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
