
ちっちゃな王子さま(超意訳版『星の王子さま』) vol.13
ⅩⅩⅠ
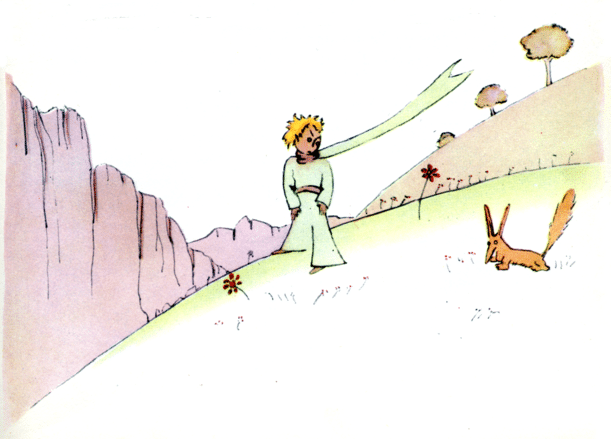
そこにあらわれたのは、一匹のキツネだった。
「や、こんちは」
「こんにちは」
うしろから声をかけられたちっちゃな王子さまは、ていねいに答えてふり向いたけれど、あたりにはだれも見当たらなかった。
「ここだよ、」
声は言う。
「リンゴの木の下」
「君はだれ?」
声の主を見つけて、王子さまは思わずたずねた。「すっごくきれい……」
「おいらは、キツネだよ」
「ねぇ、こっちに来てボクと遊んでよ」
ひと目でキツネを気に入った王子さまは、そう提案した。「ボクは今すごく哀しいんだよ……」
「あんたとは遊べないよ」
キツネはきっぱりと言った。「おいらはなついちゃいないからね」
「え? なんだって?」
王子さまは首をかしげた。そしてしばらく考えてから、こう聞き返したんだ。
「『なつく』っていうのは、どういう意味?」
「あんた、ここの人じゃないな」
キツネは言った。
「何を探しているんだい?」
「人間たちを探しているんだ」
王子さまは一応、キツネの質問に答えたけど、すぐに質問をくり返した。
「『なつく』ってのはどういう意味?」
「人間、ねぇ」
キツネは言った。
「あいつらはを鉄砲を持っていて、狩りをしやがる。まったく迷惑なもんだ! だけど美味いにわとりを飼ってもいるんだよなぁ。あいつらが役に立つのはそこだけだよ。あんたはにわとりを探しているのかい?」

「そうじゃないよ、」
王子さまは首を横にふった。
「友達を探してるんだ。ねぇ、それより、『なつく』っていうのは、どういう意味?」
「それはいつでも忘れられてることなんだけどさ、」
キツネはようやく質問に答えることにしたみたいだった。
「『絆をつくる』っていう意味さ」
「絆を、つくる?」
「ああそうさ」
キツネはうなずいた。
「あんたはおいらにとって、他の何十万もいる同じようなこどもたちの中のひとりでしかない。おいらにとってあんたは、別にいてもいなくてもいいもんなんだ。あんたにとって、おいらがいてもいなくてもいいのと同じようにね。おいらはあんたにとって、他の何十万もいる同じようなキツネたちの中のひとりでしかない、ってなわけさ。
ところが、だ。もしおいらがあんたになついたら、おいらとあんたは、おたがいになくてはならないもんになるんだ。あんたはおいらにとって、世界でたったひとつだけのものになる。おいらはあんたにとって、世界でたったひとつだけのものになる……」
「わかってきたような気がする」
王子さまは真剣な表情でうなずいた。
「ひとつの花があって……彼女はボクになついていたと思うんだけど……」
「そういうこともあるだろうな」
キツネが言った。
「広い地球の上にゃ、何だって起こりうるさ」
「ちがうよ! 地球の上のことじゃないんだ」
ちっちゃな王子さまは言った。
キツネはずいぶんと不思議に思ったみたいだった。
「別の星のことだってのかい?」
「うん」
「へぇ。その星には、狩人はいるのかい?」
「いないよ」
「おお、そいつぁいい! じゃあ、にわとりは? にわとりはいるかい?」
「いない」
「……はぁ、なかなかうまくいかねぇもんだ」
キツネはため息をついた。
それから気を取り直して、さっきの話をつづける。
「おいらの暮らしってのが変わり映えのしないもんでさ。いつだっておいらがにわとりを追いかける、人間がおいらを追いかける、ってなもんさ。にわとりはみんなおんなじで、人間だってみんなおんなじだ。正直ちょっとうんざりなんだよな。
だけどもしおいらがあんたになついたら、おいらの退屈な暮らしにパッと光が差し込むんだ。おいらは、ほかのだれのともちがう足音を知ることになる。ほかの足音は、おいらをおびえさせて土の下に押し込めるだろ? だけどあんたの足音は、まるで軽やかな音楽みたいに、おいらを外へ連れ出してくれるのさ。それから……ほら、あそこに、小麦畑が見えるだろう? おいらはパンを食べないから、小麦はおいらにとっちゃ何の役にも立ちやしない。だから小麦畑を見てもおいらはなんにも感じない。哀しいことにね。だけどさ、ほら、あんたの髪の毛は金色じゃないか。だから、もしおいらがあんたになついたら、あの景色は急にすばらしいものになるんだ! 金色の小麦を見たら、金色の髪のあんたを思い出すようになる、ってわけ。そしたら、小麦畑に吹く風のことだって大好きになるだろうな……」
そこまで一気に話してから、ふとキツネはだまって王子さまを見つめた。長いこと、見つめていた。
「もしよかったらさ……」
ようやく、キツネは口を開いた。
「おいらを、あんたに、なつかせておくれよ!」
「うん、ボクもそうしたいと思ってるよ」
ちっちゃな王子さまはキツネをまっすぐに見つめ返して答えた。
「だけどボク、あんまり時間がないんだ。友達をたくさん見つけなきゃいけないし、いろんなことを学ばなくっちゃ」
「なついたものからしか、学ぶことなんてできないぜ」
キツネは言う。
「人間たちにはもう、学ぶための時間なんてぜんぜんないんだよ。あいつらは店から出来合いのものを買うだけなんだ。だけど、友達を売ってる店なんてありゃしないだろ? だからあいつらにはもう、友達がつくれないのさ。それよりあんたがおいらと友達になりたいと思うならさ、さあ、なつかせてくれよ!」
「どうすればいいの?」
ちっちゃな王子さまはたずねた。
「そうだな、まずは忍耐強くなきゃいけねぇ」
キツネは答えた。
「最初は、おたがいにちょっとはなれた草の上にすわるんだ。ほら、こんなふうに。それからおいらはあんたのことをちらっと横目で見る。あんたも何も言わない。言葉ってのは、誤解の元だからな。それで、毎日会ううちに、あんたはちょっとずつおいらの近くにすわるようになって……」
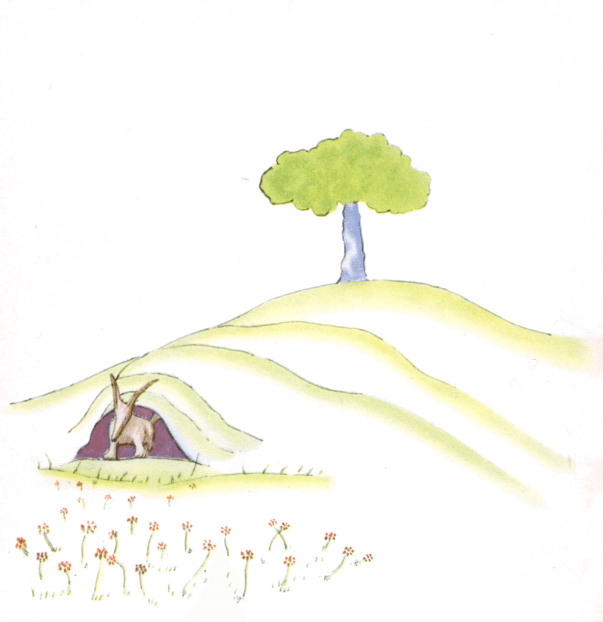
翌日、王子さまはまたキツネに会いに来た。
「いつも同じ時間に来るようにするともっといいね」
キツネは言った。
「あんたが、たとえば午後四時に来るとするだろ? そうしたら、おいらは三時にはもう、しあわせな気分になりはじめるんだ。時間が進むにつれて、おいらはどんどんうれしくなってくる。四時になるころにはもう、そわそわしちゃって大変なもんだ。そんでおいらは、幸福ってのがなんなのか実感するってわけ。もしあんたがいつでも構わずやってくるんだったら、おいらはいつ心の準備をしていいのかさっぱりわからなくなっちまうだろ? ……『習慣』が大事なのさ」
「『習慣』ってなに?」
王子さまが聞き返す。
「これもやっぱりいつでも忘れられてることなんだけどさ、」
キツネは言った。
「そいつのおかげで、ある日がほかの日と、ある時間がほかの時間とちがうものになる、ってもんなんだ。たとえばさ、おいらを追っかける狩人のやつらにだって、習慣ってもんがあるよ。あいつらは木曜日には村の娘たちとダンスをする。だから木曜日ってのは、すばらしい日なんだ! ブドウ畑の方まで散歩に行ける。もし狩人たちがいつでも構わずダンスをするんだったら、ぜんぶの日がおんなじになっちまって、おいらにゃヴァカンス、ってもんがなくなっちまう」
こうして何日かかけて、ちっちゃな王子さまはキツネをなつかせた。だけど、出発の日は近づいていた。
「ああ、」
キツネは言ったんだ。
「おいら、きっと泣くよ」
「君がいけないんだよ、」
ちっちゃな王子さまが言う。
「ボクは君に悪いことなんてしたくなかったのに、君がボクになつかせてほしいって言うから……」
「ああ、そうともさ」と、キツネはうなずいた。
「でも、君は泣くんだろう?」
「そうとも」と、やはりキツネはうなずいた。
「それじゃあ君は、なんにもいいことないじゃないか!」
「あるよ、」と、キツネは首をふる。
「小麦畑の色が、あるさ」
それから王子さまをけしかけて言う。
「ほら、もう一度バラ園のバラたちを見てきなよ。あんたのやつが、世界でひとつだけのものだってこと、わかるから。そしたらあんたはおいらにさよならを言いに、ここにもどってくるんだ。おいらはあんたに、秘密の贈り物をあげるよ」
うながされて、王子さまはバラ園に向かった。
「ああ、ほんとだ。君たちは、ボクのバラになんてぜんぜん似てない。君たちはまだなんでもないんだから」
王子さまはバラたちに向かって言った。
「君たちはだれにもなついてないし、だれかが君たちになついてもいない。君たちは、初めて会ったときのあのキツネといっしょだね。あのキツネは、ほかの何十万の同じようなキツネの中のひとりでしかなかった。だけどボクの友達になって、世界でただひとつだけのものになったんだよ」
バラたちは困惑していた。
「君たちはたしかにきれいだ。だけど空っぽだよ」
王子さまは続けた。
「だれも、君たちのためには死ねやしないんだ。もちろん、ボクのあのバラだって、通りすがりの人にしてみれば同じように思えるんだろう。でもあの花はかけがえのないもので、君たちぜんぶよりも大切な存在なんだ。なぜならボクが水をやったのはあの花だからさ。ボクが土の中に埋めてあげたのはあの花だから。ボクがついたてで護ってあげたのは、ボクが毛虫をとってあげた(二、三匹は蝶になるために残しておいたけど)のは、ボクがぐちや自慢や、沈黙に耳をかたむけてあげたのはあの花だから。あの花は、ボクのバラなんだから」
それだけ言うと満足して、王子さまはキツネのところにもどったんだ。
「……さようなら」と、彼は言った。
「さよなら」と、キツネも言った。
「それじゃ、おいらの秘密を贈ろう。簡単なことさ――心でしか、ものは見えない。本当のところは、目には見えないものなんだ」
「本当のところは、目には見えない」
王子さまは、忘れないようにくり返した。
「あんたがバラのことを大切に思うのは、バラのために費やした時間のためなんだよ」
「費やした時間のため……」
それも、忘れないようにくり返す。
「人間たちはこの真実を、忘れてしまっているんだけど、」
キツネは言う。
「君は忘れちゃいけないよ。君は、だれかをなつかせたことに、いつも責任を持たなくちゃならない。君は君のバラに、責任を持たなくちゃいけない……」
「ボクはボクのバラに、責任を持たなくちゃ……」
ちっちゃな王子さまは、忘れないように、くり返したんだ。
文章を読んでなにかを感じていただけたら、100円くらい「投げ銭」感覚でサポートしていただけると、すごくうれしいです。
