「経済成長」の起源: 豊かな国、停滞する国、貧しい国
単行本 – 2023/8/28マーク・コヤマ (著), ジャレド・ルービン (著), 秋山 勝 (翻訳)
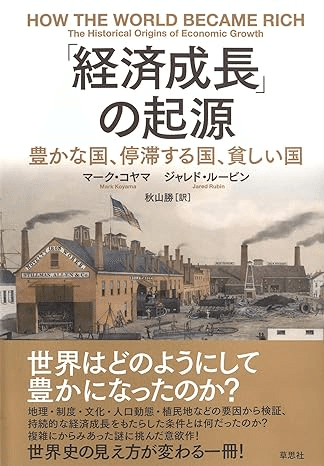
〈目次〉
はじめに
第1章 いつ、なぜ、どのようにして世界は豊かになったのか?
第I部「世界はどのようにして豊かになったのか?」──この問いをめぐるさまざまな理論
第2章|地理|幸運な地理的条件はあるのか
第3章|制度|経済成長は社会制度しだいか
第4章|文化|人を豊かにする文化、貧しくする文化
第5章|人口|人口動態と経済成長
第6章|植民地|植民地と搾取の問題
第II部 真っ先に豊かになった国、それに続いた国、そして貧しいままの国──その違いはなぜ生じたのか?
第7章|北西ヨーロッパ|なぜ最初に豊かになれたのか?
第8章|産業革命|なぜオランダではなくイギリスだったのか
第9章|工業化|近代経済にいたる道
第10章|後発国|キャッチアップ型成長の前提条件
第11章 世界は豊かである
マーク・コヤマ(Mark Koyama)
ジョージ・メイソン大学経済学部准教授、マーカタス・センター上級研究員。イギリスで誕生、オックスフォード大学で経済学の博士号を取得。専門は経済史。共著に近世ヨーロッパにおける宗教的寛容の台頭と国家の発展を論じたPersecution and Toleration: The Long Road to Religious Freedom(Cambridge University Press, 2019年)がある。
ジャレド・ルービン(Jared Rubin)
チャップマン大学経済学部教授。専門は経済発展史、宗教学、中東史、制度史。バージニア大学卒業。スタンフォード大学で博士号を取得。政治制度と宗教制度の関係と経済発展におけるそれらの役割に関する研究は多数の主要経済学誌に掲載されている。2017年に刊行されたRulers, Religion, and Riches: Why the West Got Rich and the Middle East Did Not(Cambridge University Press)でLindert-Williamson PrizeおよびDouglass North Best Book Awardを獲得している。
秋山 勝(あきやま・まさる)
翻訳者。立教大学卒。日本文藝家協会会員。訳書にホワイト『ラザルス』、ミシュラ『怒りの時代』、ローズ『エネルギー400年史』、バートレット『操られる民主主義』(以上、草思社)、ウー『巨大企業の呪い』、ウェルシュ『歴史の逆襲』(以上、 朝日新聞出版)など。
第1章 いつ、なぜ、どのようにして世界は豊かになったのか?
極度の貧困状態にあった人びとが占める比率は急激に減少した。本書の読者なら、ほとんどの人はある程度の快適な生活を送っているだろうし、最貧の生活を強いられている読者であっても、彼らの祖先からすればきっとうらやむにちがいない生活を送っているはずだ。なにしろ、こうやって本を読むことができるのだ。では、世界はどのようにして、ここまで豊かになったのだろう?
通り一遍の説明なら、この問いに対する答えはひと言ですませられる。直近の二世紀でとげてきた経済成長のおかげだ。過去二世紀の経済成長は、それ以前の歴史を通じて実現してきた経済成長を総計でうわまわる規模だった。経済成長とは、経済的な繁栄が持続的に増大していくことであり、経済活動を通じて生産される財やサービスの総量(一般にGDP(国内総生産〉と呼ばれる)によって測定することができる。
同じように、公平な社会の実現と経済成長が拮抗する場合も、かならず二者択一を迫られるわけではない。それどころか、経済成長がとまれば、モラルの面で深刻な後退を社会にもたらしかねない。歴史的に見ても、暴力や不寛容が社会にはびこり、政治的な分断に関する最悪の出来事が起きたのは経済が停滞したり、衰退したりしたときなのである。これに反して、社会の流動性や機会均等は経済の成長とともに高まっていく場合が多い。ミルトン・フリードマンが『経済成長とモラル』で述べたように、停滞した経済は、「経済的流動性やより広範な機会の開放へとうながしていくものを生み出さない」のだ(Friedman,2005,p.86)。
では、世界経済は時代とともにどのように成長してきたのだろう。【図1-5】は、西暦元年以降世界の人口最多地域の一人当たりGDPの変化をざっくりと試算したものだ。言うまでもなくこれらの数字は推定値にすぎず、十八世紀以前は図に示した以上に変動が大きかったかもしれない。だが、全体からうかがえるパターンはおそらく議論の余地がないほどはっきりしているはずだ。十九世紀以前のGDPは、世界でもっとも裕福な国でも一日平均4ドル(二〇一一年の米ドル換算)を超えられなかった。歴史の大半の時代を通じて、一日2~3ドルが標準だったのである。
そうした一方で、きわめて裕福な者がおり、彼らのような圧倒的な金持ちが存在する社会では、界に冠たる偉大な芸術や建築、文学作品が生み出されてきた(飢餓と背中合わせで暮らす庶民にはほとんど縁のない探求ではあるが)。これらの芸術家や作家は歴史書に載っているような、誰でもよく知っている人物たちだ。だが、十九世紀以前の世界に生きていた人類のほぼすべてには、このような芸〔術は無縁だった〕
過去二〇〇年の身長の伸びと一人当たりのGDPとのあいだには強い正の相関があることが観察されている。昔の人は背が低かった。一七六三年から一七六七年にイギリスの国軍に所属していた十八歳男性の平均身長は16076センチだった(Floud,Fogel,Harris,andHong,2011,p.27)。平均身長の伸びには、近代以降に始まる経済成長でもたらされた栄養水準の向上が反映されている。
過去の生活水準を推定するうえで、決定的な指標となるのが平均寿命だ。現在の経済成長も平均寿命が大幅に向上したことと関連している(PritchettandSummers,1996;Fogel,2004;AcemogluandJohnson.2007)。平均寿命には二つの点で大きな意味がある。第一に経済成長で新たにもたらされた豊かさのほとんどは、平均寿命の延びとして表れ、第二に、平均寿命が経済発展そのものをもたらす要因として考えられている点だ(Becker,Philipson,andSoares,2005)。平均寿命が延びると人的資本(ヒューマン・キャピタル)に対する投資価値が高まってくる(CervellatiandSunde,2005)。経済学者は、教育や個人の生産能力を高める技能への投資を網羅する意味で「人的資本」という言葉を使っている。
さて、「世界はどのようにして豊かになったのか?」という問いに対する答えは、人間社会が〈いつ〉〈どこで〉〈どのようにして〉持続的な経済成長をとげられるようになったのか、その疑問にきちんと答えられるものでなければならない。そして、〈いつ〉〈どこで〉の二点については答えはすでにわかっている。十九世紀初頭から半ばにかけての北西ヨーロッパと北アメリカであり、この点については、すでに説明したすべての測定基準と一致している。しかし三つ目の疑問停滞からの脱出はどのようにして起きたのかこれが実に悩ましい問題なのだ。
さらに、文化への影響を介して、制度が経済の発展を左右していると考えられるケースもある。ネイサン・ナンとプリンストン大学のレナード・ワンチェコンは、長期に及ぶ信頼関係の形成の研究のなかで、奴隷狩りの襲撃に頻繁に遭遇していたアフリカの地域では、現在でも他者を容易に信用しない傾向が認められる事実を明らかにしている(NunnandWantchekon,2011)。過去のこととはいえ、奴隷狩りの襲撃にさらされた人たちが、たとえ隣人であろうと自分を奴隷にしようとする他者に対して不信感を抱くのは無理もない話だ。そして、不信の文化が現在まで続いている事実は、文化には“粘着性〟があり、長期にわたる地域の経済的な繁栄を決定づける点にも関連していることを示唆している。
本書を通じて、著者たちは最新の研究とデータに基づいて話を進めていく。それらはいずれも経済史家や開発経済学者、政治学者や歴史社会学者のあいだで、つい先ごろまで議論されてきたテーマだ。直近の二〇年でうかがえる重要な進展のひとつは、経済成長の起源に関する議論がグローバルに展開されるようになった点であり、イギリスや西ヨーロッパに目を向けるだけではもはや十分ではない。そうした議論のなかでも、文字どおりもっとも熱心に論じられてきたテーマのひとつが、西ヨーロッパと中国の経済成長が「大分岐」した起源だった。
「大分岐」という言葉はシカゴ大学教授のケネス・ポメランツが二〇〇〇年に発表した著作で知られるようになった。
工業化の始まりと近代の経済成長という問いをめぐり、著者たちが第一に選んだのは、経済と政治の発展の関連性に重きを置いた一連の説だった。このような説は、制度的変化、国家能力の拡大、法の支配といったテーマに言及しているからである。文献や歴史を調べるかぎり、経済成長をうながしたり、あるいはさまたげたりするこちらの場合のほうがはるかに多いうえで、政治制度の影響を無視したまま、長期的な経済成長について説得力がある説はなかなか語ることはできない。
二番目に説得力があると私たちが認めたのは、文化の役割にハイライトが当てられている説である。誤解を避けるために言っておくが、私たちが言う文化とは二十世紀前半に流行した、ヨーロッパのある側面がほかの文化よりも優れているという類いのヨーロッパ中心主義の文化ではない。文化人類学者が使う「文化」と同様な意味でこの言葉を用いている。つまり、周囲の複雑な世界を解釈するために用いられる発見的問題解決法(ヒューリスティックス)としての「文化」である(Cavalli-SforzaandFeldman,1981:BoydandRicherson,1985:Henrich,2015)。最近の研究によって、本格的な社会科学の研究にも文化は有効であることが実証されており、こうした研究ラインから少なからぬ洞察が得られるのは、第一に文化的な価値がきわめて永続的であるからであり(Guiso,Sapienza,andZingales,2006;Nunn,2012)、第二に文化的な価値は制度の発展と相互に作用しあっているからでもある(Greif,1994,2006;AlesinaandGiuliano,2015;BisinandVerdier,2017)。
コロンビア大学のドナルド・デイビスとデビッド・ワインスタインによる第二次世界大戦後の日本の都市開発に関する独創的な研究は、地理に備わるファンダメンタルな重要性を裏づける事実を明らかにしている(DavisandWeinstein,2002)。二人は原爆で破壊された戦後の広島と長崎について、中心部の人口分布がどのように変化していったのかを調べた。その結果、両市ともに二〇年で日本のほかの都市と同様の人口分布に戻っていたことが判明する。つまり、人口分布に大きな衝撃が加わっても、両市にもともと備わっていた地理的優位性をくつがえすには十分ではなかったのである。
第2章|地理|幸運な地理的条件はあるのか
産業革命以前の世界に見られるさまざまな発展パターンを説明するうえで、地理による影響を否定することはできない。中東の肥沃な三日月地帯に農業と都市が出現したのも、あの地方ならではの地理的な特性が決定的な役割を果たしていた。河川や海岸へのアクセス、肥沃な農地などの地理的特性も工業化以前の発展を説明するうえで役に立っている。
とはいえ、相対的な経済発展をめぐる謎について、地理という要因だけで満足のいく解答が得られるわけではない。一八〇〇年以前の時点では、豊かな土地といっても一人当たりの所得で比べた場合、そうでない土地よりも圧倒的に豊かだったというわけではなく、人口密度が高い傾向がうかがえる程度にすぎなかった。また、経済活動がなぜそこで行われているのか、地理上の特性で大半の例は説明できるが、それですべてが明らかになるわけでもない。企業は特定の地域に集まることでたがいに利益を得ており、労働者もその点では同じだ。ある都市がほかの都市より経済活動に優れている理由として、地理的なファンダメンタルより、むしろこうした近接性に裏づけられた規模の経済とネットワーク効果によって説明できるケースのほうが多いのだ(この便益は「集積の経済」として知られる)。そしてなにより重要なのは、地理的要因だけでは産業革命や十九世紀に始まる近代的な持続的経済成長、あるいは歴史的な記録に残るさまざまな「運命の逆転」が、なぜその時期に起きたのかを説明できない点だ。
では、どう考えればいいのだろう?「世界はどのようにして豊かになったのか?」という問いに答えるうえで、地理という要因に出る幕はないのだろうか。本章をお読みになったいま、社会で異なる特定の要因を決定づける点において、地理が重要な役割を果たしていると納得されたことを願うばかりだが、もちろん、地理だけで説明はできない点もあわせて了解していただければ幸いだ。地理によって完全に説明がつくなら、私たちの運命はすでに何千年も前に決定づけられていたのも同然で、人間の働きかけが関与する余地はほとんどないからである。
第3章|制度|経済成長は社会制度しだいか
これらの問題を提起したのが、新制度派経済学を代表するダグラス・ノースとロバート・トマスの二人だった(NorthandThomas,1973)。二人は研究者が重んじていた経済成長の要因―つまり設備機械や工場施設、教育訓練などへの投資は経済成長を生み出す直接要因ではなく、それらこそ経済成長そのものだと説いた。何が経済成長をもたらすのかを理解するには、社会において何が個人の意欲を駆り立て、工場を建設させたり、投資を行ったり、あるいは教育を受けたり、新しいスキルを身につけるにいたったのか、そのインセンティブを調べなくてはならない。同時にほかの社会では、なぜそのようなインセンティブが働かなかったのかについても検討しなければならない。ノースとトマスは、こうしたインセンティブを生み出す社会的な側面を「制度」と呼び、制度の研究を軸に経済成長の研究をあらためて方向づけることを提案した。
ノースにとって「制度」は、ゲームのルールを意味している。たとえばサッカーというスポーツではルールがゲームの本質を決定し、それによってプレーヤーが向きあうインセンティブが構造化される。ラグビーとサッカーではプレーヤーの行動が異なる点を説明しようとするなら、もっともふさわしい説明は、プレーする個々の選手の違いではなく、彼らが準じているルールの違い、ひいてはインセンティブの違いを説かなくてはならない。
制度に関するノースの考えは、彼のキャリアとともに深まっていった。ノースとトマスは当初、制度には効率性に向かって進化する傾向があると想定していた(NorthandThomas,1973)。市場競争によって効率性に劣る企業が排除され、効率性に優れた企業が生き残っていくように、時間の経過とともに非効率的な制度も淘汰される一方で、より効率的な制度が強化されていく。
ノースはその後、競争市場のように、もっとも効率的な制度を「選択」するプロセスは、制度の分野には存在しないと考えるようになる(North,1981)。政治領域のインセンティブと市場のインセンティブとは異なるからだ。非効率的な制度が何十年、あるいは何世紀にもわたって残るのはこうした理由のせいであり、このような非効率的な制度こそ抜きがたい貧困の原因となっている。そしてそれは、豊かな国がある一方で、なぜ貧しい国が存在するのか――このような疑問に対する主な理由でもあるのだ。
ノースの考えに基づき、スタンフォード大学のアブナー・グライフは制度に関する別の定義を繰り広げた(Greif2006)。グライフの定義には文化的な信条が取り込まれており、この信条が制度を強化し、実際に制度を構成するうえで重要な役割を果たしている。彼が説いた制度とは、「ゲームのルール」にとどまらず、そのルールを支える信条や社会規範が含まれていた。制度と同じように、信条や社会規範もまた変えることが難しい場合がある。同様に、経済的なメリットがもたらされるとはっきりわかっていても、信条や社会規範は変えることができない。グライフの洞察のなかでもとりわけ重要なのは、文化的信条と制度はたがいに補強しあっているという点である。双方がたがいに強化しあえば、いずれもさらに変化しにくくなる。ある国では経済が繁栄し、別の国では経済が成長しそこなった決定的な理由として、グラフはそのような考えを提唱している。この点については第4章でさらに詳しく述べることにしよう。
制度を構成する重要な要素のひとつが、その制度のもとで経済的自由がどの程度認められているかである。この自由が認められているほど、人は自分が最適だと考えるリソースを思いのままに配分できる。また、経済的自由は法の支配と密接に関連しており、社会が法の支配にしたがっていれば、法律は誰にも平等に適用され、個人をめぐるあらゆる権利が保護される。もちろん、その権利には経済的権利も含まれる。さらに、経済的自由と一人当たりGDPとのあいだにははっきりとした相関関係がうかがえる(Gwartney,Lawson,andHolcombe,1999;Gwartney,Lawson,Hall,andMurphy.2019)。ハーバード大学のダニ・ロドリックらの研究によって、社会が法による支配にしたがう程度を一標準偏差高めることで、一人当たりGDPは金額にして六・四倍の差が生じる事実が明らかにされている(Rodrik,Subramanian,andTrebbi,2004)。ちなみにこれは、ボリビアと韓国の所得格差にほぼ匹敵する(【図3-1参照】)。ただし、この知見はうのみにすべきではないだろう。国ごとの差異だけを頼りに、制度の重要性を推しはかることそのものが難題であるからだ。制度をめぐってはどの国も多くの次元で異なり、制度の質がもたらす特定の効果だけを抜き出すのはひと筋縄ではいかない。
財産の保全の制度について、広く使われているもうひとつの指標は「収用危険」である。 「収用危険」とは、国家が私企業の資産を剥奪、収容、国有化、没収するリスクで、国内・国外の別は問われていない。このような没収は投資そのものに取り返しのつかない打撃を与えかねない。収用される標的にされてまで、なぜ投資をしなければならないのかという話になってしまう。
財産権に対する制限は、近代以前のヨーロッパの財産法に見られる大きな特徴だった。とくに封建時代において、土地市場を発展させたり、インフラへの投資をうながしたりするうえで、財産法はしばしば障害となっていた。たとえばイギリスでは、土地は分割されず、一人の男子相続人に受け継がれなければならないという「限嗣(げんし)相続法」が採用されていた。この法律の目的は貴族の土地を守る点にあり、貴族は戦時に際して王に仕える騎士を養うために十分な土地を所有することが求められていた。つまり、軍事上の安全保障のために経済的な生産性が犠牲にされていたのだ。使用者に土地を売却したり、分割したりできる権利があれば、土地はますます貴重なものになる。数世紀をかけて軍隊の置き換わりが進み、騎士団にかわって職業的な軍隊が幅を利かせるようになると、騎士団の維持を理由にした限嗣相読去の正当性は根拠を失っていった。
政治学者のゲイリー・コックスが指摘するように、十八世紀のイギリスが備えていた決定的な優位性は、財産権をめぐる主張の裁定をめぐり、一元的に議論できる開かれた場が議会にあった点である(Cox,2016)。財産権をあらためて振り分けることでもたらされる利益が十分に大きければ、反対する所有権者の訴えをくつがえすことができるし、実際、たびたびくつがえされていた。問題は、議会のような制度的な制約を免れている支配者の存在だった。支配者は自分の都合を優先し、財産権の再配分を行うために権力を使うかもしれなかった。フランス国王はその点で信用されていなかった。そのため地主たちは、土地利用の調整についてみずからの拒否権を決して手放そうとしなかった。以上を踏まえると、全体的な法制度から財産権を切り離して考えることはできないだろう。
貧弱な財産権がどれほど投資意欲をそいでいたのか、ユトレヒト大学のバス・ファン・バベルらはそれについて興味深い例を紹介している(vanBavel,Buringh,andDijkman,2018)。ファン・バベルらが研究しているのは、中世後期に労働節約財として主要な役割を果たしていた装置、つまり水車、風車、クレーンへの投資である。これらの装置の製作には決して安くない費用が必要だが、そのかわり莫大なリターンが得られる投資だった。そして高額の費用のため、文字どおり財産権の保護が担保されているときにしか投資されなかった。西暦九〇〇年から一六〇〇年にかけ、西ヨーロッパでは年月とともに設備は数を増やしていったが、中東では逆にその数を減らしていた。そして、この資本投資の減少は、中東において財産権の保障が守られなくなっていた時期と重なっていた。
法制度によって個人が向きあう動機は構造化される。たとえば、ハムラビ法典では厳しい刑罰が数多く定められていた。父親を殴った息子は両手を切り落とされ、夫を殺そうと共謀した妻と愛人は串刺しの刑に処されていた。身分の低い者が社会的に上位にある者に犯した罪に対しては、さらに厳しい罰が定められていた。「同輩の歯を折る者は、その歯を折らねばならない」とされていたが、社会的に上位にある者が劣位の者の歯を折った場合は罰金だけですむとされていた。このように、ハムラビ法典は既存の権力構造と階層的な社会システムを強化するものでもあったのだ。
つまり、ハムラビ法典とは公正(インパーソナル)なルールではなく、身分というアイデンティティのルールに基づい法体系であり(JohnsonandKoyama,2019)、当事者の社会的アイデンティティしだいで科される刑罰は違っていた。このようなアイデンティティに基づいたルールによって、既存の支配階級の権力は強化されていく。歴史上、こうした法律の例は枚挙にいとまがない。中世ヨーロッパのユダヤ人は独自の法律にしたがい、何を着ていいのか、どこに住めばいいかなどもそうした法律によって定められていた。また、このころのヨーロッパの都市の多くで奢侈禁止令が発布され、属する階級に応じてじて個人が着られる服が決められていた(DesignandKoyama,2020)
これに対して公正(インパーソナル)なルールでは、社会的なアイデンティティにかかわりなく、いずれの個人も同じように扱われることが約束されている。財産を保護する点では、こちらのほうがふさわしい場合が多い。また、交換もインパーソナルなルールのほうが容易にできるので、投資がうながされ、経済成長をもたらす可能性はさらに高まる。
アイデンティティに基づくルールとインパーソナルなルールを分かつ決定的な違いはもうひとつある。「法による支配』と「法の支配」の違いだ。「法による支配』に基づく社会では法律はもちろん存在しているが、かならずしもすべての人間に適用されているわけではなく、支配階級はその適用を得てして免れている。このような社会では「汝のための法律はあっても、我がための法律はない」と言われている。本草でもすでに述べたように、そのような社会を脱し、支配者が法によって制約されている社会へと移行することが経済成長への鍵となる(GrandRubin.20
法の支配が強い社会は、経済的にますます豊かになっていく傾向がうかがえる。法の支配の何が経済に対してプラスの結果をもたらすのだろうか。アメリカの法哲学者ロン・フラーは「法と道徳」で法の支配には以下の条件が必要であると説いた(Fuller196)
1.法的平等の概念。つまり、支配者以下、あらゆる個人が等しく法のもとに置かれている。
2.法律は見通しが良く、開放的で、明確であるべきである。
3.法律は時間の経過とともに安定するものでなければならない。
4.法律の制定はオープンで、インパーソナルなルールによって導かれるべきである。
5.司法は政治的に独立しているべきである。
6.裁判所のような法的機関は、万人が利用しやすいものにすべきである。
7.ルールは汎用的で、一律に適用されるべきである。
いずれも不透明さを取り除くための条件で、これらによって投資が増え、
経済交流が活発になっていく
重要なのは、法の支配はさまざまな制度の結びつきによって成り立っているという点であり、行政府の権力を抑制するルールに縛られた政治体制であるかどうかなのだ。さらに言うなら、法の支配とは法律制度が一本化されているかどうかであり、その制度において、個人が自分に何を期待されているのかを知り、汚職や利益供与によってくつがえされることのない明確に定義された基準があるかどうかにかかっている。
西ヨーロッパが台頭するうえで、法の支配が決定的な役割を果たしていたと多くの研究者が主張してきた。政府の権力に歯止めをかけ、各人に不干渉の私的領域を保証し、長期的な経済成長に資する安定した基盤を提供したものこそ法の支配にほかならなかった(Hayek,1960:Cooter,1997:Weingast,1997)。つまり、人による支配ではなく、法の支配が安定性と確実性をもたらしたことで、個人は取引や交易を行い、繁栄への道を歩むことができるという考え方である(Dicey,1908,pp.198-9)。だが、このとき問題になるのは、社会はどのようにすればインパーソナルなルールを発展させられるのかという点である。そもそも、法の支配という考えはどうやって生まれたのだろうか?
多くの学者たちは、中世に発展したイギリスのコモンローは財産権の制定とその保護において重要な役割を果たしてきたと考えてきた。そして、コモンローこそ財産権の保護に必要な、安定はしているものの、適応性のある一連の原則をもたらしたものであり、それらの原則はのちの世紀になってさらに複雑で組織的な形態をともなった原則の出現を可能にしたと論じた。
この考えに基づき、ブラウン大学のラファエル・ラ・ポルタらは、イギリスのコモンローの伝統はフランス法やゲルマン法のようなローマ法に基づいた法制度よりも財産権の保護が充実しており、規制も少なく、市場にとってより好ましい環境をもたらすことに関係していると説いた(LaPortadeSilanes,Shleifer,andVishny,1998)。ラ・ポルタらがとくに主張していたのが、コモンローが発展した国々では、投資家保護が制度的に手厚い点だった。こうした国ではGDPの規模にかかわりなく、株主と債権者の双方にもっとも強い権利を与える傾向がうかがえた。金融が発展していくうえでこの点が重要なのは、企業の内部関係者が投資家から利益を奪う範囲が制限されるからだ。
ただ、フランスのように革命前に大陸法とコモンローの双方の伝統があった国では、経済の発展にとって大陸法が好ましいものではなかった証拠はほとんどないことが別の研究からわかっている(LeBris,2019)。このような法起源論がとくに問題になるのは、金融の発展が時代とともに大きく異なるという研究結果があるからだ。一九一三年、GDPに対するフランスの株式市場の時価総額が占める割合は、アメリカのほぼ二倍だった(Rajan,Zingales,2003)。
とはいえ、各国がどのような法律を採用しているかは、植民地時代に残された重要な遺産のひとつでもある。ヨーロッパに植民地化された国第6章で見るように、ヨーロッパの植民地は世界各地に進んだは、宗主国の法制度を採用する傾向があった(【図3-5】参照)。イギリスの植民地経営が、ヨーロッパのほかの国に比べてうまくいくことが多かったのは、この国のコモンローが植民地にも浸透したからだと考える者もいる。また、異質な法的伝統が植民地にどのように移植されたのかが出題だと説く研究者もいる(Benkowitz,Pistor,andRichard,2003)。とくにパブロ・デ・オラビデ大学のダニエル・オー=ベラリアスとディエゴ・ロメロ=アビラの二人は、イギリスが植民地にコモンローを〔適用させていたという〕
...しばしば市場や分業の拡大をうながしていた。責任を負うべき政府も健全な財政政策を取りやすくなり、信用をめぐるリスクも低下したが、国家の支配者が無謀な戦争に新しい財源から得た資金を使い込む機会はつねにあった。それだからこそ、制限的政府と中央集権的な財政システムを組み合わせることで、国家はようやく低コストで貸し付けを受けられるようになったのである(Dincecco,2009)。その結果十六世紀から十九世紀にかけて、ヨーロッパの国々の歳入は大幅な飛躍をとげることができた(【図319】参照)。
ある時期を迎えたある地方のある国が、なぜ、どのようにして財政能力を備えるようになっていったのだろう?近世のヨーロッパでは、議会が徴税の承認と正当化について重要な役割を果たしていた。国家が財政的に分断されていたので、徴税に際して国王はほかの支配階級の賛同が必要だった。
ティリー同様、ホフマンもヨーロッパの経済的成功の原動力として絶え間ない戦争に着目しているが、国家形成の別を強調するのではなく、戦争が軍事技術の革新をうながす役割を重んじている。このような技術の進歩は、とくに火薬と結びついたときにヨーロッパが世界のほかの地域を植民地化するのに立つことを可能にした。しかし、なぜヨーロッパの戦争形態は世界のほかの国と異なっていたのだろう。ホフマンは、好戦性という文化的な性向が、ヨーロッパの軍事競争をほかの地域よりも激しくさせていたと説いている。
さらに、戦争が経済活動の場に与える影響もあった。経済学史を研究するジャン=ローラン・ローゼンタールらは、ヨーロッパの戦争が都市部に比べて地方に不釣り合いなほど大きな被害を与えていたのは、地方は都市部ほど要塞化されていなかったからだと説いている(RosenthalandWong.2011)。これに対して中国では、戦乱の頻度が低いため、いったん戦争になると都市部も農村部も等しく影響を受けていた。その結果、中国とは異なり、ヨーロッパでは商業と製造業の担い手は都市部に囲い込まれ、都市部の賃金は上昇、それを受けて省力化をう〔ながされた〕
第4章|文化|人を豊かにする文化、貧しくする文化
二十世紀初頭に指摘された文化的差異とされていたものの多くは、ヨーロッパの観察者が観察対象に向けていた文化的規範と同じように、観察者自身の文化的規範を反映していたのかもしれない。たとえば、十九世紀後半の日本に滞在していた西洋人は、日本の労働者の怠惰や無気力について解説している。ケンブリッジ大学の張夏準(ハジュン・チャン)によると、「アメリカの宣教師シドニー・ギューリックは一九〇三年に出版した『日本人の進化』で、日本人の多くが「怠け者で、時間の経過にはまったく無頓着であるという印象を与えている」と述べている」という(Chang2008)。ギューリックはただの観察者ではない。一八八八年から一九一三年の二五年のあいだ、日本に滞在、日本語を完全にマスターし、この国の大学で教鞭を執っていた。帰国後は、アジア系アメリカ人のために人種平等を訴える運動を展開する。そうしたギューリックでさえ、日本人は「お気楽」で「感情に流されやすい」人種で、しかも「陽気で将来への不安がなく、刹那的に生きている」という文化的ステレオタイプを裏づける証拠をありあまるほど目にしていた。二十世紀後半になると、日本人の規律正しさや勤勉、あるいは時間厳守の性向は、根強い儒教文化を反映したものだと観察者たちは説くように〔なる〕
経済成長を阻害した主因のひとつは、仕事と利益に関する人びとの考え方や評価だったという。たとえば古代ギリシャや古代ローマでは、いかなる労働ももっとも卑しむべき活動だと考えられていた。一方、富は自由をもたらし、自由な時間を授けるものとして尊ばれていたという(Finley,1973)古代社会において中流階級ブルジョワには地位らしい地位はなかった。そもそも成功しようと考えるなら、土地の所有に努め、その収益で生活するのが当たり前だと見なされていた。社会の階級を昇りつめようと考えるローマ人にとって、怠惰こそそのゴールだった。
このような文化的価値観の社会では、持続的な経済成長など望めそうにはない。後述するように、長期的な経済成長を持続させるには技術革新が不可欠である。しかし、技術革新には生産プロセスをはじめ、生産の効率化の実現に関するきめの細かい知識が欠かせない。勤勉を嫌う社会では、イノベーションをもたらすような人材を生み出す堅実な階級は育たないだろう。金融の重要性を軽視する社会では、旺盛な起業家精神にあふれる階級は出現しないだろうし、資本財への大がかりな投資もさかんにはなりそうにもない。第2章で見たように、古代ローマ帝国は高度な市場経済を持ち、道路網も発達していたが、持続的な経済成長を実現させることはできなかった。
勤勉を軽んじる文化的価値観は、中世を通して、とくにヨーロッパの支配階級のあいだに根強く残った。彼らが手を動かすとすれば戦争であり、労働ではなかった。数こそ少なかったが、下層階級から経済的に出世できた幸運な人びとは、その富を利用しておそらく高貴な称号を得ることで社会的地位を手にしていたはずだ。いったんそうした地位が手に入れば、土地から得られる成果で暮らしていくのが流儀で、富をもたらしてくれたそもそもの職業からは離れていった。
十七世紀から十八世紀にかけ、こうした文化的価値観は、北西ヨーロッパで変化していったとマクロスキーは説く。オランダ、さらにイギリスなどでは、ブルジョワの利益追求が蔑視ではなく、称賛されるようになった。ブルジョワの評価が高まることで、金融業者や商人、新技術の採用者は人びとがあこがれる職業に祭り上げられていった。経済的地位の向上は社会的地位の向上を意味するようになり、単に名声を得るための手段ではなくなる。このような文化の変化に応じ、もっとも優秀で聡明な人材が生産的な仕事に従事することがうながされていく。裕福な商人、金融業者、製造業者からなる階層が出現し、イギリスのエリート層に加わっていった。紡績工場の経営で財をなし、議会入りしてのちに準男爵になったロバート・ピール卿(一七五〇~一八三〇年)、あるいは製靴業者から政治家に転じたジョセフ・チェンバレン(一八三六~一九一四年)のような人物たちである。
これと好対照だったのが中国である。過去二〇〇〇年の大半の時代を通じ、中国は技術や科学の分野で世界をリードしてきた。しかし、一八五〇年の時点で中国は技術、科学、工学の各部門でまぎれもなくヨーロッパの後塵を拝していた。この事実をきっかけに有名な「ニーダム・パズル」が生まれる。イギリスの偉大な化学者で歴史家でもあったジョゼフ・ニーダムにちなんで名づけられた謎で、古代と中世の時代、世界の科学をリードしていた中国が、十九世紀になってなぜおくれをとってしまったのかという問いである(Needham,1995)。
この問いに対する有力な答えのひとつが文化だ。ハーバード大学のデビッド・ランデスは、中国は「科学的な専門知識にともなう経済的な可能性を、社会の大きな価値と結びつけて実現することができなかった」として謎の説明を試みている(Landes,2006,p.7)。さらにランデスは政治的な競合の欠如、強力な国家権力、自由な議論を可能にする制度の欠落といった制度的な要因を指摘する一方、中国とヨーロッパの文化的な差異について長々と語り、中国には「ヨーロッパ人が感じていた発見に対する特有の喜び(略)。新しいもの、よりよいものに対する喜び(略)。技術革新を育む土壌」がなかったと指摘していた(Landes,2006,p.9)
だが、ランデスのこの説明は筋が通っているのだろうか。中国の文化的な発明嫌いと現実を結びつけるにはやはり無理がある。ひとつには、これではニーダムのパズルは解き明かせない。なんといっでも中国は、過去二〇〇〇年のあいだ、世界の技術革新のリーダーだった国だ。また、主張を裏づける証拠に乏しい。
ヴェーバーは彼が暮らしていたドイツという国からこの説の着想を得ている。ドイツではカトリック教徒に比べ、プロテスタントの信者のほうが経済的にはるかに優れた結果を生み出していた。この相関関係はドイツ国内にかぎった話ではない。十六世紀以降、世界の経済をリードしてきたのはプロテスタントが優勢な国で、十六世紀後半から十八世紀初頭はオランダ共和国、次いで二十世紀初頭までイギリス、それ以降はアメリカが世界経済をリードしてきた。さらに言うなら、現在でもプロテスタントには一人当たりGDPに対して強い正の相関が認められる。これに対してカトリックとの正の相関は貧弱で、イスラム教とは負の相関関係にあることが【図412】からもうかがえる。しかし、ヴェーバーが説いている因果的論証は正しいのだろうか?プロテスタンティズム(とくにカルヴァン主義)が資本主義的労働倫理を介して本当に経済成長を引き起こしていたのか?もしかしたら、「相関関係≠因果関係」の典型〔ではないのか〕
十六世紀から十七世紀に台頭してきた議会は、北西ヨーロッパの経済が勃興するうえで重要な役割を果たしていた。これらの地域がプロテスタントの優勢な地であったことは決して偶然ではない。議会の多くは貴族や教会関係者、法律家、商人などの有力者によって構成されていた。国王が権力を維持するために議会を必要とすればするほど、こうした有力者は国王の統治に対して発言力を高めていった。政治の世俗化が経済成長に影響を与えたのはそのせいなのだ。議会には経済エリートの関心を反映させる傾向があり、彼らは(自己の利益のために)財産権の確保やインフラへの投資などを望んでいた。このような彼らの関心は、社会全体に経済的成功をもたらすような関心と一致していた。そうした彼らに政治的な発言力を与えることは、彼らの意向をさらに多くの政策に反映させることを意味していた。
ルービンによれば、これこそ宗教改革後にイングランドやオランダ共和国で経済的な飛躍が始まった理由で、その一方でカトリック国のスペインが、新大陸から大量の金銀が流入していたにもかかわらず、経済発展におくれをとった理由にほかならない。ハーバード大学の経済学者ダビデ・カントー二らは、宗教改革後のドイツでも、宗教エリートから世俗エリートへの権力の移行という同様な現象が起きていたことを明らかにしている(Cantoni,Dittmar,andYuchtman,2018)。プロテスタントが支配的な地域では、大学卒業者がますます公共部門に就職するようになり、建設される建物も宗教施設から公共施設や行政施設へとシフトしていった。こうした事実は、統治者がますます多くの有能な官僚を獲得したことを示しており、国家において官僚化が進むと同時に、法的な思考も宗教的なものから世俗的なものへと変化していったことを示唆している。宗教法は精神の領域に追いやられ、国家は世俗的な問題に対処するようになっていった(Berman,2003)。
こうした変化が相まって、とくに北ヨーロッパや中央ヨーロッパにおいて、近代国家の特徴である官僚制や法形式主義の基礎が整えられていった。ヴェーバーの理論とは異なり、これらの説明はプロテスタントの教義内容とはほとんど関係なく、政治において宗教が果たした(あるいは果たさなくなった)役割に焦点が当てられている。
アメリカの政治学者ティムール・クランは、たしかに停滞をもたらしていたが、その理由は「宗教法は悪、世俗法は善」というよりもさらに微妙だと説いている(Kuran.2011)。クランによると、イスラム法は多くの面で進歩的で、イスラム教が黄金時代を迎えた七世紀から十世紀にかけて経済成長をもたらしていた。こうしたイスラム法には、どちらかといえば平等主義的な相続制度、広い範囲に及んでいた共同経営法、「ワクフ」と呼ばれる基金に関する法律などが含まれる。このような法律は、イスラム黄金時代の中東経済が繁栄するうえで大きな役割を果たしていたが、それにもかかわらず経済に停滞をもたらす原因にもなっていたのだろうか?
経済状況の変化に対応する点では、イスラム法はどちらかといえばのんびりしていたとクランは言う。ただ、それは宗教上の理由からではなく、単に商業に関連する法律を変えようという意欲が乏しかったからだ。その典型が相続と共同経営に関するイスラム法である。イスラムの相続制度は当時としてはきわめて平等で、女性にも遺産の相続権が認められていた(ただし、男性の半分にかぎられていた。ヨーロッパの大半の国では女性の相続は認められていなかったので、それに比べればまだましだった)。
また、多数の相続人があらかじめ定められた方式で決められていた。経済成長にとってこれが重要だったのは、共同経営を左右していたからである。イスラムの共同経営は、パートナーの死後、共同閣係を解消することになっていた。理屈としてはふたたび結成することは可能だが、そのためにはパートナーの相続人のほぼすべてが協力しなくてはならない。だが、相続人の誰かが金銭的な窮地においった場合、その相続人は共同経営の資産の清算を求めることができ、この場合、関係する者全員がそれに巻き込まれてしまう可能性があった。
このような場合に備え、ムスリムの商人や実業家は、共同経営は小規模なままにとどめ、経営期も限定していた。理由ははっきりしている。パートナーが増えれば増えるほど、あるいは提携期間、長ければ長いほど、パートナーの一人が死亡し、共同経営が解散に追い込まれる確率が高くなるかだ。さらに重要なのは、このような制度だったので、共同経営に関する法律を変えようという要求、あまりなかった。ヨーロッパでは事業の取り決めがさらに複雑になり、とりわけ交換可能な株式の入、法人という形態の普及が進む一方で、イスラム世界では法律の改正を求めるインセンティブはぼ皆無だった。事業が意図して小規模なままであれば、会社の拡大に役に立つ株式や法人のようなのは思いつくはずもない。
イスラム教は政治の領域を介して、経済成長にも影響を及ぼしていたようである。そう考える理由のひとつは、イスラム教が支配を正当化することに長けた宗教だからだ。イスラム教の教義には、伝者はイスラム教の教えに準じて行動する統治者にはしたがうべきだが、そうでない統治者にはその要はないというものがある(Rubin,2011,2017)。そのため自身の権力が脅かされている事態に直面した支配者にとって、イスラム教は正統性を授けてくれる魅力的な源泉だった。その見返りとして、宗教の権威者たちは、政治的な意思決定に自身の意見を反映させることができた(Rubin,2017:Kuru,2019)。
これはかならずしも悪いことではないが、弊害をもたらす場合もありえた。たとえば、グーテンベルクの発明からほぼ三世紀が経過していたにもかかわらず、オスマン帝国にはアラビア文字の印刷機がなかった理由もこれで説明がつけられる。印刷機は、イスラム教の知識の伝達と解釈に関する宗教的権威者の独占を脅かすものだった。聖職者は強力な利益団体であり、過去一〇〇〇年でもっとも重要な発明でさえ、社会に持ち込むのを阻むことができた(Cosgel,Miceli,andRubin,2012)。
イスラム社会で宗教的権威が過剰に重んじられていたのは、聖職者が世俗的な教育や科学の知識の習得を犠牲にしてまで、宗教教育を推し進めてきたからだ。フランス財務省の元分析官エリック・シヤネイは、イスラムの宗教体制の強化と十一世紀から十二世紀にかけて確立されたマドラサ(イスラム教を教授する学院)のせいで、イスラム世界では宗教的な書物の制作が主流となり、科学的な書物は作られなくなっていたことを明らかにした(Chaney,2016)。印刷機の制限と同じように、イスラム科学の衰退は宗教エリートが政治的交渉力を拡大させたのが原因だったようである。
政治学者のリサ・ブレイズと経済学者のエリック・シャネイは、イスラム政治の決定的な特徴は支配者が奴隷兵を直接利用することができた点だと説いている(BlaydesandChaney.2013)。つまり、統治者は軍役や資源の使い方をめぐり、支配階級に属するほかの者たちと交渉する必要がなかった。中世や近世のヨーロッパの統治者は奴隷兵を独断で運用できなかったため、みずからの権利を封建領主(中世)や議会(近世)に譲り渡さなければならなかった。イスラム政治の場合、相対的に権力の抑制機能が欠落していたので、二十一世紀になってもいまだに中東政治の特徴である政情不安の原因となっている。
個人主義文化の重要性は、その社会の交易や金融などの制度にとどまるものではなく、個人の業績に報いようとする点にも表れている。集団主義を重んじる社会より、個人主義文化の社会において革新者は高い社会的地位が得られる。さらに、カリフォルニア大学バークレー校の経済学者ユーリゴロドニチェンコとジェラード・ローランドの研究から、個人主義を重んじる社会はそうでない社会に比べ、労働者一人当たりの所得が非常に高く、しかも所得の多くは生産性の向上とイノベーションによることがわかっている(GorodnichenkoandRoland,2011,2017)。これは非常に重要な点で、第7章と第8章で見るように、イノベーションは現代の持続的な経済成長をもたらす鍵のひとつである。
信用という規範の永続性
信用こそ経済交流にとって不可欠な要素だと、経済学者は昔からそう認識してきた。信用が重い意味を持つのは、ほとんどの交換が一度かぎりではなく、一方が相手に何かを与えるとき、その見返りとして何かを返してくれることを期待しているからである。お返しは後日になる場合もある(Greif,2000)。
スターリング大学のサッシャ・ベッカーらは、ハプスブルク家がかつて支配していたオーストリアを調べた。領土をめぐり、ハプスブルク家はオスマン帝国とロシアと戦い、国境はそのたびに移動していたが、調べてみると旧ハプスブルク領に現在も暮らす人たちは、そうでない地域の人びとに比べ、公務員や裁判所、警察に対する信頼度が高かったのだ。十八世紀から十九世紀にかけ、ハプスブルク家は東側の隣国よりも効率的に公共サービスを提供していたので、政府に対する信頼が強化されていたのだ(Becker,Boeckh,Hainz,andWoessmann,2016)。このように現代になっても信用が残っている事実は、この規範はそれを生み出した根拠がなくなっても存続することを強く示唆している。
カリフォルニア大学のサラ・ローズらは、文化規範の持続性を示す証拠を発見している。証拠は現在のコンゴ民主共和国に存在していたクバ王国(一六二五~一八八四年)が成立する以前の古い国境の向こう側に暮らしていた人びとの規範の研究で見つかった(Lowes,Nunn,Robinson,andWeigel,2017)。クバ王国は比較的強力な国家だったので、他者のために行動する向社会的なルールが奨励され、強化されていたのではないかと予想していたが、実態はそうではなく、彼らは規範意識に乏しく、盗みを働く傾向さえ認められた。その理由としてローズらは、クバの支配下で生活していた彼らには、規則に対する規範を生み出す必要性がなかったからだと考えた。
■ジェンダーをめぐる規範
大半の社会は過去において、女性の労働能力を制限する文化規範を持っていた。そのような理由から、女性は歴史的に潜在的な経済成長をもたらすもっとも大きな源泉でありながら、いまだにその能力を十分に生かしきっていないと言えるだろう。ほとんどの社会がなんらかのかたちで女性を制限してきたとはいえ、ほかの社会よりもさらに大きな制限を女性に課してきた社会が存在する。この違いはどうして生じたのだろう?
女性労働に関する文化規範は、定住農業が広まる新石器革命の時代にまでさかのぼることができそうだ。デンマークの経済学者エスター・ボズラップは、鋤による耕作の出現が性差に基づく明らかな労働区分の出現をうながしたと説いた(Boserup,1970)。鋤を扱うには屈強な上半身と強い握力が必要で、いずれも女性より男性に有利だった。その結果、鋤を使った農耕を行う社会では、男性が女性に対して大きな発言力を持つようになり、そのような社会では、男性に有利なジェンダー規範が生み出されたと考えられる。
この仮説を検証したのが、ハーバード大学のアルベルト・アレシナたちだった(Alesina,Giuliano,andNunn,2013)。鋤を使った農耕を行う社会では、男性は野外の畑で働き、女性は屋内にこもるという社会規範が生じたとアレシナたちは説く。また、鋤が使われる農耕文明で発生した性的分業は、自己強化的である点も証明された。穀物がカロリーの大部分を占め、農業を中心に構成されていた社会では、女性が農耕経済で従属的な役割を果たすことによって、社会的な地位に劣る点はますます強化された。アレシナたちが提示した証拠は、大多数の人びとが農業以外の産業に従事している今日でさえ、こうした規範が根強く残っている事実を裏づけている。二十一世紀の現在でも従来どおりの鋤を使った農業を行っている社会では、女性は労働参加率だけではなく、企業所有率や政治への参加率も依然として低いままだ(【図4−7】参照)。
また、アレシナたちの研究によって、アメリカやヨーロッパで暮らす移民の子供たちは、両親が耕作地の伝統を持つ国出身の場合、ジェンダーに関しては、そうでない子供に比べて不平等な挙動を示すことがわかった。同様にラクェル・フェルナンデスとアレッサンドラ・フォッリの二人は、アメリカ移民を親に持つ二世の女性の労働観と出産行動が、両親の出身国のジェンダーに関する文化規範に影響されている事実を明らかにしている(FernándezandFogli,2009)。以上の結果を総合すると、社会規範を最初に生み出した根拠とはかかわりなく、規範にともなう結果は長く残りつづけ、弊害をもたらしていることが示されている。
女性労働に対する文化的態度は、経済的変化によって変わる場合がある。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス助教のメラニー・メン・シュエは、一三〇〇年はじめ、足踏み式糸車が中国に導入されたことで、綿織物に携わる女性の生産性は三倍になったと報告している(Xue,2020)。その結果、綿織物の産地では女性の所得が大幅に上昇した。彼女たちの収益力は何倍にも高まり、男性の収益力に匹敵するか、もしくはうわまわるようになり、女性は社会の一員として重視されるようになった。女性の地位の向上について、ケネス・ポメランツは、「地位向上の経済力」と呼んでいた(Pomeranz,2005)。女性が自身の能力で生産的な経済活動の担い手の一人になると、親にとっても娘を持つことは経済的な負担ではなくなった。娘が自立できる見込みを得て、娘を産むことにともなうコストが低下した。さらにメン・シュエは、このような変化の影響を受けた中国の県級行政区では、女性に対する文化的態度が変容した事実を示す証拠も提示している(Xue,2020)。現在でも、近世以前に綿織物の生産を行っていた県では、女児の出生に対する偏見は、そうでない県に比べて薄い。さらにこうした県では、「男性のほうが能力は高い」「女性は家庭に専念すべき」という意見に反対する人が多く、息子よりも娘を優先する傾向がうかがえる。
女性の地位は過去の経済成長にとって重い意味を持ち、これは今後も変わらずにそうでありつづけるだろう。以上紹介してきた研究は、文化規範こそ女性の地位が経済成長に影響を与える経路であった可能性を示している。ジェンダーと経済成長の関係については、人口動態の傾向と人的資本への投資について触れる第5章でもふたたび取り上げることにする。
第6章|植民地|植民地と搾取の問題
アフリカと南アメリカでは、植民地支配者はそこで産出される資源と奴隷の強制労働から明らかに利益を得ており、その結果、アフリカや南アメリカは植民地化によってますますおくれをとる。イギリスの工業化をめぐり、植民地と奴隷制が果たしていた役割に注目した説もあるが、イギリスは大西洋を横断して奴隷貿易を行った最初の国では決してない。ポルトガルは十六世紀以降、ブラジルの植民地に数百万人の奴隷を送り込んできた。とはいえ、【図6−2】からわかるように、やがてイギリスが貿易を支配し、カリブ海の島々を次々と植民地化していき、それらの島で砂糖やタバコ、綿花などの商品作物の大農園の経営を行うようになった。そのため多くの研究者とくに歴史家のエリック・ウィリアムズやカリブ海史を研究するバーバラ・ソロー、ロチェスター大学のジョセフ・イニコリなどが奴隷制とカリブ海の砂糖プランテーション、そしてその後の工業化のあいだには何か特異な関連性ががあると考えてきた(Williams,1944Solow,1987:Inikori,2002)
[https://gyazo.com/2479b8f4dc3e995161cf6d5fc0a0458d]
ネイサン・ナン(Nunn,2008)は、多くの奴隷が“輸出”-人間について語るにはきわめて不穏当な言葉-されていた国ではGDPはいまも低く、民族の分析分断が低所得と関連していると多くの研究で判明が進み、政治制度も劣悪である事実を明らかにしている。奴隷を多く輸出していた国とそうでもなかった国の格差は、ヨーロッパの植民地支配が崩壊したあともさらに広がっていった。奴隷を多く輸出していた国の一九五〇年から二〇〇〇年にかけてのGDPはほとんど一貫して変わらないが(一日当たり3ドル以下の低水準)、輸出が少なかった国では一人当たりGDPは約4ドルから8ドルへとほぼ倍増しているのだ。この事実から、奴隷貿易がサハラのアフリカの相対的な食器とアフリカ大陸の国別の所得格差の原因である可能性がうかがえる。とはいえ。奴隷貿易が消滅してからすでに一世紀以上が経過しているにもかかわらず、なぜその残誰が、いまも変わらずに影響を与えているのだろう?
理由のひとつは、奴隷貿易で痛めつけられた社会の文化そのものが奴隷貿易によってかたちづくられてきたからである。第4章で説明したように、社会の文化特性を生み出す要因が消えたあとも、文化は執拗に残りつづけるケースがある。奴隷制が文化に与えていたもっとも執拗な影響は奴隷の捕獲方法から生じていた。奴隷のなかには、国が組織した奴隷狩りや戦争で捕らえられた者がいれば、親しい友人や親族に誘拐されたり、だまされたりして奴隷にされた者も少なくない。そのため奴隷貿易の影響を受けた地域では、不信と不安の文化が生まれた。祖先が奴隷貿易で危うい思いにさらされた民族に属する者は、今日でも親族や隣人はもちろん、同じ民族や地方政府に対する信頼度も低いことがネイサン・ナンとプリンストン大学のレオナード・ワンチュコンの研究からわかっている。
この事実はアフリカの経済発展に悪影響を与えてきた。ナンが言っていた奴隷輸出国の状態と長期的な経済への影響との関連性がこれによって説明できるかもしれない。第4章で触れたように信用は交換にとっては欠かせない要素で、初対面の相手ならなおさらだ。サハラ以南のアフリカでは奴隷貿易の結果、人間に対する信頼が希薄になってしまい、その結果、地域社会を発展させていくうえでも障害になっている。
奴隷貿易が残した影響は以上にとどまらない。ミシガン大学のウォーレン・ワットリーとピクトリア大学のロブ・ギルゾーは、奴隷貿易の影響を強く受けた地域では、部族間で激しい分断が現在でも〔続いている〕
ただし、旧植民地がすべてこのような問題の多い制度を引き継いだわけではない。オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、アメリカなどの国は、いずれも国家の収奪能力に制限を設ける制度を採用している。問題は、なぜある植民地は好ましい制度を備え、別の植民地は好ましくない制度を持つにいたったのかだ。
前出のマサチューセッツ工科大学のダロン・アセモグルらの研究は、旧植民地国のあいだに見られる現制度の性質と制度の違いがもたらした経済的成果の大きな差異について、いち早く包括的な解答を提示した研究のひとつだった。アセモグルたちは、植民地における入植者の死亡頻度に応じてタイプの異なる制度が設けられたと主張する(Acemoglu,Johnson,andRobinson,2001)。たとえばアフリカのマラリア・ベルトのように、ヨーロッパ人に適さない気候の土地では入植者の死亡率がきわめて高かった。そして、彼らのインセンティブは、入植地からできるかぎり多くのものを収奪する点にあった。制度の整備にかまけ、原住民を搾取することがおろそかになるようでは、ヨーロッパ式の制度をわざわざ導入する理由など彼らにはなかった。
一方、アメリカやオーストラリアの東海岸など、ヨーロッパと同じような温暖な気候の地域では、ヨーロッパ人がその土地に定住しようとするインセンティブが高まった。多くのヨーロッパ人が移住してきたことで、彼らは入植先の大陸の経済成長に必要不可欠な法律や政治、宗教に関連する制度を持ち込んだ。アセモグルらが行った分析もこうした関係を裏づけている。さらに彼らは、入植者の死亡率が高かった地域は今日でも制度の改善〔設備の国有化や収用、没収などの「収用危険」が図られておらず、ますます貧しくなっている点を明らかにした(【図6−6】参照)。
この事実は彼らが追跡調査で発見した「運命の逆転」(第1章で既述。三九頁の【図1―8】参照)の理由なのかもしれない(Acemoglu,Johnson,andRobinson,2002)。西暦一五〇〇年には世界でもっとも豊かであったはずの地域が、二十世紀末には世界でもっとも貧しい地域のひとつになり果てていた。まさにこうした地域こそ、容易に搾取できる天然資源を持ち、長期的な経済発展など望めない植民地時代の悪しき制度を継承した典型にほかならない。
アメリカの経済史家ケニス・ソコロフとスタンリー・エンガーマンは、この運命の逆転はとりわけ南北アメリカで顕著で、農業への適合性が高い地域――カリブ海諸国と南アメリカのほぼ全域、アメリカ南部では、土地を所有する少数の支配者をもっとも優遇する制度が導入されたと説く(SokoloffandEngerman,2000)。こうした制度は支配者層に莫大な富をもたらしたものの、同時に大きな不平等を引き起こし、そのほとんどは今日もなお変わらずに続いている。一方、アメリカ北部やカナダの耕作限界地は、南部のような換金作物の栽培には不向きだった。入植者は先住民の搾取労働を当てにはせず、人的資本への投資が比較的高いヨーロッパから渡ってきた労働者に依存した。このような地域では地元の企業を優遇する制度が生まれ、そうした制度の多くは現在でも残っている。
イギリス統治領以外のインド亜大陸は、「藩王国」と呼ばれ、各地の藩王によって統治されていたため、政治的にはある程度の自治が維持されてきた。前出のラクシュミー・アイヤーによると、藩王国だった地域に比べ、イギリスの統治下に置かれていた地域では、いまだに学校や医療機関、主要道路へのアクセスで非常な不便を強いられており、農業の生産性や投資の点でも劣っている(Iyer,2010)。このような違いは、宗主国のイギリスとは異なり、藩王たちは税収であまり私腹を肥やさず、公共財に多くの予算を支出していたことが一因だと見られる。もうひとつの理由は、イギリスが植民地時代に悪質な藩王を排除していたことで、藩王たちに対してどちらかと言えば、よい統治者になろうとするインセンティブが働いていたということもある。同様の結果がインド以外の国にも及ぶものであったのかどうかは明らかではないが、こうした説がある一方で、社会学者のマシュー・ランゲは、イギリスの直接統治下にあったインドの旧植民地(イギリスの行政組織によって支配されていた地域)は、(藩王国のような)間接統治を受けていた地域に比べ、政治の安定性や官僚制度の有効性、あるいは法の支配を保持し、政府の腐敗から免れている傾向がうかがえる点を指摘している(Lange,2004)
植民地化のもうひとつの弊害は、誤った政治設計に起因している。宗主国が支配を試みた相手は、自分たちがあまりよく知らない人間の集団である。その結果、破滅的な結果を招く決定がなされていた場合も少なくなかった。アメリカでは、先住民は部族ごとに居留地に置かれていた。だが、先住民が何か政治的な決定をくだすときには、歴史的に大半の先住民は部族以下のレベルで決定していた。
ブラウン大学のステリオス・ミハロプロスとロンドン・ビジネス・スクールのイライアス・パパイオアヌーは、いわゆる「アフリカ分割」に見られる植民地統治をめぐる列強の政治デザインの拙さを裏づける証拠を明らかにした(MichalopoulosandPapaioannou,2016)十九世紀後半、サハラ以南のアフリカの大部分はいかなる植民地支配ともまったく無縁の地上最後の場所だった。ヨーロッパの列強はこれを変えようともくろみ、ベルリンの会議室に集まった(一八八四年から翌年まで開催されたいわゆる「ベルリン会議」)。この会議でアフリカをイギリス、フランス、ドイツ、イタリア、ベルギー、ポルトガル、スペインの六カ国で分割することが確認される。
だが、アフリカを勢力圏に分けた当の責任者たちにはこの大陸に関する知識は皆無で、その結果は悲惨を極めた。彼らはすでにあった民族ごとの現地の境界線などおかまいなしに、自分たちの取り分を最大にすることだけしか考えなかった。そのため、対立する民族が同じ国に編入されてしまう。この状況は各国が独立したあとも続き、植民地時代の国境線がほぼそのまま残っている。ミハロプロスとパパイオアヌーは、アフリカ全土の多くの民族に影響を与えた分割(【図6−8】参照)が政治暴力や政情不安、あるいは民族差別や民族紛争を引き起こしていたことに気づいた。それらは、ある民族がほかの民族を支配する状況のもと、とくに民族間に反目の長い歴史がある状況のもとで起こるべくして起きた事態だった。さらに二人は、民族的に分断された集団は、教育や豊かさを含め、経済的な成果を達成することがますます困難になる事実についても明らかにしている。
そのような地域もまた今日にいたってもまだまだ貧しいままでとどまっている。オランダのヴァーヘニンゲン大学のエーヴァウト・フランケマとハーバード・ビジネス・スクールのマルラス・ファン・ワイエンブルクは、イギリスが支配していたアフリカの植民地で実質賃金が大幅に上昇した事実を報告している(FrankemaandvanWaijenburg,2012)。同時に都市化と社会の構造変化も起きていたという。その結果、一九五〇年の時点で、アフリカの多くの国の所得はアジア各地の所得をうわまわっていた。さらに二人は、「ギニアの首都アクラの一九〇〇年から一九六〇年までの年間成長率は、十九世紀のロンドン(一八四〇~一九〇〇年)の平均成長率に相当する」と報告している(FrankemaandvanWaijenburg,2012,p.912)。同様にヨーロッパの国によって植民地化された島嶼部を調べたダートマス大学のジェイムズ・フェイラーとブルース・サセルドーテは、植民地支配が長ければ長いほど、旧植民地の経済状態は良好に向かっていく傾向があるのを認めている(Feyrerand Sacerdote, 2009)。
これらの傾向はすべての植民地に当てはまるわけではなく、スペインやポルトガルの植民地化は否定的な結果をもたらす傾向が認められる。なぜ、オランダ、イギリス、フランスの植民地事業は、他国に比べて肯定的な結果に結びついているのだろう?もちろん、どの国も善意から植民地化を進めたわけではないが、これらの宗主国は往々にして、鉄道などの近代的な輸送技術や教育制度、最新の医療を植民地にもたらしていた。最近では、旧植民地の現在の経済に植民地支配がどのような影響を与えていたのか、それらの側面から考察を試みる文献も現れるようになった。
さらに多くの観点を踏まえ、本書に共通するテーマのひとつに沿って言うなら、宣教師が派遣されていた地域は現代でも教育水準が高いという点だ。たとえばアフリカでは、印刷機を所有していたプロテスタントの伝道所の周辺は、現在でも社会経済学的に優れた数々の業績が生み出されている(CagéandRueda,2016)。そうした業績には優れた教育制度や市民の信頼性、さかんな政治参加、新聞の購読者数の多さなどが含まれる。
【図6−10】で見るように、南アメリカでは一七六七年にカトリック系のイエズス会の宣教師が追放されたにもかかわらず、伝道所があった周辺地域では、今日でも高い学歴とそれにともなう高所得の住民が多く暮らしていることが明らかにされている(ValenciaCaicedo2018)。この事実については、世界中に派遣された宣教師同様、イエズス会の宣教師も読み書きの教えに重点を置いていたことが関係していると考えられる。メキシコでは、教育によって住民の貧困を和らげようとした托鉢修道士が活動をしていた地域ほど、いまでも識字率や学歴が高いことが確認されている(Waldinger,2017)。
とはいえ、宣教師が高い所得をもたらす教育や公共財の導入を推し進めていたから、植民地化は地元民にとってよいものだったと主張しているわけではない。その点はあらためてはっきりさせておきたい。要は、宣教師が派遣されていた地域は、同じように植民地化されたほかの地域よりも好ましい結果をもたらす傾向があったというだけなのである。そうした地域はまぎれもなくほかの地域よりも発展していた。歴史は豊穣(ほうじょう)であると同時に複雑でもある。植民地主義がもたらした経済的な帰結は均一ではない。悲惨を極めた地域があれば、それほどでもなかった地域、わずかではあるがおそらく好ましい結果をもたらしていた地域もあった。
植民地化が現代の豊かさと富の分配にどのようにかかわってきたかを十分に理解するには、こうしたニュアンスを重んじることが大切だ。最良のケースでは、宣教師は開発と教育において肯定的な役割を果たしていたかもしれない、最悪の場合でも、宣教師は大々的な植民地事業がもたらしていた劣悪な影響の一部を和らげていたかもしれないのだ。
植民地主義は、近代の世界がかたちづくられていくうえで大きな役割を果たしていた。ヨーロッパの一部の国には莫大な富をもたらした一方で、植民地化された国には現在でも影響を残しつづけている。しかし、世界が豊かになったのは、植民地主義のおかげなのだろうか?それをめぐる証拠はさまざまだ。
第Ⅱ部 真っ先に豊かになった国、それに続いた国、そして貧しいままの国──その違いはなぜ生じたのか?
第7章|北西ヨーロッパ|なぜ最初に豊かになれたのか?
一七〇〇年当時、世界の経済はどこの国でも持続的な成長の兆しなど見せてはいなかった。このような経済成長には通常、経済の構造的な変化、つまり農業から工業やサービス業への移行がともなう。さらに、予想をうわまわるレベルで都市化も進展する。長期的には、出生率と死亡率の低下という人日動の変化がそうした移行を後押ししてきた。なにより、技術革新のスピードが大幅に向上することが欠かせない。十八世紀から十九世紀にかけ、北西ヨーロッパではこのような要因がひとつに重なり、最終的に十九世紀半ばに近代的で持続的な経済成長をもたらしていた。問題は「いつ」「どこで」「なぜ」このようなことが起きたのかだ。
その答えは「産業」と思われるかもしれない。正解ではないが、完全にまちがっているわけでもない。たしかにイギリスの産業革命は、経済が近代へと向かう道筋をつけるうえで重要な足がかりとなった。十八世紀後半に始まるイギリスの工業化に続き、十九世紀にはアメリカやヨーロッパのいくつかの国がそれに続いた。ひとたび産業が起こると世界規模での分業が始まり、オーストラリアやデンマークのような国では、生産物を商品として販売する商業的農業のような非工業部門に特化して豊かになることが可能になった。
しかし、産業革命は直接の原因であって、工業化と一貫した技術革新、そしてそれに続く近代の経済がなぜ最初に北西ヨーロッパで起きたのかという問いには答えていない。なぜ、中世のヨーロッパ経済を支配していた南ヨーロッパではなかったのか?なぜ、イスラム教の伝播後、何世紀ものあいだヨーロッパに先行していた中東ではなかったのか?なぜ、中国ではなかったのか?一五〇〇年ごろまで技術力で世界の優位にあったのは中国だったはずだ。さらに言うなら、なぜ技術革新のペースは維持されつづけたのだろう?工業化以前の時代、経済が成長しても、技術革新は徐々に勢いをなくした。
フィレンツェ、ジェノヴァ、ヴエネチアなどの中世の都市国家は、十二世紀から十三世紀に急速な経済成長をとげていた。しかし、黒死病が発生する以前、すでにこれらの都市の経済的なダイナミズムは衰えつつあったことを示す証拠がある。たしかにこれらの都市国家は成長したものの、次の段階には発展せず、成長も後退してしまうことがあった。デビッド・スタサヴェージは、自治の都市国家は、自治が認められていない国家と比べると、独立当初こそ急速に成長したが、その後は鈍化していた事実を明らかにしている(Stasavage2014)成長が持続しなかったのである。その最大の理由は、新興財閥と化した商人たちが、みずからの地位とそれを引き継ぐ後継者の地位と財産を確固たるものにするため、しばしば参入障壁を設けようとしたせいだった。つまり、オープンアクセスが完全に達成された社会秩序に移行していなかったのである。
この点において、中世の都市国家はみずからを破滅に導く種子をすでにはらんでいた。トスカーナ地方の都市国家フィレンツェはその好例だろう。十五世紀、フィレンツェは国際貿易と金融の中心地だったが、製造業の中心地としての盛名は一世紀前にすでにピークに達していた。トスカーナ地方の優位性を維持するため、フィレンツェは市場への参入を操作したり、制限したりしていたが、その代償として地域経済の統合は阻害されていた(Epstein1991,2000)。農民にはいびつな酷税を課していた。さらにフィレンツェの金融業者が提供するサービスは、メディチ家を筆頭とする少数の一族の手にしだいに独古されていく。競争力の高い政治制度を備えていたが、十五世紀になるとその制度もフィレンツェのメディチ家によって破壊される(Belloc,Drago,Fochesato,andGalbiati2021)。
オランダ共和国は経済エリートに好意的な制度を作り上げた。その結果、スペインとの戦争が継続していたにもかかわらず、オランダは一五八〇年から一世紀のあいだ、急速な経済発展をとげた。この成長はオランダ経済の構造的変化の結果だ。つまり、この時期のオランダ経済は発展期にあった。一五六七年、スペイン軍によってアントワープが破壊されたこともあり、アムステルダムはヨーロッパの金融の中心地となる。人口が倍増していたが、実質賃金はヨーロッパのほかの国よりも高い伸びを示し、都市化も急速に進んでいた。運河をはじめ内陸輸送の整備に大規模な投資を行ったことで貿易ブームが到来、オランダの海運はバルト海を支配した。一六〇二年には東インド会社(VOC)が設立され、間もなく東南アジアに帝国を築き上げる。十七世紀から十八世紀にかけて、オランダの実質賃金と一人当たり所得は世界一の水準に達していた(【図7−2】参照)。
オランダ経済の成功は、明らかに制度の変化による結果だった。権力が制限された代表制度の台頭こそ、この国の経済を拡大するうえで決め手となった原動力のひとつだった。リソースを収奪し、市民の財産権を踏みにじり、個人の自由を侵害するような中央集権的な権力者はいなかった。とはいえ、オランダの全州総督が完璧だったとは言えない。この国では特定の利益がほかの利益より優先され実際にそうしていた。信奉する宗教が勝利したからといって、かならずしも宗教の自由が尊重されていたわけでもない。現代のような民主主義国家ではなかった。共和国を構成する七つの州がそれぞれかなりの権力を保持していた。
権力が制限された統治の出現は、長期的な経済成長にとって重要な前提条件にほかならない。だが、それだけでは十分ではなかった。工業化をめぐるレースでは、どちらかと言えばオランダは結局後れをとってしまう。もちろん、それでもなおこの国は当時、世界有数の経済大国だった。著者たちがなぜ、このような代議制を重視するのかと言えば、ひとつには、この制度によってオランダが一世紀以上にわたって世界一の経済大国でありつづけてきたからだ。そして、それはイギリスが台頭する前提条件でもあった。
十八世紀、経済成長の中心はオランダ共和国からイングランド一七〇七年の合同法でイングランド王国とスコットランド王国が合併してからはグレートブリテン王国として知られるようになる―へと移っていった。産業革命が起こる以前から、この国は世界でも屈指の経済大国だった。そしで、その発展には制度の変化がきわめて重要だった。
グレートブリテン王国の国内経済を束縛から解き放つうえで、この国の労働市場の制度変化がひと使買っていた。中世の経済は手工業ギルドや商人ギルドに支配され、市場への参入は規制されていたが、一七〇〇年の時点でイングランドのギルドの支配力は大きく減少していた。当時、ヨーロッパ大の多くの国ではギルドの力が依然として強く残っていたが、イギリスとオランダは違った。
一七〇〇年ごろになると、北西ヨーロッパは持続的な経済成長に必要な前提条件の多くをすでに備えるようになっていた。一人当たりの所得と実質賃金は、産業革命以前の基準としては高い水準に達し、市場はほかの地域に比べればよく発達して、広い範囲に及んでいた。制度的な枠組みも国内交易の拡大に寄与していた。国家機関は国内に安寧秩序をもたらすうえで十分な強度を持っていた。しかし、これらの要因だけでは、近代的な経済成長には十分ではなかったようである。
このことはオランダ共和国の例からも明らかだ。オランダ共和国は「最初の近代経済」と称賛されてきたが(de Vriesandvander Woude, 1997)、貿易に重きを置いたこの国の商業的なスミス型の成長パターンは、一八〇〇年以降の西ヨーロッパと北アメリカの特徴である持続的経済成長というより、それ以前の時代の一時的な経済成長のケースに酷似していた。ジョージ・メイソン大学のジャック・A・ゴールドストーンが書いているように、「黄金時代のオランダは、たしかにイノベーションや農業の集約化、生産性の向上だけでなく、人口の大幅な増加にもかかわらず一人当たり所得の安定化という〝開花期〟を経験していたが、このようなパターンはオランダに特有なものでもなければ、世界的な基準からしても“近代的”なものでもない」(Goldstone,2002,p.340)。
十八世紀、オランダ共和国はたしかに豊かさを維持していたものの、経済はそれ以上の急成長をとげることはなかった(deVriesandvanderWoude,1997)。停滞には多くの原因が関係していた。格差が拡大して、アムステルダムを拠点とする商人エリートは政治権力を確立していた(vanBavel,2016)。オランダ東インド会社のような勅許会社は、どちらかと言えば少数の株主にしか利益をもたらさなかった。このようにオランダ共和国も、貿易を背景に豊かになったあと、最終的には停滞していくフィレンツェやヴェネチアなどのイタリアの都市国家と似たパターンをたどっていったのだ。また、フランスを相手に生存をかけた数々の戦争で、高い税金と多額の債務を抱えたことも理由のひとつだった。さらに、イギリスの重商主義的な政策とイギリスに対するオランダの投資がかなりの失敗を負ったことも、オランダの相対的な衰退につながっていた(O'Brien,2000)。概して言うなら、オランダは生活水準を飛躍的かつ持続的に向上させることはできなかった。この状態は一八〇〇年以降に始まる
「大いなる豊かさ」まで続くもので、それを招来する原動力となったのはイギリスだった。
十七世紀の「科学革命」ではオランダ共和国は最前線にいた。クリスティアーン・ホイヘンスは天文学と数学に大きな貢献を果たし、アントニ・ファン・レーウェンフックは「微生物学の父」となった。工学とくに水理工学の分野で、オランダはめざましい発展をとげた。しかしこの国は、イギリスのような産業の発展と社会構造的な変化がひとつになった状況を経験することはなかった。
イギリスは十八世紀から十九世紀にかけてそのような状況を迎えた。そして、その結果が世界で最初の近代経済であり、経済は持続的に成長を続け、失速することはなかった。なぜ、このようなことがイギリスで最初に起こったのだろうか?本章では、イギリスが重要な制度的前提条件をいくつか備えていた点からその説明を始めた。もっとも重要な点は、イギリスには権力が(比較的)制限された代表制の政府があったことである。とはいえ、それだけで十分に説明したことにならないのは明らかだ。もしそうなら、最初の近代経済はオランダで誕生したはずだ。イギリスが繁栄するためにはほかに何が必要だったのだろう?
イングランドの統治体制で起きた変化は、フランスを相手にした対外的な費用がかかる戦争の一環だった。名誉革命でもたらされた議会と国王の和解は、対仏戦争の戦費を調達するうえでも役に立った。議会が国庫の財布のひもを握ったことで、債権者たちは政府への貸付の返済がとどこおりなく行われると進んで信じるようになった(NorthandWeingast,1989)。ウィリアム三世はオランダ共和国の財政顧問を引き連れてイギリスを統治し、この国にオランダ流の金融と財政の実務知識を伝えていた(Hart,1991)。決定的だったのは一六九四年のイングランド銀行の設立で、戦争を継続するうえで戦費の調達に大いに役立ち、時とともに借入コストは大幅に改善されていった【表7-1】参照)。その結果、十八世紀以降の課題となる国力の大々的な拡大が可能になった。
イングランド(一七〇七年の合同法以降は連合王国としてのグレートブリテン王国)を立憲君主制に変えることで、名誉革命は十八世紀以後のこの国の政党組織と議会政治の基盤を整えることになった(Stasavage,2002,2003;PincusandRobinson,2014;Cox,2016)。もちろん、そうした展開は名誉革命の直後から起きたわけではない。この革命の意義があまさず実現されるにはさらに数十年の年月を要した。しかし、それらはその後のイギリスの経済成長にとって、政治的にも制度的にも大きな意味を持つ安定をもたらすことになった。
第8章|産業革命|なぜオランダではなくイギリスだったのか
消費者革命
工業化に関連する前提条件を明らかにするには、当時とその一世紀ほど前のイギリスの社会と経済について知らなければならない。イングランド内戦(一六四二~五一年)のあと、平穏な時代が続いていた(スコットランドはともかく、イングランドでは)。国内の経済はすでに市場経済になっていたとも言えるだろう。銀貨の発行量はマネタリゼーションと呼ぶには程遠かったが、経済活動は市場交換を中心にしていた。どのような大規模な社会も市場に依存している。かつてのソビエト連邦のような国においても、合法的な市場と闇市場の双方で市場交換は行われていた。とはいえ、最終財の配分について、市場が重要な役割を果たすことを認めている多くの社会でも、土地、資本、労働などの生産要素の配分については非市場的なシステムに依存している。
一七〇〇年の時点で、イギリスでは市場経済が十二分に発展していた。十八世紀のイギリスがほかの国よりも繁栄を享受できたのは、国内市場の拡大と統合が進展したおかげだと断言してもいいだろう。第2章で触れたように、比較的大きな国内市場の統合が実現したのは、十八世紀に大幅に改善された国内の道路と運河に負っていた(Bogart,2014)ロバート・アレンは、「都市は発展し、ロンドンの賃金は高く、農業は改善され、製造業は地方に広がった」と記している(Allen,2009a,p.106)この時期、市場社会のもうひとつの特徴が出現していた。消費者の台頭であり、歴史家はこの時代を「消費者革命」と呼んできた。簡単に言うなら、個人の経済生活が市場を指向するようになったのである(MeKendrick,Brewer,andPlumb,1982:BrewerandPorter,1993)。
消費者革命とは、家庭内生産とその生産物の消費から、市場指向の生産と消費へと移行することを意味する。モノやサービスを消費する方法に一八〇度の転換をもたらした変化だった。中世後期の一般の家庭は、完全な自給自足ではないにせよ、多くの製品を家庭内で生産していた。糸や布を問屋から仕入れて自分で服を仕立て、ビールもおのおので醸造していた。しかし、十七世紀から十八世紀にかけて状況は一変する。小売店が出現して、その場で品々が購入できるようになった。問屋で材料を購入して仕立屋に持ち込んだり、自宅で裁縫して作ったりしていた服が、既製品として購入できるようになったのである(MuiandMui,1989)。
消費者革命の結果、イギリスでは消費の習慣そのものが変化していた。ローナ・ウェザリルはロンドンの孤児裁判所(遺言検認裁判所)の相続目録から、耐久消費財を所有する世帯数が一六七五年から一七二五年の五〇年で著しく増加した事実を明らかにした(Weatherill,1988)。片手鍋、カトラリー、時計、陶磁器、白目製品、陶器などの記載頼度が飛躍的に高まっていた。温かい飲み物を入れる用具は、十七世紀の目録にはほとんど記されていなかったが、一七二五年には80%の目録で確認することができた。
革新的な経済
産業革命では、さまざまな技術革新がイギリス経済の特定の分野で集中的に起きていた。ここではそのひとつ、綿工業に焦点を当てて革新的な技術の集積について説明する。
一台のつむぎ車しか使えなかったため、紡績工の生産性は何世紀ものあいだ制限されてきた。中国では十四世紀に複数の紡錘を使った紡績が試みられていたが、ヨーロッパでは十八世紀半ばまで待たなくてはならなかった。複数の紡錘を用いた最初の成功例は、一七六四年もしくは一七六五年にジェームズ・ハーグリーブスが発明したジェニー紡績機である(図8-3】参照)。この紡績機が発明されるまで紡績は労働集約的な作業だった。通常、女性が自宅で糸を紡いでいた。ヨーロッパでもアジアでも、紡績は家庭という分散システムで行われていた。その多くは農村部で、商人(問屋制前貸人)が糸にする原綿を紡ぎ手に渡し、一週間ほどしてから紡いだ綿糸を回収しに訪れていた。織物作業も労働集約的な作業だったが、男性の仕事とされており、一般に糸を紡ぐより高い対価が支払われていた。
ハーグリーブスは、紡錘の動力源である紡錘車を横に寝かして置き、紡錘は垂直にすることで複数の紡錘を同時に操作する問題を解決した。設計上の問題点を打開するために数年を要したが、完成した多軸式のジェニー紡績機をイングランド北西部で売りはじめるようになった。オックスフォード大学のロバート・アレンが記しているように、ジェニー紡績機によって紡績のコストは半分以下にまで引き下げることができた(Allen,2009a)。また、この紡績機の出現で仕事の進め方も変わった。自宅で作業をしていた個人にはこのような高価な機械は買えないので、大規模な操業ができる製糸業者が採用するほうが理にかなっていた。このようにして、紡績機は資本家である起業家が所有し、紡績工は賃金を得るという工場の出現をうながすようになる。そして、このことは労働時間の延長を可能にし、人間労働が機械労働に取って代わられる前提となった。
ジェニー紡績機は決定的なブレークスルーだったが、その影響にはかぎりがあった。当時の織機には経糸と緯糸が必要だったが、ジェニー紡績機は緯糸しか紡げないうえに、人力を動力としていたからである(Styles,2021)。一七六九年、リチャード・アークライトは水を動力源とする水力紡績機を発明する(【図8-4】参照)。このときの開発で重要だったのは、繊維をならして引き出す紡績機で撚るためのローラーである。アークライトの発明はそれまでの技術革新と設計を基礎としていた。このローラーの使用も当時の冶金で使われていた技術から借用したものだった。いずれにせよ水力紡績機は大きな進歩であり、大規模な綿糸工場を川の近くに作るきっかけとなる。次に発明されたのがサミュエル・クロンプトンのミュール紡績機である(【図8-5】参照)。ミュール紡績機はジェニー紡績機と水力紡績機の長所を組み合わせたもので、その後、蒸気を動力とする織物工場の出現を可能にした。ジェニー紡績機や水力紡績機とは異なり、ミュール紡績機はインドの手紡ぎの撚り糸に匹敵する細くて良質の糸を生産することができた。こうした機械の発明と同時に、ほかの多くの工程も機械化され、改良されていったことで、綿糸の実質価格は劇的に低下していた。一七六〇年代から一八三〇年代にかけて綿糸の生産性は二倍にまで拡大し、そのころになるとイギリスの綿織物はインドの綿織物にまさる競争力を持つようになっていたが、イギリスの名目賃金もまた四~五倍にまで増えていた(Allen.2009a,pp.151-5)°
イギリスの綿織物の生産性は著しく向上した。十八世紀後半、製鉄や時計工業など多くの産業が継続的に生産性を向上させていたが、綿織物の生産性の拡大は数ある産業のなかでも飛び抜けていた(Mokyr,1990,KellyandÓGráda,2016)。それから数十年のうちに、イギリスはさらなる大きな変化を迎えることになる。このような変化が、いつ、どこで、なぜ起きていたのか?これこそが肝心の問題であり、経済史を研究する者のあいだでいまも熱い議論が交わされている。われわれもこの議論に目を向けることにしよう。
高賃金と「誘発されたイノベーション」
ロバート・アレンは、産業革命がいつ、どこで起きたのかは、労働と資本そしてエネルギーの相対的な価格に対応していると説いた(Allen.2009a)。これは、経済学者が誘発されたイノベーション」あるいは「偏向的技術進歩」と呼ぶ議論のひとつだ。具体的に言うなら、イギリスでは労力を節約し賃金の抑制をうながす技術を発展させれば利益は出るが、ほかの地域で省力化を行っても利益が出ない。前述したようにイギリスでは労働者の賃金が大幅に増加していた。だが、資本やエネルギーは比較的安価に調達できた。
アレンは自説を立証するため、基本的な生産関数は同じだが、要素賦存量(土地、労働、資本などの生産要素の理論上の総量)が異なり、したがって要素価格が違ってくる二つの経済を比較した。アレンの主張は二段階からなり、第一段階では、初期の相対的な要素価格の違いによって技術の初期選択は決定される。賃金が相対的に高ければ、生産者は労力を節約できる資本集約的な技術を選ぼうとし、逆に賃金が安価な場合、生産者は労働集約的な生産を選ぼうとする。第二段階では、前者の資本集約的な技術の場合、後者に比べて技術の進歩は速く進む。このような技術の進歩によって、労働コストが低く、資本やエネルギーが相対的に高い場所でも、資本集約的な技術によって利益を生み出すようになる。
アレンのモデルは、綿織物における技術革新のパターンを説明するのにもっとも適しているだろう。ジェニー紡績機は高度な数学や科学の知識は必要としなかった。実現のために多くの細々とした問題を克服しなければならない工学的な挑戦だった。もちろん、そのためにも資本は必要だ。ハーグリーブスは地元で紡績商を営んでいた独立農民のロバート・ピール〔一三四頁で前出したロバート・ピール卿の父〕の支援を受けていた。アークライトの水力紡績機も工学的な問題を解決するものだった。「独創性はローラーを考え出した点にあったのではなく、ローラーを実用化するという実務的な点にあった」(Allen,2009a,pp.2001)
だが、蒸気機関は違った。蒸気機関の発明には、発明に先立つ科学の進歩がどうしても必要だった。とくに重要だったのが大気圧に関する理解で、水が蒸発すると空間は大気圧よりも低い圧力の気体で...
啓蒙主義と経済
ここまで、工業化に先立つ数々の前提条件について述べてきた。工業化前夜のイギリスでは、このような前提条件が明らかにすべて備わっていた。たとえば、熟練工の大量供給、大規模な国内経済、権限が制限された安定した統治、成長を続ける大西洋経済へのアクセスなどである。しかし、これらの説明のどれをとっても、なぜイギリスのイノベーターたちが最新科学の成果を巧みに利用したのかを説明することはできない。そして、この問いを明らかにしなくてはならない最後の謎なのだ。
まさにこの謎に取り組むうえで必要な理論を説いているのがノースウェスタン大学のジョエル・モキイアだ(Mokyr,2009,2016)モキイアが重視するのは、ヨーロッパとりわけイギリスが技術革新を推し進めるうえで果たしていた啓蒙主義を奉じる文化エリートの役割である。具体的に言うなら、イノベーションに報い、それを奨励する文化を生み出すうえで果たしていた「文芸共和国」の役割にモキイアは焦点を当てている(Mokyr,2016)。
文芸共和国とは、啓蒙主義を唱える知識人が当時の最先端の科学的知見や哲学的洞察を発信し、論争していた公共の場で、政治的な国境を越え、ヨーロッパ全体に広がっていた。文芸共和国という場を介して、理念が検証され、啓蒙主義にふさわしい言動や科学的な規範が形成されていった。それ以前の時代や別の社会では、革新をもたらす創意に富む人間はしばしば孤立していた。ルネサンス期の博学者レオナルド・ダ・ヴィンチのように、才能ある者は社会から隔絶して仕事をすることが多かった。彼らは特定の個人の庇護を頼みにしていたが、多くの場合、そうした庇護者は国王であり、彼らの怒りや不興を買うこともあった。だが、個人の才能だけではイノベーションという文化は生み出せない。前近代的な社会でもっぱら行われていた支援制度では、それまでにない革新的なアイデアの追求という気運をもたらすことはできなかった。
文芸共和国は、国境や宗教の違いを越え、知性で結びつくという厳格なルールにしたがっていた。そして、このような公共の場がなければ不可能だった知識人たちのネットワークが生み出され、たとえばフランスの有名な哲学者ヴォルテールは、パリから遠く離れたイギリス、スペイン、イタリア、ポルトガル、ドイツ、ネーデルラントの知識人らと手紙のやりとりをしていた(【図8-8】参照)。既存の正論をくつがえす考えを持つ新しい学者には非常に寛容だったが、エセ学者やうわべだけの知識人には固く門戸を閉ざしていた。文芸共和国の参加者は、個人が血統ではなく、本人の思想に基づく真価によって判断されるヒエラルキーを作り上げることになった。こうした試みが成功したのは、旧弊な考えを淘汰し、時代にふさわしい正しい理念を紹介して普及させたからである。
モキイアによれば、この時代の偉大な哲学者や科学者の存在はたしかに重要だったが、彼らだけの活動が文芸共和国を左右していたわけではないという(Mokyr,2016)。彼らの陰に隠れ、「進歩」という新しいイデオロギーを広めるために重要な役割を果たしていた信奉者たちの姿をモキイアは鮮やかに描き出している。たとえば、サミュエル・ハートリブは、王立学会の設立で中心的な役割を果たしていた。王立学会は一六六○年にイギリスで設立され、現存するものとしては世界最古の科学アカデミーだ。オックスフォード大学のワダム・カレッジの学長ジョン・ウィルキンスも王立学会の創設に関係していた一人だった。このように、あまり有名ではない科学者たちが、アイザック・ニュートンのような当時の有名な思想家とともに、知識のために開かれた場所の構築に貢献していた。この事業は意図的でもなければ、計画的に行われたものでもない。ヨーロッパ中のさまざまな作家や知識人、科学者たちの活動を通じて、思想家と革新者が共有するコミュニティーが築かれ、そのコミュニティーから文芸共和国は産み落とされた。
このような成長をもたらす文化は、社会のほかの進展と切り離して考えることはできない。モキイアも、ヨーロッパ全域を網羅する郵便事業の出現がこのような学術的なコミュニケーションを生み出す鍵だったと説く(Mokyr,2016)。ヨーロッパの郵便事業は、イタリアのデ・タッソ一族が組織したべルガモ飛脚に端を発し、それから一世紀後の十五世紀には神聖ローマ帝国にも拡大した。十七世紀には、ヨーロッパ全土を網羅する郵便網が整備され、各国に住む学者たちのあいだで継続的で確実な文通ができるようになっていた。
政治的な分断も重要な役割を担っていた。モキイアに言わせると、ヨーロッパがユニークであるのは、文化的な統一と政治の分断がひとつに組み合わさっていた点だという。分断そのものは多くの代償をともない、そのうちのいくつかについてはすでに第7章で触れた。一方、このような分断から得られる恩恵は、分断によって国境の向こう側で繁栄している知的文化の成果が得られる点だった。ヨーロッパの政治的分断は、革新的で異端的な思想家が、自国の弾圧的な政治権力から逃れる道を開い
一六〇〇年以降、南ヨーロッパで反宗教改革の勢力が台頭すると、ルネサンスや宗教改革でもたらされた思想や技術革新は弾圧された。だが、こうした道があったのでそれらは弾圧や消滅から逃れることができた。政治的な分断と多中心化していたおかげで、哲学者のデカルトやピエール・ベールは母国フランスから逃れ、ホッブズやロックはイギリスをあとにして亡命することができた。
政治的分断は、文芸共和国の住民たちにとって、潜在的な後援者や保護者が複数いることを意味していた。どの作家も科学者も、一人の有力な君主の寵愛だけを当てにすることはできなかった。さらに言うなら、ヨーロッパは文化的に統一されていることで、イングランドやオランダ共和国の発明家や革新者、鋳掛け職人は、ヨーロッパの全土に広がった科学革命の恩恵にあずかることができた。ヨーロッパ大陸全土に啓蒙主義の文化が広がっていくうえでも、文芸共和国によってヨーロッパの国々が相互につながっていたことが役に立っていた。
ところで、文芸共和国はどのようにして工業化の進展に貢献していたのだろうか?さらに重要なのは、全ヨーロッパに広がる組織が、ほかの国ではなくイギリスの工業化になぜ貢献していたのかという点だ。ここで非常に重要になってくるのがほかの前提条件である。モキイアは、啓蒙思想だけが重要だったわけではなく、その思想を受け継ぎ、実践できるある種の者たちの能力も必要だったと説いている(Mokyr,2009)。それを実行するためには職人や高い技術を持つ手工芸者、鋳掛け職人のような実践的な技能を備えた大勢の人間集団が必要だった。
工業化前夜のイギリスにはこのような人材が豊富だった。徒弟制度によって鍛えられた熟練の職人集団は、科学的探究心というそれまでにない精神にみごとに反応した。イギリス以外の世界の大半の国には、このような高度な技術を持った機械工はいなかったのである。神聖ローマ帝国の独立都市では、労働者だけではなく、成長に必要なそのほかの前提条件の多くが欠落していた。重要な前提条件を満たせなかった国はほかにもある。中世の中東や近代以前のインドでは、政治的分断がイノベーションを阻んでいたようだ。清朝による政治的統一の結果、中国には保守的で、自由な発想を抑制する支配者の文化が生み出されていた。
第9章|工業化|近代経済にいたる道
啓蒙文化の重要な理念を内在化させ、みずからの精神に取り込んでいたのはイギリスの熟練労働者だったとモキイアは言う(Mokyr,2009)。そうした理念のなかでももっとも重要だったのは、人類をよりよくするために世界を変革できるという考えだった。世界は改善できるという精神こそ、技術的な変化をもたらすペースをさらにうながしていく決め手だった(Howes,2017)。この時代の多くのイノベーターたちが、関連する技術基盤やあるいは自分の専門以外の分野に対しても新しい知恵を提供していたのは、こうした精神のたまものだった(Mokyr,2009)。
力織機の発明で知られるエドモンド・カートライトもこの精神を体現していた人物だった。カートライトが改善を試みたのは自動織機だけではなく、「農機具の開発、耐火性建材の考案、医学上の発見、クランク操作の馬なし馬車「ケンタウルスの馬車』の考案、ベッドフォード公爵のモデル農場の管理人として肥料とジャガイモの実験を行っていた」(Howes,2017,pp.3-4)。この点において、カートライトは決してユニークな存在ではなかった。この時代の有名なイノベーターの多くは、幅広い分野に貢献していたのだ。これらの理念は最終的に、モキイアが「産業的啓蒙主義」と呼ぶイギリスを中心に発展する理念へと結実していく(Mokyr,2009)。
ワーウィック大学のニコラス・クラフツが記しているように、アレンとモキイアの産業革命の起源に関する知見には整合性が認められる(Crafts,2011)。アレンが言うように産業革命における技術革新は、労働力を節約することで、高い労働費用に対応しようとしていた可能性がある。同時に、モキイアが考えるような文化的な変革が、発明家や鋳掛け職人、起業家の出現をうながしていくうえで重要だったのかもしれない。著者たちは後者のほうがより必須の条件だと考えるが、いずれにせよ両者の主張は、なぜイギリスが工業化したのかについて大きな光を当てている点で変わらない。
それはともかく、一七八〇年代から一八五〇年代にかけての著しい経済成長にもかかわらず、労働者階級の実質賃金の上昇率は1.5%未満にすぎなかった。産業革命の真っ最中だったにもかかわらず、なぜ実質賃金は伸び悩んでいたのだろう?もちろん、いくつかの説明は試みられてきた。ひとつは、マルサス主義でいう人口圧力が依然として関係していたという説だ。イングランドとウェールズの人口は、一七五〇年の六一〇万人から、一八五一年には一七九〇万人に増加していた。マルサス主義の理屈にしたがえば、このような急激な人口増加によって、実質賃金には厳しい下降圧力がかかるはずである。
第二の要因は戦争だった。産業革命のさなかのイギリスは、フランス革命戦争とそれに続くナポレオン戦争と、フランスを相手に二五年間ほぼ継続的に戦っていた。その間も人口は増えつづけ、前述したようにイギリスは食糧の純輸入国に転じた。戦争と大陸封鎖、混乱によって食糧価格は高騰し、労働者の可処分所得を圧迫していたが、穀価は一連の穀物法が一八四一年に廃止されるまで、地主の利益を保護するために高値のまま維持されていた。ナポレオン戦争の終結後、イギリス政府は金本位制への移行と長年の紛争で疲弊した財政再建に努めたものの、景気後退と危機の時代を迎えていた。第三に、この時期の技術革新はおおむね労力の節約を目的にしていた。もちろん、労働組合がない時代だ。省力化が図られたことで労働者の賃金は低下、産業革命の初期段階では一人当たりGDPは上昇していたものの、そこに占める労働者の割合は低下した。一方、国民所得に占める利潤の割合は大きく増えていた。その結果、所得の不均衡が拡大、増大した所得の大部分は、労働者ではなく、土地や資本の所有者のもとに流れ込んでいった。ロバート・アレンは、一人当たりのGDPは上昇しながら、実質賃金の上昇は停滞するという状態を「エンゲルスの休止」と呼んだ。
「経済学原理』(一八四八年)を書いたジョン・スチュアート・ミルでさえ、機械や機械化によって生活水準が持続的に向上させられるかどうかには懐疑的だった(Berg,1980.pp.332-42)。
その一方で、いわく言いがたい何かが起きていると評価する者もいた。サウジーに対して、トーマス・マコーリーは、一八三〇年代のイギリスの庶民の経済状況について次のような楽観的な見解を描いていた(Macaulay,1830,pp.560-1)。
人口が少なかったころ、この島は野蛮に満ちていた。資本に乏しく、その少ない資本さえ確実ではなかった。いまでは世界でもっとも豊かで、もっとも高度に文明化された国となったが、人口はあまりにも密集している。したがって、われわれは、アメリカの下層階級がいま享受しているような黄金時代は一度も経験しなかった。われわれは自由の時代、秩序の時代、教育の時代を知らず、機械科学がこのうえない高みに達していながら、もっとも肥沃な谷を耕すのに十分な人手にさえ事欠くような時代を知らない。しかし、われらの祖先とわれわれ自身の状態を比べてみば、文明の進歩がもたらした利点は、人口増加で生じる欠点をはるかに凌駕しているのは明らかた。人口は一〇倍に増えたが、われわれの富は一〇〇倍に拡大していた。
マコーリーの評価はたしかに楽観的だ。しかし、持続的な経済成長という結果を正しく見通していたのはマルサスやスミス、マルクスではなくマコーリーだった。
[訳註] トーマス・マコーリー:一八〇〇~五九年。 イギリスの歴史家、政治家。名誉革命を中心主題とした 「イギリス史」の著者として知られる。
一九三〇年、現在のイギリス人よりも衣食住に恵まれた五〇〇〇万人の人間でブリテン諸島が あふれ(略)、まだ発見されていない原理で作られた機械があらゆる家庭に置かれ、あらゆる路線 に鉄道が敷設され、移動手段はことごとく蒸気を動力にしている。いまの私たちには手に負えな いと思える巨額の負債も、私たちの曾孫の目にはわずかな負担としか映らず、一、二年足らずで 苦もなく完済できるこんな予言をすれば、ほとんどの人はそんな人間は狂人だと思うだろう。 だから予言は差し控えておくが、これだけははっきり言えそうだ。一七二〇年の大暴落 〔南海泡 沫事件〕 のあと、困惑と恐怖のなかで開かれた議会で、ある人間がこんな予言をしていたらどう だろう。一八三〇年、イギリスの富は途轍もない想像をはるかに超える規模にまで増えているこ と、年間の歳入は耐えがたい重荷と考えられていた大暴落の負債の元本に匹敵していること、一 万ポンドを所有する男性一人に対し、その時代には五万ポンドの財産を持つ男性が五人いること、 ロンドンは二倍に広がり、二倍の人口を抱えていること、それにもかかわらず死亡率は当時の半 分にまで減少していること(略)、 こんな予言をしたとしても、私たちの祖先は「ガリバー旅行記」ほどにしか信じてくれはしないだろう。だが、この予言は誤っていただろうか (Macaulay,1830, pp.563-4)。
工業化をめぐり、経済史家たちは十九世紀前半から悲観主義者と楽観主義者のどちらが真理を突いていたか議論してきた。長い目で見た場合、楽観主義者が正しかったことは明らかである。マコーリ1の予測には、驚くほど先見の明があった。
当初、不平等と実質賃金の停滞の原因となっていた同じ力が、一八四〇年以降、すべての人の生活水準を持続的に上昇させる経済を生み出していた。この変化はなぜ起こり、どうやって多くの人びとの生活水準を向上させることになったのか?そして、それがどのようにしてイギリス以外の国々に波及していったのか? 次にこうした問題について考えてみたい
第二次産業革命
今日、世界を変えるテクノロジーというと、科学的な知識に基づいた、いわゆるハイテク技術をつい思い浮かべる人は多い。たとえば、ロボット工学、コンピューター、半導体、ロケット工学、航空学、宇宙飛行、核技術などである。しかし、つねにそうだったわけではなかった。第8章で述べたように、第一次産業革命(一七五〇~一八三〇年)の主要技術の多くは、科学に基づいたものではなかった。たとえば、綿工業で飛躍的な進歩をもたらした発明のほとんどは、産業革命前から知られていた生産方法を機械化したものだった。
これに対して、一八七〇年代以降の主要な技術的進歩の大半は、科学に関する人類全体の知識を基盤にして築かれてきた(Mokyr,1990,2002)。ダグラス・ノースは、技術変化のペースに見られる劇的な転換を「科学とテクノロジーの結婚」と呼んだ(North,1981)。そして、それは第二次産業革命と呼ばれることが多い。
[https://gyazo.com/6cb211ffe3338a33e4f837cbb8ac07cb]
一般に第二次産業革命は一八七〇年から一九一四年まで続いたとされ、第一次産業革命とは科学とのかかわり方の点で異なっている。この違いは技術革新のペースを加速させるという点で大きな意味があり、医学、化学、エネルギーに関する新たな発明が、さらなる発明やその改良へといたる道を開いた。それまで以上の科学的な発見も可能になっていた。このころから科学から技術へのフィードバックが可能になり、それは今日においても支配的なパラダイムであるのは変わらない(Mokyr,1998)°
この時代、世界を変えるような技術がいくつも生まれた。【表9-1】はそれらをまとめたもので、こうした技術から顕著にうかがえる特徴は、ジョエル・モキイアが「有用な知識」と呼...
...な教育を受けた労働者が多い社会ほど、新しい技術を生産的に利用することができる。
それだけに、教育水準が高い国ほど工業化の第二波がもたらした新たな経済的機会を生かすことができた。その格好の例がプロイセンだった。他国と比べると、プロイセンは遅れて工業化したものの、十九世紀にそれを達成すると、多方面で世界のリーダー国に追いつき、やがて追い越していった。それができたのは、教育面においてこの国が当初から先行していたことが大きな理由だった(Becker.HornungandWoessmann,2011)。十九世紀初頭、ナポレオン戦争に敗れたプロイセンは、その後、教育を重視した一連の改革を行った。そしてこのときの改革は、のちにプロイセンがイギリスなどの国から取り入れた技術を改良する基盤を整えるという、予期せぬ結果をもたらすことになる。プロイセン国内では、十九世紀初頭に高い教育制度を整えていた地域が、この国の産業をリードすることになった。結局、第二次産業革命は一八七一年に統一を果たしたドイツ帝国が担い手となる。
教育こそ第二次産業革命を成功に導いた直接の要因にほかならなかった。高度な教育を受けた労働者がいる地域ほど、新技術を採用して導入する傾向があり、最終的には自分たちで技術を生み出していった。だが、教育水準が低い地域、とくに新しいタイプの資本を補完する「有用な」教育が行われていなかった地域では、新しい世界に適応していく準備が整っていなかった。とはいえ、それもまた物語の一部にすぎない。そもそも、世界のある地域はどうして教育に投資したのだろう?この問いに対する答えは山ほどあり、それらはいずれも第I部で述べてきた特徴に関連している。
?マルサス主義の観点からすれば、これは〈出生率所得〉の関係が逆転したことを意味している(第5章参照)。そして十九世紀半ば以降、所得が増大しても出産する子供の数は増えなくなっていった。
人口転換は経済成長の結果にさまざまな影響を与えていた。もっとも直接的な影響は、マルサスが聞いていた人口圧力が緩和された点だ。しかし、この事実は、それにともなって起きていた人的資本への投資の拡大はどおそらく重大ではないだろう。
人口転換と人的資本への投資の拡大は関連していた。第5章で紹介したブラウン大学のオデッド・ガローらの「統一成長理論」によれば、後者つまり人的投資の拡大が人口転換を引き起こしていた。技術的な進歩によって人的資本への投資に対するリターンが増加したからだ。これが誘因になって、親たちは子供に対する人的資本を高めていった(Galor,2011)。これ以降、親の投資先は子供の量ではなく、子供の心(つまり教育)に投資するようになっていく。【図9-4】からうかがえるように、イギリスで十九世紀半ばごろに、人的資本の転換が始まっていた。
現代の経済成長を研究するうえで経済学者が用いている標準モデルが「ソローモデル」だ。ノーベル賞受賞者ロバート・ソローが一九五六年に発表した成長理論にちなんで名づけられた。ソローモデルでは、長期的な経済成長の最終的な原動力はイノベーションとされている。このモデル理論自体は、持続的な経済成長の起源にはほとんど言及していないが、経済成長の拡散を理解するうえで重要な洞察を授けてくれる(Solow,1956)。
ソローモデルによると、先進国のイノベーションが後発国でも利用できるかぎり、貧しい国の経済は豊かな国よりも速く成長していく。「キャッチアップ型成長」、あるいは「収束」と呼ばれている現象だ。難しい理屈ではない。経済や技術の最前線からはるかに遅れていた国では、それだけ資本の限界生産性が高くなる。このような国は、すでに資本が豊富な国よりも高いレベルの投資を呼び込み、経済はますます急速に成長していく。
キャッチアップ型成長を踏まえると、十九世紀後半以降、なぜ西ヨーロッパの多くの国で加速度的な経済成長が始まったのかを説明するうえで役に立つ。キャッチアップをとげた国は、第一次と第二次産業革命で生まれた技術を輸入していたからだ。その好例こそドイツであり、一八四〇年代以降、ドイツの経済成長は異例の速さで進み、第二次産業革命では数多くの分野で技術革新の担い手となっていた。
キャッチアップ型成長の別バージョンについて説いたのが、すでに古典的な労作となったアメリカの経済史家アレクサンダー・ガーシェンクロンの『発工業国の経済史 キャッチアップ型工業化黄」である(Gerschenkron,1962)。ガーシェンクロンは、工業化へのスタート地点が遅れていればいるほど、つまり後進度が高いレベルから工業化に着手した国には、ある種の経済的な優位性があると主張した。その優位性のおかげで、ドイツやドイツに続いた日本やロシアのような国は、特定の経済分野で技術的な最前線に想像以上に速く到達できたのだ。これらの国は、とくに資本集約的な産業分野において、中間段階を経ることなく一気に成長をとげていた。さらに後発工業国の場合、民間の資本市場に依存するのではなく、投資銀行や国家の出資を通じて資本を動員する場合が多かった。
ここまでの各章で検討してきた大半の要因によっても、なぜ経済成長の格差を収束できた国があるのか、またそうでない国があるのかを説明できる。制度について考えてみよう。独裁的な政治権力に対するチェックがほとんど機能しない国では、新技術の導入は起こらないかもしれない(Scheidel,2019,ch.12)。次章で見るように、国外に目を向けようとしなかった徳川時代の日本や明朝や清朝の中国は、その内向性のために西洋技術の採用を何世紀も遅らせることになった。オスマン帝国は西洋に二五〇年遅れて印刷機を導入した(Cosgel,Miceli,andRubin,2012)。技術のメリットはあまねく行き渡っていくものだが、支配階級の思惑しだいという潜在的なデメリットをともなっていた。権力が制約されていない支配者であれば、技術が社会に普及していくのを阻むことができるのだ。だが、権力が制約されていれば、そうしたことも容易ではない。
同様に十九世紀後半から二十世紀初頭にかけて、世界のほかの地域で起きていた”収束”と”分岐〟の双方にも制度は決定的な影響を与えていた。世界経済の主導国へと収束していった国々、とくに西ヨーロッパと北アメリカでは、政治制度の質は劇的な向上を果たしていた。
この時代に広まったのは製造技術だけではなく、それまでにない輸送技術と通信技術も普及していた。第2章でも述べたように、このような技術への投資は“悪質な地理〟の問題を克服するのに有効だ。単位貨物量当たりの国際運賃も下がっていった。運賃が安くなり、輸送技術が向上したことで、ありあまる土地に恵まれた北アメリカから、ヨーロッパへの穀物輸出が可能になった(O'RourkeandWilliamson,1999)。こうした穀物輸入は、ヨーロッパの都市で働く労働者に大きな恩恵を授け、彼らの実質賃金も上昇した。スエズ運河のような交通施設への投資も決定的だった。需要だけでなく、供給量も足並みをそろえて拡大していった。ただし、海運の料金は50%以上も低下していたが、それだけで貿易がこれほどの規模で拡大をとげたのかは説明できない(Jacks,Meissner,andNovy,2011)。このような輸送手段に関する投資は、貿易財に対する需要増と世界各国の制度の改善によって推し進められていたからだ。
この時代、もっとも重要な交通手段の改善が汽船の出現だった。汽船の発明以前、貿易にかかる費用は、帆船が目的地に向かう航路がどれほどアクセスしやすいかで決まっていたが、汽船の出現以降、そのようなことはもはや問題ではなくなる。新しい技術によって貿易ブームにいっそう拍車がかかったが、貿易の拡大と世界経済の統合による恩恵を得られるかは、やはりその国の制度しだいだった。
近代的な経済成長に向けて、あらゆる国が同じ道を歩んでいたわけではない。工業化することによってのみ、国が豊かになれると考えるのは誤っている。たしかにイギリス、アメリカ、ドイツは工業化によって豊かになったが、工業化とは別の道を歩んで豊かになった国もある。そうした国のなかでもとくに抜きん出ていたのが、デンマーク、オランダ、オーストラリア、ニュージーランドだった。これらの国は、たいていの場合、輸出市場向けの市販食品の生産あるいは加工に特化することができたからだが、そのためには国際市場と経済がある程度グローバル化されていなければならなかった。たとえば、デンマークではバター産業が発展した。生産には科学的なアイデアも取り込まれていた産業として工業製品の生産ではなく食品製造だった。デンマークの成功には、制度と文化の両面においてある発展が前提となっていた。ウィーン経済大学のマーカス・ランプと南デンマーク大学のポール・シャープが記しているように、教育を受けたエリートが新しい科学技術の導入と出資において重要な役割を果たしていた(LampeandSharp,2018)。これらの技術は小規模農家や発展しつつあった酪農の協同組合に採用されていった。しかし、こうした技術革新の他国への移転は容易ではなかった。アイルランドのような国では、政治的な対立のせいで、協同組合という形態と新技術の普及が制限されてしまった(O'Rourke,2007a,2007b)。
第一次グローバリゼーションは、オーストラリアの経済発展にとっても中心的な役割を果たしていた。当初、流刑地として開発されたオーストラリアは、一八四〇年代から五〇年代にかけて金が発見されると、急速な移民の増加と実質賃金の上昇を経験していた。ほかの小規模経済圏同様、オーストラリアの繁栄も世界貿易と安定した国際情勢しだいだった(McLean,2013)。この国で最初に主要輸出品になったのは、東南部に位置するニューサウスウェールズ州で産出されるメリノ種の羊からとれる最高品質のウールで、イギリスの繊維産業に向けて重要な輸出品になった。それだけにオーストラリアの経済は、ゴールドラッシュ後の一八九〇年の不況や第一次世界大戦中に起きた国際経済の悪化などには脆弱だった。とはいえ、全体としてはオーストラリアの経済は繁栄を謳歌した。デンマーク同様、この国が豊かになるうえで、十九世紀後半の第一次グローバリゼーションの波が決定的な役割を果たしていた。
第一次グローバリゼーションの時代、持続的な経済成長が多くの国に広がったが、その一方で経済的な分岐はますます拡大していた。西ヨーロッパや北アメリカでは経済成長をとげていたものの、中国やインド、中東では一人当たりの所得が停滞していた。それには多くの理由があった。第6章で述べたように、植民地という制度もその理由のひとつであり、第5章で論じたように急激な人口増加も所得の増加を阻んだ一因だった。さらに言うなら、世界貿易の拡大でさまざまな地域が結びつけられると、貧しい国は一次産品の輸出に特化するようになる。たしかにこれは経済成長の源泉となりえるもので、二十世紀初頭の西アフリカの経済発展には換金作物の輸出が重要な役割を果たしていた。しかし、換金作物の輸出にはマイナス面がともなうのだ。とくに問題となるのは、大きな価格変動が生じやすい点である(Williamson,2006)。そのため、このような作物の輸出に依存していた国では経済が破綻してしまうことになった。
[https://gyazo.com/c20e800722ca8c1896fe07de4e6a5f12]
まったく残忍な生産システムであったにもかかわらず、南部社会の中心的な役割を担っていた。とはいえ、綿花の輸出はアメリカ経済の6%にも満たなかった事実は知っておく必要があるだろう。数字自体は決して小さくはないが、アメリカ経済が成長するうえで、奴隷制と綿花がきわめて重要だったとあまりにも誇張された説が唱えられてきたからである。
それどころか、奴隷制が存在していたため、アメリカ南部の工業化と都市化はむしろ遅れてしまうことになった。南部のエリートは主に奴隷というかたちで富を保有していた。奴隷への投資は利益を生み出していたが、その結果、綿花以外の産業を生み出すうえで必要なリソースを奪われていた(RansomandSutch,1988)。そのため地域の市場規模が制限され、工業生産に対する魅力がますます薄れてしまった。
移民の増加はアメリカの経済成長と工業化にさまざまな影響を与えていた。第一に、国内市場の成長に移民は貢献していた。すでに一八五〇年代の時点で、国外の専門家たちも、アメリカの製造業の国内市場は大きいうえに深みがあると評している。第二に、移民はアメリカが製造業の世界的拠点になるために必要な大規模な労働力を提供していた。第三に、移民は人的資本ももたらしていた。この事実はアメリカの発明に大きく寄与した。アメリカの発明家の多くは移民の一世や二世だったのである。実際、この時期に移民が多く流れ込んだ地域では、製造業を営む会社の数ばかりか規模も大きく拡大し、農業の生産性も向上して、技術革新が起こる確率も高かった(Sequeira,Nunn,andQian,2020)。このような歴史的に移民が多かった地域は、今日にいたるまで所得水準が著しく高いばかりか、貧困層の割合や失業率が低いうえに、都市化が進んで教育水準も高い。
ソ連がたとった回り道
工業化にいたるもうひとつの道はロシアによって切り開かれてきた。しかし、その道は指揮統制のもとで開かれ、市場経済に基づいてはいなかった。なぜ、このような道が選ばれたのだろうか?そして、最終的にソ連の工業化はなぜ失敗に終わってしまったのだろう?
ソ連以前の帝政ロシアの経済をめぐるこれまでの見解は、近年の実証研究によってくつがえされてきた。十九世紀半ばの帝政時代、ロシアでは閉鎖的で後進的な農耕経済が営まれていた。しかし、十九世紀末に行われた一連の近代化改革を経て、ロシアは明治の日本とともに後発工業化国の仲間入りを果たし、二十世紀初頭には、世界でもっとも急速に経済が発展した国のひとつになっていた(Gregory,1994)。
そのような急速な成長をとげていたにもかかわらず、依然として農業が支配的な国である事実に変わりはなかった。一九一三年の時点で、ロシア経済の約60%は農業によって占められていた(Gregory,2004b,p.185)。一八六一年に「農奴解放令」が発布され、農奴制が正式に廃止されたあとも、十九世紀の大半を通じ、非効率的な農奴制農業がロシア経済の生産性にとって大きな足かせになっていた(MarkevichandZhuravskaya2018)。しかし、農業改革とくに皇帝ニコライ二世のもとで首相を務めていたピョートル・ストルイピンが進めた一九〇六年と一九一一年の「ストルイピン改革」によって、自営農家が生み出されるようになる。これらの改革は農業生産性の足かせを解き放つ可能性を秘めていた(CastañedaDowerandMarkevich,2018)。しかし、二十世紀初頭の急速の高度成長期も、第一次世界大戦(一九一四~一八年)、ロシア革命(一九一七年)、ロシア内戦(一九一七~二二年)の勃発を経て、ロシア経済の崩壊とともに終焉を迎える。
こうした騒乱のさなか、ウラジーミル・レーニンはソビエト政権を防衛するため、「戦時共産主義」と呼ばれる政策を断行、この政策によって市場経済や私有財産は事実上廃止され、飢饉と貧困がもたらされる。共産主義時代のロシアについて詳しく説明する余裕はないが、以下に述べるような骨子は、現代の経済成長を語るうえで見落としてはならないだろう。一九二〇年代初頭の壊滅的などん底から、「ネップ」と呼ばれるレーニンの新経済政策のもとで、ソ連経済は回復に向かい、市場原理を一部復活させ、穀物の強制徴発を廃止したことで市場活動の復活を可能なまでにしていた。
マルクス主義の理論では、世界で最初の社会主義革命は重工業化した経済の国で起きると考えられていた。しかし、ロシア経済は第一次世界大戦前に急成長していたとはいえ、工業化されてはいなかった。ネップでゆるんだ体制の強化を図っていたレーニンのあとをついだスターリンの「成果」は、農業の集団化と一連の五カ年計画を通じて、工業化のプロセスを一気に加速させたことだった。しかし、その代償はきわめて大きく、大勢の犠牲者が生み出されていた。集団化によって農業の収量は激減し、強制徴発によって大規模な飢饉が発生していた。五五〇万から一〇八〇万人にも及ぶ人間が餓死し、その大半はウクライナの住民だった(Markevich,Naumenko,andQian,2021:Naumenko2021)
ソビエトの工業化の急速なペースは、ほかの発展途上国に工業化へといたる別の道を提供していた。とりわけ、第二次世界大戦直後にそれは顕著だった。ソ連という国家は、数多くの基本的な公共財、とりわけ優れた技術教育や必要不可欠な医療を国民に提供することに成功した国であり、また天然痘をはじめとする病気については、アメリカよりも早く撲滅していた(Troesken.2015)。
しかし、このような加速的な工業化のペースは維持されることはなかった。急成長が始まった初期の段階においてさえ、ソ連経済の非効率性と浪費は伝説の域に達していた(GregoryandHarrison,2005)。だが、そうした問題の多くは当初、ソ連経済が動員できる膨大な労働力(その多くは奴隷労働のようなものだった)、生産に必要な設備などの物的資本、豊富な天然資源などによって隠蔽されていた。しかし、最終的に経済をめぐるあらゆる決定が独裁者一人の手に一元化されたことで混沌が生み出されていく。
スターリンは一見するとあまりにもささいな決定地下鉄の料金設定や些末な管理職の任命などに時間を費やしていた(Gregory,2004a,pp.112-14)。しかも、この国では汚職とレントシーキングが蔓延していた(AndersonandBoettke,1997Boettke,2001)。スターリンの死後、改革が行われ、一九五〇年代から六〇年代にかけてソ連経済は一応の発展は見たものの、国民が購入したいと思うような基本的な消費財を供給することにも四苦八苦するようになっていた。
煎じ詰めれば、経済成長とは経済的な価値を生み出すことにつきるが、ソ連経済はその点において失敗した。この国の支配階級は、西側の製品が手に入る特別な店に出入りできたが、一般国民は立ち入ることが許されなかった。ソ連経済はますます石油や天然ガスの輸出に依存するようになっていく。そして、一九八〇年代に原油価格が暴落すると、ソ連経済に向けられた改革圧力はもはや抑えることが不可能になっていた。ミハイル・ゴルバチョフが改革に着手したものの、この改革を契機に間もなソ連経済と共産主義体制そのものが崩壊に向かっていった(Boettke,1993)。
ソ連の工業化の物語には二つの教訓が含まれている。第一の教訓は、共産主義は長期的な経済成長と相容れないという事実であり、経済に関する当初の設計図をソ連は実行することができなかった。現実のソ連経済は非合法のブラックマーケットに依存し、利潤動機を抑制することもできず、それどころか時間が経つにつれ、それらはますます強化されていった。第二の教訓は、独裁的な政府は長期的には成長の息の根を止める可能性があるという点だ。もちろん、独裁政治のもとでは経済成長はありえないというわけではない。近年の中国の経済成長については次章で論じている。また、権限が制限されている統治のもとなら、かならず近代的で持続的な経済成長がうながされるというわけでもない。
第10章|後発国|キャッチアップ型成長の前提条件
〔インドは〕一九四七年に独立を果たしたが、その結果、経済成長の機会はむしろ制限されてしまう。当時、独立したほかの発展途上国と同じように、インドの経済政策もソ連経済を手本にしており、計画経済は支持を得ていた。インドの初代首相ジャワハルラール・ネルー(在任一九四七~六四年)などのインドの政治家たちは、国家主導による国内工業の自立を目ざした。カリフォルニア大学のディーパック・ラルのような、こうした政策方針に批判的な研究者は、計画経済という技術官僚たちの主張は、カースト制度に根ざした商業に対する深い不信と結びついていると指摘していた(Lal,2005,pp.263-4)。
だが、このような政策は、たとえば駐インド大使として赴任したハーバード大学のジョン・ケネスガルブレイスやイギリスの経済学者ジョーン・ロビンソンなどの経済顧問によって声高に支持され、手厚い開発援助に支えられていた。ジョージ・メイソン大学のローレンス・ホワイトによると、ガルブレイスは、「後進国が計画経済を必要としている点に疑いの余地はない。(略)長足の進歩が必要とされても、市場経済ではそれを可能にする躍進をもたらすことはできない」と忠告していたとい
そして、これらの政策はきわめて残念な結果に終わる。一部ではキャッチアップ型の成長も見られたが、全体的にはさらにおくれをもたらしていた。一九五〇年から一九八〇年の三〇年間のインドの一人当たりGDPの成長率は年平均1.2%で、東アジアの主要経済国には遠く及ばなかった。後述するように、東アジアの国々は国際貿易に対してインド以上に開放的で、インドほど保護主義ではなかったことが大きかった。民営よりも公営が重んじられる「許認可支配」は、レントシーキングと汚職がはびこる温床になっていた。一九八〇年代になると、輸入品から国産品への代替を推進することで工業化への転換を図る輸入代替工業化政策と中央計画経済がもたらしてきた結果が、誰の目にも明らかになる。そうした結果を受け、インド政府は一九九〇年代に経済の規制緩和を開始、方針転換を図ることによって、経済はようやく転機を迎えることができた。
当時の日本の一人当たりGDPや実質賃金を調査した最新の推計によると、十九世紀の平均的な日本人は、同時代のヨーロッパや北アメリカの国民よりもかなり貧しかったことが明らかにされている(【10-3】)。しかし、同じく最近の研究から、徳川時代の日本は多くの点において、前工業化経済を達成していたことがわかっている。
徳川時代の経済発展には顕著な点がいくつかうかがえる。第一に、都市化の水準が比較的高かった点だ。一八〇〇年、日本では人口の1%が一万人以上の町に住んでいたのに対して、同時期の中国は3~4%程度だった(Vries,2020,p.68)。第二に、徳川時代を通じて、日本は市場と国内交易の拡大に基づくスミス型成長を経験していた点である(Sugihara,2004)農民は市場とのかかわりを高め、結びつきをさらに深めていった。また、この国のかぎられた耕地という圧力は、農業における労働投入量の増加につながり、二期作や二毛作が行われるようになっていった(Saito,2005)。さらに農民は、市場向けの手工業生産に従事することも多かった。このような原初的な工業化の過程は、近世ヨーロッパの一部の地域で起きていた動きととてもよく似ている。
第7章において、ヨーロッパの持続的な経済成長の前提条件として、生産要素市場が機能していた可能性が高いことについて確認した。そうした市場は、徳川時代の日本にも存在していた。正式な財産権は認められていなかったものの、農民は土地に対する事実上の権利を持っていたのだ。理屈のうえでは、土地の永続的な売買は禁止されていたものの、実際には、土地市場が存在しており、農民が一定期間、財産を譲渡できる抵当契約を通じて機能していた(Saito,2009)。
しかし、相対的な生産要素価格の違いは、北西ヨーロッパの違いとはまったく異なっていた。実質賃金が高かった北西ヨーロッパに比べると、日本の実質賃金は、ヨーロッパの水準から見ればはるかに低かった。その結果、日本の工業化への道は、ジェニー紡績機を生み出したような労働節約型の技術を開発していくには有利な環境ではなかった。むしろ、ロバート・アレンが唱える説(第8章の二九六頁参照)にしたがえば、かぎられた土地やエネルギー、資本を節約するために労働集約的な技術改良をうながすインセンティブはほとんど働かなかった。幸いだったのは、日本は技術的な開発を一から生み出す必要がなかった点である。第9章ですでに触れたように、先進国の技術を取り入れれば、キャッチアップ型の成長はただちに実現できた。もっとも、そのためには、ある種の制度的・文化的な前提条件が必要である。徳川時代の日本には、そのような条件が整っていたのだろうか。
そうした前提条件のひとつが人的資本だ。人的資本への投資は、制度(資金が必要なため)と文化(教育がよいものと評価されているもとでは人的資本への投資が進む)の双方の影響を受けている。徳川時代の日本では、制度も文化も障害にはならなかった。明治維新以前の段階でさえ、日本の人的資本のレベルは工業化以前の社会としては高かった。識字率や計算能力も西ヨーロッパの水準に匹敵していたようだ。日本史を研究するジョージ・メイソン大学のブライアン・プラットは、徳川時代には「庶民向けの何万もの教育施設、二七六の藩校、約一五〇〇の私塾が設立されていた」と記している(Platt,2004,p.4)。これらの存在が第二次産業革命の技術の導入を促進することになった。
工業化が始まる以前の段階で、日本の人的資本の水準が高かったのはなぜだろう?明治維新前の日本は、国家としてはきわめて分権化されていたが、一方、各地方のレベルで見た場合、公共財の供給はどちらかと言えば効果的に行われていた。清朝中国と比べると、徳川幕府の統治下のほうが人口一人当たりの税収額は多く、この差は時間とともに拡大していった(SngandMoriguchi,2014)。徳川時代の日本では、地方領主が道路インフラや水利事業などの地方公共財に投資していたので、耕地を新たに開墾することが可能になっていた(Kanzaka,2019)。
総体的に見た場合、徳川幕府が残した遺産のひとつとして、比較的高い税制と地方政府の経済生活への関与があげられるだろう。これらの制度的・文化的な要因は、一八六八年に徳川幕府に取って代った新政府連合が、国家建設を成功裡に達成するうえでどちらかと言えば有利な立場にあったことを意味している。しかし、新たな国家建設を実現させるには、文字どおり国家レベルの政治革命が必要だった(Koyama,Moriguchi,andSng,2018)。
明治維新に続いて始まった改革は激しさを極めたが、日本という国家はわずか数十年でふたたび鍛え上げられて生まれ変わった。日本のこうした変貌は、国家の近代化としてもっとも驚異的な例のひとつである。明治政府は義務教育を制度として確立し、大幅な増税を行った。新政府の改革に反発して各地で一揆や暴動が起きたものの、それらは力ずくで鎮圧された。さらに新政府は武士階級を廃止したが、それまでの法的特権のかわりに公債を授けることで、大部分はこれという抵抗もないまま廃止できた。
経済史家のピア・ヴリーズは、明治政府の日本は「資本主義国家」だったと言っている(Vries,2020)ヴリーズがそう言うのは、日本ではギルド的な同業者組合や地方の独占が廃止され、その結果、単一で統一された労働市場が生み出されていたからだ。さらにこの国は、財政政策と規制政策の両面から企業を優遇する国家で、そうした政策のなかには「財閥」として知られる巨大コングロマリットの形成を支援することも含まれていた。
財界を優遇していたが、しかし、明治政府は保護貿易政策を採用していない。それどころか、産業を保護しようと願っても、この国にはそれができなかった。明治の日本は、徳川時代の末期に締結された諸外国との条約によって、海外から輸入品に高い関税をかけることができなかったのである(平均的な関税率は4%未満)。関税障壁を設けることができなかったことで、世界経済との一体化がうながされ、さまざまな製品を国内生産していたそれまでの経済から、コストのかかるものは輸入し、安生産できるものは輸出するという経済に移行していった。この変化は日本の消費者に大きな利益をもたらしていた。アメリカン大学のダニエル・バーンホーフェンとクラーク大学のジョン・ブラウンは、日本が閉鎖経済のままであった場合と比較し、自由貿易によってこの国のGDPは8~9%拡大したと推定している(BernhofenandBrown,2005)
こうした輸出主導型の経済成長は、製造業の成長を前提としていた。二十世紀初頭には、日本経済の構造は、すでに世界の産業界の主導国と同じ構造を示すようになっていた。もちろん、日本ははるかに貧しかったが、それにもかかわらず、総生産に占める製造業の割合はアメリカに劣ってはいなかった(PerkinsandTang,2017,p.173)
このような産業経済の構築には、高水準の投資と産業労働者の動員が欠かせなかった。産業革命期のイギリスがそうだったように、日本でも地方から来た労働者は、工場の規律と長い労働時間のもとに置かれていた。また、多くの女性が繊維工場で働くために労働力として参入し、たいていの場合、過酷な環境のもとで日々を送りながら働いていたHunter,2003)。
もうひとつの要因は教育だった。すでに見てきたように、労働生産性にとって教育は重要なファクターだ。日本の場合、明治維新前の時点で識字率は比較的高かったものの、第三の教育〟いわゆる中等教育以降の高等教育が不足していた。徳川幕府は一八六四年の時点で、ロンドン大学やケンブリッジ大学などをはじめとする欧米の大学に留学生を派遣していたが、明治時代になっても留学生の派道は続き、欧米をモデルとした三段階制の教育制度が導入されていった(Koyama,2004)。ピア・ヴリーズは、「一八八〇年から一九四〇年のあいだで、高等科学技術教育への入学者数は四〇倍、さらに工業や商業教育施設への入学者数は八〇倍に増加した」と記している(Vries,2020,p.212)。
日本という国が教育面で優れていた点は、最終的にこの国を世界経済の主導国に収斂していくうえで大きな貢献を果たすことになる。しかし、ほかの後発国同様、日本にも乗り越えなければならない大きな課題があった。生産要素価格が欧米の先進国と異なっていたままだったのである。日本に比べて、ヨーロッパの賃金ははるかに高かった。日本が工業化していくうえでこのことが大きな障害となったのは、費用がかかる西洋の技術的な課題は、日本ならではの安価な労働力ですますことができたので、技術革新が阻まれてしまうことにつきた。
しかし、ここで日本の教育の優位性が重要な役割を果たしていた。ロバート・アレンは次のように指摘している。「(低賃金の)国のなかには、不適切な技術が原因で成長が跛行した国もあったが、日本の対応ははるかに創造的だった。日本人は西洋の技術を日本の低賃金経済に見合う、費用対効果に優れた技術に改良していったのである」(Allen,2011a,p.122)。その後、日本人は時間をかけながら、西洋の技術を自国の生産要素価格に見合うよう改良を加えていき、二十世紀初頭には、この国は世界でもっとも生産コストの低い綿織物の生産国になっていた。同様の進展は日本のほかの産業でも起きており、一橋大学の馬徳斌は絹織物産業について検証している(Ma,2004)。
徳川幕府が政権を返還した一八六七年以降の日本の経済成長は目覚ましいものだった。とはいえ、西ヨーロッパや北アメリカの主要経済圏に完全に追いつくほどのスピードはなかった。明治時代の日本経済は、十九世紀後半に発展したグローバル経済を介して形成された。グローバル経済とは、これまで見てきたように、〈モノ〉〈カネ〉〈ヒト〉の自由な移動を基礎とする経済である。日本は資源に乏しく、とくに石炭、石油、ガスなどのエネルギー資源が不足していた。そのような国が自国の製造業を発展させていくには、国際市場へのアクセスが不可欠だった。第一次世界大戦中、日本の繊維製品の輸出は活況を呈し、イギリスの生産者をそれまでの市場から駆逐するほどだったが、世界恐慌とそれに続く世界的な保護貿易主義の台頭のせいで、日本の繊維輸出は深刻な打撃を免れることはできなかった。
この経済危機は日本の強純派を勢いづかせ、彼らは中国本土で帝国を建国することによって、世界中を経済的打撃から国を守ろうとした。しかし、こうした戦略は第二次世界大戦で壊滅的なこの国にもどし、日本経済がふたたび成長を始めるのは一九五〇年代と六〇年代になってか〔らである〕
の人口に占める割合が比較的小さかったからだ。世界が豊かになるためには、そのような富が多くの 人口を抱える地域に広がっていかなければならない。そのためには、まずアジアに豊かさを広げてい かなければならないだろう。世界人口の約六割をアジアが占めているからだ。もちろん、まだまだ道 のりは遠いが、本章で紹介してきたような動きは、近い将来、世界全体が確実に豊かになるという楽 観的な見方を許してくれるだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
