
【ブログ】質と量ならどちらが大切なのか
ブログの質と量なら、どちらが大切なのか。
詳しい答えは、こちらの記事にもまとめました。
そう、基本的には、質の方を優先して考えるべきです。
もちろん、ブログにたくさんの記事があった方が、検索エンジンからの評価を受けやすく、アクセス流入が見込めるのですが、それは最終的にという話。
大切なことは、質の良い記事をブログ内にストックしていくことです。
ポイント1:基本は量より質
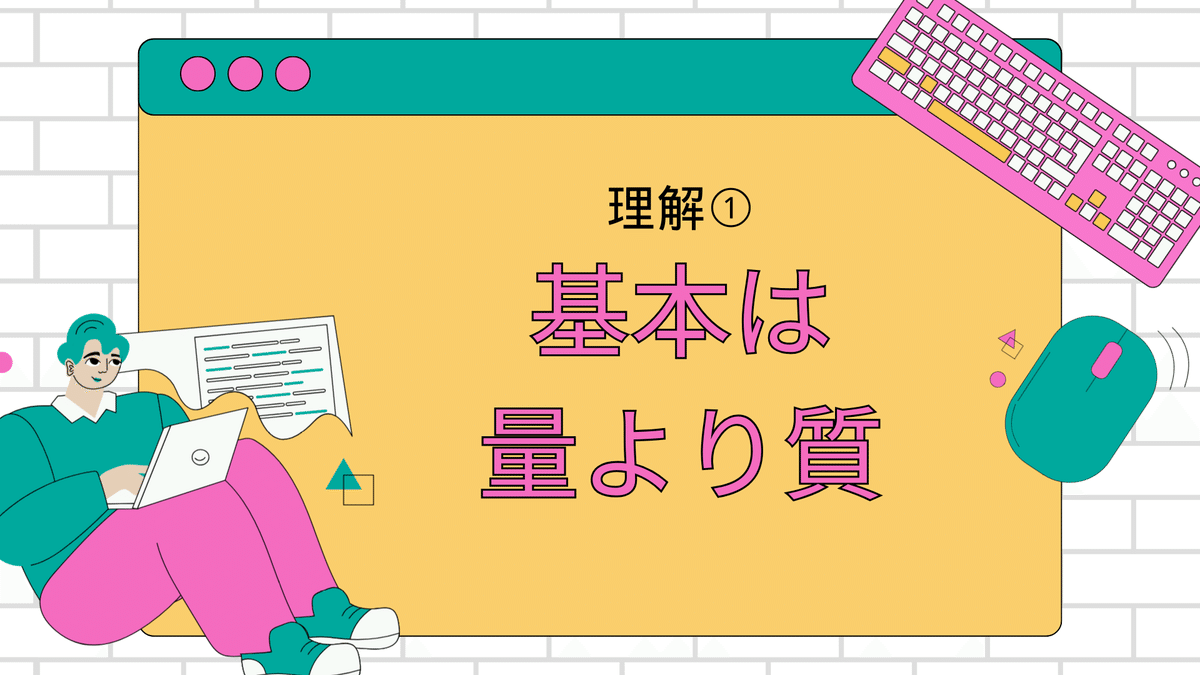
昔の検索エンジン対策=SEOだと、クローラー(サイトをチェックしに来る検索エンジンのロボット)が今ほど記事の内容をチェックできる精度の高さではなかったため、とにかく更新した方が検索エンジンに評価してもらえるという考え方がありました。
しかし、現在の検索エンジンは非常に頭が良いため、
どのキーワードに対して、どんな需要があるのか
記事の内容や品質が十分かどうか
その記事を見た、実際のユーザーが満足しているかどうか
などを、かなり正確に解析できると考えられます。
たとえば、Googleのさまざまな製品(Chrome、検索エンジン、YouTubeなど)によって、人の検索需要はビッグデータとして取得できますし、実際に検索ユーザーがどんなサイトを見て、どんなサイトで検索作業を終了できたのか、ということも解析できるはずです。
つまり、現在の検索エンジンは、相当高いレベルで、記事の内容に判定をつけることができます。
そのため、記事の量を増やしたいがために、低品質な記事を書くのは有効ではありません。
記事の量より、質。
これが基本姿勢です。
ポイント2:読者のニーズ

読者のニーズを想定してから、記事を執筆しましょう。
この流れについては、こちらの記事でも詳しくまとめました。
もし、ブログにアクセスを集めたいのでしたら、そのブログは読者さんのためのものでなければいけません。
まだブログに慣れていないうちは、まずはご自身の好きなテーマについてブログを書いてみるのも良い練習になります。
しかし、本格的にアクセスを増やしていこうと決めたら、あくまで読者さんのためになる記事が読めるブログにしていかないと、読者さんにとっては「読む理由」が見当たらないので、ブログに人が訪れなくなるのです。
そして、先ほどご紹介したように、現在の検索エンジンは、ビッグデータを活用して「どのキーワードには、どんな検索ニーズがあるのか」ということを、かなり正確に把握しています。
そのため、しっかりと読者のニーズに応える記事を書かなければ、検索エンジンにも評価されず、やはりアクセスの増加が見込めないということになります。
では、読者のニーズとは何でしょうか?
ポイントは2つあります。
解決したい悩み
解決して手に入れたい未来
この二つを想定することが大切です。
あなたも、何かのキーワードで検索をする時には、「◯◯について調べて、■■しよう。」というように、何かを解決して、何かを手に入れようとしていませんか?
その目的の大きさは、かなり大きなことから、非常に小さく身近なことまで、幅が広いでしょうが、いずれにしても、
「◯◯について調べて、■■しよう。」というように、何かを解決して、何かを手に入れようという意識が、検索という行動にはあるのです。
そのため、記事を書く際には、
その記事で上位表示を狙うキーワードを決める
そのキーワードで検索する人の悩みを調べる
その悩みを解決して実現したいことを調べる
こういった読者ニーズの事前リサーチが欠かせません。
ポイント3:一つの記事では、一つのテーマ
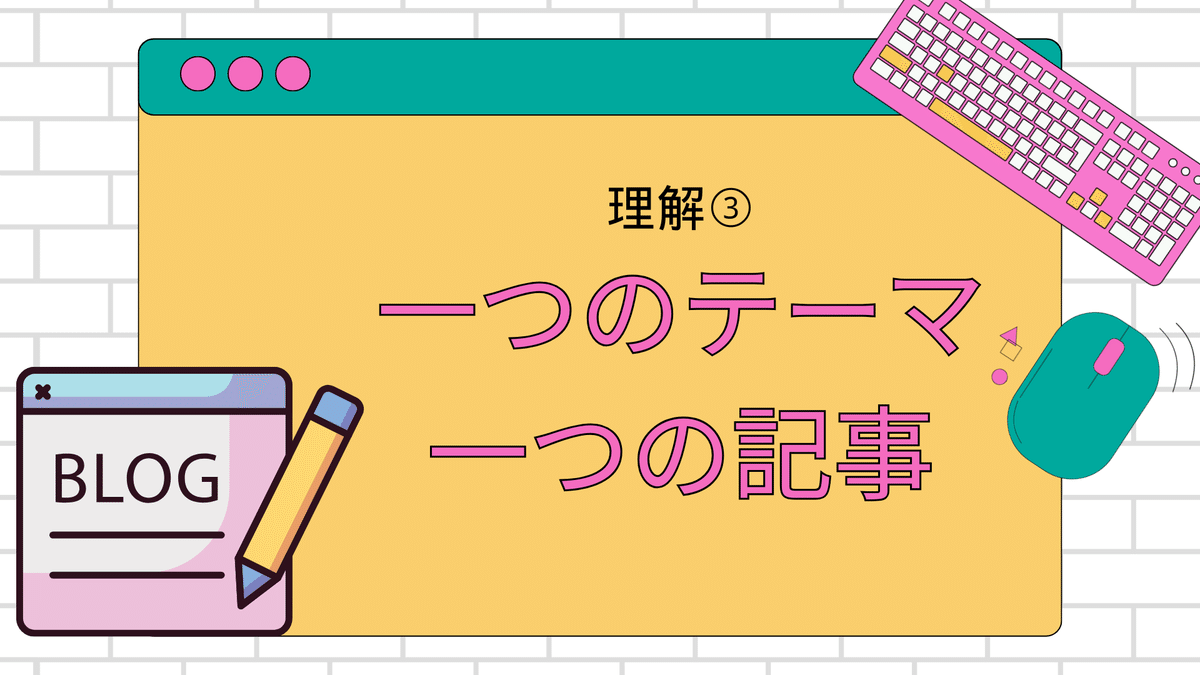
たとえば、今お読みいただいているこの記事では、「ブログの質を上げる」という一つのテーマに対して、5つのポイントを説明するという構成を取っています。
そう、記事で取り扱うテーマは一つ。
話の軸は一つに絞るわけです。
その一つの軸に対して、いくつかのポイントを紹介していくのは構いません。
ただし、軸を定めないで、ポイントを列挙していくだけだと「何のための説明なのか」「結論は何なのか」「話はどこに向かっているのか」ということが読者さんに伝わりづらくなるため、よくわからない記事になってしまうのです。
少し、例文を用意しました。
たとえば、こちらの文章はどうでしょう。
「私はハンバーガーが好きだ。野菜はトマトだな。レストランは良い。晴れの日は気分が良いよ。人生とはシンプルだ。」
何が言いたいのか、さっぱりわからない文章じゃないですか?
話の軸がないからです。
では、同じような文章ですが、こちらはいかがです?
「私の人生の幸せは、シンプルな習慣に支えられている。週末には、子どもたちとレストランでハンバーガーを食べる。ジューシーなハンバーガーに、野菜はトマト。そんな、どこにでもある週末の外食と、家族で歩く時間が好きだ。晴れの日には家族で散歩に出かける。気分が良い。そう、人生とは、シンプルで良いのだ。」
こちらの文章は、最初に「私の人生の幸せは、シンプルな習慣に支えられている」という結論から入ることで、その後の説明がすべて「シンプルだけど、幸せなことの例なんだな」ということがわかりやすくなっています。
そして、最後にもう一度「そう、人生とはシンプルで良いのだ。」と結論を持ってくることで、この一つの結論を印象付けています。
このように、一つのテーマを軸に展開していく書き方が伝わりやすい書き方です。
ブログの中で、そもそも複数のテーマについて書きたい場合には、記事ごとにテーマを分けましょう。
ポイント4:画像やブレットの活用

検索エンジンは「ユーザーにとって読みやすい記事」も評価します。
つまり、検索エンジンからすれば、たとえばGoogleの場合、「Googleで検索をすると、知りたいことがわかるな」と検索ユーザーに思ってほしいわけです。
そのため、「何だよ、このサイト。読みづらいから他にしよう。」と思われる記事は上位には持ってきません。
では、ユーザーにとって読みやすい記事とは、どんなものか。
すぐに真似できるやり方があります。
たとえば、私のこの記事の中にも、画像が差し込まれていますよね。
このような画像の差し込みがあるかないかだけで、読みやすさも変わります。
私の場合は、画像はCanvaで作っています。
あとは、ブレットと呼ばれる表示形式。
いわゆる箇条書きです。
リンゴとミカンとバナナとキウイとブドウ
と書かれるよりも、
リンゴ
ミカン
バナナ
キウイ
ブドウ
と書かれた方が、読みやすいですよね。
このような小さな工夫が、「ユーザーが最後まで読みたくなる記事になるかうか」を決めます。
そして、検索エンジンは、ユーザーが最後まで読んでいる記事や、滞在時間の長い記事を、評価する傾向が強いのです。
ポイント5:例えや体験談の活用
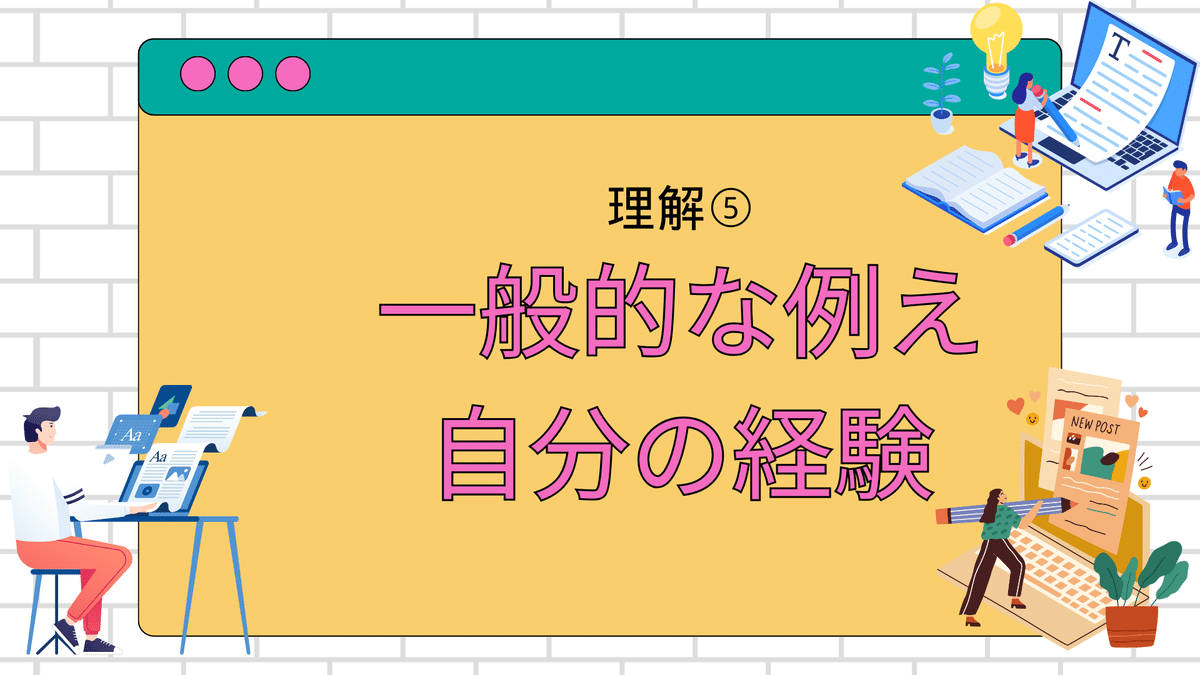
私の場合、各記事の中に「たとえば」というのが、かなりたくさん出てくるという特徴があると思います。
たとえ話というのは、その説明を、よりわかりやすくするために使う、置き換えた話のことです。
そのため、たとえ話で使う例は、「誰でもイメージできそうな内容」である必要があります。
私の場合、
むずかしいビジネスの話を、身近なケーキ屋さんの例に置き換えて説明したり、
ちょっと覚悟が必要な思考法を説明するときに、有名な童話を引用したり、
そうやって、みんながイメージできることに置き換えて、理解してもらえるように努力しています。
また、このようなたとえ話とは別の狙いで実体験の紹介があります。
実は、この二つ(たとえ話と、実体験)を一緒の狙いで使ってしまう人が少なくありません。
ですが、実体験というのは、あくまであなただけの体験ですので、親近感を持ってもらえるものかどうかは、よく考える必要があります。
自分にとっては当たり前だけど、みんなには違うかも
自分は好きだけど、嫌いな人もいるかも
自分の地域では当然だけど、みんなの地域ではわからない
そんな風に、読者さんのことを考えて、使いどころを見定めてください。
共感されない実体験でも、実績や異例として打ち出したい場合には効果的でしょう。
ありふれた実体験でも、共感を得る目的になら、使えるでしょう。
そう、狙いと使いどころによって、あなたの体験が価値に変わります。
そして、それがブログの良さでもありますよね。
今回の記事では、ブログの質を高めるためのポイントをいくつかご紹介しました。
少しコツを意識するだけで、あなたのブログがより魅力的なものへと変わります。
将来のために、今、何かを変えよう。
あなたの挑戦を、私は応援しています。
株式会社フレンドマーク
五十嵐
よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!
