
CFP®になろう!2021年第2回試験を分析(後半)
11月21日の試験(第2日程)の3課目を分析し、出題内容を振り返ります。後半第2日程は、リスク、タックス、相続です。どれも定番の計算問題が多い課目ですが、今回はさて...。
リスクと保険

従来からの定番問題(とくに「時間のかかる資料読み取り」、保険金受取りに関する計算問題)の出題が減りました。一方、コンサルティングに関する知識・法令についての出題は基本的な事項として必須事項です。また相変わらず、資料の読み取り問題にはかなりの時間が必要なので、「時間配分」「回答順」を決めておきましょう。とくに損害保険の約款の”どこに何が記載されているのか”をざっと把握しておくことをおススメします。
❶《一般論・知識》
統計資料やディスクロージャーに関する出題が無かったので、大きな時間ロスは生じなかったですね。法令に関しては、保険法、保険業法を中心に定番の出題でした。また、昨今の時代背景からからペット保険、認知症保険の出題があったり、法人契約の損害保険の出題が減るなど、出題対象の保険商品が変化した印象があります。

●コンサルティング
保険相談、必要保障額の算出手順
●法令・制度
保険法、保険業法(クーリングオフ)、少額短期保険業制度
●相続対策
代償分割、遺留分、生命保険信託
●法人のリスク
従業員の保障(退職金制度)、事業保障資金、退職慰労金・弔慰金
●保険の概要
損害保険契約者保護機構、損害保険料の算定
❷《保険商品の理解》
毎回ほぼ同じ内容なので、全て正解したい出題でした。法人(団体)契約の医療保険についての出題がなく、全体として易しい出題が多かったように思います。法人契約の損害保険商品は、すべてを詳細に覚えるのは大変ですから、概要だけ理解しておけば十分な内容です。

●生命保険商品
個人年金、引受基準緩和型終身(資料読解)、認知症保険(資料読解)
●従業員の保障
中小企業退職金共済、ハーフタックスプラン、役員退職慰労金
●損害保険商品
地震保険付帯住宅総合保険、普通傷害保険、所得補償保険、施設所有者賠償責任保険
●法人契約の損害保険
拡張危険負担特約(火災)、フリート契約(自動車)、生産物賠償責任保険など
❸《税額の計算・税金のしくみ》
個人年金や生命保険料控除の出題は定番ですが、時間がかかるので回答を後回しにしましょう。名義変更による課税体系についての出題がなく、全体として易しい出題でした。

●所得税など
個人年金、生命保険金、生命保険料控除、医療費控除、損害保険金の課税
●相続税など
名義変更時の税務、収入保障保険の課税、課税対象額(非課税金額控除)
❹《資料の読取り》
定番の出題がメインでした。生命保険の証券については、落ち着いてゆっくり回答することが正答への近道です。また、約款に関しては損害保険(ヒト)だけでなく、ペット保険の出題、さらに医療保険の出題がありました。基本的な対処方法は同じなので、時間に余裕がある場合にのみ回答することが、合格への近道です。

●パンフレットの正誤 引受基準緩和型終身、認知症保険
●生命保険の証券の理解
●従業員の退職金規程
●損害保険の約款 対物賠償責任保険、普通傷害保険、ペット医療費用
●医療保険の約款 総合医療保険
❺《経理処理と課税(法人)》
定番ばかりの出題のため、得点できることは当然。ここで得点できないことがあるのは合格から遠のく要因です。今回は、圧縮記帳に関する出題が無かったのが意外でした。

●生命保険の譲渡
個人事業からの法人化・名義変更
●仕訳/生命保険
死亡退職金、保険料(役員退職慰労金目的の定期保険)
●仕訳/損害保険
積立普通傷害保険(保険料、満期返戻金)、介護費用保険(保険料)
●地震保険料控除
《総括》
何と言っても、回答の時間配分・順序が大切です。証券や約款の読み取りが不得意な場合は、後回しにしましょう。時間をかけて読み取って導き出した答えも、簡単な計算問題も、点数は同じです。
それと、これまでの定番問題で、今回出題が無かったものは無視することなく今後も学習が必要です。
▼お知らせ
CFP🄬試験(リスク管理)に合格したいあなたへ(過去記事)
2022年6月試験向け 受験対策講座 オンラインにて開催決定!
受験対策テキスト 最新版
タックスプランニング

出題の大半が計算で、今回は過去最多の9割(45問)でした。ほぼ定番の内容と言えますが、冒頭からボリュームたっぷりの計算でした。所得税、住民税の課税体系全般を正確に理解していることが大切だと言えます。従来通り、引っ掛けには注意が必要です。
❶《所得税・住民税 / 手取額の計算》
所得税や所得税の計算プロセスを十分理解したうえで、税額を控除した手取り額の計算を問う出題がはじめから連発しました。結構な時間を要したかもしれません。

●給与所得 源泉徴収票の読み取り
●退職所得 退職一時金
●雑所得 個人年金、公的年金/老齢給付
●譲渡所得 総合課税の資産
❷《所得税 / 所得の計算、経費》
各所得の計算方法について、何が収入となるのか、どれが必要経費になるのか、各所得独特の計算方法をどれだけ理解しているのかの質問でした。どれも、基本中のキホンでした。所得のみを問う出題は少なくなりました。

●事業所得
減価償却、従業員給与/事業専従者給与
●不動産所得
収入額、キャッシュフロー、青色申告、取得額/取壊し費用、減価償却費
●配当所得
上場株式/非上場株式の申告、損益通算、繰越控除、配当控除
❸《所得税 / 総所得・課税総所得・税額の計算》
何が控除の対象か、控除の要件は何か、基本がどれだけ理解できているのかを問う内容でした。税制改正により新たに設けられた「給与所得における所得金額調整控除」の出題が複数ありました。うっかり忘れてしまっていた人が多かったかも知れません。

●給与所得
所得金額調整控除
(1)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
(2)給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除
●譲渡所得 総合課税の資産の通算
●一時所得 生命保険金
●所得控除/人的控除
扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除
●所得控除/物的控除
医療費控除
●損益通算
●繰越控除
純損失、上場株式の譲渡損、居住用不動産の譲渡損
●税額控除
配当控除、住宅ローン控除、耐震改修特別控除
●その他
非居住者に対する課税
❹《個人所得課税》
久しぶりに消費税の納付税額を問う出題がありました。いずれも確実に得点したい内容です。

●消費税 課税/非課税の判断、納付税額(簡易課税)
●事業税 損益通算と税額
●住民税 所得割、申告
❺《法人税》
法人税も定番が多い出題でした。貸倒損失やCVP(損益分岐点)分析の出題が復活したので、過去問を遡って演習していれば難なく回答できたはずです。一方、法人所得の増減や財務諸表(PL,BS)の出題はなく、残念に感じたひとが多かったかも知れません。
また、法人税でも申告に関すること、必要書類の理解などを問う出題が無くなり、出題傾向が計算問題にシフトしたようです。

●法人成り(会社法)
●損金(役員給与、租税公課、交際費、減価償却費、貸倒損失)
●青色欠損金の繰越控除
●役員と法人の取引
●CVP(損益分岐点)分析
《総括》
前回(2021年第1回)では出題のなかった内容が復活したので、過去問での対策が十分であった場合には余裕をもって回答できる内容でした。典型的な出題が並びましたが、冒頭にやや時間のかかる問題が続き、焦ったかも知れません。ちょっとしたミスが合否を分けることになりそうです。
▼お知らせ
CFP🄬試験(タックス)に合格したいあなたへ(過去記事)
2022年6月試験向け 受験対策講座 オンラインにて開催決定!
受験対策テキスト 最新版
相続・事業承継
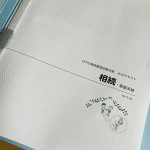
相続・事業承継で常に注意が必要なのは「民法と相続税法の違い」です。民法は、相続する人たちの間でモメごとが発生した場合の解決方法が決められています。財産の分け方、話し合いのルールなどです。一方の相続税法は、相続税や贈与税の税額の算出方法を決めた法律です。それぞれのルールがどのように異なるのかを理解しておく必要があります。
❶《相続の概要 / 民法》
民法の規程に関する出題は、相続分に始まり、分割協議、遺言など様々な場面でのトラブル等が問われます。いずれも判断基準が「いま」であることを意識して回答することが大切です。近年の相続を取り巻く環境や民法の改正を受けて出題内容が変化しつつありますが、多くは定番ですので必ず得点しましょう。

●相続財産の計算
法定相続分、相続人(放棄)、修正(寄与分)、遺留分
●時事問題
特別の寄与、配偶者居住権、特別縁故者、
●遺言
自筆証書遺言、遺贈
●その他
成年後見制度(任意後見、法定後見)
❷《相続税の仕組み》
税法は相続税がいくらになるか算出するルールであり、どのように財産を評価するかの理解が必要です。課税される財産の分類や、税額の計算ステップに関しては、これまで通りの出題が並びました。ただ、畳みかけるように計算問題が続きますので、問題ごとに頭を切り替える練習が必要です。なお、久しぶりに相次相続控除の出題がありました。
制限納税義務者に関しては、出題内容は従来通りでしたが、回答方法が非常にラクになりました。

●課税価格
保険金、生前贈与財産、退職手当金・弔慰金、債務控除
●相続財産に関する知識
小規模宅地の特例
●相続税算出過程
基礎控除、贈与税額控除、配偶者の税額軽減、2割加算、相次相続控除
●制限納税義務者、国外財産評価
●相続税の申告および納付
❸《相続対策》
保有資産の変更により、課税遺産総額をどの程度少なくできるかを問うものです。回答に少し時間を要する出題ですが、過去問で繰り返し演習をしてコツを掴んでいれば、容易に正答できる内容でした。

●課税遺産総額の引き下げ額
現金の生前贈与、生命保険契約、賃貸用アパートの取得
●相続対策と効果
相続時精算課税制度、小規模宅地の特例、相続財産の譲渡、納税資金
❹《贈与税》
計算問題、知識を問う問題とも少なくなりました。すべて基本的な内容なので、全問正答したいところでした。

●贈与税額の計算
暦年課税、相続時精算課税、配偶者控除
●贈与財産の知識
特例財産(住宅取得等資金、教育資金)
❺《財産評価》
不動産(土地)の評価については、親切(質問内容を理解しやすい)な出題になりました。細かい設定がどう評価額に影響するのか、過去問で演習を繰り返した人にとっては容易な出題でした。
金融商品や自社株の評価については標準的な出題、事業承継に関する知識は専門性が高まっていますが、定番の出題を確実に正答できていれば合格できると思います。

●土地の評価
自用地、貸家建付地
●金融商品の評価
生命保険契約に関する権利、株式、公社債
●事業承継
自社株の評価、納税猶予および免除の特例、遺留分に関する特例、取引相場のない株式の売買、譲渡制限株式、中小M&Aガイドライン
《総括》
過去問への依存度が高い課目です。徐々に出題方法が変化していますが、出題内容については概ね従来通りと言えます。時事問題についての対応も必要ですが、まずは過去問を繰り返し演習していればかなり高い確率で合格できる内容でした。
▼お知らせ
CFP🄬試験(相続)に合格したいあなたへ(過去記事)
2022年6月試験向け 受験対策講座 オンラインにて開催決定!
受験対策テキスト 最新版
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
